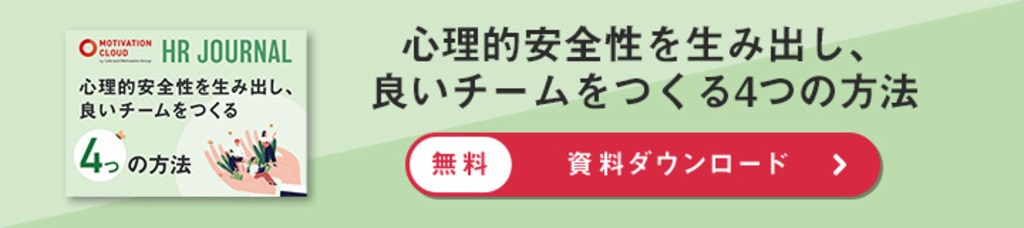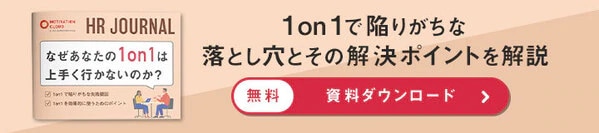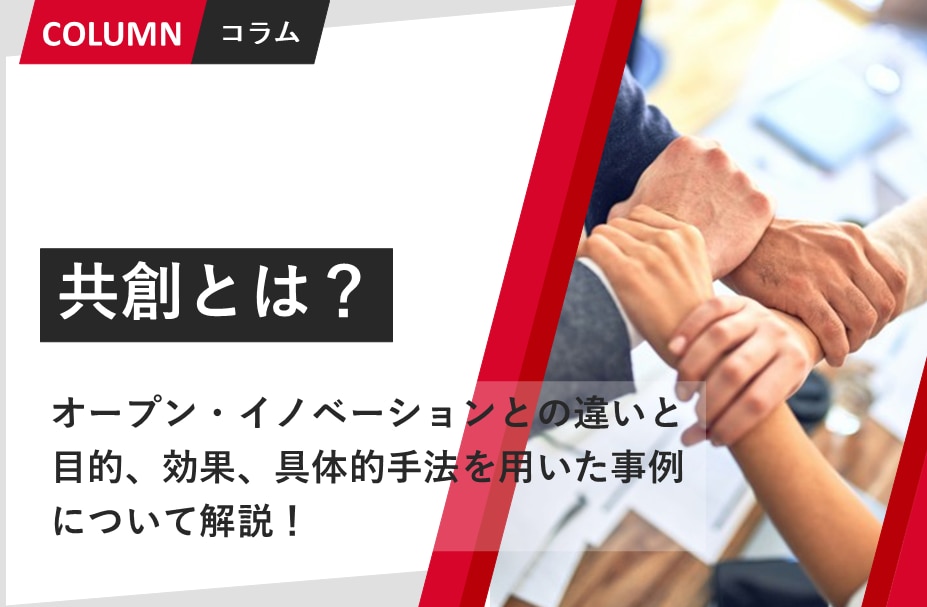
共創とは?オープン・イノベーションとの違いと目的、効果、具体的手法を用いた事例について解説!
共創(コ・クリエーション)とは、多様な立場のステークホルダーと対話しながら、ともに新しい価値を生み出していく考え方のことです。
ビジネス環境が目まぐるしく変化し、自社単独で競争優位性を確保するのが困難になりつつある近年、共創によって新たな価値を生み出そうとする企業が増えています。本記事では、共創の考え方や共創の3つのタイプについて解説するとともに、共創の事例もご紹介していきます。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ コミュニケーション溢れる【良いチーム】を作るポイントとは?資料はこちら
共創(コ・クリエーション)とは?
共創(コ・クリエーション/Co-Creation)は様々な意味で用いられる言葉ですが、ビジネスの世界では、多様な立場のステークホルダーと対話しながら、ともに新しい価値を生み出していく考え方のことを言います。
企業は、消費者やパートナー企業、社外人材などのステークホルダーを巻き込みながら、共創プロジェクトを進めていきます。
新商品の開発や既存サービスの改善、イノベーションの創出など、共創する目的は様々ですが、近年のビジネス戦略において一般化しつつある考え方です。
共創という言葉が広く知られるきっかけになったのは、『価値共創の未来へ―顧客と企業のCo‐Creation』(C.K.プラハラード、ベンカト・ラマスワミ 共著)という書籍です。
同書では共創を「企業が様々なステークホルダーと協働することで、共に新たな価値を創造すること」と定義しており、これからの時代、顧客と一緒になって価値を生み出していかなければ企業は生き残っていけないと説いています。
また、共創という考え方は、シャープの元副社長で小型電卓の生みの親である佐々木正氏がモットーとしていたことでも有名です。
佐々木氏はシャープ(当時、早川電機)に入社して早々、部下に対して以下のように諭したと言います。
「いいかい、君たち。分からなければ聞けばいい。持っていないなら借りればいい。逆に聞かれたら教えるべきだし、持っているものは与えるべきだ。人間、一人でできることなど高が知れている。技術の世界はみんなで共に創る『共創』が肝心だ」
共創(コ・クリエーション)が注目される背景
共創(コ・クリエーション)が注目されているのは、まさに今、既存のビジネスの枠組みや常識が通用しない時代が訪れているからです。
従来、ビジネスにおける競争は同業他社とシェアを争うように、「業界」という枠組みのなかでおこなわれるものでした。
シェアを争うと言っても、いったん業界内でのポジションが確立してしまうとなかなか変化は起こりにくく、いったん築いた競争優位性を長期的に持続できるのが従来のビジネス環境だったと言えます。
しかし、近年はビジネス環境が目まぐるしく変化しており、「VUCA(Volatility:変動性/Uncertainty:不確実性/Complexity:複雑性/Ambiguity:曖昧性)」と呼ばれる時代が到来しています。
業界という枠組みはもはや「あってないようなもの」であり、異業界から予想もしていなかった競争相手が出現することで、築き上げてきた競争優位性があっと言う間に崩れ去ってしまう事例が続出しています。
顕著な例としてよく紹介されるのが、UberやAirbnb、AmazonやNetflixです。
Uberの登場によってタクシー業界は大きな打撃を受け、Airbnbの登場によってホテル業界の常識は覆されました。Amazonは出版業界のルールを激変させ、Netflixはレンタルビデオ業界のビジネスモデルを破壊しました。
コロンビア大学ビジネススクールの教授であるリタ・マグレイス氏は、自書『競争優位の終焉』のなかで、変化の激しい経営環境の下では、企業戦略の目標とされてきた「持続的な競争優位を構築して、そこから長期間にわたって利益を得る」という考え方はもはや通用しなくなったと述べています。
このようなビジネス環境において、自社単独で競争優位性を確保するのは難しいと言わざるを得ません。
そこで、注目されるようになったのが「共創」という考え方であり、今、消費者をはじめとするステークホルダーとの共創によって新たな価値を生み出そうとする企業が増えています。
共創(コ・クリエーション)とオープン・イノベーションの違い
共創(コ・クリエーション)と意味が似た言葉に「オープン・イノベーション」があります。
オープン・イノベーションとは、企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造することを言います。
「組織の外部で生み出された知識を社内の経営資源と戦略的に組み合わせてイノベーションを創出すること」と、「社内で活用されていない経営資源を社外で活用することによってイノベーションを創出すること」の両方がオープン・イノベーションです。
上述した佐々木氏がモットーとしていた共創は、オープン・イノベーションに非常に近い考え方だと言えます。なお、オープン・イノベーションと対になる概念が「クローズド・イノベーション」です。
商品の研究・開発から製造・販売までのバリューチェーンを、企業が自社グループのリソースだけでまかなうことがクローズド・イノベーションであり、「自前主義」とも呼ばれます。
このように、共創とオープン・イノベーションは似た意味を持っていますが、共創のほうが広義の概念であり、オープン・イノベーションは共創を実践するための一つの手段だと捉えるのが一般的です。
共創の目的および効果
共創は、企業が多様なステークホルダーと協力し、新たな価値を創造する取り組みです。近年、ビジネス環境の変化や社会課題の複雑化に伴い、共創の重要性が増しています。ここでは、共創の主な目的および効果を3つご紹介します。
新規事業・新製品の開発
共創の最大の目的の一つは、新しいビジネスや製品の創出です。企業単独では気づきにくい市場のニーズや課題を、異なる視点を持つパートナーと共有することで、革新的なアイデアが生まれやすくなります。
例えば、異業種の企業やスタートアップ、研究機関との連携により、自社にはない技術や知見を取り入れた新製品の開発が可能となります。
また、消費者との共創を通じて、実際のニーズに即した製品やサービスを提供することができ、市場での競争力を高めることができます。このように、共創は新たな価値の創出を促進し、企業の成長を支える重要な手段となっています。
企業ブランディングの強化
共創は、企業のブランド価値を高める効果もあります。ステークホルダーとの協働を通じて、企業の理念やビジョンを具体的な形で示すことができ、社会的な信頼性や好感度が向上します。
例えば、社会課題の解決を目指すプロジェクトに参加することで、企業の社会貢献活動が可視化され、ブランドイメージの向上につながります。
また、共創によって生まれた製品やサービスが話題となり、メディアやSNSで取り上げられることで、企業の認知度が高まることもあります。このように、共創は企業のブランディング戦略においても重要な役割を果たしています。
コミュニティ形成と組織力の強化
共創を通じて、企業は多様なステークホルダーとの関係性を築き、持続的なコミュニティを形成することができます。これにより、情報やリソースの共有が促進され、組織全体の柔軟性や対応力が向上します。
例えば、共通の目的を持つ企業や団体が連携することで、知識や技術の相互補完が可能となり、新たなビジネスチャンスが生まれます。また、社内においても、共創の文化が浸透することで、部門間の連携が強化され、イノベーションが生まれやすい組織風土が醸成されます。
このように、共創は企業の組織力を高め、持続的な成長を支える基盤となります。
共創に必要な要素
共創は、企業が多様なステークホルダーと協力し、新たな価値を創造する取り組みです。近年、ビジネス環境の変化や社会課題の複雑化に伴い、共創の重要性が増しています。ここでは、共創を成功に導くために必要な2つの要素について詳しく解説します。
パーパス(共通目的)の明確化
共創を効果的に進めるためには、関係者全員が共有する明確な目的、すなわち「パーパス」の設定が不可欠です。パーパスとは、ステークホルダーの共通の課題を言語化した共通目的のことを指します。
業種や専門性、立場が異なるステークホルダーと共にプロジェクトを推進するには、パーパスの策定が必要不可欠といえるでしょう。
また、イノベーションの実践を推進するためのアライアンス組織であるFCAJの研究プロジェクトから派生して生まれたフレームワークとして、パーパスと各ステークホルダーの目的・役割を図化した「パーパスモデル」も注目されています。
共創の場(共創空間)の構築
共創を実現するためには、創造的な対話や実験を継続的に行える「共創のための場=共創空間」が重要です。リアル空間やオンライン上のコミュニティなどで、対話やプロトタイピングができる共創の場を作り、運営することが求められるでしょう。
例えば、オープンイノベーションを活性化させるには、自社リソースの積極的な開示が必要であり、そのためには、外部に広く開かれた拠点となる場、すなわち「共創の場」が重要です。共創ラボ、フューチャーセンター、イノベーションハブ、インキュベーション施設、ハブスペースなどの呼び方もあります。
共創(コ・クリエーション)の3つのタイプと実践する際のポイント
共創(コ・クリエーション)はステークホルダーとの関係性によって、「双方向」「共有」「提携」の3つに分類することができます。
■共創のタイプ① 双方向の関係性
従来のように、企業が消費者に対して一方的に商品・サービスを提供するのではなく、企業と消費者がフラットな立場で議論を交わしながら、ともに課題を解決したり、新しい商品・サービスを生み出したりする形の共創です。
近年はSNSの普及によって、企業と消費者が直接コミュニケーションを図り、情報をシェアし合うことが容易になっているため、双方向の関係性をベースにした共創が生まれやすくなっています。
■共創のタイプ② 共有の関係性
企業がコンソーシアム(共同事業体)やコミュニティを形成し、オープンな関係性のなかで新しい価値を生み出していく形の共創です。
同じ目的・テーマを持った企業・団体・政府などが参加し、アイデアを出し合ったり議論を交わしたりしながら価値創出に取り組みます。
共創を成功させるには、各参加者がそれぞれ役割と責任を持ち、リーダーシップを発揮し、知恵を出し合うことが重要です。
■共創のタイプ③ 提携の関係性
企業同士がお互いに不足している資源を補い合い、協力して新しい価値を生み出していく形の共創で、いわゆる「アライアンス」の関係性です。
企業規模による上下関係や業界の枠組みを排除して、対等なパートナーシップのもとで協力・協同することが重要です。
共創を実現するための具体的な手法
近年、ビジネス環境の変化や社会課題の複雑化に伴い、共創の重要性が増しています。ここでは、共創を実現するための具体的な手法を3つご紹介します。
パーパスモデルの活用
パーパスモデルは、単に人々が集まるだけでなく、多様な背景を持つステークホルダーが、それぞれの専門性や視点を持ち寄り、共通の「パーパス(共通目的)」を中心に据えて、有機的に連携し、価値創造を目指す「共創プロジェクト」を成功に導くための、綿密に設計された「設計図」としての役割を果たします。
従来のプロジェクト設計とは異なり、パーパスモデルは、プロジェクトの根幹となるパーパスを明確化し、参加する全てのステークホルダー間でその理解と共感を深めることを重視します。
この共通理解を基盤として、各ステークホルダーがプロジェクトにおいてどのような役割を担い、何を目的として参加するのかを、共通のフォーマットを用いて具体的に可視化します。
共創空間の構築と活用
共創空間の構築は、単なる物理的な場所の提供に留まらず、組織内外の多様な関係者が集い、知恵やアイデア、技術を結集させるための戦略的な取り組みです。
この空間は、研究開発の加速、革新的なプロトタイプの創出、社内における先進的な技術の демонстрация、業界を超えた交流を促進するイベントの開催、重要な意思決定や新たなビジネスチャンスを生み出す会議や商談の場として多岐にわたる活用が期待できます。
このような共創の場を戦略的に設けることは、これまで独立して活動してきた関係者間の壁を取り払い、活発なコミュニケーションを促進する強力な要素となります。
自由でオープンな対話を通じて、参加者それぞれが持つ暗黙知や専門知識が共有され、結合することで、単独では成し得なかった斬新な発想や解決策が生まれる可能性が高まります。
プロトタイピングとワークショップの実施
共創プロジェクトにおいて、アイデアを具体化し、迅速に検証するための手法としてプロトタイピングが有効です。
プロトタイピングとは、製品やサービスの試作品を作成し、実際の使用感や課題を把握するプロセスを指します。これにより、関係者間での認識のズレを早期に発見し、改善点を明確にすることができます。
また、ワークショップを通じて、参加者が共にアイデアを出し合い、試作品を作成することで、チームの一体感や創造性が高まります。
例えば、DNP(大日本印刷)の「P&Iラボ・コラボレーション」では、共創型デザインプロジェクトを効果的に行える場を提供し、プロトタイピングを通じて仮説やアイデアの検証、具体的な課題や改善点の抽出を行っています。
共創(コ・クリエーション)の事例
共創(コ・クリエーション)の事例を3つご紹介します。
■共創事例① カンロ × ファーメンステーション
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社と、未利用資源を再生・循環させる社会を構築するスタートアップである株式会社ファーメンステーションの共創事例です。
カンロの工場で排出される規格外で販売不可の飴(削りかす・割れ等)を原料に、ファーメンステーションが発酵アルコール(エタノール)を精製し、そのエタノールを活用したオリジナルの「マスクスプレー」「アロマスプレー」を開発しました。
カンロは、従来から食品ロスの削減に積極的に取り組んでおり、工場で排出される規格外の飴を飼料や肥料として活用していましたが、「サステナブル」をテーマにした事業に取り組むにあたり、より主導的に資源の循環につながる取り組みを検討しました。
そこで、独自の発酵技術をもとに未利用資源をアップサイクル(※)した商品開発に取り組むファーメンステーションとの共創に至りました。
※ リユース(再利用)、リサイクル(再循環)と異なり、廃棄物や副産物など、従来、不要と考えられていたものや有効活用されていないものを、様々なアイデアや手法でさらに価値の高いプロダクトに転換すること
■共創事例② ネスレ日本
ネスレ日本株式会社は、コーヒーマシン「ネスカフェバリスタ」をオフィスに普及させるプロセスを消費者と共創しています。この取り組みが「ネスカフェアンバサダー」です。
同社はWeb上でアンバサダー(ファン)を募集し、アンバサダーに選ばれた人のオフィスに無料でバリスタを貸し出します。
アンバサダーは、コーヒーマシンに使用するカートリッジも安価に購入することができます。
オフィスでコーヒーを楽しむアンバサダーは、その様子をSNSに投稿したり、定期的に同社のアンケートに協力したり、アンバサダー座談会に参加したりします。
このような取り組みから消費者の声を吸い上げ、サービスの向上や新しいサービスの開発につなげています。
■共創事例③ Oisix
有機野菜などの食品宅配専門スーパー「Oisix」は、共創コミュニティ「Blabo!」と共同で「みんなの商品企画部」というプロジェクトを運営し、消費者との共創に取り組んでいます。
みんなの商品企画部は、消費者がOisixや作り手に対してアイデアを届け、それを実現できる仕組みです。
消費者はOisixのプロデューサーとなり、「あったらいいな」と思うようなアイデアを届けます。それを見た他の消費者が「わたしもほしい!」「わかる!」と感じたら応援します。
そして、多くの消費者に支持されたアイデアが実際に商品化されるという流れです。
みんなの商品企画部で活躍した消費者は「公認プロデューサー」に認定され、実際にOisixのオフィスでおこなわれる企画会議に参加できるなど、様々な特典が用意されています。
組織変革のことならモチベーションクラウド
リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました
・経営方針や戦略が現場に浸透せず、行動に結びつかない
・組織全体の連携が弱く、成果に結びついていない
・優秀な人材の採用・育成が思うように進まない
・従業員の給与・待遇に対する不満が高まり、離職リスクが懸念される
といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。
▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら
まとめ
従来の考え方にとらわれている企業は、想定外の事象が次々と起こるVUCAの時代を生き抜いていくことはできません。
自社単独で、商品力・サービス力を向上させるのには限界があります。消費者をはじめとするステークホルダーとオープンでフラットな協力関係を構築し、共創(コ・クリエーション)戦略によって活路を切り開いていきましょう。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 1on1で陥りがちな落とし穴とその解決ポイントをご紹介!