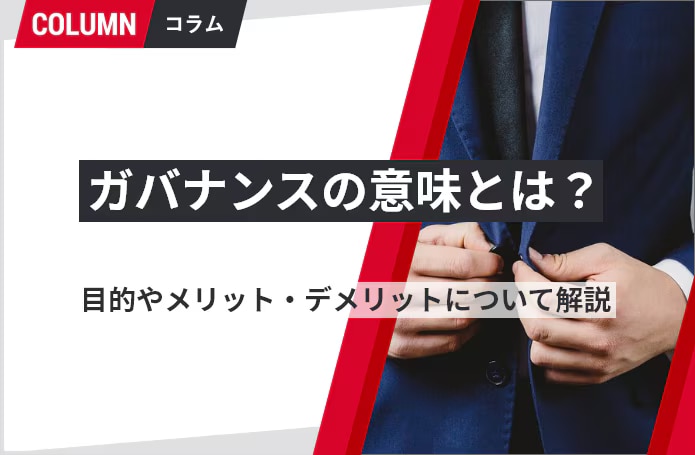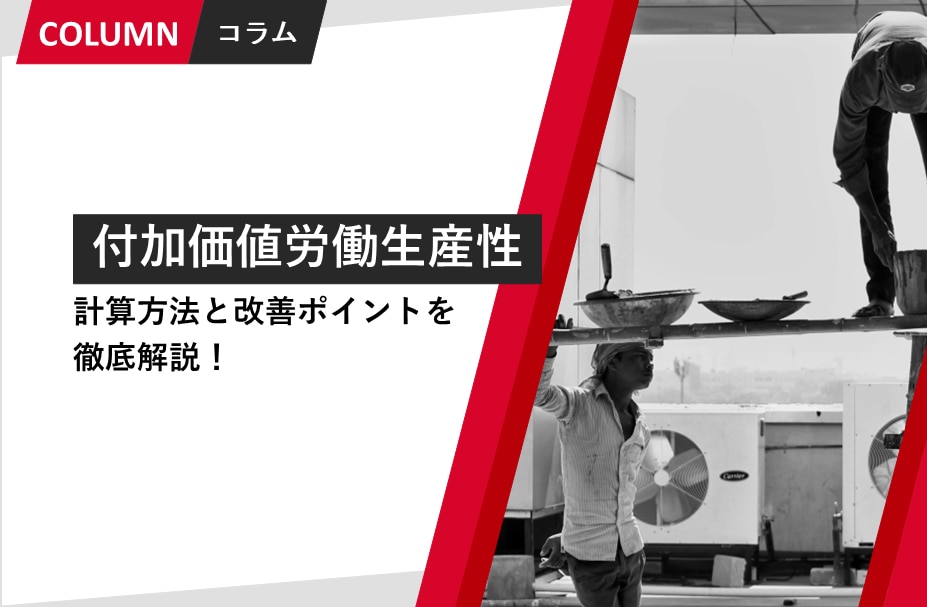
付加価値労働生産性の計算方法と改善ポイントを徹底解説!
付加価値労働生産性とは、従業員一人あたりが生み出す付加価値の大きさを示す指標であり、企業の収益性や競争力を測る重要な基準となります。単なる売上高や利益とは異なり、企業が外部コストを差し引いた「真の価値創出力」を評価できるのが特徴です。
近年、少子高齢化や人手不足を背景に、限られた人材で最大限の成果を上げることが求められており、付加価値労働生産性の向上は、企業経営においてますます重要なテーマとなっています。
目次[非表示]
付加価値労働生産性とは?わかりやすく解説
付加価値とは、企業が生産活動を通じて新たに生み出す価値であり、売上高から外部購入費用を差し引いたものです。労働生産性は、従業員一人当たりまたは労働時間当たりの産出量を示す指標です。付加価値労働生産性は、この二つを組み合わせたもので、「付加価値額 ÷ 労働投入量」で計算されます。
この指標の重要性は多岐に渡り、企業の収益性向上、競争力強化、人材育成の促進、そして経済全体の成長に貢献します。算出された数値は、労働者一人または一時間あたりが生み出す付加価値を示し、数値が高いほど労働生産性が高いと評価できます。
業界によってその目安は異なり、例えばIT業界は付加価値・労働生産性ともに高い傾向がある一方、建設業界のような労働集約型産業では低くなる傾向があります。
付加価値労働生産性を高めるためには、ITツールの活用、成功企業の事例からの学習、そして日々の業務における改善(会議時間の短縮や書類作成の効率化など)が有効です。付加価値労働生産性は、企業の持続的な成長に不可欠な指標であり、定期的な測定と改善への取り組みが重要となります。
付加価値と労働生産性の定義
企業が生み出す新たな価値である付加価値は、売上高から外部購入費用を差し引くことで算出されます。例えば、売上高が1億円で外部購入費用が5000万円の場合、付加価値は5000万円となります。
一方、労働生産性は、従業員一人当たりまたは労働時間当たりの産出量を示す指標で、「産出量 ÷ 労働投入量」で計算できます。
10人の従業員が1000個の製品を生産した場合、労働生産性は100個/人です。そして、付加価値労働生産性は、従業員一人当たりまたは労働時間当たりが生み出す付加価値を示し、「付加価値額 ÷ 労働投入量」で求められます。
先の例では、付加価値が5000万円で従業員数が10人のため、付加価値労働生産性は500万円/人となります。付加価値労働生産性は企業の収益性や競争力を測る上で重要な指標となります。
付加価値労働生産性の計算方法は?具体例で理解
計算式の基本構造
付加価値労働生産性とは、従業員一人あたりがどれだけの付加価値を生み出しているかを示す指標です。
計算式は以下の通りです。
【計算式】
付加価値労働生産性 = 付加価値額 ÷ 従業員数
ここでの「付加価値額」と「従業員数」について、次に詳しく定義します。
・付加価値額
企業が生み出した成果から、外部購入費用(原材料費、外注費など)を除いたもの。
具体的には次のように求めます。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費(給与・賞与・福利厚生費)+ 支払利息・賃借料(場合に応じて)+ 減価償却費
・従業員数
パート・アルバイトを含めた総労働者数。必要に応じてフルタイム換算(FTE換算)することもあります。
【例】ある会社のデータ
・営業利益:5,000万円
・人件費:2億円
・減価償却費:3,000万円
・支払利息・賃借料:1,000万円
・従業員数:100人
この場合、付加価値額は
5,000万円 + 2億円 + 3,000万円 + 1,000万円 = 2億9,000万円
付加価値労働生産性は
2億9,000万円 ÷ 100人 = 2,900万円/人
つまり、1人あたり年間2,900万円の付加価値を生み出していることになります。
付加価値額の算出ステップ
付加価値額は、企業の経済活動によって新たに生み出された価値を示す重要な指標であり、その算出は以下の手順で行われます。まず、企業の財務諸表の中でも特に損益計算書(P/L)を参照します。
付加価値額を求める基本的な計算式は、「営業利益 + 人件費(給与、賞与、福利厚生費)+ 支払利息・賃借料(状況に応じて加算)+ 減価償却費」です。
損益計算書における各項目の位置づけを確認すると、営業利益は売上総利益から販売費および一般管理費を差し引いた、企業の主要な営業活動による利益を示します。人件費は、従業員に支払われる給与、賞与、社会保険料などを含み、通常は販売費及び一般管理費に計上されます。
支払利息・賃借料は、借入金の利息や固定資産の賃借料であり、営業外費用として計上されますが、付加価値額の計算に含めるかどうかは分析の目的によって判断されます。減価償却費は、固定資産の価値の減少分を費用として計上するもので、販売費及び一般管理費に含まれます。
具体的な算出にあたっては、最新の損益計算書を入手し、これらの各項目の金額を丁寧に抜き出すことから始めます。そして、上記の計算式にこれらの数値を当てはめることで、付加価値額を算出します。
財務諸表の項目とこのように紐付けて計算することで、付加価値額の構成要素が明確になり、企業の生産性や収益性をより深く理解するための分析が可能となります。
実践で使える計算式と数値の読み方
付加価値労働生産性の計算式は以下の通りです。
【計算式】
付加価値労働生産性 = 付加価値額 ÷ 従業員数
※付加価値額の求め方
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 支払利息・賃借料(場合による)
この数値を見ることで、従業員1人あたりがどれだけの価値を企業にもたらしているかを測ることができます。
一般的な業種ごとの付加価値労働生産性(年間、1人あたり)は次のような目安となります。
業種 | 付加価値労働生産性(目安) |
製造業 | 800万円~1,200万円 |
情報通信業 | 1,200万円~2,000万円 |
金融・保険業 | 1,500万円~3,000万円 |
建設業 | 900万円~1,300万円 |
小売業・サービス業 | 500万円~900万円 |
医療・福祉 | 400万円~700万円 |
自社の位置付けを評価するためには、下記のような方法をとると良いでしょう。
1.自社の付加価値額と従業員数を使って、付加価値労働生産性を算出します。
2.業種別の標準範囲と比較し、自社の位置を把握します。
- 標準範囲より上 → 生産性が高い(効率的な経営)
- 標準範囲内 → 平均的な水準(改善余地あり)
- 標準範囲より下 → 生産性が低い(業務効率や付加価値向上施策が必要)
3.改善策を検討する際は、売上拡大、コスト削減、業務プロセスの見直し、人材育成などを総合的に検討します。
この評価を定期的に実施することで、経営の健全性や競争力を定量的に把握できるようになります。
業界別の付加価値労働生産性の目安と比較
業界 |
平均付加価値労働生産性(年間・1人あたり) |
製造業 | 約1,000万円 |
建設業 | 約1,100万円 |
情報通信業 | 約1,700万円 |
金融・保険業 | 約2,200万円 |
卸売業 | 約900万円 |
小売業 | 約600万円 |
サービス業(宿泊・飲食除く) | 約700万円 |
医療・福祉 | 約500万円 |
運輸・郵便業 | 約900万円 |
付加価値労働生産性は、業界のビジネスモデルや付加価値の生み出し方によって大きな違いがあります。
・高い業界(情報通信業、金融・保険業)
これらの業界は、知識や技術、資本力による付加価値創出が中心であり、少人数でも高い成果を出せる傾向にあります。またデジタル化が進んでおり、業務効率が非常に高いのも特徴です。
・中程度の業界(製造業、建設業、運輸業)
製造や建設、輸送といった「モノ」や「サービス」を提供する業種では、一定数の労働力が必要なため、生産性は中間的な水準にあります。ただし、最新設備の導入やDX推進により、さらなる向上が期待されています。
・低めの業界(小売業、サービス業、医療・福祉)
人対人の接客やサービス提供を中心とする業界では、付加価値を一人で大きく伸ばしにくいため、労働集約的な構造になりやすく、生産性は相対的に低い傾向です。しかし、IT導入や業務プロセス改善による底上げが重要課題となっています。
建設業界の生産性の特徴
建設業における付加価値は、プロジェクトごとの受注から引き渡しまでの各工程で生み出されます。主な流れは以下の通りです。
1.受注活動
顧客ニーズの把握、提案設計、入札・契約締結に至るまでの営業活動で、プロジェクトの方向性と収益性が決定します。
2.設計・計画
建築設計や施工計画を立案し、工期・コスト・品質を最適化。設計段階での工夫(VE=Value Engineering)により、付加価値の向上が図られます。
3.施工管理
実際の建築作業において、品質・安全・工程・コスト管理を徹底。無駄を省き、効率的に施工することで付加価値が高まります。
4.完成・引き渡し後フォロー
竣工後もアフターサービスやメンテナンス契約を通じ、顧客満足度を高め、長期的な収益を生み出します。
建設業では、現場ごとに条件が異なるため、プロジェクト単位で最適なマネジメントが求められます。
付加価値労働生産性を高める方法
付加価値労働生産性を高めるためには、単なるコスト削減にとどまらず、企業全体の付加価値創出力を高めるための多面的な施策が必要です。ここでは、効果的な改善施策を5つ挙げ、それぞれ具体的な実施方法についてご説明いたします。
まず第一に、業務プロセスの見直しを行うことが重要です。現場の業務フローを洗い出し、無駄や重複を可視化した上で、標準化や自動化を推進します。たとえば、ペーパーレス化の推進や、作業のデジタル管理によって、事務作業にかかる工数を削減し、本来の付加価値活動へ集中できる時間を確保します。
次に、従業員一人ひとりのスキルアップを支援することが効果的です。業務に直結する資格取得支援や、リスキリング(新たなスキル習得)プログラムを導入し、個々の生産性を底上げします。
具体的には、社内研修の充実、eラーニングの活用、メンター制度の導入などが挙げられます。これにより、現場で即戦力となるスキルの習得が促進されます。
第三に、目標管理制度(MBO)やOKRを取り入れ、成果志向の組織文化を醸成します。組織全体と個人目標を連動させることで、各自が自らの役割と成果に責任を持つ意識を高めることができます。
定期的な進捗確認ミーティングや1on1面談を通じて、目標の柔軟な見直しとフィードバックを行い、モチベーションの維持向上にもつなげます。
ITツール活用による改善方法
さらに、ITツールやテクノロジーの積極活用も欠かせません。たとえば、業務管理ツール(Asana、Trello)やコミュニケーションツール(Slack、Teams)を導入することで、情報共有やタスク管理を効率化し、非効率な会議や報告作業を削減できます。
最近ではAIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入も進んでおり、定型業務の自動化により、より高付加価値な業務へのシフトが可能になります。
成功企業に学ぶ生産性向上のポイント
生産性向上に成功した企業の事例をいくつかご紹介し、共通するKey Factorを抽出して説明します。
まず、トヨタ自動車は「カイゼン(改善)」活動を通じ、現場主導で業務のムダを徹底的に排除し、生産性を飛躍的に高めました。小さな改善を積み重ねる文化が、全社的な高付加価値体制を築いています。
リクルートグループでは、OKR(Objectives and Key Results)を取り入れ、全社員が目標と成果を可視化し、迅速にPDCAサイクルを回すことで、組織のスピードと柔軟性を確保しています。
また、サイボウズ株式会社は、個人の働き方に合わせた柔軟な勤務制度を整備し、従業員満足度を高めた結果、離職率を大幅に低下させるとともに、生産性も向上させました。
これらに共通するKey Factorは、「現場主導の改善文化」「目標の見える化」「柔軟な働き方の推進」という点です。単なる制度導入にとどまらず、組織文化まで変革していることが成功の要因と言えます。
即実践できる改善事例
すぐに着手できる生産性向上施策を、企業規模別に整理してご紹介します。
【小規模企業向け】
・業務の棚卸しと優先順位付け(タスクの見える化)
・チャットツール(Slack、Chatwork)の導入による情報共有の迅速化
・業務マニュアルの整備による標準化
【中規模企業向け】
・定例ミーティングの短縮・ペーパーレス化
・ワークフローシステムの導入による承認プロセスの簡素化
・社内イントラネットによるナレッジ共有の仕組み構築
【大規模企業向け】
・部門横断プロジェクト(タスクフォース型チーム)の立ち上げ
・AI・RPA導入による定型業務の自動化
・リモートワーク体制の本格整備と運用ルールの明確化
規模に応じた施策を選定し、すぐに試行導入することが生産性向上への第一歩となります。
組織変革のことならモチベーションクラウド
リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560社、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました
・業績が上がらず、組織にまとまりもない
・いい人材の採用や育成が進まない
・給与や待遇への不満が挙がっている
といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。
▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら
まとめ
付加価値労働生産性は、単なる効率化を超え、企業の持続的成長を支える基盤となる指標です。業界特性に応じた目標設定と、現場に根ざした改善活動を組み合わせることで、確実な向上が期待できます。
今後の経営戦略においては、従業員一人ひとりの付加価値創出を最大化するための仕組み作りが不可欠です。継続的なモニタリングと柔軟な施策の見直しを通じ、付加価値労働生産性の向上に取り組みましょう。