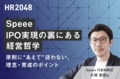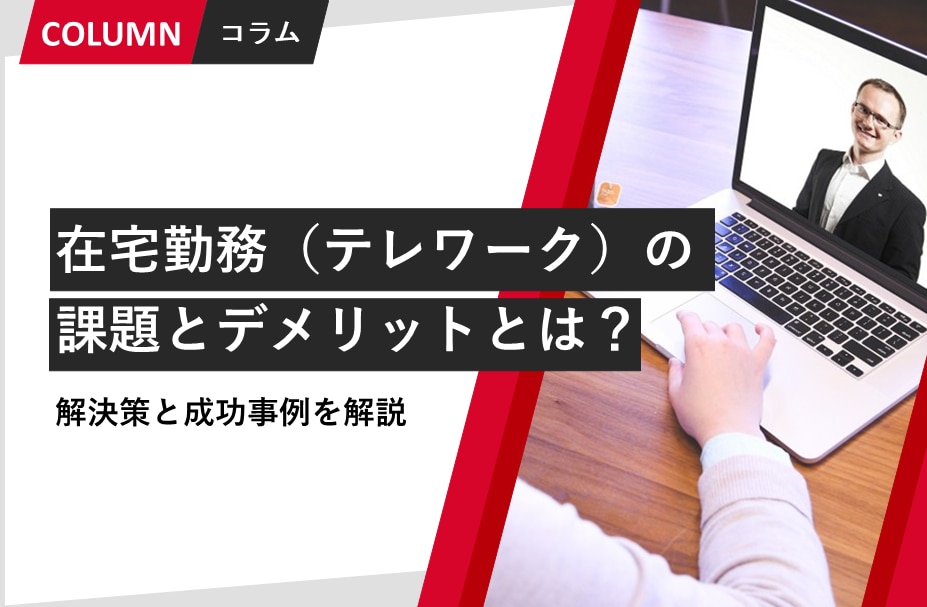
在宅勤務(テレワーク)の課題とデメリットとは?解決策と成功事例を解説
昨今、働き方改革やコロナウイルスの流行により、多くの企業で導入が進んだ「在宅勤務」。オフィスに行かずに仕事をすることで、業務内容やコミュニケーションをこれまで通りに行うことは難しくなりました。
在宅勤務によって得られる果実を大きくするには、そのための対策が必要です。在宅勤務の導入によって発生するメリットやデメリット、そしてその対策について考えていきましょう。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 人事が知っておくべき「働き方改革」の内容とは?その実現方法についても独自の視点で解説!資料はこちら
在宅勤務(テレワーク)の現状
テレワークの形態
そもそもテレワークとは、「tele=離れた場所」と「work=働く」を組み合わせた言葉で、デジタルツールを利用した時間や場所にとらわれない自由な働き方のことを指します。テレワークと一口に言っても、働く場所や環境の違いで細かく分類することができます。
代表的な分類の1つ目としては、従業員の自宅で勤務をする「在宅勤務」、2つ目に、取引先のオフィスや移動中の車内や駅、カフェなどで働く「モバイルワーク」、3つ目にコワーキングスペースやシェアオフィス、レンタルオフィスなどの、専門の事業者が提供している施設で勤務をする「サテライトオフィス勤務」があります。
厚生労働省が推進するワークスタイル「テレワーク」
新型ウイルスの流行によって一層注目度を増しているテレワークですが、厚生労働省も新たなワークスタイルとしてテレワークを推進しています。
厚生労働省がテレワークを推奨している目的としては、少子高齢化に伴う労働人口の減少、育児や介護との両立などの働くニーズの多様化に応えるための「働き方改革」の一環としてテレワークを提唱しています。
厚生労働省のホームページには、テレワーク導入に関する相談窓口、助成金や利用できる制度、セミナー情報がまとまっており、テレワークの導入を考える事業者は一度目を通してみるとよいでしょう。
テレワーク導入による企業の課題とデメリット
テレワーク導入に伴い企業が直面する主な課題やデメリットについて、代表的な5つの観点から解説します。
コミュニケーション不足
テレワークでは対面での会話が減少するため、業務連絡や意思決定に時間がかかる、メンバー間の信頼関係が築きにくいといったコミュニケーション課題が発生しやすくなります。雑談や偶発的な会話の機会も減り、情報共有の偏りや孤独感の増加にもつながります。
SlackやZoomなどのチャット・オンライン会議ツールの活用だけでなく、定期的な1on1やバーチャル朝会の導入が重要です。
セキュリティの問題
テレワーク環境では、従業員が自宅やカフェなどで業務を行うことが多くなるため、社内ネットワークと比べて情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。
特に、個人端末の利用やWi-Fiの安全性が確保されていないケースでは、重大なセキュリティ事故につながる可能性があります。また、クラウドサービスの導入拡大により、アクセス権管理の煩雑さも課題です。
このようなリスクに対応するためには、VPNや端末認証、アクセス制限などのセキュリティ対策を強化するとともに、従業員へのITリテラシー教育も重要になります。情報セキュリティポリシーの明確化と定期的な見直しが、安全なテレワーク運用の鍵を握ります。
労務管理の難しさ
テレワークでは、従業員の勤務状況を把握しにくくなるため、労働時間の過不足や勤怠の曖昧さが問題になります。特に、長時間労働やサービス残業の温床になりやすく、メンタルヘルスの悪化を招くリスクもあります。また、労災認定の判断が難しくなるケースも存在します。
対策としては、クラウド型勤怠管理システムや打刻アプリの導入が有効です。加えて、業務量の可視化や作業報告のルール化、マネージャーによる定期チェックなど、明確な労務管理体制が必要です。柔軟な働き方を促進しつつ、法令遵守と従業員保護のバランスを取ることが求められます。
評価体制が整っていない
テレワーク環境では、上司が部下の業務プロセスや働きぶりを直接確認できないため、従来の評価方法が機能しづらくなります。結果として、評価が曖昧・主観的になりやすく、社員のモチベーション低下や不満につながる恐れがあります。
また、成果主義に偏りすぎると、チーム貢献や協働姿勢などの定性的評価が軽視されることもあります。
この課題を解消するには、目標設定の明確化とプロセス評価の導入が重要です。OKRやMBOといったフレームワークを活用し、上司と部下の定期的な1on1を通じて進捗確認とフィードバックを行うことで、公平性のある評価制度が実現できます。
テレワーク時代に適した「透明性」と「納得感」のある制度設計が必要です。
コストがかかる
テレワーク導入には、環境整備に伴う初期投資や継続的な運用コストが発生します。たとえば、ノートPC・モバイルWi-Fiの貸与、セキュリティソフトの導入、勤怠管理システムやビデオ会議ツールのライセンス料などが挙げられます。
また、従業員の自宅勤務に関する通信費・光熱費補助も検討対象となるケースがあります。
ただし、オフィス維持費や通勤手当の削減といったコストメリットもあるため、全体的な費用対効果を見極めた運用が求められます。
テレワーク導入による従業員の課題とデメリット
テレワークの普及により、従業員が直面する代表的な課題や働き方のデメリットについて整理し、対処法のヒントも紹介します。
生産性の低下
テレワークでは業務環境が自宅となるため、オフィスに比べて集中しづらい状況が発生しやすくなります。たとえば、家族や生活音による中断、仕事スペースの不備、設備の不足などが原因で生産性が低下することがあります。
また、タスク管理や進捗の自己管理が苦手な人にとっては、業務の遅延や優先順位の混乱も起こりやすいです。これを防ぐには、明確なスケジュール管理や集中できる環境整備、業務の可視化ツールの導入が有効です。
仕事とプライベートの切り替えができない
テレワークでは通勤がなくなることで時間に余裕ができる反面、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。
特にワンルームや個室のない環境では、「常に仕事モードが続いてしまう」「つい働きすぎてしまう」「オン・オフの切り替えができず気持ちが休まらない」といった悩みが多く報告されています。
この状況が続くと、心身の疲労が蓄積し、メンタル不調やモチベーションの低下につながる恐れがあります。対策としては、「仕事専用のスペースを確保する」「業務開始・終了時刻を明確に区切る」「服装や音楽などで切り替えの儀式をつくる」などの工夫が効果的です。
また、企業側が休憩取得を促進する仕組みを設けることも、従業員の健康維持に役立ちます。
コミュニケーションの取りにくさ
対面での何気ない会話や相談がなくなることで、テレワークでは上司・同僚とのコミュニケーションが希薄になりやすくなります。特に新人や中途入社者は、周囲との関係構築に時間がかかる傾向があり、孤独感や不安を抱えがちです。
これにより、情報共有の遅れや誤解の発生、心理的安全性の低下といった問題も発生します。
こうした課題に対しては、定例のオンライン会議、チャットでの雑談チャンネル、1on1ミーティングの実施が有効です。コミュニケーションの質と量の両方を意識することが求められます。
テレワークの課題に対する解決策
テレワークに伴う課題を乗り越えるための、企業や従業員が実践できる具体的な対策について解説します。
コミュニケーションツールを導入する
テレワークでは対面機会が減少し、情報共有やチーム内の連携が弱まりがちです。これを補うには、チャット(SlackやChatwork)、ビデオ会議(ZoomやTeams)などのコミュニケーションツールの導入が効果的です。
リアルタイムのやり取りを通じて、業務の進捗や困りごとを素早く共有できるだけでなく、ちょっとした雑談や感情の共有も行えるため、孤立感の防止にもつながります。
さらに、1on1や朝会など定期的な対話の機会を設けることで、心理的安全性の向上やチームの結束力強化にも寄与します。
クラウドシステムを活用する
業務の場所を問わず進めるためには、社内の情報や業務環境をクラウド化することが有効です。
クラウド型の勤怠管理システムやワークフロー、グループウェア、ファイル共有ツール(Google Workspace、Microsoft 365など)を活用することで、社外からでもスムーズに業務が遂行できます。
これにより、紙ベースでのやりとりや出社を前提とした業務フローを見直すことができ、生産性や業務の透明性も向上します。また、業務プロセスの可視化によって、マネジメント層は進捗状況を把握しやすくなり、部下へのサポートや指導も迅速に行えます。
一方で、セキュリティ対策の強化も同時に求められるため、多要素認証やアクセス制限、VPNの整備といった施策もあわせて導入する必要があります。
評価制度の見直しや意識改革
テレワーク環境では「働いている姿が見えない」ことから、従来の出社ベースの評価制度が機能しにくくなります。そのため、成果やプロセスを定量的に評価できる制度への見直しが不可欠です。
目標管理制度(MBO)やOKRの導入により、達成度合いに基づいた公正な評価が可能になります。また、マネージャー側も評価基準を明確にすることで、評価の属人化を防ぐことができます。
あわせて「時間ではなく成果を見る」という意識改革を全社的に進めることで、柔軟な働き方の中でも公平で納得感のある評価が実現されます。
テレワークの課題を解決し成功事例
テレワーク導入により生じた課題に対して、企業がどのように取り組み、乗り越えたかを示す成功事例を紹介します。業種や規模の異なる2社の具体的な取り組みを通して、導入のヒントを得られます。
株式会社リクルートホールディングス
リクルートホールディングスは、パンデミック初期から迅速にテレワーク体制へ移行し、約90%以上の社員が在宅勤務を継続できる環境を整えました。
コミュニケーション不足への対応としては、オンライン上での雑談や朝会の導入により、チームの結束力を維持。また、社内に専任の「リモートワーク支援チーム」を設置し、困りごとや不安を随時吸い上げ、制度改善に活かしています。
さらに評価制度も成果ベースに刷新し、「見えない働き方」に対応。目標設定と定期的なフィードバックを徹底し、従業員満足度とパフォーマンスの両立に成功しました。
結果として、離職率の低下や業務効率の向上を実現し、柔軟な働き方を推進する企業ブランドの強化にもつながっています。
ヤフー株式会社(現:LINEヤフー株式会社)
ヤフーはテレワーク制度の導入において先進的な取り組みを進め、2020年以降「どこでもオフィス制度」を開始。居住地を原則自由とし、全国どこからでも働ける柔軟な働き方を実現しました。
課題となる業務管理や労務管理については、クラウドベースの業務ツールや人事管理システムをフル活用。コミュニケーションにはSlackやZoomを用い、定期的な1on1ミーティングを制度化することで、上司と部下の信頼関係を維持しました。
また、心理的安全性を確保する取り組みとして「バーチャル社内カフェ」などの工夫も施され、従業員の孤独感軽減とエンゲージメント向上を実現しています。
同社ではテレワーク導入後も高い生産性を維持し、採用力・離職防止・地域多様性の促進といった多方面において成果を上げています。
よくある質問
在宅勤務・テレワークに関するよくある疑問や悩みに対し、簡潔にわかりやすく回答します。企業担当者・従業員双方に役立つ情報をまとめています。
在宅勤務の課題は?
在宅勤務の主な課題には、コミュニケーションの希薄化、評価の不公平感、勤怠管理の難しさ、仕事とプライベートの境界が曖昧になることなどが挙げられます。
特に、情報共有の不足によるミスや、上司・部下間の信頼構築が難しくなる点は、多くの企業で問題視されています。また、自宅環境による集中力の低下や孤独感の増加も、従業員のストレス要因となります。
これらの課題には、ツールの導入、制度設計の見直し、マネジメントの強化が必要です。
テレワークのメリットとデメリットは?
テレワークのメリットには、通勤時間の削減、柔軟な働き方の実現、育児や介護との両立がしやすい点などがあります。企業側にはオフィスコストの削減、従業員満足度向上による定着率アップの効果も見込めます。
一方でデメリットとしては、コミュニケーション不足や業務の属人化、情報漏洩リスク、評価の難しさが課題となります。効果を最大化するには、目的に応じた制度設計と適切なIT環境の整備が不可欠です。
まとめ
在宅勤務やテレワークは、働き方の多様化を実現する手段として急速に普及しましたが、一方でコミュニケーションや評価制度、セキュリティなど様々な課題も浮き彫りになっています。
企業がこの制度を成功に導くためには、単なる勤務形態の変化ではなく、組織全体の仕組みや文化の見直しが求められます。ツールの導入や制度改革、マネジメントスキルの強化により、柔軟で持続可能な働き方を実現することが鍵となります。