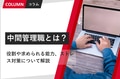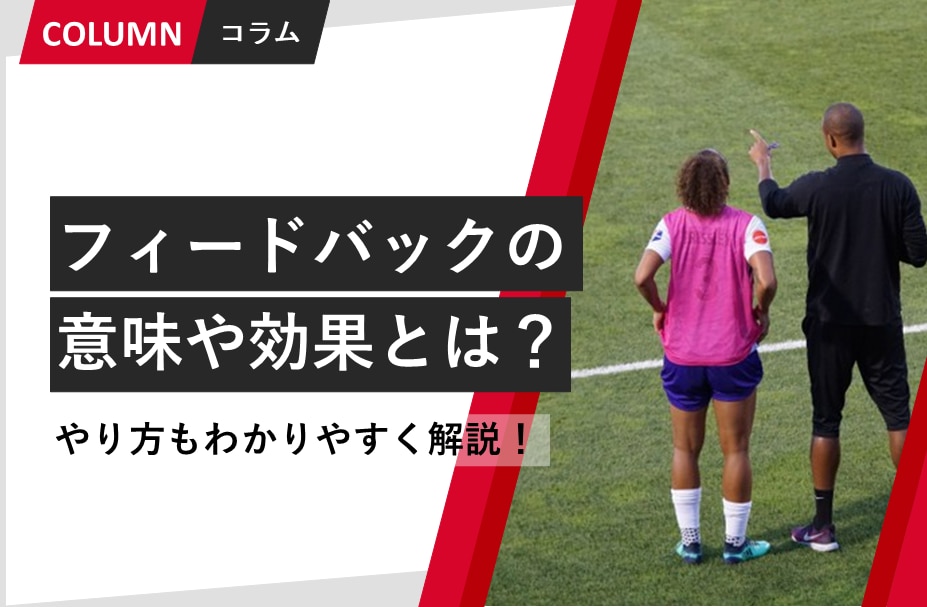
フィードバックの意味や効果とは?やり方もわかりやすく解説!
フィードバックは、部下の成長やパフォーマンス向上のために不可欠なアプローチです。適切なフィードバックをおこなうことで部下の改善を促すとともに、仕事に対するモチベーションアップを図ることができます。
その結果、部下のパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性向上が期待できます。管理職のなかには「自分のフィードバックは間違っていないだろうか?」といった不安をお持ちの方も多いでしょう。
そこで今回は、フィードバックの意味や効果、具体的な手法などについて解説していきます。
▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
目次[非表示]
フィードバックとは?
フィードバック(英語:feedback)とは、日本語では「反応」「意見」などと言い換えられるのが一般的です。小学館のデジタル大辞泉では、「顧客や視聴者など製品・サービスの利用者からの反応・意見・評価。また、そうした情報を関係者に伝えること」と定義されています。
フィードバックという言葉の使い方としては、以下のような例文が考えられます。
・現場からのフィードバックを設計に反映させる。
・アンケートの結果を担当部門にフィードバックする。
ビジネスにおけるフィードバック
フィードバックという言葉の本来の意味は「反応」や「意見」ですが、ビジネスにおいては「成果を評価したり、課題を指摘したり、改善のためのアドバイスをしたりすること」を言います。フィードバックは、上司から部下に対しておこなわれるのが一般的です。
上司は、部下が成果をあげているのであれば良い点を称賛し、誤った方向に進んでいるのであれば改善点を示し、軌道修正を図ります。適切なフィードバックをおこなうことで、効果的に部下の成長を促すことができます。
フィードバックの重要性とは
上司から部下に対してフィードバックがおこなわれていないと、部下は「上司は自分に関心がない」「期待されていない」「放置されている」などと感じるようになります。その結果、仕事に対するモチベーションや責任感を失い、パフォーマンスが低下するおそれがあります。
また、フィードバックがないと部下は自分の仕事の評価や、組織への貢献度合いを知ることができません。そのため、自分の強みや改善点が分からず、スキルや能力の向上が遅れてしまいます。部下のスムーズな成長を促すためには、こまめなフィードバックが不可欠です。
人材教育でのフィードバックの意味と目的
人材教育におけるフィードバックは、個人の成長と職務の効率向上を目的としています。これには、具体的な行動や成果に対して、正確かつ建設的な情報を提供することが含まれます。
フィードバックは双方向のコミュニケーションを促し、受け手が自身の行動や成果を客観的に評価し、改善点を自ら見つけ出す機会を提供します。また、励ましや認識の共有も重要な役割を果たし、モチベーションの向上や職場のポジティブな環境作りに貢献することが期待されます。
人事評価でのフィードバックの意味と目的
人事評価におけるフィードバックは、従業員の業務遂行能力と成果に基づく評価を伝え、その結果をもとに個人の成長と組織の発展を支援することを目的とします。このプロセスでは、具体的な成果や改善点に焦点を当て、正直かつ建設的な情報を提供します。
フィードバックは、従業員が自己認識を高め、キャリア目標に向けて具体的な行動計画を立てるための基盤を作ります。また、明確な目標設定と期待管理を通じて、従業員のモチベーションを向上させ、職場の生産性を高める効果も期待されます。
▼人事評価制度について詳しくはこちら
人事評価制度とは?役割と目的やメリットデメリットを事例をあわせて解説
フィードバックの2つの方向性
フィードバックの方向性は、大きく「ポジティブフィードバック」と「ネガティブフィードバック」に分けることができます。
①ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、肯定的なフィードバックのことを言います。優れた成果をあげた部下や、模範となる行動をした部下に対して肯定的な評価をおこない、称賛することがポジティブフィードバックです。
人は良いパフォーマンスが評価されることで、それを維持・向上させようとする心理が働きます。ポジティブフィードバックをすることで、部下のモチベーションや自己肯定感が高まり、継続的な成長をサポートすることができます。
②ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックとは、批判的なフィードバックのことを言います。目標を達成できなかった部下や、間違った方向に進んでいる部下に対して批判的な評価をおこなうのがネガティブフィードバックです。
仕事がうまくいかないとき、その原因を把握できていない人も多くいます。このような部下に対してネガティブフィードバックは有効であり、不足しているスキルを指摘したり、誤った行動を正したりすることでパフォーマンスの改善を促していきます。
フィードバックの効果・メリット
フィードバックの効果・メリットについてご説明します。
パフォーマンスの向上
フィードバックをおこなうメリットとして大きいのが、部下のパフォーマンス向上や目標達成が期待できることです。「頑張っているけど成果が出ない」という部下は、間違った方向に努力しているケースが多々あります。
このような場合、フィードバックによって部下の行動を改善させることが重要です。的確なフィードバックができれば、部下は自らの行動を見直し、仕事の効率やクオリティの向上につなげることができます。
また、フィードバックを通して期待を伝えることで、部下は自分がやるべきことを明確にできるため、目標達成に近付くことができます。
スキルアップや成長
フィードバックは、部下のスキルアップや成長につながるアプローチです。弱みを克服し、強みを伸ばすことが成長への近道ですが、特に若手のうちは自分の強み・弱みを正しく認識できていない人も多くいます。
そのため、上司がフィードバックを通して客観的な視点から部下の強み・弱みを示してあげる必要があるのです。
的確なフィードバックができれば、部下は自らのスキル・能力を客観視することができ、自らの成長のために正しいアクションプランを立て、それを実行できるようになるでしょう。
モチベーションやエンゲージメントの向上
フィードバックの効果・メリットとして忘れてはいけないのが、部下のモチベーションやエンゲージメントの向上につながることです。特に、ポジティブフィードバックによって称賛を受けることで、部下は仕事に対する自信を深め、モチベーションを高めることができます。
また、フィードバックを通して仕事の意義を伝えることができれば、部下のやりがいや貢献意欲が喚起され、エンゲージメントの向上にもつながります。モチベーションやエンゲージメントが高い部下が増えれば、組織全体として大きなパフォーマンスアップが見込めるでしょう。
関係性の強化
フィードバックは、上司・部下間のコミュニケーションを促進し、関係性を強化するのに大いに役立ちます。フィードバックを受けた部下は、自分に不足していることや自分に期待されていることを明確に認識したうえで業務に臨むことができます。
上司は、部下の課題や困りごとを理解したうえで必要なサポートを提供することができます。こまめなフィードバックをすることでコミュニケーションの品質が向上するため、部下の誤解や不満が減少し、上司と部下はより建設的な関係性を築くことができるでしょう。
フィードバックの手法・フレームワーク
フィードバックをおこなう際に活用できる手法・フレームワークについてご説明します。
サンドイッチ型フィードバック
サンドイッチ型フィードバックとは、肯定→指摘→再度肯定という順番で伝えるフィードバック手法です。
部下やチームメンバーに対して、改善点を伝えやすくする効果があります。
【具体的な手順】
- 肯定的なコメントを伝える→ 「〇〇の進め方は素晴らしかったです!」
- 改善が必要なポイントを指摘する→ 「ただ、締め切り管理の部分では、少し注意が必要です。」
- 最後に再度ポジティブなコメントを加える→ 「全体としては、着実に成長しています。この調子で頑張ってください!」
【メリット】
- 相手の心理的防御を下げ、素直に受け入れやすくなる
- 改善点もポジティブに伝えられる
- モチベーションを下げずに改善行動を促せる
特に、フィードバック慣れしていない若手社員への対応に効果的な手法です。
ペンドルトン型フィードバック
ペンドルトン型フィードバックは、相手の主体性を尊重しながら進める対話型のフィードバック手法です。
「相手の振り返り」→「フィードバック」→「相互確認」という流れで行います。
【具体的な手順】
- まず相手に自己評価をさせる→ 「今回の仕事でうまくいった点は何だと思いますか?」
- 良かった点をフィードバックする→ 相手の自己評価を肯定しながら、プラスの視点を加える。
- 改善点を質問で引き出す→ 「さらに良くするためには、何ができると思いますか?」
- 改善案を一緒に考える→ 解決策を押し付けず、本人に考えさせるスタイルをとる。
【メリット】
- 相手の内省を促進し、自己成長につなげられる
- 上司・部下間の信頼関係が強化される
- 自発的な改善行動を引き出しやすい
教育・育成を重視する場面に非常に向いているフィードバック手法です。
FEED型フィードバック
FEED型フィードバックは、「Fact(事実)」→「Example(具体例)」→「Effect(影響)」→「Different(変更点・改善点)」の4段階で進めるフィードバックです。FEED型フィードバックの分かりやすい具体例をご紹介します。
・Fact:昨日のプレゼンテーションでは、資料にいくつかの誤りがありました。
・Example:たとえば、6ページのデータは過去の数値になったままでした。
・Effect:そのため、クライアントの誤解を招いたおそれがあります。
・Different:次回のプレゼンテーションでは情報の正確性を担保するため、前日までに必ず上長のチェックを受けてください。
SBI型フィードバック
SBI型フィードバックは、「Situation(状況)」→「Behavior(行動)」→「Impact(影響)」の3段階で進めるフィードバックです。SBI型フィードバックの分かりやすい具体例をご紹介します。
・Situation:今日のチームミーティングでは、
・Behavior:Aさんの発言がほとんどなく、他のメンバーからの質問に対する回答も不十分なものでした。
・Impact:他のメンバーも腑に落ちない表情をしていましたし、何より、あのような態度ではチーム全体のモチベーションに悪影響が及びます。次回以降、Aさんにはもっと積極的なコミュニケーションを期待しています。
KPT型フィードバック
KPT型フィードバックは、「Keep(継続しておこなうこと)」→「Problem(うまくいかなかったことや今後はやめること)」→「Try(今後新しくおこなうこと)」の3段階で進めるフィードバックです。KPT型フィードバックの分かりやすい具体例をご紹介します。
・Keep:今回のプロジェクトでは、Aさんのデータ分析のスキルが存分に活かされていました。今後も、そのスキルを活かしてデータドリブンな意思決定をしていきましょう。
・Problem:一方で、今回のプロジェクトは全体のスケジュールに遅延が生じてしまいました。メンバー間での情報共有が不足していたことが原因なので、今後は注意を払ってください。
・Try:今後、プロジェクトの進捗を可視化するためにプロジェクト管理ツールを導入してみてはどうでしょうか。ツールを使えば、メンバー間でより綿密な情報共有ができると思います。
フィードバックを効果的に行うには
フィードバックを効果的におこなうための7つのポイントについてご説明します。
具体的にフィードバックする
フィードバックは、できるだけ具体的な内容でおこなうことが重要です。漠然としたフィードバックでは、部下の改善を促すことはできません。
具体例や明確なシチュエーションを挙げることで、部下は自分の弱みや課題を明確に把握できるので、どのように改善すべきかという方針を見いだしやすく、行動変容につながりやすくなります。
ポジティブフィードバックの場合も、具体的に良かったポイントを挙げることで、部下は自分の貢献を正しく認識できるので、モチベーションや自己効力感の向上につながりやすくなります。
リアルタイムにフィードバックする
フィードバックは、できるだけリアルタイムでおこなうことが大切です。フィードバックをするまでに時間が空いてしまうと、部下に「なぜ今さら、あのときの話を?」と思われてしまいます。
また、時間とともに記憶も薄れるので、フィードバックを受けてもピンとこない場合もあるでしょう。記憶が鮮明なうちにフィードバックをおこなうことで、部下に示唆を与えやすく、迅速な行動変容につながります。
行動に対してフィードバックする
フィードバックの際に上司がやってはいけないのが、部下の性格や人間性に対してフィードバックをおこなうことです。
特に、ネガティブフィードバックの対象を「人」にしてしまうと、部下は攻撃されているような気持ちになり、場合によっては「人格否定」「パワハラ」だと感じてしまうこともあります。
「人」ではなく「行動」にフォーカスしたフィードバックなら客観的な視点が生まれるため、部下の理解を得られやすくなるはずです。
理由を添えてフィードバックする
フィードバックには、できるだけ理由や根拠を添えるようにしてください。「ここが良かった」「あれがダメだった」というだけのフィードバックでは、部下は改善すべきポイントや強化すべきポイントを把握することができません。
具体的な理由や根拠を明示することによってフィードバックの説得力が増し、上司の指摘やアドバイスを受け入れやすくなります。その結果、部下の意識や行動が変わりやすくなるはずです。
親身な態度でフィードバックする
フィードバックをおこなうときの上司の態度によって、部下の「受け入れ度合い」は大きく変わってきます。高圧的な態度でフィードバックをおこなうと、部下はストレスや不信感を覚えるため、指摘やアドバイスを受け入れにくくなります。
逆に、親身な態度でのフィードバックは安心感を与え、部下は「尊重されている」と感じやすくなります。それゆえ、上司への信頼感が高まり、フィードバックの内容を素直に受け入れやすくなります。
こまめにフィードバックする
フィードバックは、できるだけこまめにおこなうことが大事です。適切な頻度は業種や職種、職場などによって変わってきますが、少なくとも週に1回はフィードバックをおこないたいところです。
人事評価面談のときに長めの時間をとってフィードバックすればいいと考える方もいると思いますが、それよりは、一言二言であってもこまめにフィードバックをするほうが効果的です。
こまめなフィードバックによって部下は迅速かつタイムリーに改善行動を起こせるため、成長スピードも早くなります。
普段から信頼関係を築いておく
フィードバックを効果的なものにするためには、普段から信頼関係を築いておくことが大前提になります。部下が上司に対して信頼を抱いている場合、フィードバックを受け入れやすく、改善点などをポジティブに捉えることができます。
上司の意図や期待が部下に伝わりやすくなるため、自然と行動変容が促され、パフォーマンスの向上につながるでしょう。また、信頼関係があると、部下のほうから気軽に質問したり相談したりすることができるので、フィードバックがより有意義な時間になるはずです。
フィードバックの効果が現れない場合の対処法
フィードバックをしてもすぐに効果が現れないことは珍しくありません。
ここでは、効果が出ない場合に取るべき具体的な対処法について説明します。
対処法① 継続してフィードバックを続ける
フィードバックの効果は、一度のやり取りでは現れにくい場合があります。
重要なのは継続的にフィードバックを繰り返すことです。
【実践ポイント】
- 定期的な面談や1on1を設定する(例:月1回)
- 小さな改善も積極的にフィードバックする
- 変化を確認できたら、すぐにポジティブに承認する
短期的な変化に一喜一憂せず、長期視点で行動変容を促すことが大切です。
特に、新しいスキルや行動パターンは定着に時間がかかるため、辛抱強いフィードバックが成功のカギとなります。
対処法② 相手に合わせて伝え方を変える
フィードバックが伝わりにくい原因のひとつに、相手とのコミュニケーションスタイルの不一致があります。
相手に合わせた伝え方を意識しましょう。
【実践ポイント】
- ロジカルな人には「データや事例」で具体的に説明する
- 感情を重視する人には「感謝や共感」を先に伝える
- 若手社員には「シンプルで分かりやすい言葉」を選ぶ
また、対面ではなくチャットやメールの方が伝わりやすい場合もあります。
相手の性格や傾向を観察しながら、フィードバック方法を柔軟にアレンジすることが効果を高めるポイントです。
対処法③ 関係性そのものを見直す
フィードバックの効果が全く見られない場合、上司・部下間の信頼関係が希薄になっている可能性も考えられます。
この場合は、まず関係性の改善に取り組む必要があります。
【実践ポイント】
- 日常的な雑談や1on1で「心理的安全性」を高める
- 業務外の相談にも耳を傾ける
- 自分自身の弱みや失敗体験も共有してみる
信頼関係が築かれていない状態では、どんなに正しいフィードバックも「攻撃」と受け取られるリスクがあります。
まずは人間関係の土台作りを優先し、そのうえでフィードバックを重ねていきましょう。
社員のモチベーション管理ならモチベーションクラウド
リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました
・業績が上がらず、組織にまとまりもない
・いい人材の採用や育成が進まない
・給与や待遇への不満が挙がっている
といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。
▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら
まとめ
上司からのフィードバックは、部下の成長の原動力になるものです。フィードバックによって部下のスキルアップや成長を促すことができれば、組織全体の生産性向上につながります。ぜひ本記事を参考に、ご自身のフィードバックを見直してみましょう。