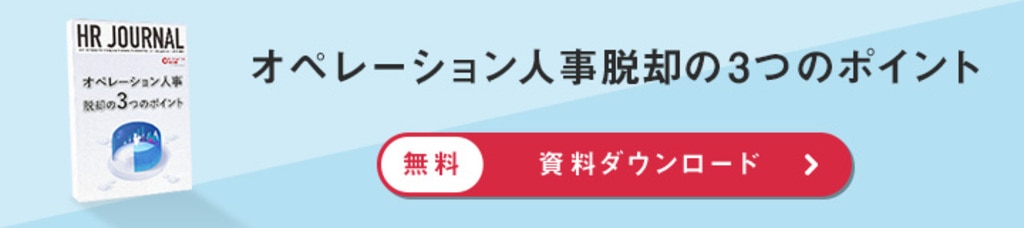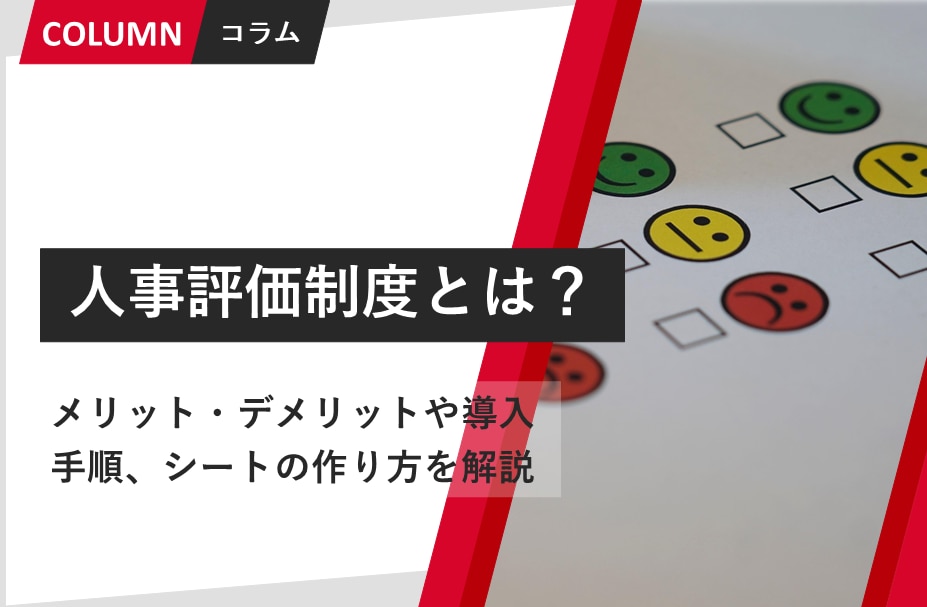
人事評価制度とは?メリット・デメリットや導入手順、シートの作り方を解説
人事評価制度は、従業員の企業への貢献度合いや本人の能力をどのように待遇に反映するのかを整理し、明文化したものです。上手く活用することができれば、従業員の成長を促進し、企業の成長にも繋がります。
しかし、お金を扱うものでもあるため、上手く活用できない場合はせっかく作っても従業員の不納得感を生み出し、反発やトラブルに繋がってしまうことも事実です。
本記事では多くの企業が気になる人事評価制度の設計から、メリットやデメリット・運用の方法等を踏まえてわかりやすくご紹介します。
▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
目次[非表示]
▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら
人事評価制度とは?3つの仕組みと機能
人事評価制度とは、組織内の従業員の業績、能力、情意(意欲や態度)を定量的・定性的に評価し、その結果に基づいて報酬や昇進などの処遇を決定するための仕組み全体を指します。この制度は、公平な処遇決定の根拠となるだけでなく、従業員の能力開発や組織目標の達成を促進する重要な経営ツールです。人事評価制度は、主に以下の3つの要素で構成されています。
等級制度
等級制度は、従業員の能力や職務、または役割の大きさに応じて社内での序列(グレード)を定める枠組みです。この制度は、昇進・昇格の基準となり、後述する評価制度や報酬制度の土台となります。等級制度は、主に以下の3つの種類に分類できます。
・職能資格制度
職能資格制度は、従業員が持つ職務遂行能力(スキルや知識)のレベルによって等級を定める仕組みです。能力が高まれば、実際の職務や役職が変わらなくても等級が上がり、それに伴って給与も上昇します。この制度のメリットは、年功序列型の運用がしやすく、従業員に長期的な育成目標を与えやすい点にあります。
一方で、能力が等級に反映されても、実務でその能力を発揮するポストが用意されない場合があり、人件費が上昇しやすいという課題もあります。
・職務等級制度
職務等級制度は、従業員が現在遂行している職務の内容や責任の大きさによって等級を定める仕組みです。職務の価値や難易度を評価し、等級と結びつけるため、「同一労働同一賃金」の原則に沿った運用が可能です。欧米企業で広く採用されており、特に専門性が明確な職種やグローバル企業に適しています。
メリットは、評価基準が職務に直結するため納得感が得られやすい一方、職務内容が変わりにくい部署では昇格の機会が限られるという特徴があります。
・役割等級制度
役割等級制度は、従業員に期待される「役割の大きさや価値」によって等級を定める仕組みです。職務等級制度と職能資格制度の中間的な特徴を持ち、役割とは「組織目標を達成するために、その人が担うべき貢献範囲」を指します。
この制度は、成果主義をベースとしつつも、職務内容の細かな定義に縛られず、変化の激しい現代のビジネス環境に柔軟に対応しやすい利点があります。等級が個人の能力や職務経験だけでなく、期待される貢献度によって決まるため、従業員の主体性や多様な働き方を促進しやすいと言えます。
評価制度
評価制度とは、上述した等級制度を元にして、企業ごとに決められた行動指標をふまえ、従業員の業務内容やその成果を評価する方法を定めた制度のことです。
個人の業績・成果といった定量的な目標と共に、行動指針の体現度合いや成長度合いといった定性的な目標も設定して評価することが多いです。
一方的な点数をつける機会ではなく、しっかり「できたこと」「できなかったこと」「次に期待すること」を企業と従業員との間ですり合わせる機会にすることで成長のサイクルを効果的に回していくことができます。
▼【定性評価】に関する記事はこちら
定性評価とは?定量評価との違いや評価方法と注意点について解説
報酬制度
報酬制度とは、評価制度に基づいて従業員にどのような「報い方」をするかを定めたものです。もちろん給与、インセンティブといった「金銭的な報酬」に反映させる方法もありますが「非金銭的な報酬」もあります。「非金銭的な報酬」は次の仕事、役割や学習機会の提供などを指します。
どのような仕事や行動に対して、どのような形態で評価し報酬を与えるかで企業ごとの特徴や色を従業員と認識を合わせることができます。
人事評価制度を導入する役割と目的
人事評価制度を導入する目的は様々ですが、主に目的とするものをご紹介します。
企業のビジョンや方針の明示
人事評価制度は、設計する過程で「企業として何を大切にするのか?」「従業員にどんなことを期待するのか?」といった企業のビジョンや目指す姿、そしてそれに向けた従業員への期待を考えることになります。
それを明文化・ビジュアル化して従業員に共有し、人事評価制度を元に日々の行動や評価を通して意識することで経営との認識を合わせることができます。
つまり、人事評価制度とは「経営から従業員に向けたメッセージ」だと捉えられます。
単なる賃金を決めるルールではなく、効果的な理念浸透の仕組みとして活用することができます。
人材配置の最適化
かつての日本では、年功序列型賃金体系や終身雇用制度が主流でした。
しかし、日本独自の雇用システムであったそれらの制度は、景気の低迷やグローバル化の促進、人材の流動化などの市場や環境の変化によって成り立たなくなりつつあります。
そこで、日本企業の多くは生き残るためにも人事評価制度の見直しにより、従来のような年功序列で賃金を決めるような方法ではなく、社員の能力や業績・成果を評価し、評価結果から昇給や昇進等の待遇に紐づけるようにしました。
それにより個々人の能力・成果やこれまでの評価結果によって、役職・役割の見直し、人材配置の最適化を図ることができるのです。
人材育成の促進
人事評価制度を上手く活用することができれば、人材の育成に繋げることができます。
評価制度の説明でも触れましたが、企業の方針に合った目標設定→軌道修正→評価(フィードバック)→次の目標設定・・・といったサイクルを回していくことで目指す組織像・人材像に即した成長を促進することができます。
また、従業員の成果や能力をふまえて、公平な評価がされ、適切に昇給や昇格がされるようになれれば、従業員もモチベイティブに働くことができるでしょう。
マネジメントの効率化
従業員のマネジメントを効率化することも、人事評価制度導入の一つの目的になり得ます。様々な人事評価制度がありますが、各従業員が上司と相談のうえで個人目標を設定し、個人目標の達成度合いによって評価をするのが一般的な形です。
このように個々の従業員が目標を設定することで、目標達成までのプロセスや進捗度合い、目標達成に向けた行動などが分かりやすくなるので、マネジメントがしやすくなります。
従業員満足度やエンゲージメントの向上
人事評価制度を導入する目的の一つになるのが、従業員満足度やエンゲージメントの向上です。
人事評価制度がない会社や、人事評価制度があっても形骸化していて最終的には年功序列で処遇・査定がおこなわれている会社は従業員の不満を招きやすく、処遇に納得できない従業員が離職してしまう可能性があります。
反対に、正当性のある人事評価制度を導入し、公平感・納得感のある処遇・査定ができれば従業員満足度やエンゲージメントの向上が期待できます。
人事評価制度を運用するメリット
では、実際に人事評価制度を導入して運用していく中でどのようなメリットを得られるのでしょうか。
企業理念・ビジョンが浸透する
重ねてにはなりますが、人事評価制度は企業理念やビジョンを示し、浸透を促すものの1つです。 会社としてどんなことを目指し、そのためにはどのような人材が集まったチーム・組織であるべきなのかを表現して伝えることができます。
特に、理念に即した行動指針を評価項目の中に入れることで直接望ましい行動を意識してもらって日々の業務にも当たってもらうことができます。
従業員のモチベーションが向上する
従業員のモチベーションの向上も大きなメリットです。 人事評価制度を上手く活用することができれば、「きちんと頑張ったこと、成果を見てもらえている」という従業員のモチベーション向上に繋げることができます。
フレデリック・ハーズバーグという心理学者が提唱した「二要理論」によると、人間の仕事における満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度が上がり、不足すると満足度が下がるものではないと言われています。
「満足」に関わる要因(動機付け理論)と「不満足」に関わる要因(衛生理論)はそれぞれ独立して存在しているということがポイントです。 まずは従業員の納得感が生まれない人事評価制度のままでは「不満足」を招いてしまうため、それを除外できる効果が期待できます。
更に、目標を達成した時や、メンバーから承認をされた時にモチベーションが向上する(動機付け要因となる)と考えられます。 明確に目標を決め、目標を達成した者に称賛の機会を提供するような場を制度設計に組み込むことで、従業員のモチベーション向上に繋げることができるのです。
(参考:「ハーズバーグの二要因論」) ▼【モチベーション】に関する記事はこちら 「モチベーションとは?代表的な理論とマネジメントのコツ」
人材スキル管理が可能になる
定期的な人事評価を通して、人材のスキルの管理をすることができます。 個々人のスキルや特性を把握する機会になるため、適切な採用や配置に活用することができ、企業における大切な人的資源を無理、無駄なく活用できるきっかけになります。
マネジメントが向いている人材、スペシャリストとして商品・サービスのクオリティを向上することが向いている人材など、多様な人材を活かすためにはある程度のモノサシを設定しておくことが効果的です。
コミュニケーションが活性化する
人事評価制度を運用する過程では、目標設定やフィードバックのために上司・部下の面談が設定されます。フィードバックの際には、上司から部下に「なぜこの評価になったのか?」ということを明確かつ丁寧に伝えることが重要です。
このような面談を通して上司・部下間のコミュニケーションが活性化すれば、信頼関係が高まり、パフォーマンスアップも期待できるようになるでしょう。
人事評価制度を運用するデメリット
もちろん、人事評価制度を運営することでメリットのみを得られるわけではありません。
人材開発の視野が狭まってしまう
人事評価制度は、もちろん自社における望ましい人材像に向けた育成を促す為、自社でしか活躍のできない型にはまった人材になる可能性も孕んでいます。 外部環境の変化により新たな事業やそれに適した人材が必要になった際に内部で確保できない場合も生じる可能性があります。
それを避けるために、詳細すぎる評価項目や期待を作らずにある程度人事評価制度自体に幅を持たせる、あえて抽象的な部分を残しておくなどの工夫をすることが大切です。
評価範囲外の業務が停滞する
目標設定の仕方にもよりますが、評価の対象ではない仕事に関しては従業員が意欲的になりにくい為、設定した評価項目以外の業務が滞る可能性があります。
もちろん、期初に完璧な目標設定を行うことは難しく、その後の事業状況では注力して欲しいことが変化することは往々にして起こりうるものです。 そのため、期中に振り返り・軌道修正の機会を設けたり、定期的に人事評価制度全体の見直しをすることが大切です。
労働意欲の低下によって生産性が低下する
人事評価制度とは、従業員の個々人の行動や成果を評価する為、高評価者と低評価者が必ず出てきます。その結果「なんで自分はあの人よりも評価が低いんだ」といったような軋轢を生み出しかねません。 そこで大切なポイントが納得感の醸成です。
しっかりと評価の理由や背景を伝えると共に次はどうすればいいのかをフィードバックを行いましょう。しっかりと「ただ悪かった」のではなく、「成長のポイントが見えた」といった状態にすることが重要です。
人事評価項目の設定方法
評価項目の設定の仕方も様々なものが存在しますが、大きくは
- 成果評価
- 能力評価
- 情意評価
といった分け方ができます。
成果評価
成果評価とは文字通り、役割に対して「創出した成果」を評価します。営業職であれば売上目標であったり、間接部署であれば社内での課題解決ができたか、改善の進捗があったかを設定します。
分かりやすく、業績への意識を強化して成果へのモチベーションを湧かせることができますが、一方で短期的な成果のみを見る傾向が多くなるため開発・チームビルディング・育成といった中長期的なものを軽視してしまう可能性もあります。
能力評価
業務を遂行する上で必要とされるスキルや知識といったものを評価するものです。「成果を出している人はどういうスキルがあるのか」を抽出して、それを身につけることを促すことができます。
また、成果が目に見えにくい管理部門の従業員を評価しやすいというメリットもあり、スキルアップへのモチベーションを高めることができます。 ただ、能力向上には一定の期間がかかる場合も多く、短期的な成果への意識も薄れることがあります。
主観・印象評価としても受け取られやすいため、成果評価と併せて設定することでバランスを取ることが大切です。
情意評価
業務遂行にあたっての意欲や姿勢を評価します。仕事に対して頑張っている人や前向きな人を評価したい際に用いられることが多い方法です。 会社として大切にしたいタイプの社員を評価しやすいというメリットがありますが、項目の設定が難しく、正確には測定しづらくなってしまいます。
しかし、チームとしての風土醸成やコミュニケーションの活発化を促すことができるため、新規入社した従業員ではある程度このような要素を取り入れることで職場への好影響を見込むことができます。
人事評価制度の導入手順
人事評価制度を導入する際の一連のステップを、現状分析からフィードバックまで7つの手順に分けて詳しく解説します。
①現状の分析
人事評価制度の導入にあたって最初に行うべきは、現行の制度や人事運用の現状を正確に把握することです。組織内で評価がどのように行われているのか、評価制度に対する従業員の満足度や不満点、業務内容との整合性などを調査・分析します。
加えて、離職率や社員のモチベーション、キャリアパスの見通しなど、制度が影響を与える各領域の現状も併せて確認する必要があります。
この段階で得られた課題や期待値を明確にすることが、以降の評価制度の設計において極めて重要な指針となります。現場の声を丁寧に拾い上げ、定量・定性の両面から現状を可視化することが成功の第一歩です。
②評価目的の設定
人事評価制度の導入では、制度の目的を明確に定義することが欠かせません。目的には、従業員のモチベーション向上、公平な処遇、能力開発、組織目標との連動などがあります。
何を達成したいのかを明文化することで、制度の設計がブレるのを防ぎ、社内での合意形成も進みやすくなります。目的が曖昧なまま進めると、制度運用後に不信感を招く恐れもあるため、導入初期にしっかりと設定しましょう。
③評価基準の策定
評価基準は、評価の公平性・納得性を左右する重要な要素です。職種や等級ごとに必要とされる成果や行動を具体的に定義し、「成果評価」「行動評価」「スキル評価」などの視点を組み合わせて策定します。
また、評価基準は定性的なものだけでなく、可能な限り数値や具体的行動に基づいて設けることが望ましいです。基準が曖昧だと評価者ごとのばらつきが大きくなり、不満や不信感を生む原因になります。
④評価項目を作成
策定した評価基準をもとに、職種や階層に応じた評価項目を具体的に設計します。例えば、「目標達成率」「チーム貢献度」「業務改善提案数」など、業務と直結した内容にすることで納得感が高まります。
策定した評価基準をより具体的に落とし込み、職種や階層ごとに求められる能力や貢献度を明確に示す評価項目を設計することが重要です。
例えば、営業職であれば「売上目標達成率」や「新規顧客獲得数」、開発職であれば「プロジェクトの納期遵守率」や「技術的な課題解決能力」、事務職であれば「業務効率化への貢献度」や「正確な事務処理能力」といった具体的な項目が考えられます。
⑤評価方法を構築
評価方法は、一般的に5段階評価が広く用いられていますが、企業の文化や評価の目的によっては、3段階、4段階、または7段階評価といったより細分化された、あるいはシンプルな段階評価を取り入れているケースもあります。
評価制度を構築する際は、評価項目(業績、能力、情意など)を明確に定義し、評価者全員が同じ基準で評価できるように、評価者研修などを実施することが極めて重要です。
⑥導入スケジュールを作成
制度の完成後は、実施に向けたスケジュールを明確に策定します。設計からトライアル導入、本番運用までを段階的に進め、各ステップに必要な準備(マニュアル作成、社内説明、評価者研修など)を計画に組み込みます。
特に初期導入期は現場の混乱を避けるため、パイロット部門での先行実施を検討するのも有効です。スケジュールの柔軟性も持たせながら、定期的な進捗確認とフィードバックを行い、制度の完成度を高めていきます。
⑦評価内容のフィードバックをする
評価の最終段階では、被評価者へのフィードバックが不可欠です。単なるスコア提示ではなく、評価の根拠や今後の成長課題、目標設定などを面談形式で丁寧に伝えることが求められます。
フィードバックは従業員の納得感を生むと同時に、今後の行動改善やキャリア形成への動機づけにもつながります。
また、評価者と被評価者の相互理解を深め、信頼関係の構築にも寄与します。定期的なフィードバック文化を根付かせることが、制度の成功に直結します
人事評価制度を補う評価手法とは
ここからは、設定した項目を評価するための手法をご紹介します。設定した評価項目によって効果的な評価手法も変わってくるので、どのような手法が自社に適していて実施がしやすいかを考えると良いでしょう。
①評価管理制度(MBO)
MBOとはManagement By Objectivesの略称であり、直訳すると「目標(Object)による管理(Management)」です。元々は経営学者であるピーター・ドラッカーが1950年代に提唱したマネジメント手法であり、有名な「もしドラ」の中でも活用されていました。
MBOは簡単に言うと、「チーム、あるいは個人ごとに目標を設定してその達成度合いを元に評価を決める方法」です。ある程度は全社の方針や目標と繋がりは持ちながら、個々人の業務内容や能力・特性を鑑みてそれぞれ目標を設定します。
そのため、例えば同じ等級の社員でも異なる目標が設定され、それぞれの達成度合いで評価されます。
そのため、各人に合わせた成果・能力目標の設定や評価が具体的に行いやすくなります。一方で、基本的に達成率で評価が行われるため「達成しやすい目標」を設定する傾向も生まれる可能性があります。
しっかりと評価者と被評価者の間で目標設定の基準を明確にしておくことが重要です。
▼【MBO】に関する記事はこちら
MBOとは?OKRとの違い、実際の運用に関するメリット・デメリットを解説
②目標管理制度(OKR)
OKR(Objectives and Key Results)は、米国のインテル社が開発した目標管理手法です。OKRの大きな目的は、すべての従業員が一丸となって高い目標を目指すことで組織の生産性を高めることです。そのため、OKRでは非常にチャレンジングな目標を掲げます。
MBOとOKRでは、そもそも目的が違います。MBOの主な目的は人事評価や査定ですが、OKRは組織の成長や生産性の向上です。MBOは、目標達成度によって人事評価をおこなうのが前提ですが、OKRの場合は人事評価や査定とは切り離して運用されるのが通常です。
また、MBOは目標に対する達成度によって評価されるので、100%を目指しますが、OKRは高い目標を設定することに意味があり、達成基準は60~70%に設定されるのが一般的です。
OKRについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>> OKRとは?Googleも採用する効果的な運用方法を解説
https://solution.lmi.ne.jp/column/6502
③コンピテンシー評価
「コンピテンシー」とは、「能力・適正」といった意味を持ちます。そのため、コンピテンシー評価は「高い成果を出すための行動を行えていたか」を評価するものです。
業界・自社内でのハイパフォーマーはどのような能力を持っているのか、どのような行動を行なっているのかを把握してそれを評価基準とするため、能力評価との相性が良いです。
また、ハイパフォーマーの行動をある程度トレースする形にもなるため業績への好影響も見込めます。
しかし、行動や特性を評価基準とするためハイパフォーマーのコンピテンシー(能力・行動)をしっかりと分析・整理をしないまま運用してしまうと期待を下回る成果に繋がってしまいます。
管理職のみで設計・評価するのではなく、同僚や第三者の意見を収集しながら作り上げ、適宜修正をしていくことが大切です。
④360度評価(多面評価・周囲評価)
360度評価(多面評価)とは、上司だけではなく、同僚、部下の複数名から、日々の職務行動を評価する評価方法のことです。
複数名によってつけられた評価を平均することによって評価のばらつきを抑え、より客観的な結果を得ることができます。これは評価される本人に対しても評価に対する納得感を高めることができます。能力・情意評価と相性が良いでしょう。
周囲からの評価を求めるため、様々な関係者からの評価を集めることになりますが、下記のような評価者、目的、優先順位での調査を推奨しています。
①上司・管理職(業務の基準の確認)
②職場メンバー・部下(実際の業務の様子を把握)
③自分(周囲の認識との相対化)
④同僚・同期(よく知る仲間からの評判)
⑤顧客・関係部署(価値の提供先からの評価)
実際の業務の様子をもとに、個々人の現状が明確にできるため、課題の抽出がしやすく、業績面の成果を補足する形で、パフォーマンスが見える化されます。
加えて、職場の連携がうまくいっているか、本人の能力が発揮できる環境か(関係性にねじれが生じていないか)どうかを判断できるという効果もあります。
一方、同一の状況を準備した上で回答ではないため、状況の単純比較はできません。また、能力やポテンシャルを評価するわけではないため、絶対的な評価や経年変化は計測できない場合が多いです。
納得感を生むための相互フィードバックの場を設けたり、職場内での風土をよくする取り組みとセットで行うことが重要です。
⑤1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が一対一で定期的に行う対話の時間を指します。これは、従来の評価面談のように過去の業績を評価・決定するためではなく、部下の成長支援とエンゲージメント向上を主な目的としています。実施頻度は週に1回から月に1回程度と高頻度で、1回あたりの時間も30分から1時間程度と比較的短いのが特徴です。
1on1ミーティングでは、上司はコーチングスキルを活用し、部下の日々の業務における課題、キャリア志向、心理的な状態について傾聴します。部下が自ら気づきを得て、目標達成に向けた行動計画や解決策を自発的に立てられるように促すことが重要です。
人事評価制度の導入手順
人事評価制度を導入するプロセスは、等級・評価・報酬等の各制度の企画・設計を行う「設計フェーズ」と、制度説明会や評価研修などで浸透を図る「運用フェーズ」の2つに分かれます。
各フェーズにおいて、下記の手順を一つ一つ丁寧に進めることが効果的です。
設計フェーズ
①現状把握
インタビューやアンケート調査を実施し、経営や現場の意見を踏まえて現行人事制度の課題を洗い出します。
②人事ポリシー策定
ビジョンや事業戦略からブレイク・ダウンして、会社の人事・組織戦略の骨子となるコンセプトを決定します。
③人事制度アウトライン設計
「人事ポリシー」に基づいて、各社の事業や組織にとって最適な人事制度の具体的内容を決定します。
運用フェーズ
⑤導入準備
分かりやすさと精緻さのバランスを検討しながら、運用に伴い必要になる手順書やマニュアルを準備します。
⑥運用サポート
評価者向けの研修や被評価者向けの説明会など、新しい人事制度への理解を深める場を設定します。
主には
- 目標設定研修(評価者向け)
- 人事制度共有会(被評価者向け)
- 評価研修(評価者向け)
- 現場フォロー(評価者向け)
- 運用改善フォロー(人事向け)
のように対象ごとに運用に向けたサポート・情報提供機会を設けることが重要です。
人事評価シートの作り方
人事評価シートは、従業員に対する評価を公正かつ効率的に行うための重要なツールです。評価シートの作成には、自社の等級制度や評価制度(職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度など)と評価要素(業績、能力、情意)が明確に連動していることが求められます。
■作り方と書き方のコツ
- 評価項目の定義と連動: 企業の経営戦略や部門目標に直結する項目を設定します。等級制度や職務記述書に基づき、「期待される役割」と「具体的な行動」が評価に反映されるようにします。特に、成果を測る「業績(MBOなど)」、プロセスを測る「能力(スキル、知識)」、仕事への姿勢を測る「情意(意欲、態度)」の3つの要素をバランスよく組み込みます。
- 評価基準の明確化: 評価者の主観が入る余地を最小限にするため、各項目について「S・A・B・C・D」といった各段階の定義を具体的かつ客観的な行動例で示します(例:「B評価のレベルは、上司の指導のもとで業務を安定して遂行できる」)。
- 記述欄の工夫: 定量的な評価だけでなく、定性的な記述欄(コメント欄)を設けます。評価者には、点数だけではなく、評価の根拠となった具体的な事実やエピソードを記入するよう徹底させます。これにより、評価の納得感を高め、次期目標設定や育成に活かすための具体的な指導ポイントを明確にできます。
- 運用のシンプル化: 評価者が過度な負担を感じないよう、項目数を絞り、記入形式を統一するなど、記入・集計が容易なシンプルな設計を心がけます。
人事評価シートのテンプレートは、厚生労働省のウェブサイトや、人事・労務管理関連のサービスサイト(例:あしたのチームのテンプレートなど)で入手できる場合があります。
人事評価シートの例文
人事評価シートの具体的な記述例文を、評価項目別に紹介します。重要なのは、曖昧な表現を避け、具体的な行動や結果に基づいたコメントを記載することです。
人事評価制度の導入・運用でよくある失敗と解決策
人事評価制度の導入・運用でよくある失敗と解決策についてご説明します。
人事評価制度の目的が浸透していない
経営陣や人事部門は人事評価制度の目的を明確に認識している一方で、評価される従業員が人事評価制度の目的を十分に理解していないまま運用されているケースも見られます。
このように、人事評価制度の目的が従業員に浸透していない場合、「なぜ、こんなに細かい目標設定をしなければいけないのだろう?」「これをやることにどんな意味があるのだろう?」といった疑問から、従業員が不信感や「やらされ感」を抱くようになり、仕事への意欲やモチベーションが低下してしまうことがあります。
人事評価制度を導入する際は、被評価者である従業員に対して人事評価制度の意義や目的を説明し、十分に理解を得たうえで運用を始めるようにしましょう。
評価基準が明確になっていない
人事評価制度の作り込みが甘く、評価基準が明確になっていないケースも見受けられます。評価基準が明確になっていないと評価者の主観が入り込みやすくなり、その結果、評価にバラツキが生まれてしまいます。
被評価者である従業員からしても、自分がどのような基準で評価されているのか分からないので不信感を覚えやすくなります。
評価に対する納得感が欠如していると、「自分のほうがあの人より頑張っているのに・・・」といった感情から、組織内の人間関係や雰囲気が損なわれてしまう可能性があります。
人事評価制度を策定する際はできるだけ明確な評価基準を設けるとともに、従業員にきちんと説明をするようにしましょう。
評価者のスキルが不足している
どんなに優れた人事評価制度を策定しても、実際に評価をおこなう評価者のスキルが低いと人事評価制度の運用がうまくいかないケースがあります。評価者は第一に、人事評価制度の目的や評価基準、会社が求める従業員の姿などをきちんと把握していなければいけません。
そのうえで、評価基準に則って、偏りなく客観的に評価をする必要があります。また、従業員に説明を求められたときに、納得のできる説明ができることも重要です。
当然のことですが、新任の管理職などは特に評価スキルに差があるので、評価者研修や説明会などで評価スキルの標準化を図るようにしましょう。
▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】
人事評価制度の運用を成功させるポイントとは
人事評価制度の運用を成功させ、望ましい成果に繋げるためにはいくつかポイントがあります。主に目標設定、評価の仕方でのポイントをご紹介します。
明確であること
評価する項目や基準はもちろんですが、評価の方法や時期といった人事評価制度の全体像が従業員の中で明確になっていることが重要です。
いつ、どのように評価が行われるのかが曖昧だと従業員もどのような行動をすれば評価に繋がるかが分からなくなってしまいます。
そうなると業績への影響はもちろん、自社への信頼感も薄れていってしまいます。しっかりと設計と運用でその曖昧さを排除できるようにしましょう。
具体性があること
目標設定、評価の仕方共に従業員が納得できるような内容でなければいけません。具体的にいつまでに何ができたら評価されるのかといった「具体的な理由」を共通認識として持っておけるようにしましょう。
特に低い評価を付ける際には「なぜこの評価なのか」「次はどうしたら良いのか」といった部分まで具体性にこだわって伝えなければ、従業員に不信感が生まれてしまい、組織の雰囲気も悪くなってしまいます。
絶対評価・相対評価を活用すること
従業員同士を比較する相対評価だけでは、パフォーマンス自体も中心・平均に寄りやすい傾向が生まれるため、絶対評価と相対評価を活用することが大切です。
一定の基準を元に各従業員が設定した目標に対する達成度を評価のベースとすることで納得感や全体のレベルの引き上げに繋がります。
ただ、昨今で社会情勢、企業を取り巻く市場環境は急に変化する場合もあるので、特に中小企業は絶対評価のみでは原資のコントロールが難しくなってしまう場合があります。
そのような場合に備えてある程度コントロールしやすい相対評価も組み合わせて人事評価制度を運用すると良いでしょう。
コーチングを活用すること
人事評価制度を運用する過程では人事評価面談がおこなわれますが、面談をより効果的なものにするためには、評価者がコーチングを活用することが重要です。
コーチングスキルに優れた評価者なら、面談を通して従業員のモチベーションアップを図ることができ、より前向きに仕事に取り組んでもらえるようになるでしょう。
コーチングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
>> コーチングとは?仕事における意味や効果的なやり方などを解説
https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c230
中小企業の人事評価の実践事例
株式会社喜久屋
東京都でクリーニング事業を営んでいる株式会社喜久屋は、140名規模で「職能等級制度」を運用しています。正社員のみではなく、パート・アルバイトにも適用することで、正社員への登用や店長へのステップアップの道筋も示してるところがポイントです。
人事評価制度を通して、従業員のステップアップへのモチベーション向上や、自社らしい社員登用も同時に実現しています。
まとめ
人事評価制度は「賃金を決めるためのルール」ではなく、「会社と従業員の認識を強烈に繋げる仕組み」だということがご理解いただけたら幸いです。
その実現のためには「納得感」をいかに生み出すかが最も重要なポイントであるため、本記事を参考に自社らしい人事評価制度をご検討ください。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
人事評価制度に関するよくある質問
Q:人事評価制度の導入率は?
2022年版の中小企業白書(※)によると、従業員数が5~20人の企業で人事評価制度を導入しているのは35.0%であるのに対し、従業員数が101人以上の企業では87.2%となっており、企業規模による差が大きいことが分かります。
なお、従業員数が21~50人の企業の導入率は57.2%、従業員数が51~100人の企業の導入率は72.5%となっています。
Q:人事評価制度は見直したほうが良い?
2022年版の中小企業白書(※)では、人事評価制度の見直し状況別に売上高増加率を調査したデータが公開されています。
「数年に1度など定期的に人事評価制度を⾒直している企業」の売上高増加率は12.8%、「定期的ではないが、10年以内に人事評価制度を⾒直したことがある企業」の売上高増加率は6.4%、「10年以上、人事評価制度を⾒直していない企業」の売上高増加率は0.2%となっています。
このデータからは、人事評価制度を導入するだけでなく、外部環境や内部環境の変化に合わせて見直していくことの重要性が分かります。
▼社員の働きがいを“見える化”して改善するクラウドサービスはこちら
※参考:中小企業庁:2022年版「中小企業白書」全文
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho.html