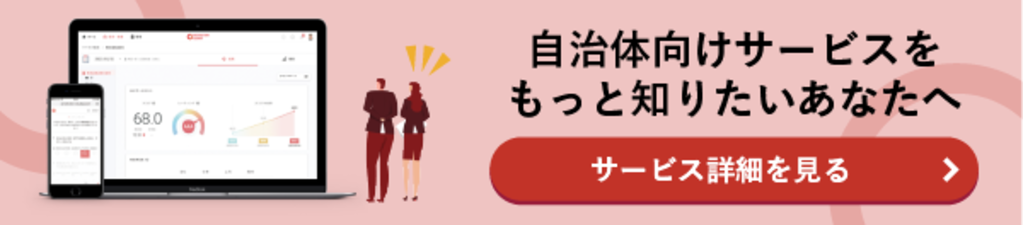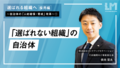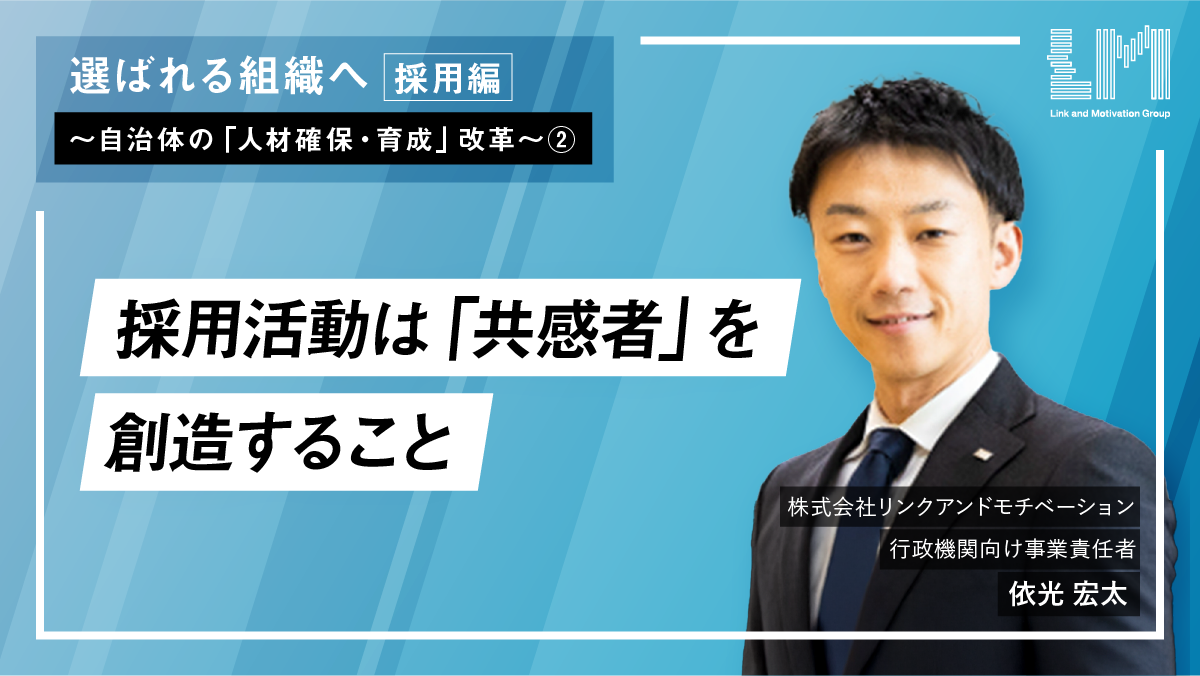
選ばれる組織へ〜採用編~ 採用活動は「共感者」を創造すること
かつて就職先として高い人気を誇っていた自治体だが、近年では「選ばれない組織」となり、人材の獲得・確保に苦戦を強いられている。この難局を打開するためには、労働市場から選ばれるための取り組みを精力的におこない、成果に繋げている民間企業をロールモデルとした組織改革を推進できるかどうかが鍵になる。では、労働市場で選ばれている民間企業は、何に注力しているのだろうか。
今、多くの民間企業が注目し、組織づくりの重要指標としているのが「エンゲージメント」だ。エンゲージメントとは、組織と従業員の相思相愛度合いを示すものであり、エンゲージメントの向上が労働生産性の向上や離職率の低下につながることが明らかになっている。
自治体が再び労働市場で選ばれる存在になるためには、エンゲージメントの高い組織づくりが欠かせない。その実現に向けた重要なステップの一つが「採用」である。
内閣府の調査では、最初の就職先を離職した理由として「仕事が自分に合わなかったため」という回答が一番多かった。また、自治体では、入庁1年目の職員はエンゲージメントが高いものの、2年目、3年目になるにつれて急降下する傾向が見られた。当初は「活気ある街づくりに携わりたい」という思いで入庁したが、日々、住民票や戸籍の発行などの窓口業務に追われるなかで仕事の意義を感じられなくなり、離職に至るというケースは少なくない。
こうした背景には、採用活動中に応募者が仕事内容や業務の意義を十分に理解できる機会が少ないことが影響している。入庁後に自身の想像と実際の業務内容との間にギャップを感じ、若手職員が早期に離職してしまうのは、双方にとって不幸なことである。
■「人材確保」からのシフト
採用はよく「シャツの第一ボタン」に例えられる。第一ボタンをかけ違えてしまうと、その後の人材育成や配置、定着など、あらゆる取り組みがうまく機能しなくなるからだ。採用時のミスマッチを、入庁後に解消するのは簡単なことではない。
自治体が選ばれ続ける組織をつくるためには、採用活動の在り方を根本から見直していく必要がある。その第一歩として、採用活動の考え方を「人材の確保」ではなく、「共感者の創造」へとシフトすべきだ。
自分たちは「何の目的のために存在し、目的達成のためにどのような取り組みを行い、どのような仲間たちと共に事を成そうとしているのか」を明らかにすることが大切だ。そして、民間企業でもなく、他自治体でもなく、「この自治体だからこそ味わえる働く魅力」を訴求し、共感者を生み出すことが重要だ。
※本稿は、『都政新報』2025年4月18日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。