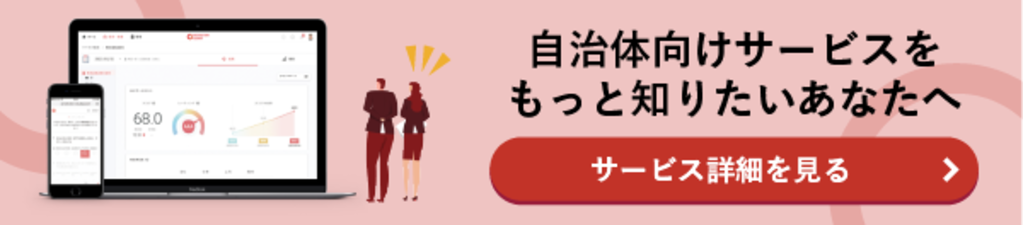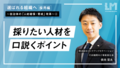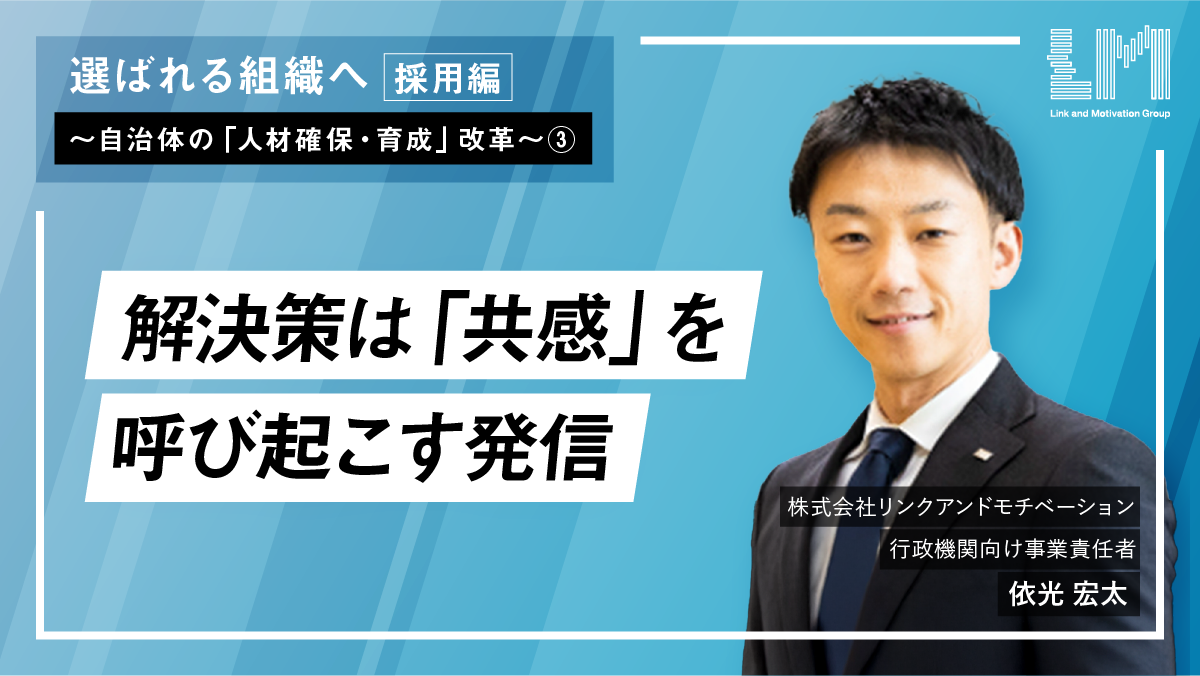
選ばれる組織へ〜採用編~ 解決策は「共感」を呼び起こす発信
自治体が選ばれ続ける組織になるためには、採用活動が重要なステップの一つになる。自治体は「人材の確保」ではなく「共感者の創造」という考え方で採用活動に取り組まなければいけない。では、共感者を創造するためには、どのような取り組みが求められるのだろうか。
昨今は、民間企業の採用イベントに出展する自治体が増えている。筆者もイベントに参加した際に「共感者創造合戦」では、自治体は民間企業に大きな差を付けられていると感じた。
多くの自治体は、仕事内容や職種、1日の過ごし方など「事実情報」の発信にとどまっているが、これでは共感を生むのは難しい。事実情報はホームページにも載っている無機質なものであるため、イベントでそれを伝えても、「この自治体で働きたい」という気持ちは引き出せない。
■魅力を際立たせて共感を創造する
学生・求職者の共感を得るためには、前提として、「どのような職場であると認識してもらいたいか?」を設計することが不可欠だ。当社では、人が組織に所属する要因を「目標・活動・組織・待遇」の4つに分類している。
たとえば、民間企業に比べ待遇が劣っていたとしても、「次世代に誇れる持続可能な街づくり」「社会のルールをつくる仕事」など、理念や意義を強調することで、魅力を伝えることはできる。このように魅力を際立たせることで、共感を呼び起こしたい。
そのうえで、事実情報の発信だけでなく「解釈」を伝えることが重要だ。例えば、ケースワーカーの仕事を、「生活保護申請者の相談に乗り、管理している」と伝えたところで、応募者はどのような魅力を感じてよいかわからない。しかし、ここに解釈を加えて伝えるとどうだろうか。「社会復帰の支援を通じて、市民の自律的な生活と社会参画を支援することで、個人の豊かさに社会の発展に貢献している」と伝えると、仕事の意義や意味が理解でき、魅力的な仕事として伝わるようになる。
こうした魅力は、応募してきた人だけに伝えても意味はない。共感者の創造には、労働市場に向けた「自治体で働くこと」の魅力を発信する機会を増やすことがポイントだ。そのため、合同説明会に参加したり、自治体独自の採用説明会を開催したりすることで、応募前の学生・求職者との共感創造を図ることも重要だ。
共感を醸成できれば、応募者は集まるようになるだろう。しかし、現在の自治体では「応募したけど入らない」人材も増えている。応募者が民間企業やより大きな規模の自治体に流れないようにするためには、応募者が納得感のある意思決定ができるよう、三顧の礼を持って「口説けるか」が鍵になる。
次回は採りたい人材を口説くポイントについてお伝えしたい。
※本稿は、『都政新報』2025年4月25日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。