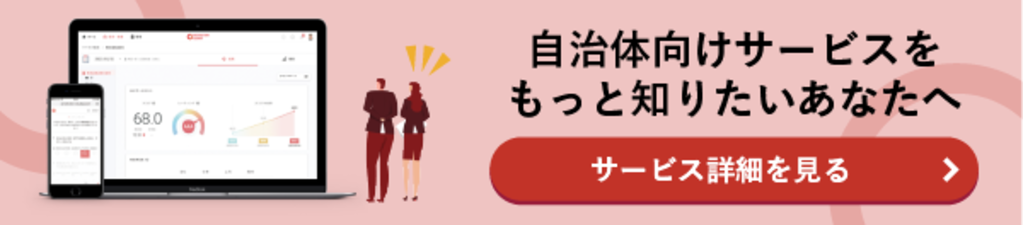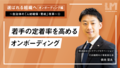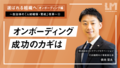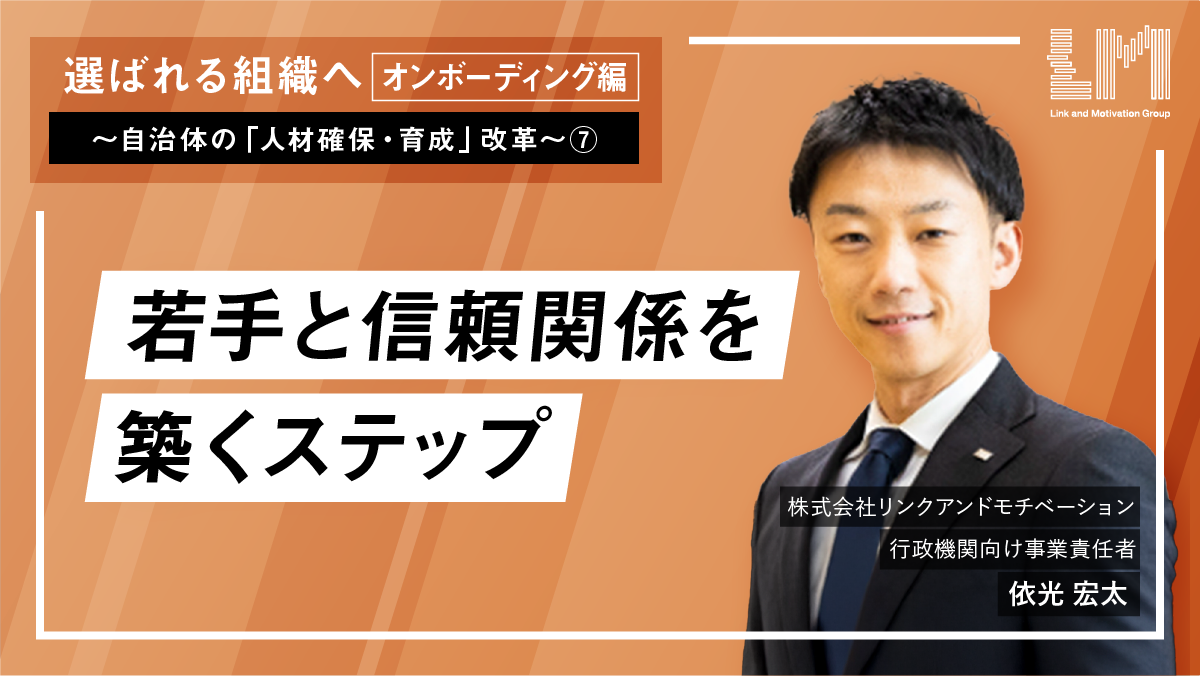
選ばれる組織へ〜オンボーディング編~ 若手と信頼関係を築くステップ
自治体が若手職員の定着率を高められるかどうかは、オンボーディングの成否が大きく影響する。ただ、現場の管理職と若手職員の間に「信頼関係」ができていないと、オンボーディングは失敗に終わってしまう可能性がある。
昨今は、多くの自治体で上司と部下のコミュニケーションが希薄化し、十分な信頼関係を築けていない。当社では、このような状態を「相互信頼不足症」と呼んでいる。
相互信頼不足症に陥った組織では、上司・部下がお互いの価値観を理解しないまま働いているため、何かトラブルが発生すると「人のせい」にしがちになり、さらに関係性が悪化していく。
その要因の一つに、管理職のプレイングマネジャー化がある。業務量の増加により、多くの管理職がプレーヤー業務に追われ、部下のマネジメントに十分な時間を割けなくなっているのが現状だ。結果、若手職員の成長支援や、モチベーションを高めるコミュニケーションが不足し、定着率の低下につながっている。
■関係の「質」を高める
部下との信頼関係は、一朝一夕で築けるものではない。大切なのは、「相互無関心→相互理解→相互信頼→相互要望」というように、一つずつステップを上りながら、関係の「質」を高めていくことだ。
①「相互無関心」から「相互理解」へ
相互理解を深めるためには、「人生の共有」が欠かせない。時間軸を区切り、「過去の経験」「現在の価値観」「未来に向けたビジョン」などの対話によって、お互いを知ることから始めたい。もちろん、最初に「人生の共有」をするのは上司側である。よく知らない相手には自己開示は進まないものだ。
②「相互理解」から「相互信頼」へ
相互信頼を得るためには、「約束と実行」が不可欠だ。信頼は、一度の大きな出来事によって築かれるものではない。「期限を守る」「毎月1回面談をする」など、小さな約束をたくさん行い、それを着実に実行することで、部下からの信頼を獲得したい。
③「相互信頼」から「相互要望」へ
相互要望の関係(お互いに遠慮をせず、要望を出し合える関係)を築くためには、「期待の伝達」が必要だ。「○○を頑張ってほしい」「○○のスキルを磨いてほしい」というように、部下の強みや課題に合わせて明確に期待を伝えたい。また上司から部下に一方的な要望をするだけではなく、部下から上司への要望を伝えてもらう働きかけも必要だ。
若手職員との関係性が「相互要望」の状態になっていれば、オンボーディングはより効果的なものになる。
次回はオンボーディングの成功に向けて押さえておきたい「組織観」についてお伝えしたい。
※本稿は、『都政新報』2025年5月23日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。