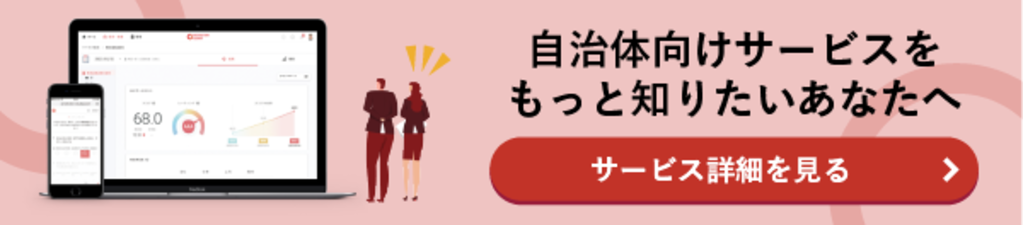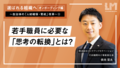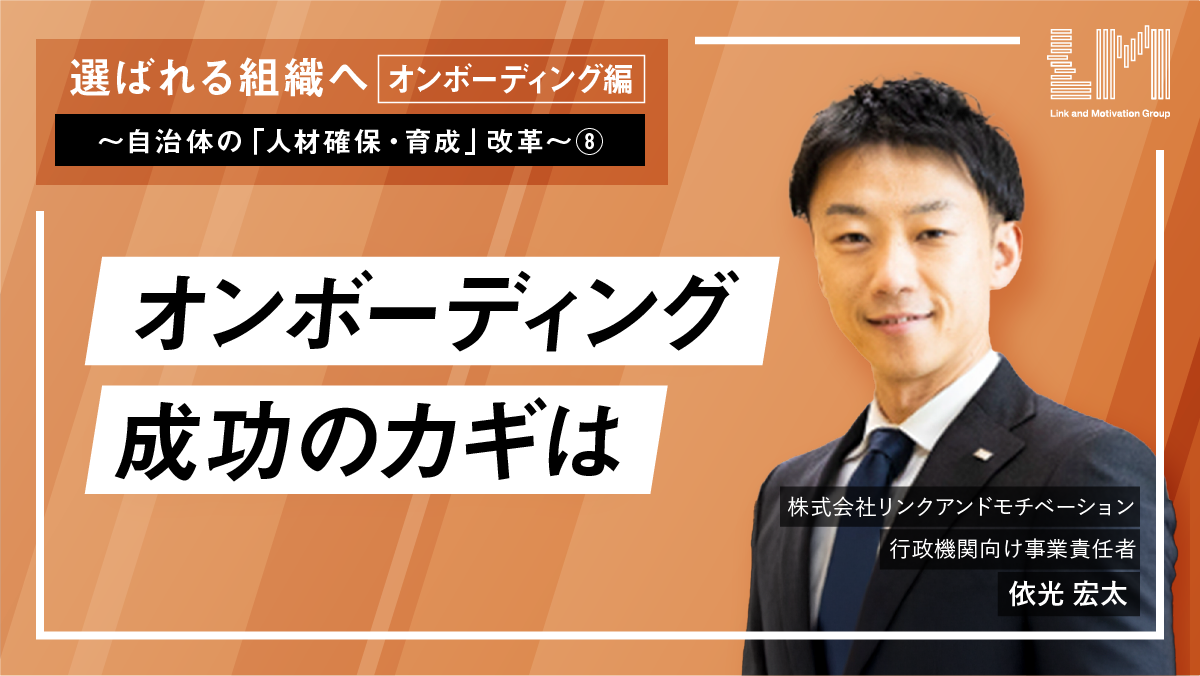
選ばれる組織へ〜オンボーディング編~ オンボーディング成功のカギは
若手職員の定着率向上と戦力化を目指し、業務や組織風土にスムーズに馴染めるように支援する取り組みの総称が「オンボーディング」である。オンボーディングを成功へと導くためには、適切な組織観に立脚したうえで、様々な施策を複合的に講じていくことが重要だ。では、適切な組織観とは何だろうか。それは、組織の本質が「個人」ではなく、個人と個人の「関係性」にあるという考え方だ。
■組織の問題は「人」ではなく「間」に起きる
当社では、組織を「要素還元できない協働システム」と定義している。たとえば、5人のチームがある場合、「5人の個人が集まったチーム」と捉えるのではなく、「5人の間に10本(5人×4人÷2)の関係性があるチーム」と捉える考え方だ。つまり、組織を見るときに、その構成要素である「個人」に注目するのではなく、「関係」に注目することが大切だ。
組織に問題が起きた際に、「Aさんが悪い」「Bさんに問題がある」と個人(要素)に原因を求めても根本的な問題解決には至らない。組織とは要素還元できない協働システムであり、問題のほとんどは「人」ではなく「間」に起きるからだ。問題の根本的な原因は、個人の能力や意欲ではなく、職場における人間関係や風土、コミュニケーションに潜んでいるのである。
別の視点から言えば、組織とは「機械」ではなく「生き物」であるといえる。機械が故障した場合、部品を交換すれば再び動くようになるが、生き物が病気になった場合、そう簡単にはいかない。たとえば風邪を治すためには、薬を飲むだけでなく、栄養を摂る、身体を休める、温かくするなど、複合的な対処が必要になる。これと同じように、組織においても、一つの問題に対して単一の対策を施すだけでは根本解決には至らない。
オンボーディングは、どのような人材をどのような期待で採用するか、どのような行動を評価するかなど、施策や制度が複合的に影響しあうものである。その一つには、上司と部下の関係の質も関係している。
現場の管理職と若手職員の間に信頼関係が築かれていなければ、どんな施策も失敗に終わる可能性が高くなる。信頼関係を強化するためには、組織の問題は人と人との「間」に起きているという認識を持ち、若手職員側にも、上司や業務との向き合い方や行動を変えることが重要だ。
その第一歩になるスキルが「思考の転換」である。
次回は若手職員に思考の転換を促す方法についてお伝えしたい。
※本稿は、『都政新報』2025年5月30日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。