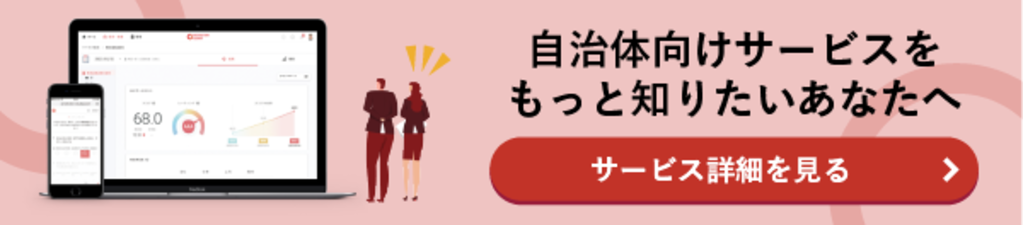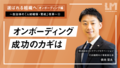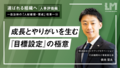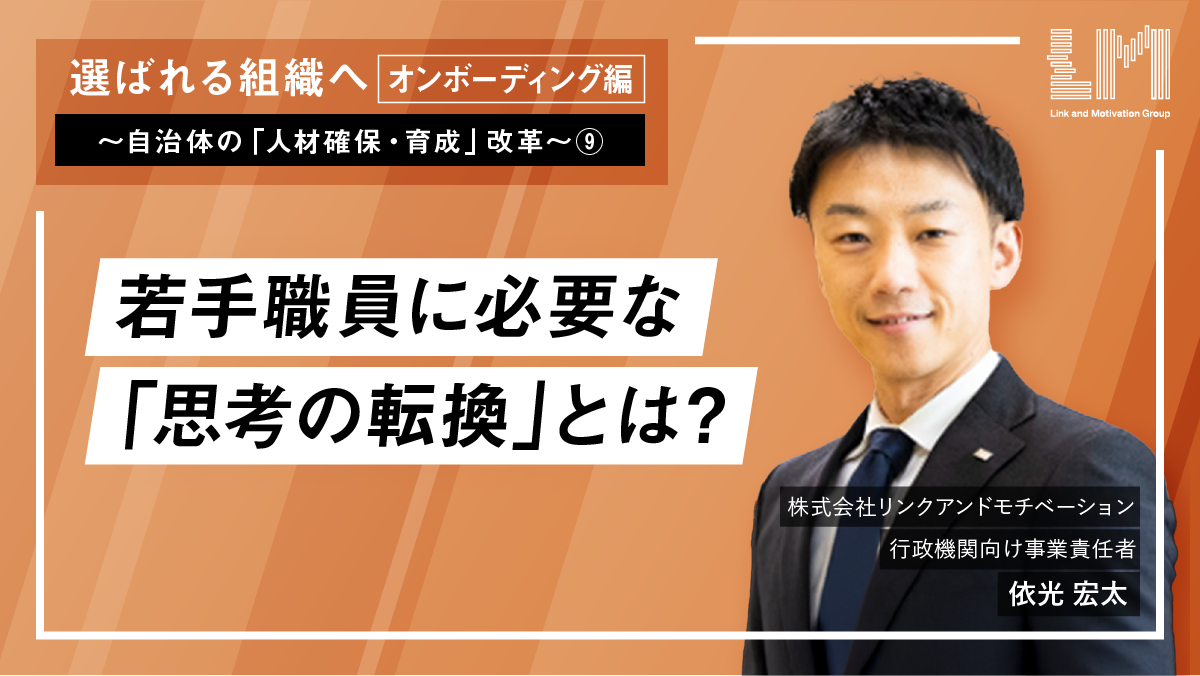
選ばれる組織へ〜オンボーディング編~ 若手職員に必要な「思考の転換」とは?
オンボーディングを成功へと導くためには、管理職だけでなく、若手職員自身も変わり、間にある「関係の質」を向上させる必要がある。そのために若手職員が身に付けるべきスキルが「思考の転換」だ。
自治体に入庁する若手職員の多くは「魅力的な街づくりに携わりたい」といった志を抱いていることが多い。しかし、目の前の業務に追われるなかで、志が徐々に薄れてしまう人は少なくない。
例えば「子供も高齢者も安心して暮らせる街づくりをしたい」という思いを持って入庁したAさん。最初に配属された住民窓口で日々、住民票の発行業務を担当していた。入庁して1年が経った頃から、Aさんは「イメージしていた仕事と違う」といったモヤモヤを抱き始める。そして、2年目の終わりと同時に民間企業に転職してしまった。このような事例は、昨今の自治体では珍しいことではないだろう。
■「変えられるもの」に意識を向ける
Aさんのように、希望とは異なる部署に配属されたという、過去の事実は変えることができない。また、現状に対する不満の感情を消し去るのも容易ではない。過去や感情など「変えられないもの」ばかりに囚われている若手職員は、前向きに働く意欲が損なわれ、早期離職に至る可能性も高い。
ここで必要なのが「思考の転換」だ。噛み砕いて説明すると、現状の捉え方や未来の行動など、自分次第で「変えられるもの」に意識を向けるということだ。配属先や業務内容を変えることは難しい。だが「今の環境で何を学べるのか?」「どのような力を伸ばせるのか?」などの視点を持つことで、現状を捉え直すことができ、今後の行動を変えていくことができる。
若手職員に思考の転換を促すには、管理職が業務の意義や意味を伝えることが求められる。
前述のAさんでいえば「住民窓口は市民と行政の最初の接点であり、市民の暮らしを支える最前線の仕事である」「住民窓口は職員に求められるコミュニケーションスキルを高める機会である」などだ。
”目の前の仕事が、自身の成長に繋がる”という意味や意義を伝え、若手職員が思考を転換できるようになれば、目の前の仕事の捉え方が変わる。目の前の仕事の捉え方が変われば、行動にも変化が生まれる。単に住民票を発行するだけでなく、「他にも生活で困っていることはありませんか?」といった声かけが自然とできるようになるかもしれない。
「思考の転換」ができる若手職員は、職場に定着する可能性が高い。
次回は自治体における人事評価制度の運用についてお伝えしたい。
※本稿は、『都政新報』2025年6月6日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。