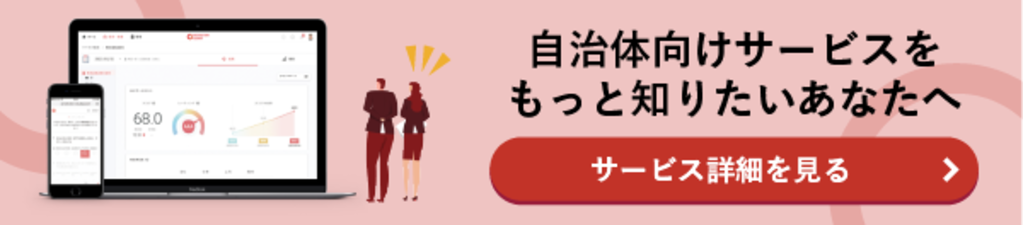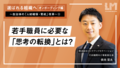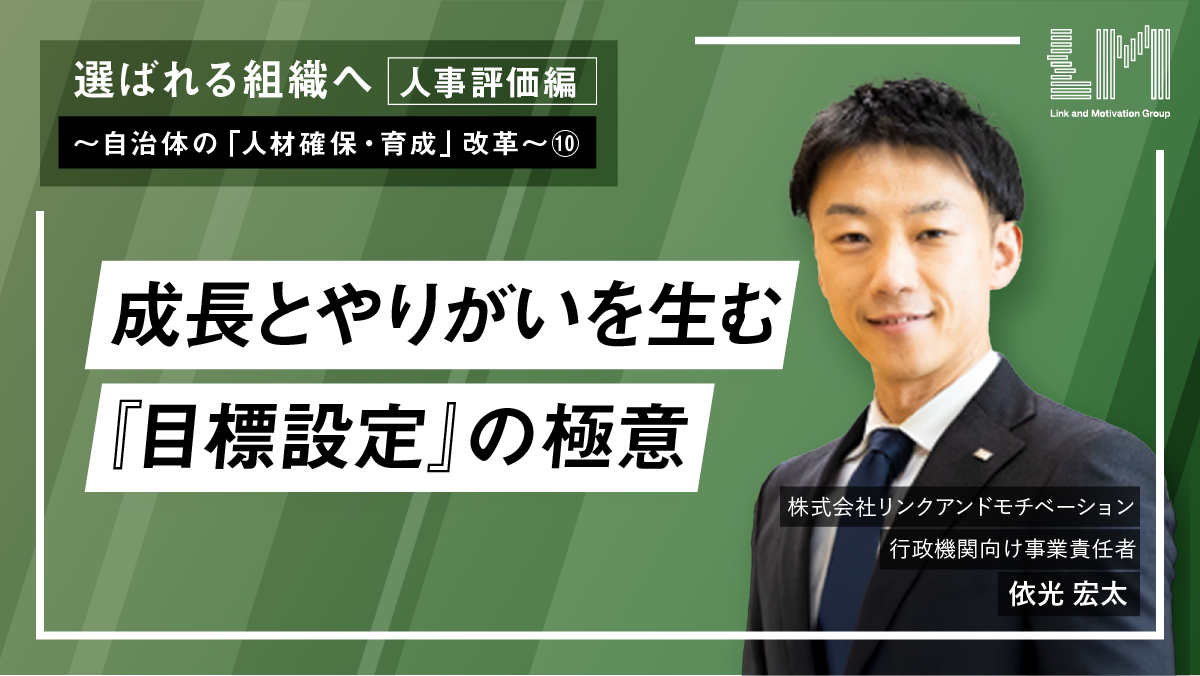
選ばれる組織へ~人事評価編~ 成長とやりがいを生む「目標設定」の極意
人事評価制度をうまく運用できている自治体は多くはない。その要因の一つに、目標設定の難しさがある。民間企業は売上や利益など定量的な目標を設定できるが、自治体の場合はそれが難しい。そのため、「住民満足度の向上」や「丁寧な窓口対応」など、目標が曖昧になりがちで、その結果、目標が形骸化してしまっているケースが少なくない。
そもそも人事評価制度とは、「目標を設定し、評価を行い、結果を伝達し、さらなる成長に向けて目標を定める」という繰り返しによって、職員の成長を促していく仕組みである。その起点になるのが「目標設定」だ。
明確で高い目標があるほど、職員は成長実感を得やすく、仕事のやりがいも高まりやすい。自分が目指すべき方向が見えているため、「やってみよう」「ここまでできた」という達成感を積み重ねることができるのだ。
一方で、目標が曖昧だと、業務の意味や成果が見えにくく、仕事は「ただこなすもの」と化す。そうなると、自己効力感や成長実感を得にくくなる。その結果、「この職場では成長できない......」と悲観し、民間企業へと流れる職員が出てきてしまう。
■3つの目標を使い分ける
目標は大きく3つに分類でき、使い分けることが重要である。
①行動目標
「何を、どのように実行するか」という具体的な行動を示す目標である。行動目標は、特に若手職員にとって重要だ。迷いなくアクションに移しやすいため、経験の浅い職員や業務初任者にとって特に効果的である。
②成果目標
「いつまでに、何を達成するか」を示す目標である。成果目標は、特に係長から課長層の職員にとって重要だ。職員は達成のために必要なプロセスを逆算し、自ら考え、具体的な行動を示すことができる。
③意義目標
「組織として実現したいこと」のような抽象的な状態を示す目標である。意義目標は、特に部長層以上の職員にとって重要だ。中長期視点かつ広域視点で、自部門としてどのような成果を創出するか、そのためにどのような事業を行うかを、自ら考える力を育むことができるだろう。
理想的なのは、「なぜこれが重要なのか」ということに職員自身が納得している目標である。納得して目標に向かうことで、仕事は「やらされるもの」から「挑戦したくなるもの」へと変わり、自然と自律的な行動が生まれるようになる。
次回は目標を「設定して終わり」にしないためのポイントについてお伝えしたい。
※本稿は、『都政新報』2025年6月13日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。