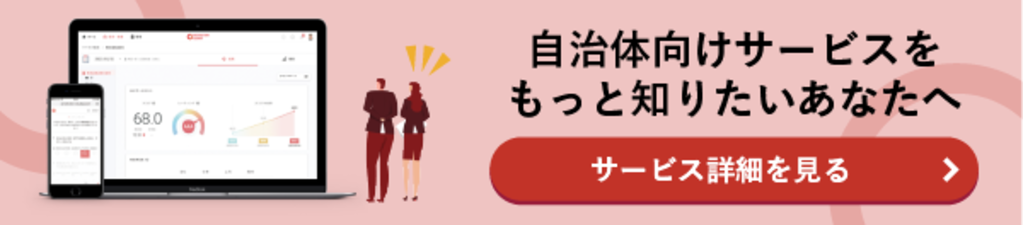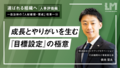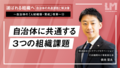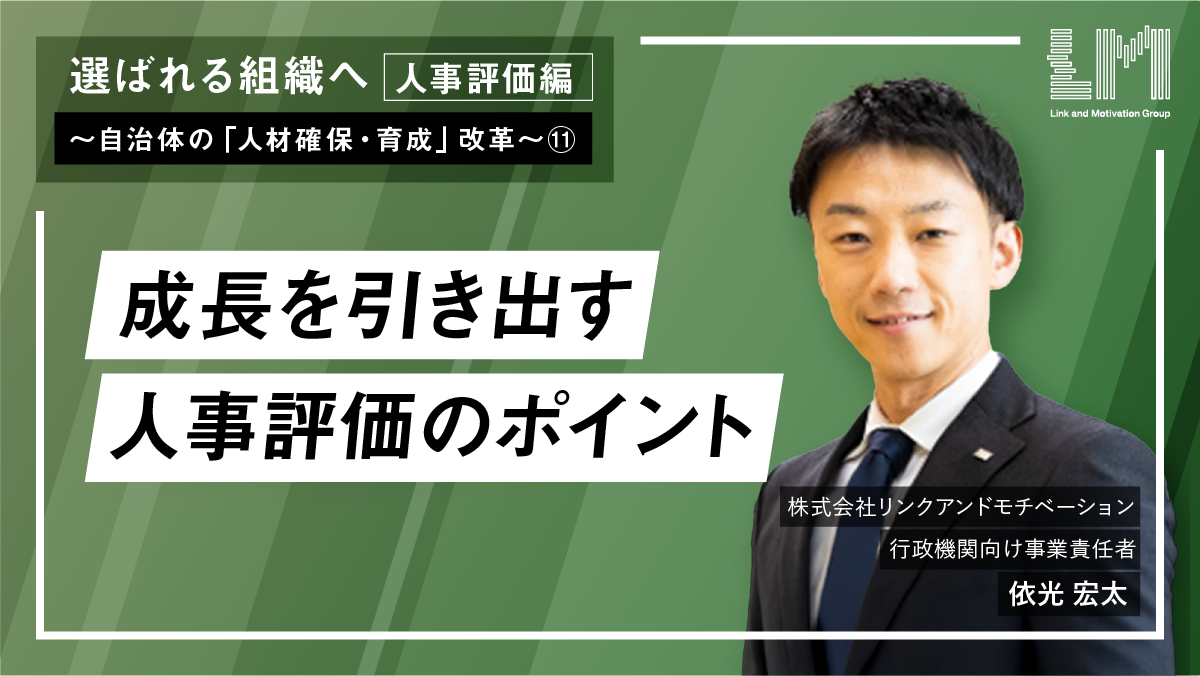
選ばれる組織へ~人事評価編~ 成長を引き出す人事評価のポイント
「目標設定をするようになったけど、これに時間をかける意味があるのだろうか?」と思ったことはないだろうか。
近年、人事評価システムを導入し、目標設定や評価面談を行う自治体も増えている。一方、目的や意義が十分に伝わっておらず、「やらなければいけないことだから」という理由だけで、その効果を最大化できていない自治体も多い。
一体、なぜ人事評価を行う必要があるのだろうか。
人事評価の目的は、上司が部下に点数をつけることではない。本来は部下の努力や課題を中長期的に捉え、「どうすればより良くできるか」を共に考え、成長を促すことである。
その際、評価者である管理職と、評価を受ける部下との間には、役割や年次、経験に基づく「視界の個別性」によるズレが生じやすいことを理解しておく必要がある。
例えば、管理職は組織全体の成果や将来のリスクを見据えている一方で、部下は目の前の業務に集中している。そのために、同じ目標でも受け取り方や意識の向け方が違ってしまうケースが発生しやすい。こうした前提を踏まえ、人事評価には取り組まなければならない。
■「認識のすり合わせ」と「伝え方」
では、より成長を促進するためには何が必要なのだろうか。ポイントは次の2つだ。
①期中でのすり合わせ
民間企業では、月に1回程度の1on1ミーティングを通して目標の進捗を確認し、認識をすり合わせる取り組みが一般的になっているが、こうした取り組みをしている自治体は少ない。だからこそ、自治体でも期中のすり合わせをおすすめしたい。
管理職は、部下との間に視界の違いがあることを十分に理解していなければいけない。そのうえで、目標に対する捉え方や期待する成果について丁寧に対話を重ね、必要であれば軌道修正を行いながら、期中をどのように過ごしていくかすり合わせることが重要だ。
②成長を実感できる評価伝達
期末に評価を伝える際に必要なのが、「部下が自身の成長を実感できること」である。単に結果だけを説明するのではなく、期初と比較して成長した点や今後への期待や伸びしろを合わせて伝えることが重要だ。部下は自身の成長を実感し、前向きに受け止め、成長意欲が高まりやすくなる。
人事評価で重要なのは、いかに部下の成長を促すことができるかだ。期初の目標設定から期中のすり合わせ、期末の評価伝達に至るまで、一貫して部下の成長を支援する姿勢が求められる。
※本稿は、『都政新報』2025年6月20日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。