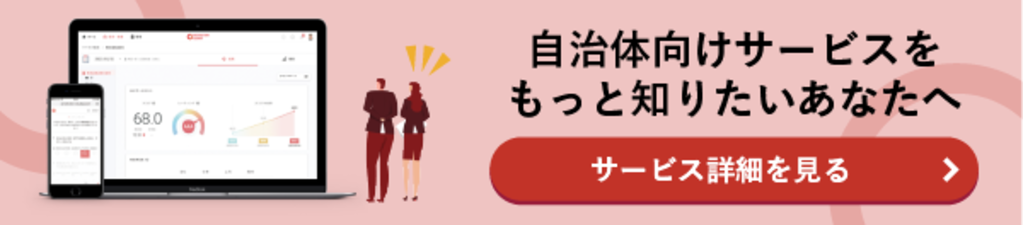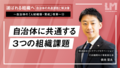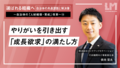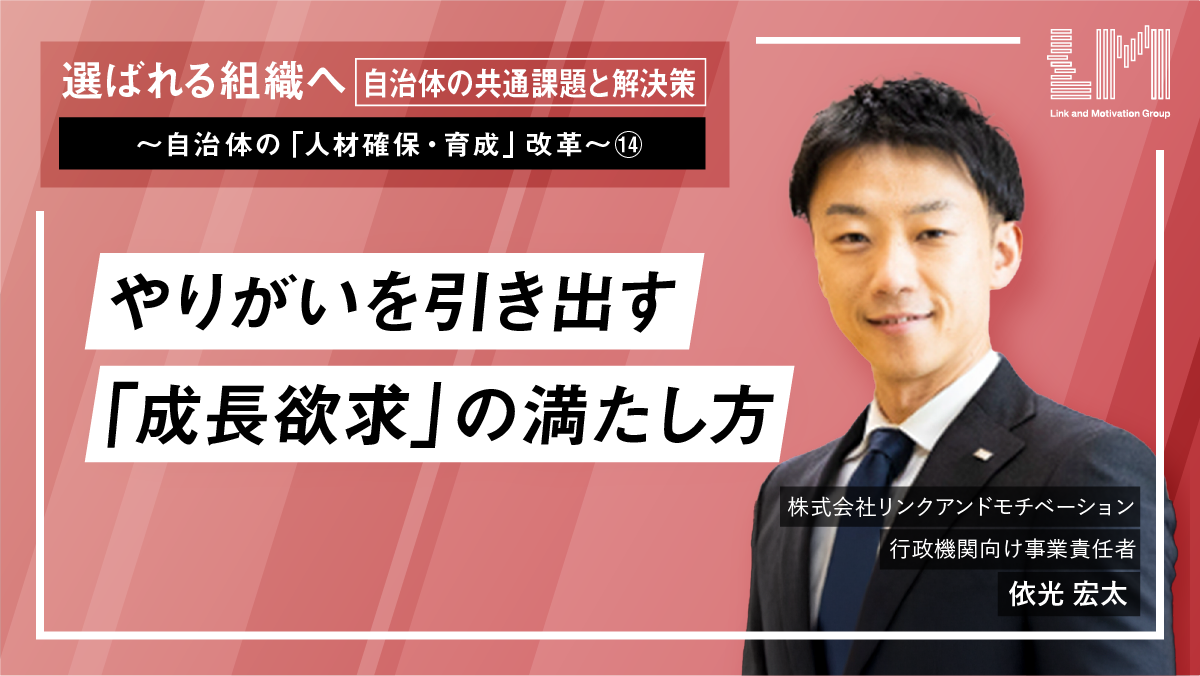
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ ⑬やりがいを引き出す「貢献欲求」の満たし方
自治体の共通課題の一つは「職員が仕事にやりがいを感じていない」ということだ。仕事の満足度は職位が下がるほど低く、特に一般職では、やりがいを実感できてない職員が多数を占めることが多い。
今回から3回にわたって、職員のやりがいを高める「感情報酬」について解説する。
■感情報酬でやりがいを高める
仕事のやりがいを感じる理由の一つに『自分の頑張りが報われること』、つまり報酬の存在がある。当社では、報酬を「金銭報酬」と「感情報酬」の2つに分類している。感情報酬とは、貢献欲求・成長欲求・親和欲求を満たすことである。金銭報酬は原資に限りがあるが、感情報酬はコミュニケーションによって生み出すことができるため、工夫次第でいくらでも提供できる。特に自治体は、民間企業の人事制度改革のように金銭報酬を変更することが難しいため、感情報酬が特に重要だ。
まず、感情報酬として「貢献欲求」を満たす取り組みを紹介する。
貢献欲求とは、他者や組織への貢献を実感したいという欲求のことだ。自治体の業務は、仕事を通じて貢献を実感できるシーンは少ない。市民に対して良いサービスを提供していても「当たり前」と受け取られやすく、むしろクレームのほうが注目されがちである。そのため、職員が自らの貢献を実感できる仕組みづくりが、やりがいの向上には不可欠だ。
貢献実感を高める施策として、民間企業で導入されている「ありがとうカード」が参考になる。これは、職員同士が感謝の気持ちをカードに書いて送り合う取り組みだ。住民からの感謝の声は届きにくい現場でも、職場の仲間や協働者からの言葉を通じて「自分の仕事が認められた」「あの人の役に立てた」という実感を得ることができる。
ポイントは、単に「賞賛し合う」ことではなく、「組織として大切にしたいことに則した行動を称える」ことだ。
例えば、自分の業務が終われば周囲に目も配らずに帰ってしまう職場なのであれば、協働を促すために、業務における連携や業務をサポートしてくれたことに対して感謝を送りあうことが効果的だ。また、周囲を助ける行動を取った職員に対して上長が全体にそのエピソードを共有するなど、促したい行動に対して方向付けすることが重要だ。それにより、職員一人ひとりのやりがいを高め、組織の成長にもつなげることができる。
次に、感情報酬の一つである「成長欲求」を満たし、職員のやりがいを高めるポイントをお伝えする。
※本稿は、『都政新報』2025年7月4日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。