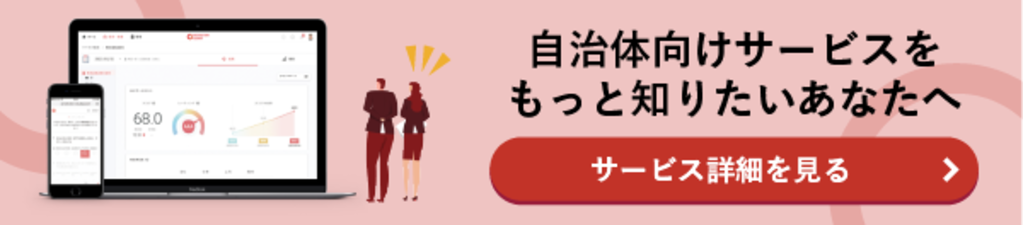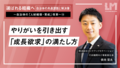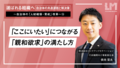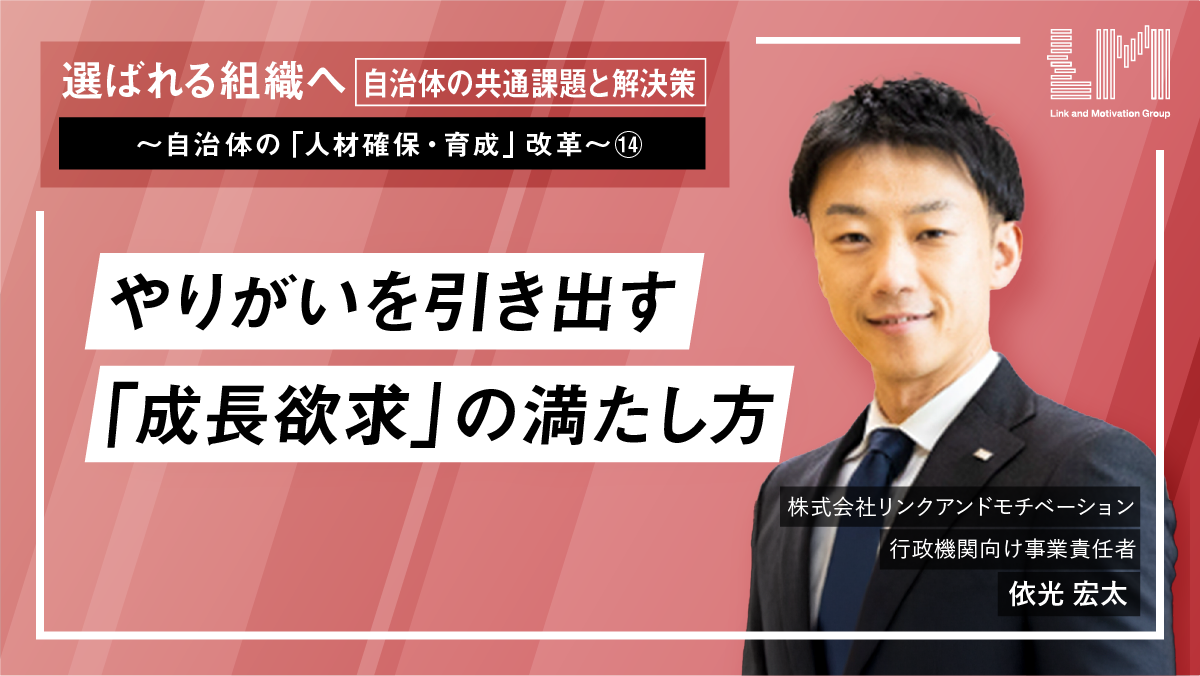
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ やりがいを引き出す「成長欲求」の満たし方
前回は仕事のやりがいを感じる理由の一つとなる報酬には「金銭報酬」以外に「感情報酬」があり、感情報酬の一つである「貢献欲求」の満たし方について説明した。今回は、「感情報酬」のうち、「成長欲求」を満たす取り組みを紹介する。
「成長欲求」とは、自己の成長を実感したいという欲求のことである。自治体の職員は、異動の「幅」が広いため、特定の分野で専門性を高めることが難しいと言われている。労働経済学、人事経済学を専門とする神戸学院大学の圓生氏は、「民間企業では一つの職能を中心に、その周辺の職能に広がる傾向がある一方で、ある県の職員は入庁から20年目までに一人当たり平均4.6の職能分野を経験している」と言う。
自治体では、税務から福祉、ケースワーカーから水道局というように、異なる分野へ異動が珍しくない。さらに近年は、人員不足の部署への異動が優先される傾向も強くなっている。結果、入庁してしばらく経つと「経験が積みあがっていない」「民間の方が成長できそうだ」と感じてしまうことがある。
■「スキルの汎用化」」と「成長の言語化」
成長欲求を満たし、成長実感を高めるための鍵は「スキルの汎用化」と「成長の言語化」だ。
「スキルの汎用化」とは、日々の業務で発揮している能力を他業務にも応用できるよう汎用的な形で整理することだ。
たとえば、「窓口対応の能力が高い」と伝えるだけでなく、「相手の言葉や態度から意図を読み取って対応できる」と伝えることで、職能が変わっても成長を感じやすくなる。
「成長の言語化」とは、自身の成長を言語化することだ。その際には、本人だけでなく周囲からの伝達も重要である。たとえば、上司との1on1で「1ヶ月でできるようになったこと」を振り返るなど、周囲からの「1か月の変化」を伝えることも有効だ。
日々の業務に取り組む中では、自分の業務経験が何に役立ち、どのような経験だったかを考える機会は少ない。そうした状況で急な異動に直面すると戸惑いや不安が生まれ、さらには「自分は本当に成長できているのか?」と感じてしまう。だからこそ、普段のコミュニケーションの中に「汎用化」と「言語化」を組み込み、少しでも成長実感が得られるような仕組みを作ることが重要だ。
次回は感情報酬の一つである「親和欲求」を満たし、職員のやりがいを高めるポイントをお伝えする。
※本稿は、『都政新報』2025年7月11日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。