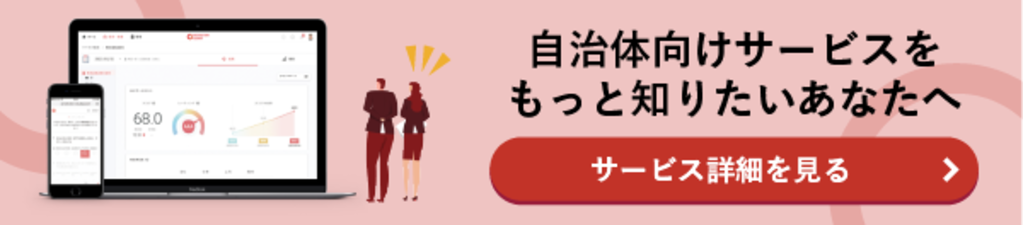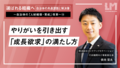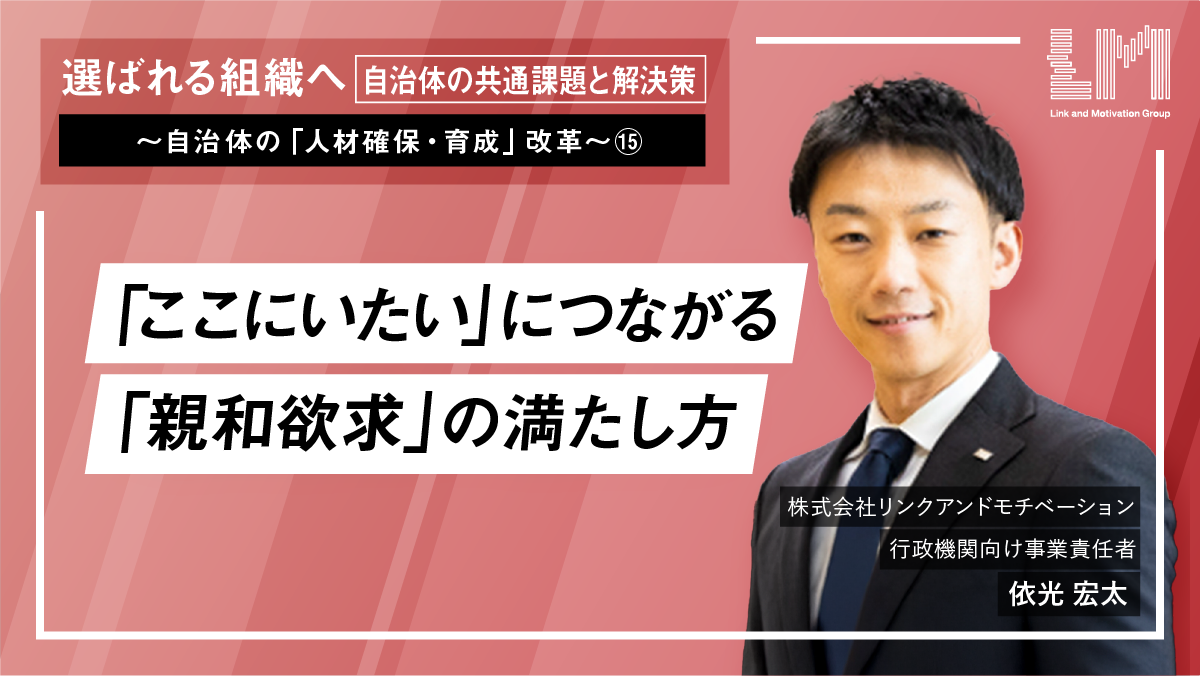
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ 「ここにいたい」につながる「親和欲求」の満たし方
ここまで感情報酬を活用した「やりがい」の高め方を伝えてきたが、感情報酬は若手職員の離職や民間企業への転職防止にもつながる。今回は感情報酬の一つである「親和欲求」を満たすポイントをお伝えする。
親和欲求とは「良好な人間関係のなかで働きたい」という欲求のことである。自治体では「業務上のつながりはあるが、異動が多く、深い関係性は築きにくい」という声がよく聞かれる。友達のような関係性を築く必要はもちろんないが、気軽に相談できることや居心地の良さは「ここに居たい」という理由につながる。
所属する組織への共感も重要である一方、普段の業務で関わる上司や仲間との関係性の方が構築しやすいため、周囲と良い関係性を構築できていることが職員の離職防止にも繋がりやすい。
では、どうすれば職員の親和欲求を満たせるのだろうか。前提として、管理職が部下にとって「気軽に相談できる存在」であることが不可欠だ。管理職は日頃から「部下に話しかけられたら手を止めて話を聞く」「雑談から会議を始める」など、相談しやすい雰囲気づくりに努める必要がある。
■感情を共有することで人間関係を深める
気軽に相談できる関係性を整えたうえで、実践したいのが「感情の共有」だ。民間では、月末や月初に「納会」を実施して、業績の振り返りや、個人の振り返りを実施している。特に個人の振り返りでは、1か月のモチベーションの変動をトピックスとともに共有しあうなど、感情の共有機会を設け、関係性を深めている企業もいる。第13回で紹介した「ありがとうカード」のコミュニケーションも、こうした機会で取り入れるのが効果的だ。
また、地域の祭りや催事の企画・運営にあたり、部門を越えて担当職員を選出することも有効である。その他、飲み会やバーベキューなど、オフコミュニケーションの場を設けることで相互理解を深めるのも良いだろう。
大切なのは、ただ場を設けるのではなく、共通体験が得られたり、1年間の振り返りや次年度の抱負を共有するようなコンテンツを設計したりすることだ。意図的に一人ひとりの状況や感情を共有する時間を設けることで、職員の親和欲求が満たされ「この人たちともっと一緒に働きたい」「みんなで成果を出したい」などの前向きな協働を促すことができるはずだ。
なお、昨今の自治体では「上司・部下の関係性の希薄化」も課題になっている。次回以降、その解決に向けた具体的なポイントや施策についてお伝えする。
※本稿は、『都政新報』2025年7月18日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。