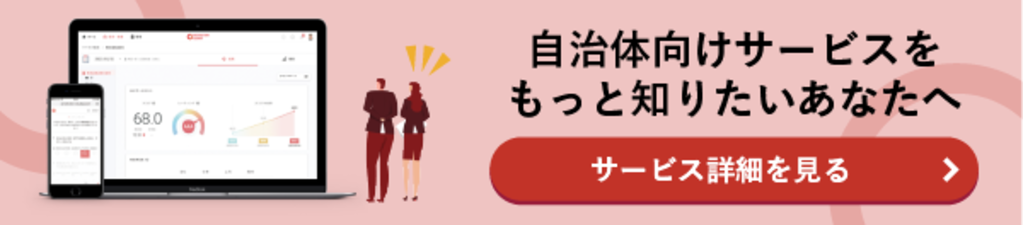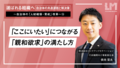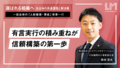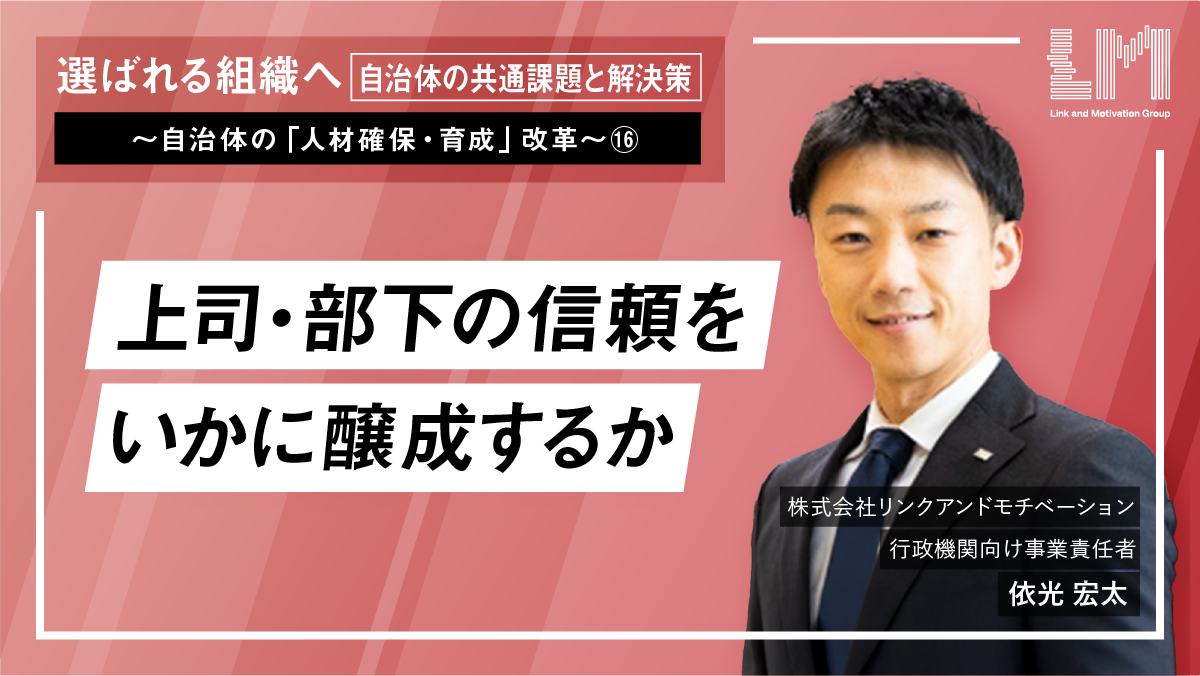
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ 上司・部下の信頼をいかに醸成するか
昨今の自治体の職場では、「上司・部下の信頼関係が希薄になっている」という声をよく聞く。「関係の質」は「行動の質」につながり、やがて「成果の質」に結びつく。だからこそ、組織の生産性を高め、職員一人一人の働きがいを育むためにも信頼関係の構築は不可欠だ。今回から3回にわたり、上司・部下の信頼関係をいかに築いていくか、その具体的な方法をお伝えしたい。
当社のエンゲージメント調査の結果からも、上司と部下の間に信頼関係が築かれていない自治体が多いことが明らかになっている。背景には、上司がハラスメントを過度に恐れ、部下とのコミュニケーションを控えてしまう傾向がある。
また、ワークライフバランスの「ライフ」を重視し、業務時間外での関係構築を避ける部下が増えていることも無関係ではない。さらに、定期的な人事異動により、「どうせすぐに異動があるから」と考え深い関係づくりに踏み込まない職員も少なくない。
■「関係の質」向上のステップ
では、どうすれば信頼関係を築けるのだろうか。ポイントは「相互無関心→相互理解→相互信頼→相互要望」の四つのステップを意識して関係の質を高めていくことである。まずは「相互無関心」から「相互理解」のステップに進むポイントを押さえていきたい。
相互理解を育むには、まず上司から自己開示を行い、部下との間に「共通の接点」をつくることが重要だ。心理学では、相手から受けた行為に対して何かを返したくなる「返報性の法則」が知られている。上司が過去の経験や価値観を開示することで、部下にも自然と「自分も話してみようかな」という気持ちが芽生えやすくなる。
こうした自己開示を促す実践例としては、個人の「自己紹介シート」の活用がある。出身地や大学、入庁動機に加え、趣味などを簡潔にまとめてあるものだ。たとえば、「同じ大学だったんですね」「その映画、私も好きです」といった共通点をきっかけに、自然な会話が生まれやすくなる。人は共通点を持つ相手に対して親近感を抱きやすく、それが信頼の土台をつくることにつながる。
信頼関係を築く第一歩として、まずは上司自身が「知ってもらうための行動」を起こすこと。それが、相互理解のステージへ進むための鍵となる。
次回は、この相互理解をさらに深め、信頼関係を構築していくためのポイントを紹介する。
※本稿は、『都政新報』2025年7月25日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。