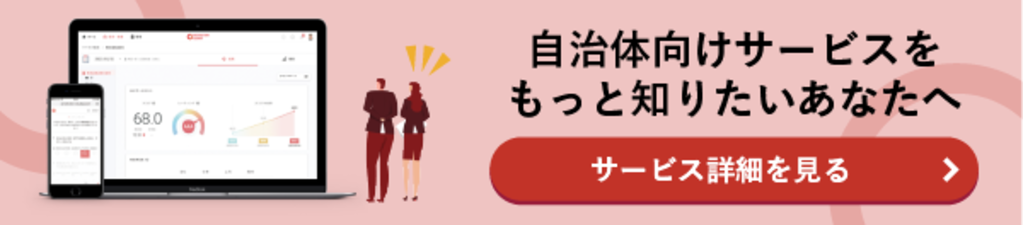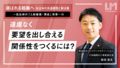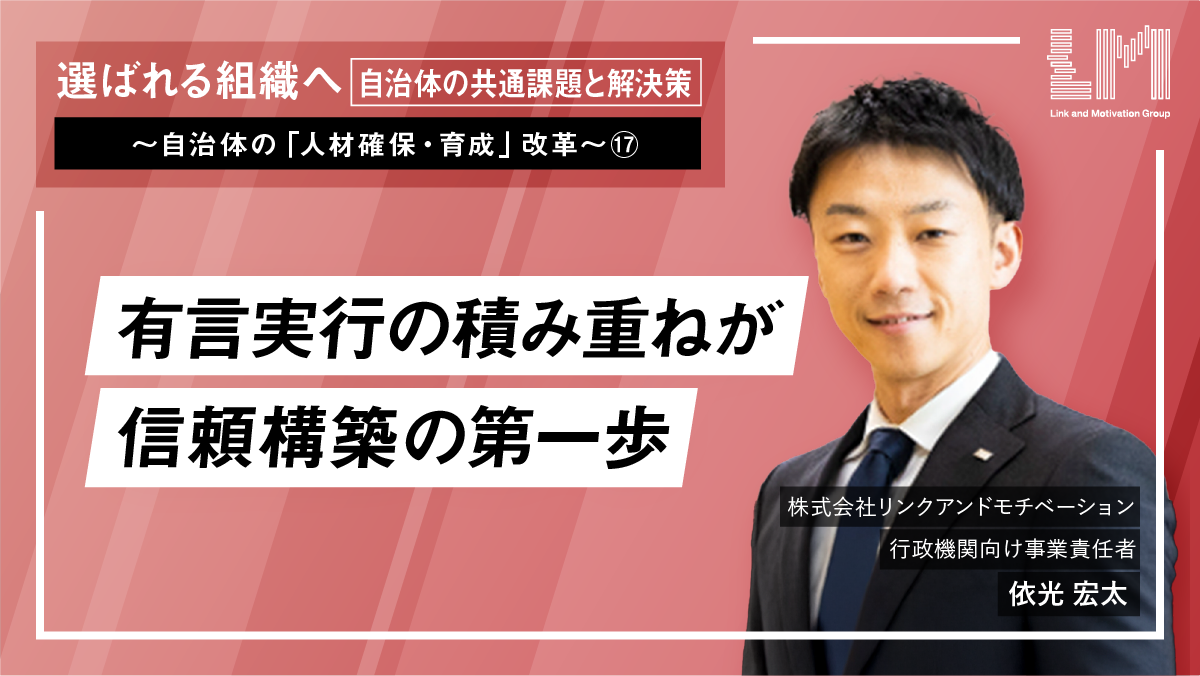
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ 有言実行の積み重ねが信頼構築の第一歩
前回は「上司・部下の信頼関係の希薄化」の解決を図るため、「相互無関心→相互理解→相互信頼→相互要望」の四つのステップの重要性を説明した。このうち今回は「相互理解」から「相互信頼」へ進むポイントをお伝えしたい。
「相互理解」とは、上司と部下がある程度お互いを知っているものの、まだ本音で頼り合える関係には至っていない状態である。ここから「相互信頼」へと進むためには、上司によるちょっとした心がけが必要だ。
実際、多忙な自治体の職員からは「上司が動いてくれない」「放置されている」といった声がよく聞かれる。たとえば、市民サービスの改善案を上司に伝えても、「検討してみる」と言われたまま進展がなかったり、「いいアイデアだね」と言われても実行されないといったケースである。こうした言動が多いと、部下は「上司に話しても意味がない」と感じるようになり、それ以上の関係構築は難しくなる。
また、仮に上司が水面下で対応を進めていたとしても、部下からは見えにくいこともある。そのため、まずは上司と部下との間で情報格差が生まれる構造を理解しておくことが大切だ。
■信頼は「有言実行」の積み重ね
部下の信頼を得るために欠かせないのが、上司の「有言実行」である。特別な成果を挙げる必要はなく、むしろ、日常の小さな約束を守ることを徹底したい。どんなに些細なことでも、言ったことは必ずやる。この積み重ねによって、部下の中に「この人は信頼できる」という感情が芽生えてくるのだ。
ポイントは、実行可能な約束をできるだけ多く積み重ねることだ。「月に1回、1on1を実施する」「○日までに資料を確認する」などで良い。そして「忙しいから今月の1on1は無しにしよう」「資料のチェックはやっぱり来週で」というように約束を反故にしていたら、いつまで経っても部下の信頼は得られない。逆に言えば、約束したことをきちんと実行するだけで、着実に信頼関係を深めていけるのだ。
上司と部下の関係性が「相互理解」から「相互信頼」へとステップアップすれば、部下は安心して意見を出したり、上司に相談したりできるようになる。次回は「相互信頼」から「相互要望」へ進むポイントをお伝えする。
※本稿は、『都政新報』2025年8月1日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。