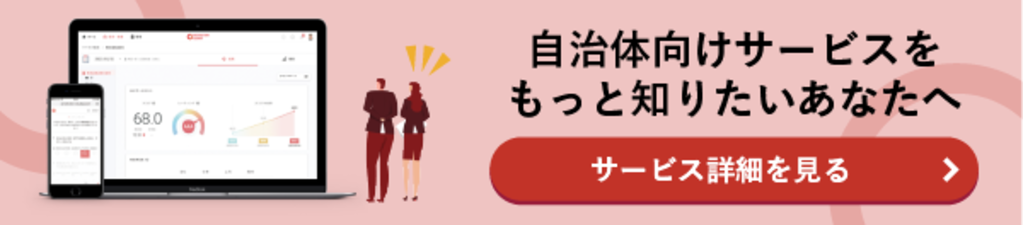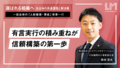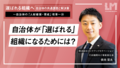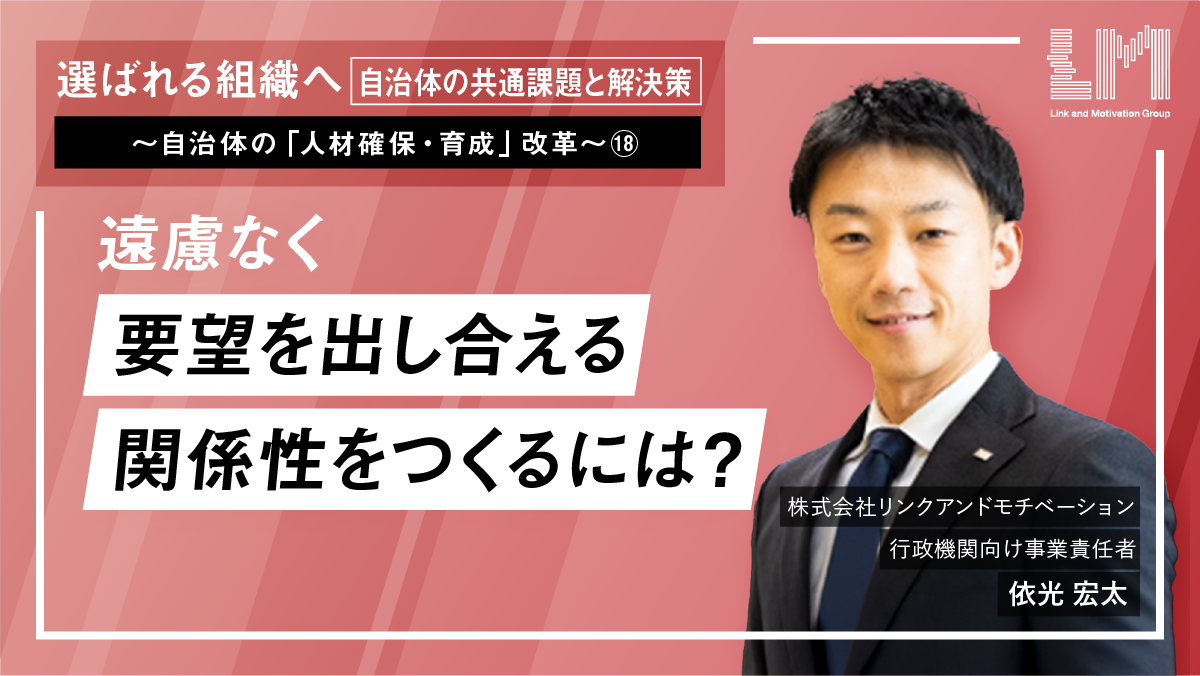
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ 遠慮なく要望を出し合える関係性へ
前回に続き、上司・部下の信頼関係構築の四つのステップのうち、今回は「相互信頼」から「相互要望」へ進むポイントをお伝えしたい。
自治体では業務の多忙さから、管理職がプレイングマネジャー化しているケースが多い。部下と面談する時間を確保できないだけでなく、日常的な対話も不足しがちになり、上司は部下への指示や評価だけで手一杯になってしまうケースも少なくない。この状況が続けば、部下は「言われたことだけやればいい」と受け身になり、主体性や成長意欲を失いやすくなる。
この状況を打開するには、「相互要望」の関係性をつくることが有効だ。これは、上司と部下がお互いに期待や要望を遠慮なく伝え合える関係のことを指す。
■「相互要望」の関係性を築く
たとえば、サッカー日本代表の試合中に見られる選手同士の激しい言い合いは、単なる口論ではなく、勝利という共通目的に向けた建設的なコミュニケーションである。信頼関係と役割の明確化があるからこそ、成り立つやり取りだ。職場でも「この仕事は任せてほしい」「ここは改善してほしい」といった要望を言い合える環境が必要である。
「相互要望」の関係性を築くためには、上下関係に縛られず、部下が安心して上司に要望を伝えられる機会をつくることが重要だ。たとえば、イベントの企画会議など自由な意見交換が求められる場において「正解はないので、遠慮なく意見を出してください」と伝えると発言しやすい雰囲気をつくることができる。このように「この場は自由に意見を出していい」という前提を明示すると、立場にかかわらず本音が出やすくなる。
一例として、自治体でも導入が進んでいる360度サーベイの活用が効果的だ。これは人事評価としての「360度評価」とは異なり、周囲からの期待や自分の見られ方を本人が把握するための人材育成ツールとして機能する。
また、ヒアリングシートや定期面談で「どの業務に挑戦したいか」「どのような経験を積みたいか」といった問いかけに加え、「実現に向けて、上司にどう関わってほしいか」と尋ねることも、部下の要望を引き出すうえで効果的だ。部下の意向を具体的に把握し、上司がそれを丁寧に受け止め、行動に移すことで、部下の中に「声が届いている」という実感が生まれ、より要望を伝えやすくなる。「相互要望」の関係性を築くことができれば、主体的に発言・行動する職員が増え、組織全体が活性化していくはずだ。
次回は自治体において「部署間の協働」を促す方法をお伝えする。
※本稿は、『都政新報』2025年8月8日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。