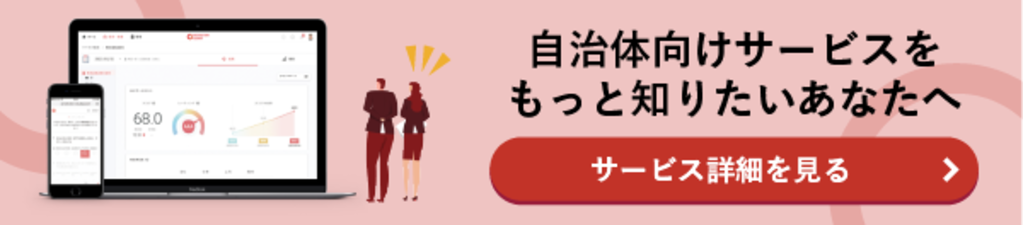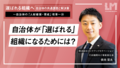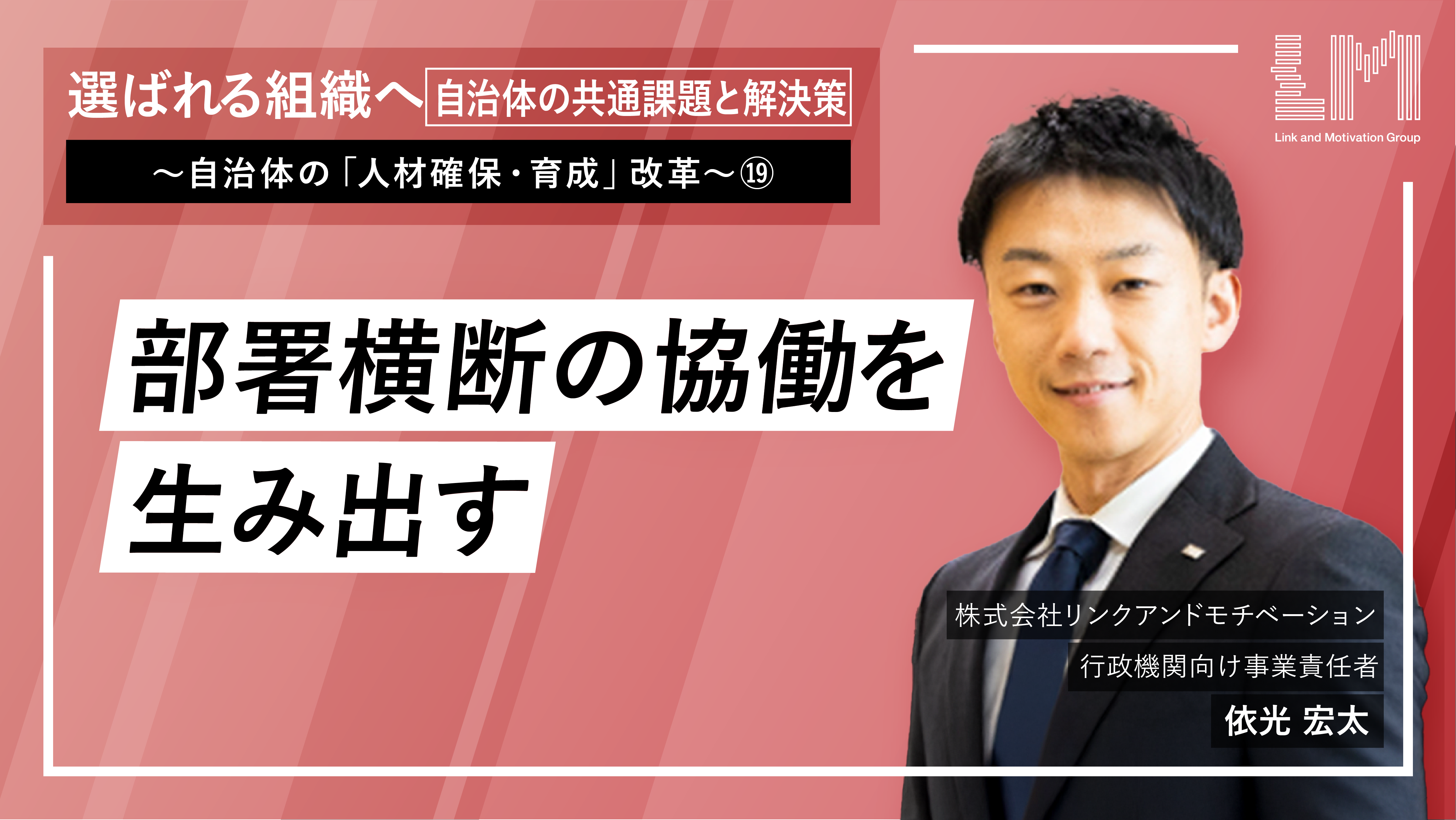
選ばれる組織へ~自治体の共通課題と解決策~ 部署横断の協働を生み出す
上司・部下の信頼関係、すなわち「縦」の関係性が強化されれば、部署としての「関係の質」や一体感は高まっていく。ただし、部署内の関係が良好でも、「横」の関係性が希薄なままでは、自治体全体で市民サービスの向上を目指すまちづくりの実現は難しい。今回は部署間の壁を越え、横断的な協働を生み出すための視点と取り組みを紹介したい。
自治体では、部署間で業務や対応の「押し付け合い」が起きるケースが少なくない。議会対応などで、回答する部署をお互いに押し付け合っているというのはよくある話だ。
背景には、「自部署の負担を増やしたくない」「部下に余計な仕事をさせたくない」といった上司の気持ちがあるだろう。しかし、こうした対応は、結果的に部署間の分断を生み、協働の機会を遠ざけているのが現状だ。
また、自治体全体として「市民サービスの向上」や「地域課題の解決」といった方針を掲げていても、現場ではどうしても「自分の部署の業務をこなすこと」が優先されがちである。その結果、「目的を実現するには何が必要か」よりも「これ以上負担を増やしたくない」という思考が先行し、部署間の協働は生まれにくい。
■「共通の目的」に向かう文化をつくる
解決に必要なのは、自部署の役割を越えてでも、自治体としての「共通の目的」を意識できる状態をつくることだ。そのためにはまず、上司が共通の目的を言語化し、現場に落とし込むことが重要だ。
たとえば、「市民サービスの向上に各部署がどのように貢献できるか?」を議論する場を設けるのは効果的だ。こうした議論に参加することは、「うちには関係ない」という意識を変えるきっかけになる。
さらに、他部署の業務を理解することも大切である。民間企業で広がる「社内留学制度」のように、一定期間、他部署の業務を体験できる機会があると、役割の違いを理解でき、互いの強みを活かした協働が生まれやすくなる。
加えて、部署横断のプロジェクトチームの結成や、定期的な合同ミーティングを通じて、日常的に部署を超えた連携を図ることも効果的だ。
部署間の壁を越えた協働が生まれるようになると、自治体の組織力は格段に高まり、目指す姿や理念の実現が近付くはずだ。最終回となる次回は、自治体が「選ばれる」組織になるために押さえておきたい考え方を解説する。
※本稿は、『都政新報』2025年8月15日付「選ばれる組織へ 実践編 〜自治体の『人材確保・育成』改革〜」に寄稿した記事を再編集したものです。
※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。
※法人名、役職などは掲載当時のものです。