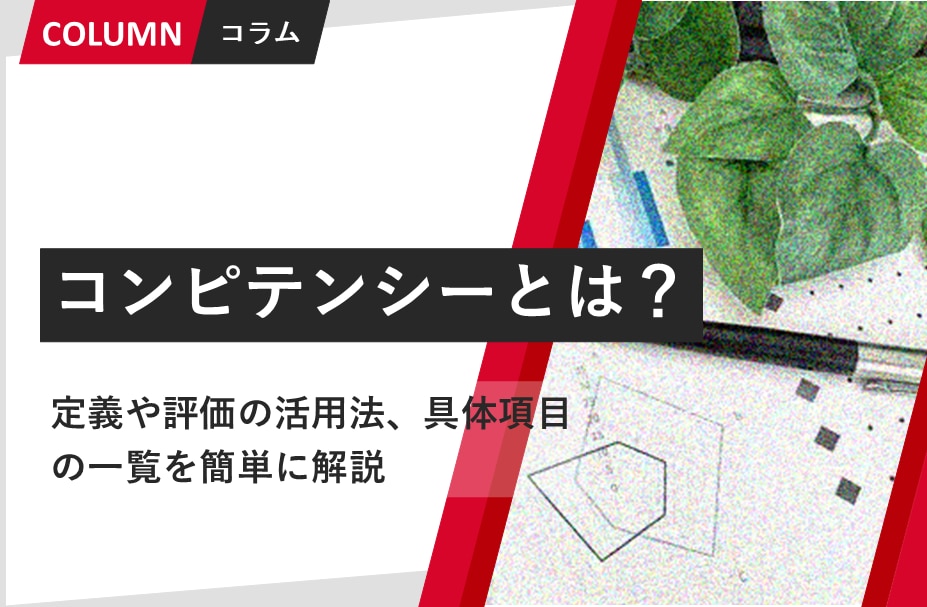
コンピテンシーとは?定義や評価の活用法、具体項目の一覧を簡単に解説
昨今、コンピテンシーという言葉に注目が集まっていることをご存知でしょうか?
コンピテンシーは後述するように、『高い業績を収めている従業員に共通して見られる「行動特性」のこと』を指しますが、デジタルトランスフォーメーション(DX)のデータ分析の一環で、以前に比べて専門家の手を借りずに簡易的にコンピテンシーを抽出できるようになったことが背景にあると考えられます。
とはいえ、昔聞いたことはあるけれど、実は何かよくわからない、、、という方も多いのではないでしょうか。ここでは、コンピテンシーの概要とともに、導入のための具体的な方法もご紹介していきます。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ エンゲージメントの向上に有効なアクションプランとは!記事はこちら
コンピテンシーとは?
コンピテンシーとは、特定の職務において、平均的な水準をはるかに超える顕著な業績を継続的に生み出す従業員に共通して見られる行動特性の集合体です。
これは、表面的なスキルや知識といった顕在的な能力に留まらず、それらの行動を根底で支える、個人の価値観、思考様式、行動パターン、性格特性、意欲、自己概念といった潜在的な要素までを含んでいます。
企業がコンピテンシーに注目する背景には、従来の学歴や職務経歴といった要素だけでは、入社後の実際のパフォーマンスを十分に予測できないという課題意識があります。コンピテンシーは、具体的な行動を通して観察可能であるため、より客観的かつ実践的な評価基準となり得ます。
■コンピテンシーとは?
コンピテンシーは、特定の職務で卓越した成果を上げる個人が示す行動特性を指します。これは、単に技能や知識ではなく、行動の背後にある価値観、思考パターン、性格などの深層的な要素に焦点を当てます。
企業はコンピテンシーを人事評価や採用プロセス、従業員の育成に活用し、公正で理解しやすい評価基準を設けることができます。これにより、適切な人材の採用、効果的な人材育成、生産性の向上に貢献することが可能になります。
■コンピテンシー定義の一覧
組織における人材の能力や行動特性を可視化・評価するために、「コンピテンシー(行動特性)」という指標が活用されます。以下は、代表的なコンピテンシーの分類とその具体例です。
- 達成・行動
目標達成や成果に向けた行動に関する特性です。
・達成思考:高い目標に挑戦し、結果を重視する姿勢
・秩序・品質・正確性への関心:ルール遵守やミスの防止への意識
・イニシアチブ:自ら率先して行動する積極性
・情報収集:必要な情報を意識的に収集する能力 - 援助・対人支援
他者との関係性や支援行動に関する特性です。
・対人理解:他者の立場や感情を理解する姿勢
・顧客支援志向:相手の期待を超える支援を提供する姿勢 - インパクト・対人影響力
組織内外での影響力や対人関係の構築に関する特性です。
・インパクト・影響力:相手の考えや行動に影響を与える力
・組織感覚:組織の構造や力学を把握する感度
・関係構築:信頼関係やネットワークを築く力
・他者育成:後輩や部下の成長を支援する行動 - 管理領域
チームの運営やマネジメントに関する特性です。
・指導:他者の行動を導き、正しい方向に進める
・チームワークと協力:協働しながら成果を出す姿勢
・チームリーダーシップ:目標達成に向けてチームをまとめる力 知的領域
思考や判断に関する特性です。
・分析の志向:データや事象を論理的に整理・判断する力
・概念の志向:抽象的な情報を構造的に捉える力
・技術的・専門的・管理的専門性:分野に特化した知識・スキル個人の効果性
個人の自律性や心理的な安定性に関する特性です。
・自己管理:感情や時間、行動を自己統制する力
・自信:自分の能力や判断に対する確信
・柔軟性:変化や新しい状況に適応する力
・組織コミットメント:組織の目標達成に貢献しようとする意識
■ コンピテンシーの歴史、注目されている背景
コンピテンシーの歴史は、1980年代のアメリカで生まれた考え方です。
ハーバード大学のデイヴィッド・C・マクレランド氏は米国文化情報局からの依頼を受けて業績と関係のある従業員の特性についての調査を行いました。 その調査では一般的にイメージのある「学歴」と「業績」の相関は強くないという結果になりました。
一方で、高い業績を挙げる従業員には共通した「行動パターン」やそれにつながる「性格」、「価値観」、「考え方」があることがわかりました。
この調査結果により、成果を挙げられる従業員の行動特性をモデル化し、評価基準などに組み込むことで従業員全体の行動の質を向上して測定する、コンピテンシーという手法が確立していき、アメリカでは1990年代初頭から起業に広がっていきました。
日本ではバブル崩壊後である1990年代後半に、それまで「ヒット商品が売れ続ける時代」から「一度ヒットしても早く廃れてしまう時代」へと移行しました。
その中で「成果主義」を重視して、従業員にも高いパフォーマンスを出し続けられる行動が求められるようになりました。 そのため、アメリカに続いて日本でも評価指標の1つとしてコンピテンシーを取り入れる動きが増えたのです。
■日本企業におけるコンピテンシーの必要性
日本において最初にコンピテンシーが注目されたのは、バブル崩壊以降のことです。バブル崩壊によって、企業の人事評価制度は年功序列から成果主義へとシフトしていきましたが、成果主義に基づいた評価基準の一つとしてコンピテンシーが導入されるようになりました。
時代が進み、昨今では労働人口の減少が深刻な社会課題となっています。労働力不足の問題を解決するためには、すべての従業員が行動の質を高め、組織として生産性の向上を図っていかなければいけません。そのための手段として、再びコンピテンシーに注目が集まっているのです。
コンピテンシーと類語や関連語との違い
コンピテンシーは個人の職業上の成功に必要な能力のことですが、それと似た言葉にも微妙な違いがあります。ここでは、コンピテンシーとそれぞれの類語や関連語との違いを詳しく見ていきましょう。
コンピテンシーとスキルとの違い
コンピテンシーとスキルはしばしば混同されますが、実は異なる概念です。スキルは特定の作業やタスクを遂行するための具体的な技能や知識を指します。例えば、プログラミングや外国語などがスキルに該当します。
これに対して、コンピテンシーはより広範で、仕事を効果的に遂行するために必要な能力、態度、知識を総合的に含む概念です。コンピテンシーは単に技能を超え、問題解決能力やチームワーク、リーダーシップなど、より包括的で柔軟な対応を可能にする資質を含みます。
コンピテンシーとアビリティとの違い
コンピテンシーとは、総合的な行動能力を意味し、特定の職務や状況において成功を収めるために必要とされる一連の能力や特性を総合的に包含した概念です。
具体的には、リーダーシップ、コミュニケーション、問題解決能力など、特定の職務を遂行する上で必要な各種のスキルや才能が含まれることが多いです。
それに対して、アビリティは、特定のタスクや活動を実行するために必要な、より具体的な個々の能力や才能を指します。これは、生まれつき持っているものであることもありますし、また特定のトレーニングや経験を通じて鍛え上げられるものであることもあります。
コンピテンシーとコア・コンピタンスとの違い
コンピテンシーは個々の人が保有する能力や特性を示し、これは特定の職務や状況での効果的な行動を可能にします。これは特定のスキル、知識、または行動パターンを指し、これらが個人の成果やパフォーマンスに影響を与えます。
一方、コア・コンピタンスは、組織や企業全体が持つ、競合他社に比べて優れた独自の能力や専門知識を指します。これは、企業が競争環境で優位に立つために必要な独自の技術や知識、リソース、能力などを指す用語です。
コア・コンピタンスは、企業が長期にわたって培ってきた重要な強みや、市場における競争優位を確立するための基盤となります。
コンピテンシーとケイパビリティとの違い
コンピテンシーは、個人が職務を遂行する際に必要とされる特定のスキル、知識、行動、態度を指します。
一方で、ケイパビリティは、組織や個人が特定の成果や目標を達成するための全体的な能力や潜在力を指します。これは、単なるスキルや知識だけでなく、資源、プロセス、システムといったさまざまな要素の組み合わせを含んでいます。
ケイパビリティは、特定のタスクを遂行するための能力よりも、より広範な範囲での可能性や適応性を示します。
要するに、コンピテンシーは個人の具体的なスキルや特質に焦点を当てているのに対し、ケイパビリティはより広い視野で、組織や個人が持つ総合的な能力や潜在力を指す言葉です。
コンピテンシー評価の活用シーン
ここではコンピテンシーがどのような場面で活用できるのか、「採用」「人材育成」の2つのシーンについてご説明していきます。
■採用面接におけるコンピテンシーの導入
コンピテンシーは採用面接で活用することができます。採用面接でコンピテンシー評価を行うことによって、自社が求める行動ができる人物なのか、入社後成果を出すことができる人物であるのかを見極めることができます。
コンピテンシー評価を採用面接で実施する場合は、「直近で最も成果を上げたエピソードがなんですか」「その際にどんな工夫をしましたか」など、具体的な行動をとったのかを質問することが重要です。
また、採用面接でコンピテンシーを活用するメリットは、下記のようなことが主に挙げられます。
①評価のバラつきが少なくなる
主観的な「印象」や「感覚」も大切ですが、それに偏り過ぎると面接官・採用担当者ごとに基準や評価軸のズレが生じやすくなります。 事前に自社、募集職種に合ったコンピテンシーを採用に関わる従業員同士で共通認識を持っておくことでより効果的に望ましい人材の採用に繋がります。
②求職者・応募者の満足に繋がる
①のような客観的な評価やフィードバックが得られることは求職者・応募者側にとってもありがたいものです。
「なんで受かったのか/落とされたのかあまり分からない」という状態では、落選者の不満が大きくなったり、通過者の辞退増加や入社前後で感じるギャップが大きくなる可能性があります。
③面接・採用担当者の負荷が減る
面接・採用担当者の「目利き」に任せ過ぎると、人間は判断すべきことが多いと選ぶのに大きな労力を割かなければならないため、当人達の負荷が大きくなる傾向があります。
あらかじめコンピテンシーという共通の指標で見るべきポイントを絞って任せる事でより担当者のパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。
一方でデメリットとしては、評価基準を作成するには事前に時間を要する場合が多いため、計画的なコンピテンシーの策定、運用が必要な点が挙げられます。
■人材育成におけるコンピテンシーの導入
人材育成にコンピテンシーを導入することも、一般的な活用シーンの一つです。 ハイパフォーマーを育成する研修内で、コンピテンシーの要件を伝え、浸透させていくことで、従業員が成果を上げる行動を取ることを促します。
そのためには、事前にコンピテンシーモデルを定め、研修内で「どのように考え、行動すればパフォーマンスを出すことができるか」を伝えていきます。
また、研修をするだけではなく、コンピテンシーに基づいて個人の成長目標を設定することで、従業員の積極的な行動を促します。従業員が成果創出に向けて何をすればいいのかを明確にすることができ、達成可能性を高めることができるので、従業員のモチベーション向上も期待ができます。
■人事評価におけるコンピテンシーの導入
コンピテンシーを人事業化に導入することのメリットとして、評価のブレをへらすことができる点があります。コンピテンシー評価を行うために、ハイパフォーマーにヒアリングを行い、評価項目を作成し、その評価項目に基づいて従業員の思考や行動度合いを測ります。
また、副次的なメリットとして、評価基準にハイパフォーマーのノウハウやコツが反映されているため、パフォーマンスを上げるための望ましい行動や思考が従業員に共有され、会社全体としての生産性向上も期待できます。
■コンピテンシーの運用ポイント
このようにコンピテンシーは採用、育成、評価など様々な場面に応用して導入することが可能ですが、導入しただけで上手く運用されないというケースも珍しくありません。 では成功のコツは何でしょうか。ポイントは「仕組み化」です。
採用面接や社内研修、評価面談の際に使用している既存システムやフォーマットにコンピテンシーを組み込むことで、必然的にコンピテンシーを基に思考や行動をせざるを得ない環境をつくり、モノサシを当て続けることが非常に重要です。
また、今は会社に眠るデータを活用し、営業や品質管理といった職種ごとだけでなく、職種×会社ごとのカスタマイズされた「理想とされる行動」を明文化し、各現場で活用されているようですが、これも原理はコンピテンシーの考え方と近しいと思います。
DXの活性化によって、一層このような活用方法は増えていくでしょう。
コンピテンシー評価導入のメリット・デメリット
コンピテンシーを導入した際のメリットとデメリットを紹介します。
■コンピテンシー評価導入のメリット
コンピテンシー評価導入のメリットは大きく下記の4つがあります。
①優秀な人材の獲得、育成ができる
採用面接や人事評価にコンピテンシーを活用することによって、自社の事業や業務にあった特性を持っている、パフォーマンスを出しやすい人物を獲得、育成することができます。
たとえ現時点ではスキルが不足していても、成果をあげるために必要なコンピテンシーを持ち合わせていることが分かれば、育成後の活躍を期待できます。
一方で、スキルは十分にあるけれども、コンピテンシーを持っていない場合は、自社が求めているような働きが望めない可能性が高まるため、採用しないという判断が先んじてできるのです。
②従業員全体のパフォーマンス向上が期待できる
採用面接、人事評価、研修にコンピテンシーを活用することで、従業員にとってコンピテンシーは自分自身の評価や成長にも関わる重要な指標となります。
そのため、コンピテンシーを従業員の間で普及することができ、従業員がパフォーマンスの出し方を理解し、PDCAを回し、努力することで、会社全体としての生産性向上が期待できるでしょう。
③納得感のある評価ができる
コンピテンシーを人事評価に取り入れることで、これまでは絶対的なKGIやKPIの達成率などの定量的な指標でしか評価できなかったものを、コンピテンシーによって成果を出すまでの過程の行動を評価することができるようになります。
また、コンピテンシー評価では、評価に値する行動が明確に示されているため、これまで上司からみた印象や感覚で評価されていた定性的な部分を、公平に評価することができるようになります。これによって、評価を受ける従業員の納得感も高まるのです。
④人事評価の負担が減る
③にも繋がりますが、定性的な要素を評価して優劣を付けることは大変難しく、特に人事・評価担当者が悩みやすいポイントです。 コンピテンシーを活用することで従業員の納得感を生むと共に、評価者の運用コストも低減させて、より効果的な人事評価の運用を行う事ができます。
■コンピテンシー評価導入のデメリット・課題
コンピテンシー評価導入のデメリットは3つあります。
①コンピテンシー策定のコストが高い
コンピテンシー評価は、全企業共通のテンプレートがあるのではなく、個社ごとにコンピテンシーを作成する必要があります。さらに、一企業に一つのコンピテンシーがあればいいというわけではなく、部署や業務によって異なる行動特性が存在しているため、個別にコンピテンシーを作成する必要があるのです。
また、コンピテンシーを策定するためには、ハイパフォーマーの行動分析やヒアリング、コンピテンシーモデルの作成、人事評価などの運用面の整備など、導入までにかかるコストが大きいということがデメリットと言えます。
「せっかくコンピテンシーを作ったのに、運用に乗らずに忘れられてしまった」などといったことがないよう、導入までのステップを具体的に描くことが必要です。
②「正しい」コンピテンシーの作成は難しい
策定したコンピテンシーが、必ず成果を生むとは限りません。 一度コンピテンシーを策定して完了するのではなく、実際に運用し、何度も修正を加えながら、精緻なコンピテンシーにブラッシュアップしていくことが必要なのです。
こういったコンピテンシー策定・運用に対する正しい理解がないと、コンピテンシーを運用した現場から不満の声が生まれてしまうでしょう。
③柔軟な環境変化への対応が難しい
コンピテンシーは、部署や業務によって細分化して決めれられている分、事業内容や業務内容の変更などに柔軟に対応することが困難です。 企業の成長にともなった、事業の変化、業務の変化、組織編成の変化などに合わせてコンピテンシーを修正するためのコストは大きいと言えるでしょう。
さらに、頻繁にコンピテンシーが変更されることによって、従業員は何を目指すべきなのか分からなくなってしまうという懸念もあります。
④定期的な改善が必要である
コンピテンシー評価は導入して終わりではなく、定期的な振り返りや改善が欠かせません。運用中にメンテナンスが必要になるのはコンピテンシー評価のデメリットだと言えるでしょう。
当初はうまく機能していたコンピテンシー評価も、自社の変化や市場・時代の変化によって機能しなくなるケースがあります。新型コロナウイルスの感染拡大は良い例で、テレワークが普及したことでコンピテンシー評価の見直しを迫られた企業は多かったはずです。
自社で定義したコンピテンシーが業績アップのために機能しているかどうかの検証を重ね、うまく機能していないようであれば、より的確なコンピテンシーを再定義しなければいけません。
コンピテンシーの導入方法・手順
コンピテンシーの導入までの方法について解説します。
■コンピテンシー評価導入の手順
ここでは、一般的なコンピテンシー評価導入までの手順を解説していきます。
①ハイパフォーマーの調査・インタビューを実施する
ハイパフォーマーにインタビューを行い、他の社員との違いを抽出し、成果につながっている行動特性を洗い出していきます。
インタビューだけでなく、ハイパフォーマーの周囲の同僚にインタビューを行ったり、ハイパフォーマー自身の日々の仕事の様子を観察したりなどして、ハイパフォーマー自身が気づいていない行動特性を見つけるのも有効でしょう。
②コンピテンシーを抽出する
ハイパフォーマーへの調査から導き出した行動特性を、コンピテンシー・ディクショナリーの要素と照らしわせ、コンピテンシーの候補を選定します。
コンピテンシー・ディクショナリーとは、ライル・M.スペンサー とシグネ・M.スペンサーが1990年代に発表した、「さまざまな職務に通じ得るコンピテンシーリスト」のことです。
「コンピテンシーの評価項目群」と、それを細分化する「コンピテンシーの評価項目」、評価するための行動が体系的にリスト化されているため、このリストの中からインタビューをもとに抽出した行動特性を洗い出すことで網羅性を担保することに役立ちます。
ただ、コンピテンシー・ディクショナリーもあくまで例ですので、自社特有の行動特性があれば残してもよいでしょう。
③企業のビジョン・ミッション、戦略とのすり合わせをする
洗い出したコンピテンシー候補の中で、企業理念やビジョン・ミッションにそぐわないものがあれば排除してきます。こうすることで、現実と理想のバランスを調整していきます。
④評価に取り入れるコンピテンシーの選定
コンピテンシーの中で、評価に取り入れるコンピテンシーを選定します。 すべてのコンピテンシーを評価に取り入れてしまうと項目が多すぎて運用の負担がかかってしまいます。
コンピテンシーの中でも特に影響力が強いものとそうでないものがあるため、 成果への影響が大きく、継続的に従業員の能力育成に使うことができるコンピテンシーを選ぶと良いでしょう。
⑤コンピテンシーのレベル分けをする
各コンピテンシーに3~5段階程度のレベルを設け、人事評価に活用しやすいようにします。公平性を保つためにも、レベルごとの達成度や習熟状態の判断がはっきり分かるよう、基準を明確化しましょう。
⑥テストして調整をする
コンピテンシー評価のたたき台ができたら、評価基準が適正かどうかテスト運用をします。 テストでは自社のハイパフォーマーを評価基準に照らし合わせ、実際に高い評価になるかどうか確認しましょう。
中程度の業績の社員についても、評価をし、ハイパフォーマーより高評価にならないか確認をします。 複数回にわたって複数人を評価すると、より精度の高いコンピテンシー評価基準を策定できます。
【参考資料のご紹介】
「従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン」はこちらからダウンロードいただけます。
コンピテンシーの5段階レベル
コンピテンシーを用いた評価は5段階のレベルに分かれています。このレベルイメージを元に評価対象の従業員が、どの段階の行動をしているかを評価していきます。
■①受動行動
受動行動は、いわゆる「指示待ち」の状態を指します。上司や周囲からの指示があるまで行動を起こさず、具体的な指示がないと行動し切れない従業員が当てはまります。評価としては、場当たり的や一貫性がないという評価ができます。
■②通常行動
通常行動とは、行うべきことを必要なタイミングで行うことを指します。任された業務を「ミスなく・確実にこなそう」という前向きな思考を持っていることがポイントですが、決められたこと以上のことを行う意欲はなく、決められたことをそのまま行う普通レベルの評価と言えます。
■③能動・主体行動
能動・主体行動とは、明確な目的や判断に基づき主体的に行動することを指します。
例えば、任された業務でより良い成果をおさめるために、自主的に情報収集やスキルアップのための学習をしたりなど、決められたルールの中で能動的に工夫をするような従業員のことです。
■④創造・課題解決行動
創造・課題解決行動は、自ら工夫をして現状の状況を変化させようという行動を指します。
例えば、社内で新たなプロジェクトが始まった際に、自主的に提案をしたり、アイデアを出すような行動が該当します。評価としては、PDCAサイクルを回し、高い成果を出すために考え行動できるなどという評価ができます。
■⑤パラダイム変換行動
パラダイム変換行動とは、新たな発想・アイデアで周囲の状況を変えるような行動のことを指します。新たなアイデアを提案し、イノベーションを起こすだけでなく、リーダーシップを発揮して周囲に好影響を与える点も評価されます。
代表的なコンピテンシーモデル
■モデル化のポイント
コンピテンシーモデルを作成するには、まず「目指す人物像」を明確にします。 例えば「好業績を上げる」「作業効率がよい」などの目標に対するコンピテンシーを把握し、それぞれに適した評価を整理していきます。 以下では、コンピテンシーモデルのベースとなる三つの型について解説します。
<実在型モデル>
コンピテンシーモデルを作成する手法として最も一般的に用いられる手法です。 実際に高い成果をあげているハイパフォーマーをモデルとしてコンピテンシーを策定するため、現実に即したコンピテンシーモデルを作成することができ、比較的実用的です。
しかし、作成したコンピテンシーがモデルとしたハイパフォーマー個人の特性に偏ってしまっていないか、他の従業員でも獲得しうるものであるかは確認をする必要があります。
<理想形モデル>
理想形モデルは、企業が理想とする人物像を策定し、その理想人材からコンピテンシーを抽出するという方法です。企業理念や事業戦略などから逆算して策定するので、実在の人物から考える実在型モデルよりも策定の難易度が下がります。
事業が始まったばかりでハイパフォーマーがまだ生まれていない業務などにおいても、理想形モデルであればコンピテンシーを策定することができます。
しかし、理想を追い求めすぎてコンピテンシーのハードルが高すぎ、現場の従業員の意欲をそいでしまう懸念もあるので、レベルの調整は要注意です。
<ハイブリッド型モデル>
実在型モデルと理想形モデルの良い部分を組み合わせたモデルが、ハイブリッド型モデルです。
実在のハイパフォーマーから抽出したコンピテンシーの中で、企業理念などの理想から逆算した際に不足している部分も盛り込んでコンピテンシーを作成することができるため、より実用がしやすいモデルを策定することができる方法です。
コンピテンシー定義の一覧
コンピテンシーの研究を行っているSpencer & Spencerからは下記のように「コンピテンシーの定義」が発表されているので抽出→整理の参考にしてください。 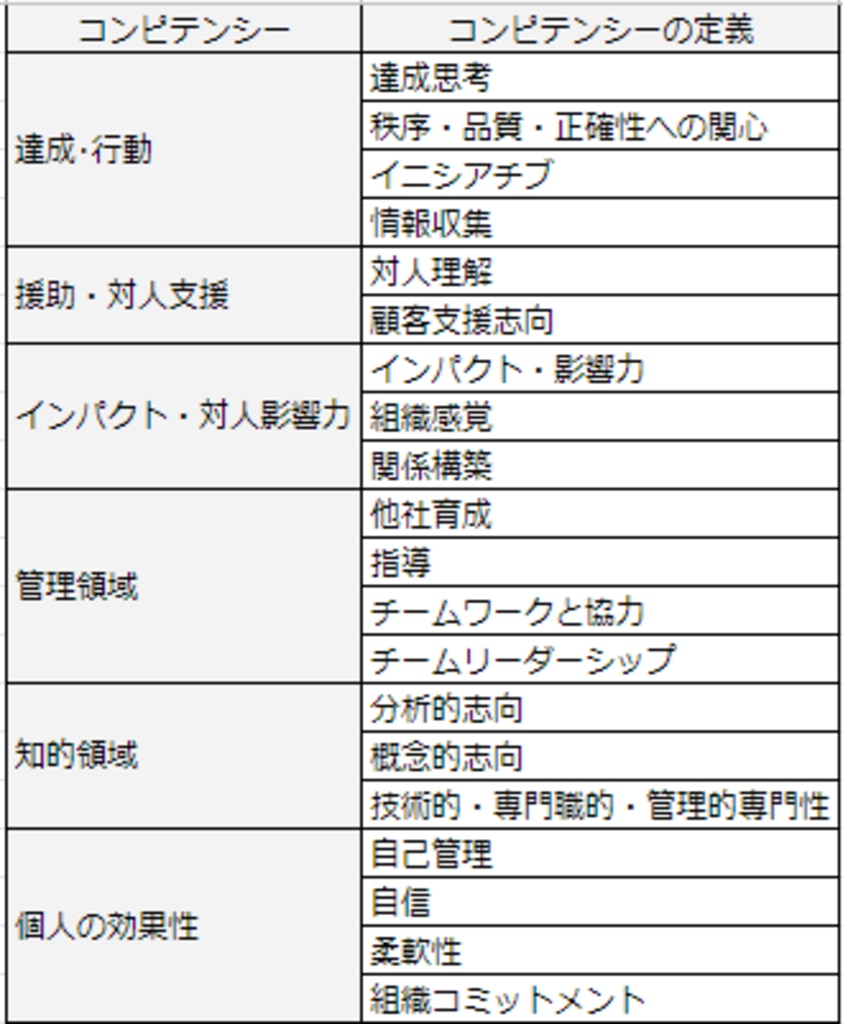 出典:Spencer & Spencer「コンピテンシー・ディクショナリー」(1993)
出典:Spencer & Spencer「コンピテンシー・ディクショナリー」(1993)
コンピテンシー評価の導入と運用のポイント
コンピテンシー評価は、従業員の能力と潜在力を効果的に測定し、組織の人材育成とパフォーマンス向上に貢献するために重要です。その導入と運用には、戦略的な計画が必要です。ここでは、コンピテンシー評価を成功させるための三つの主要なポイントについて詳述します。
明確な評価基準の設定
コンピテンシー評価を導入する際、最初に行うべきは、企業の目標と密接に連携した評価基準を設定することです。これには、特定の職位や役割で期待される具体的なスキル、知識、行動特性を明確に定義する作業が含まれます。
評価基準を明確にすることで、従業員自身も自らのパフォーマンスを客観的に把握し、自己改善の方向性を定めやすくなります。また、評価プロセスの透明性が保たれ、従業員の受け入れやすさが向上します。
継続的なトレーニングとサポート
評価システムの導入後、従業員に対してそのシステムの使用方法や目的を教育するためのトレーニングが必須です。トレーニングプログラムを通じて、従業員は評価基準の理解を深め、自己評価や同僚評価を効果的に行うためのスキルを習得します。
さらに、評価プロセスにおけるフィードバックの受け方とその活用方法についても学べます。このようなサポートは、評価システムの有効性を高め、組織全体のパフォーマンス改善に直接的に寄与します。
評価結果の活用
評価結果を単なる数値で終わらせず、それを基に具体的な行動計画を立案し、実行することが重要です。
個々の従業員の強みを活かした業務配置や、必要なスキル開発のための研修プログラムの提供など、組織として評価結果を積極的に活用することで、従業員のモチベーションの向上やキャリアパスの明確化が期待できます。
また、定期的な評価を通じて、従業員の成長を促し、組織全体の競争力を強化することも可能になります。
コンピテンシー評価の活用事例
では、実際にコンピテンシー評価はどのように活用されているのでしょうか。ここでは、実際の企業・団体のコンピテンシー評価の活用事例をご紹介します。
共済組合A
共済組合Aでは、組合の理念に合致する人材の採用に向けた新たな取り組みとして、コンピテンシー(能力やスキル)を活用する方法を導入しました。
これまでは、採用プロセスにおいて履歴書や職務経歴書が中心的な役割を果たしてきましたが、それだけでは候補者の潜在的な能力や価値観を十分に評価することが困難でした。
この新たなアプローチを導入することで、候補者の具体的な経験やスキルだけでなく、その背後にある思考パターンや価値観などを理解し、より適切な評価を行うことが可能となりました。
共済組合Aの目的は、教職員に対する福祉サービスの提供であり、そのためには単に知識や技能を有するだけでなく、共感力や責任感などのコンピテンシーが重要となります。
これらの能力は、組合員に対して真に価値のあるサービスを提供するために不可欠な要素であり、従来の採用プロセスでは評価が難しい部分でした。
この問題を解決するために、共済組合Aではコンピテンシー診断ツールを導入しました。これにより、候補者が持つ潜在的な能力や価値観をより具体的、かつ効果的に見極めることが可能となり、組合員にとって価値あるサービスを提供するために必要な人材を採用することができました。
メーカーB社
メーカーB社では、製品開発の革新性と品質向上を目指し、コンピテンシー(スキルや知識、態度)を重視した人材採用戦略を採用しました。この戦略は、特に「チャレンジする人」という特性を持つ人材を探す際に重要となりました。
しかし、従来の採用方法では、このような特質を見極めるのが困難でした。
そこで、メーカーB社では、社内で成功している従業員のコンピテンシーを詳細に分析しました。その結果、それらの特性を新たな採用基準として取り入れることを決定しました。これにより、革新的な思考を持ち、積極的に新しい挑戦を行う人材を探し出すことが可能になりました。
また、現代社会ではWeb面接の機会が増えてきています。このような状況下でも、面接では見えにくい候補者の内面的特性を把握するために、コンピテンシー診断が非常に有効でした。
このような取り組みにより、採用後のミスマッチを大幅に減らすことができ、社内の革新文化を支える人材を獲得することに成功しました。これは、メーカーB社の長期的な成功にとって非常に重要な成果です。
サービス業C社
サービス業C社では、多様な事業展開を行う中で、コンピテンシーを活用した人材採用で次世代のリーダーを育成する取り組みを行いました。従来、エージェントからの紹介に頼っていた採用方法では、実際に働いてみないと候補者の本質がわからないという問題がありました。
そこで、コンピテンシー診断ツールを導入し、候補者の細かい特性を評価することで、企業文化にマッチする人材を見極めることができました。
特に、「ストレス耐性」や「チームワーク」など、実際の業務で重要となる特性を明確に把握し、それに基づいた採用決定を行うことで、企業の長期的な発展に貢献する人材を確保することができました。
これにより、これまで曖昧であった「求める人物像」が明確になり、採用段階からコンピテンシーの評価ができるようになりました。
また、コンピテンシー診断を行うことで、これまで会社の中でイメージしていた求める人物像が違った角度から分析できることがわかりました。採用の効果を高めるだけではなく、自社で育成するべき人材像も、コンピテンシー評価を活用することでより幅広く考えることができるようになりました。
社員のモチベーション管理ならモチベーションクラウド
リンクアンドモチベーションは、導入実績12,560、509万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました
・業績が伸び悩み、組織の一体感が不足している
・優秀な人材の採用や育成がうまく進まない
・給与や待遇に対する不満の声が多くなってきた
といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。
▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら
記事まとめ
いかがでしたでしょうか。コンピテンシーという言葉の意味、活用シーン、導入方法などを解説してきました。
成果だけではなく、コンピテンシーを使った評価を取り入れることで、人材の獲得、育成をより効果的に行うことができるようになるとご理解いただけたのではないでしょうか。
組織経営にとって重要な要素である人材マネジメントに、コンピテンシーを取り入れてみてはいかがでしょうか。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼コンピテンシーに関する記事はコチラ
コンピテンシー評価とは?導入メリット・デメリットや必要性、導入の手順について解説
コンピテンシーに関するよくある質問
Q:コンピテンシー評価と職能資格制度の違いとは?
コンピテンシー評価とよく比較されるのが、多くの日本企業において採用されてきた職務遂行能力評価(職能資格制度)です。コンピテンシー評価では、行動に結びつく性格や思考パターンを含めた総合的な能力を評価します。
一方、職能資格制度では、能力やスキル・知識など単独の能力を評価します。
コンピテンシー評価は「従業員が評価に納得しやすい」「適材適所のマネジメントがしやすい」「能力開発がしやすい」といった利点がありますが、導入・運用の負担が大きい点などはデメリットだと言われます。
一方、職能資格制度は「中長期的な人材育成がしやすい」「ゼネラリストの育成に向いている」といった利点がありますが、年功序列の評価になりやすく、人件費が高額になりがちなのがデメリットだと言われます。
Q:コンピテンシー評価を導入している企業は?
従来の日本企業にはコンピテンシー評価が馴染まず、導入が進みませんでした。しかし、90年代以降に多くの研究が発表されてコンピテンシー評価のメリットが次第に認識されるようになり、導入企業が増えていきました。
代表的なところでは、ソニーが1995年から新卒採用にコンピテンシー評価を導入しており、アサヒビールは1999年に人材育成・任用を目的としてコンピテンシー評価を導入しています。ユニチャームは役員候補者の育成のために、NECや味の素、JTBや東京電力などは人事評価のために導入しています。







