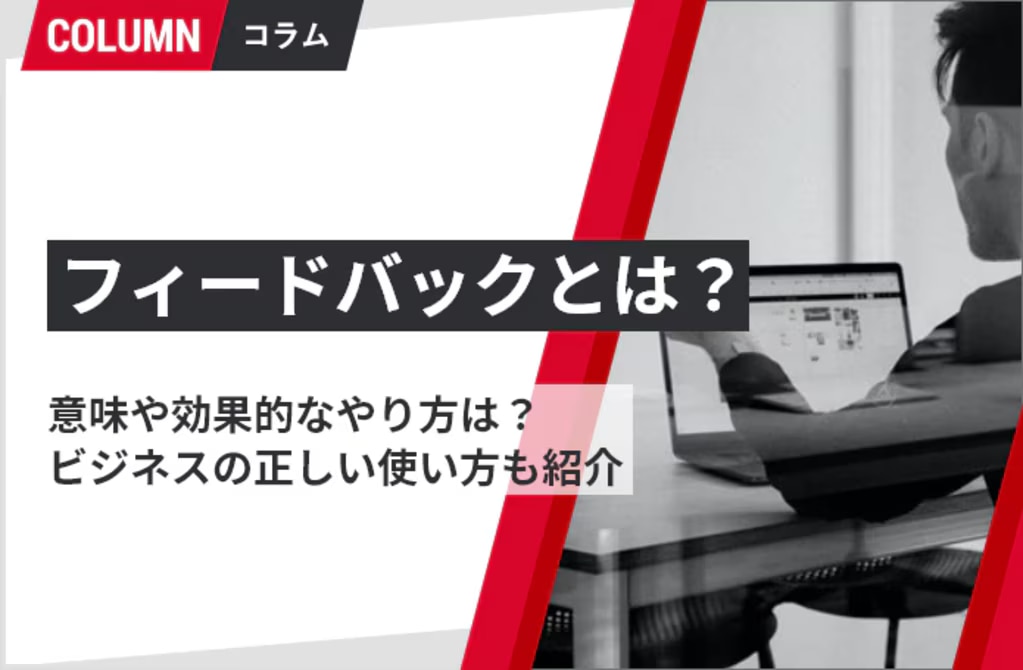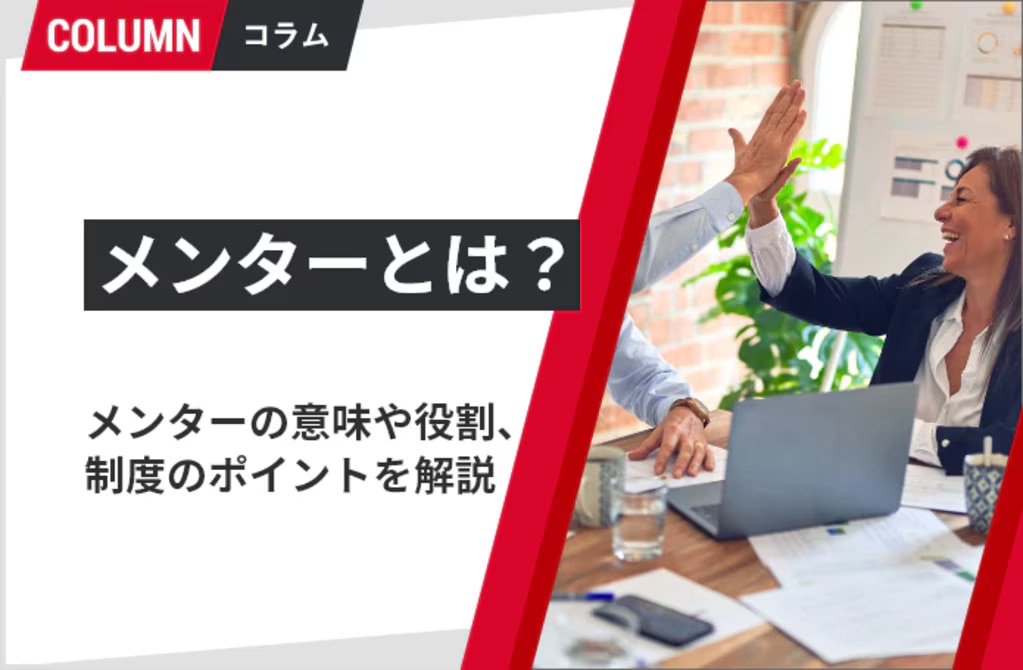山陰合同銀行×守島教授 地方銀行の枠を超えた企業変革への挑戦 ~たゆまぬ対話で培った変革のDNAとは~
地方銀行の再編は30年以上前から続いています。1990年に132行あった地銀は、2025年には97行まで減少。青森銀行とみちのく銀行の合併では、独禁法の特例が初めて適用されるなど、再編の動きは一層加速しています。
「金利のある世界」が戻ったいまも楽観視はできません。一見追い風に見える中でも、2025年4〜6月期決算では上場地銀の約4割が減益を計上するなど、明暗ははっきりと分かれているのが現状です。人口減少や首都圏への一極集中による預金流出といった構造的なリスクが高まる中、事業と組織のあり方を抜本的に変えていくことが不可欠となっています。他業界にとっても、その変化のプロセスは学ぶべき点が多くあります。
このような中で、「地域金融機関」という枠組みを超え、抜本的な構造転換に挑んでいるのが山陰合同銀行です。事業戦略と連動した人材ポートフォリオの再構築と、対話を軸とした組織変革により、事業成果を大きく伸ばしています。
本稿では、株式会社山陰合同銀行 取締役頭取・吉川浩氏と人材マネジメント論(人的資源管理論)が専門の守島基博氏との鼎談を通じて、山陰合同銀行の挑戦を支える原点について探ります。
【収録日】
2025年7月15日
【スピーカー】
・株式会社山陰合同銀行 取締役頭取 吉川 浩氏
・一橋大学名誉教授 学習院大学教授・経営学者 守島 基博氏
【モデレーター】
・株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員 川内 正直
▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら
リンクアンドモチベーション 川内:山陰合同銀行様は、オンリーワンの取り組みを進める地方銀行として今大きな注目を集めています。人口減少率が全国平均を上回る山陰地方を基盤としながら、積極的な拠点展開と事業の高付加価値化によって大きな成長を遂げています。
近年は大都市圏での展開を進め、貸し出しの原資となる預金残高は山陽・関西・東京で2兆円を突破しました。さらに、本業での収益力を示す顧客向けサービス業務における過去4年間の成長率は、山陰地方で約120%の成長を実現しながら、東京では約170%、関西では約290%という高い伸びを記録しました。さらに、社内でキャリアを重ねた女性役員を代表取締役に登用、外国籍人材を社外取締役に迎えるなど、経営改革も進んでいます。
しかし、注目すべきはそのニュース性だけではありません。
その成長を支えているのは、同社が長年取り組んできた「人づくり・組織づくり」です。定年退職などで行職員数が自然減少する中でも、人材ポートフォリオの見直しやリスキリングを進めることで、成長分野への人材シフトを加速させています。また、組織状態を表すエンゲージメントスコアも年々上昇しており、働きがいも向上しています。30歳未満の若手行員の離職率は、目標である5%以下を達成する見込みとなっています。
本日は、山陰合同銀行の吉川頭取と、学習院大学 経済学部 経営学科教授であり、一橋大学名誉教授でもいらっしゃいます守島基博先生をお招きし、「組織と事業の変革」についてじっくりお話を伺ってまいります。
変化を受け入れ、自ら変化するのが、ごうぎんらしさ
リンクアンドモチベーション 川内:早速ですが、まず「山陰合同銀行らしさ」についてお伺いしたいと思います。吉川様は、どのように捉えていらっしゃいますか。
山陰合同銀行 吉川頭取:一言で申し上げますと、「変化を受け入れる。自ら変化する。」これこそが山陰合同銀行らしさだと考えております。
今、私たちの想定をはるかに上回るスピードで世の中が変化しています。その変化に臆病になったり、「自分は変われない」と思う行員が増えてしまったりすると、組織は立ち止まり、成長できなくなり、やがて埋没してしまうでしょう。そうならないよう、変化を前向きに受け入れ、自分たち自身も変化していきたい。変化をポジティブに捉え、チャンスに変えていきたい。こうした考え方は、山陰合同銀行らしさの一つであると思います。

リンクアンドモチベーション 川内:そうした山陰合同銀行らしさは、昔から育まれてきたものなのでしょうか。それとも、最近になって生まれてきたものなのでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:最近になって醸成されてきたという実感はあります。私たち経営陣もそうですし、行職員も同じように感じていると思います。ただ一方で、「変化するDNA」のようなものは、元々あったと思います。
私たちがフランチャイズ(※)としているのは島根県と鳥取県です。この2県の人口は47都道府県中、下から2番目と最下位です。少子高齢化が進んでいるのはもちろん、事業所の数も徐々に減少しています。いわば「課題先進地域」とも言えるでしょう。ですが、課題の前に立ち尽くしているだけでは、地方銀行の大きな使命である「地域を守る」ことを果たせず、地域は衰退してしまします。そうならないように、変化せざるを得なかったという側面もあると思います。
※フランチャイズ:金融業界で用いられる用語で、主たる営業基盤・担当エリアを意味する。一般的な「チェーン加盟店方式」とは異なる。
リンクアンドモチベーション 川内:地方銀行が変化していく中で、今後の役割や在るべき姿は、どのように描いていらっしゃいますか。
山陰合同銀行 吉川頭取:私たちの大きな役割は、地域を守り、地域を育て、地域のみなさまのお役に立つことです。これが変わることはありません。東京一極集中が進む中、地方には厳しい逆風が吹いているとよく言われますが、だからといって、地方が沈んでいくようなことはあってはならないし、そんなことはないと思っています。
今後、地方銀行同士の競争がますます激しくなる中で、いかにして生き残っていくのか。その答えは、やはり「変わり続けること」です。しなやかに変化し続けることで生き残っていきたいと考えています。
また、地方の金融機関も積極的に首都圏に進出したり、金融業以外の事業展開を行うなど、もはや「地方銀行」というカテゴリでは語れない世の中になりつつあります。もしかすると将来、「そう言えば、昔は地方銀行ってあったよね」と言われる時代が来るかもしれません。ただ、そのくらいのイメージを持って変わり続けていかなければ、この先、生き残っていくことはできないでしょう。
守島教授:「地方創生」が叫ばれて久しいですが、地域そのものが変わっていかないと、一極集中する都市圏にはなかなか対抗できません。その時、地域を変えていく中心的な存在になるのは何だろうかと考えると、私は地方の金融機関、特に銀行だと思っています。その意味で、山陰合同銀行さんは自分たちが変わることで、同時に地域も変えていくという戦略を取っていらっしゃる。その姿勢が非常に頼もしいなと感じました。

「課題先進地域」だからこそ、成長の機会も多くある
リンクアンドモチベーション 川内:山陰合同銀行様は、電力事業に参入したり、スタートアップ企業と連携したり、山陰にとどまらず山陽や関西、さらには東京へ拠点を拡大したり、実に様々なチャレンジをしています。従来の枠を超えた取り組みを進める原点には、どのような思いがあるのでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:私たちは、課題に向き合い、課題を解決することで進化していくことをビジネスモデルとしています。「課題先進地域」というのは、考えようによっては「課題があるからこそ成長できる地域」であるとも捉えられます。
たとえば、近隣の中国地方でも瀬戸内側には大手製造業などの企業が多くあります。こうした企業は、取引先からのプレッシャーなどから「脱炭素」への意識が必然的に高まっています。一方、山陰地方は「脱炭素が大事なのは分かるけど、それ以前に経営課題が山積している」という企業が大半です。私たちは山陰の「リーディング・バンク」と自認していますが、こうした環境からくる意識のズレを放置していていいのだろうかという葛藤がありました。「脱炭素に取り組みましょう」と、お客様に呼びかけをするような啓発活動も進めてきましたが、その他の経営課題に対して優先度を上げられない状況でした。
それならば、まずは自分たちがリスクを取って動き、それから地域に波及させていこうと。こうした発想から、2022年にごうぎんエナジー株式会社という再エネ発電事業子会社を立ち上げたという経緯がございます。
また、私たちはごうぎんキャピタル株式会社というベンチャーキャピタル会社を持っており、以前から地域のスタートアップを支援してきました。そこには、自分たちの街から出てくる創業案件・起業案件を育てていこうという考え方がありました。しかし近年は、東京や大阪のスタートアップとのネットワークを構築し、そのつながりを地域に還元することで、創業・起業の芽を生み出すことはできないかという発想にチェンジしています。それ以降、東京のベンチャーキャピタルを介して東京や大阪のスタートアップに投資をすることで、関係性を築いてきました。
その取り組みの一つが、今年3月に開催した「ごうぎんスタートアップフェス」です。これは、松江市にある私たちの本店に主に東京から約40社のベンチャーキャピタル、約70社のスタートアップをお招きしたイベントで、地元企業や行員合わせて総勢で400人規模のイベントになりました。地元の経営者、特に若手経営者と東京の参加企業の接点が生まれ、ベンチャーキャピタル、スタートアップの双方からも高い評価をいただきました。こうしたイベントを単発で終わらせるのではなく、継続的に取り組んでいくことで、地域の経営者の発想を刺激したり、チャレンジ精神を喚起し、地域のオープンイノベーションの創出に繋げたりしたいと考えています。
守島教授:吉川頭取から「課題先進地域」という言葉がありましたが、それは同時に「オポチュニティー(機会)先進地域」でもあるということです。課題がたくさんあるということは、機会もたくさんあるということです。工夫を凝らして課題を解決することで、地域も変わっていくし、銀行も変わっていくし、住民の意識も変わっていく。まさに、そこを目指していらっしゃるのだろうなと思いました。

女性取締役や外国籍の社外取締役など、着実に多様性を拡大
リンクアンドモチベーション 川内:山陰合同銀行様は、ボードメンバー、経営体制にも特徴があります。社内でキャリアを重ねた女性取締役や、外国籍の社外取締役がいらっしゃるのは地方銀行では珍しいと思いますが、どのような背景があるのでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:日本全体、地域全体が高度成長の波に乗っていた時代は、同質性にあふれた組織が強かったと思います。みんなが同じ考えを持ち、力を合わせて同じ方向に突き進んでいけば、うまくいきました。しかし、この変化の激しい時代において、同じやり方のままでは生き抜いていくことはできません。
特に、同じ年代の男性たちで意思決定をする従来の姿からは変わらなければならないと感じていました。性別にとらわれず、優秀な人材が活躍する組織が今後は生き残っていくだろうと考え、能力や人間力、向上心や協調性などの観点で女性管理職候補を十数人選抜し、育成するプログラムを開始しました。これが14〜15年前のことです。そして、その時の初期メンバーの一人が、2024年から代表取締役専務を務めています。
十数年前から計画的に進めてきた取り組みですが、初期メンバーの女性たちが部下など周囲に伝えていくことで少しずつ広がり、女性行職員の登用が進んでいったように思います。2021年にはプロパーの女性取締役も誕生し、社外取締役にはコンサルタント出身の女性にも入っていただくなど、じわじわと多様性を広げることはできています。
先日、東京で機関投資家向けの会社説明会を行った際には、社外取締役の全員が出席してくれました。我々の説明会は2021年12月開催から社外取締役が継続して参加していますが、極めて異例なこととして、投資家の方々からも評価をいただいています。その場で、取締役会の様子の質問を受けた一人の社外取締役は「我々は“ガチの取締役”だ」と語っていましたが、まさに言い得て妙だなと思いました。我々の取締役会は、事前の根回しは一切ありません。それでも、毎回非常に活発なディスカッションが行われます。実際に、社外取締役のみなさまは「山陰合同銀行の企業価値をいかにして高めていくか」ということを一切遠慮せずに議論し、真剣に取り組んでくださっています。いろんな意味で、多様性は確実に広がっているなと実感しています。
守島教授:重要なのは、「多様性を大切にし、様々な意見を尊重する」というポリシーが、一貫して全社に息づいていることだと思います。その点、山陰合同銀行さんは、女性管理職の登用から経営層でのディスカッションに至るまで一貫しています。そこがすごいところだと思います。
たゆまぬ対話が組織変革を後押しする
リンクアンドモチベーション 川内:成長分野に人材を配置していく一方で、定年退職などで行員の総数は少しずつ減っているかと思います。このような中で、人材ポートフォリオをどのように見直し、組織変革へとつなげているのでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:大元をたどれば、もう二十数年前から人材ポートフォリオの見直しは始まっていたと思います。当時は、職員の役割が業務ごとに明確に分けられており、営業は営業、窓口担当は窓口担当といったように固定的な配置が一般的でした。ですが、私たちくらいの規模の地方銀行だと、こうしたやり方ではハイコスト経営にならざるを得ません。
そこで、窓口や事務を担当していた行職員を、投資信託や保険商品の営業担当にシフトできないかと考えたのが最初です。それを実行できたのは、実際にシフトした行職員が、前向きに変化を受け入れてくれたからこそだと思っています。
証券業務に関しても収益性とシステムコストなどを照らし合わせると課題感があり、私たちが取り組むにはハードルの高いビジネスでした。一方で、地域のお客様のニーズも高いビジネスです。都市部では最高のサービスを受けられるのに、地方ではサービスを受けられないとなると、地方銀行としての責務を果たせていないことになります。じゃあどうしようかということで、私たちが選んだのは、野村證券様とのアライアンスでした。
この数年は、アライアンスや店舗の見直しやDXの取り組みなどで人材構造が変化し、法人営業やコンサルティング業務を担える行職員を育成するためリスキリングに力を入れています。一方で、窓口業務や事務業務は、正行員ではない方々にお願いしています。私たちは「パートナー職員」と呼んでいるのですが、もともと事務中心だった方々にも窓口のセールスなどを担っていただけるよう、理解を得ながらシフトを進めてきました。
また、当行の「役員IR」もユニークな取り組みです。これは、役員が従業員に向けて決算説明と意見交換を行う場で長年継続した取り組みです。決算期に合わせて半年に一度、役員が分担して営業店や本部の各部を回って財務状態や業績を説明したり、行職員とコミュニケーションを図ったりします。役員IRでは、行職員から文句に近いような声が出ることもありますが、そうした一つひとつの声に役員が丁寧に答えています。また、山陰合同銀行が進む方向や、行職員にどうあってほしいかというメッセージを直接伝えたりしています。今回のリスキリングや役割のチェンジについても役員IRで行職員に前向きに捉えてもらえるよう対話して回りました。

守島教授:戦略に合わせて人材ポートフォリオを変えるのは、今や必須といえます。特にリスキリングは、一人ひとりを変え、組織全体を変えるという意味で非常に重要な取り組みです。ただ、それを受け入れるかどうか、実行するかどうかは一人ひとりの行職員にかかっています。当然、行職員の気持ちを変えるには時間がかかります。
山陰合同銀行さんは、そこに20年前から取り組んでいらっしゃるということで、これは本当に素晴らしいことです。対話を続けていらっしゃるのが何より大事なポイントで、その結果、エンゲージメントも高まっているのだと思います。今、多くの企業がエンゲージメント向上に苦心していますが、結局は、経営と現場がどれだけ対話をし、どれだけ意思疎通を図れるかが重要です。山陰合同銀行さんは、そこを丁寧にやっていらっしゃるってきた点が素晴らしいと思います。
「エンゲージメントスコアが高いから問題ない」ではない
リンクアンドモチベーション 川内:守島教授から「エンゲージメント」というキーワードが出ましたが、山陰合同銀行様のエンゲージメントに関する取り組みについて教えていただけますでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:エンゲージメントサーベイを導入して、モニタリングと改善活動に取り組んでいます。やはり、サーベイによってエンゲージメントを可視化・数値化できるようになったのは大きなことだと感じています。部門ごと、部署ごとにスコアがつまびらかになるので、管理者側としては意識せざるを得ません。
初回のサーベイを実施した時は、スコアに一喜一憂する場面もありました。経営側もすべての結果を見るので、どうしても「この部署は問題があるのではないか」「どうしてここだけ低いんだ」といった見方になりがちです。一方で、スコアが良いところは目を向けられにくいという傾向もありました。ですが今は、スコアはあくまでも気づきを得る材料だと考えています。スコアが低いからといって何から何までダメということではありません。スコアから得た気づきをもとに、「どうしたら共感を生み出せるのか」「どうしたらモチベーションを上げられるのか」「どうしたらチームのベクトルを合わせられるのか」といったことを考え、取り組みを実行するためのツールだと捉えています。
以前はスコアが高い店舗はあまり注目していませんでしたが、今は「本当に問題はないのだろうか?」という視点で見るようにしています。たとえば、支店長は何でも聞いてくれるとか、ミッションに対して厳しさがないとか、ある意味で「ぬるま湯」の組織になっているかもしれません。人によっては、居心地が良いと感じている可能性もありますが、もし、そういった組織がハイスコアで評価されているとしたら本末転倒です。
やはり、厳しさの中にも働きがいがあり、環境的にも働きやすいというのが一つの理想です。そこを目指すためには、スコアを表面的に捉えず、丁寧に見ていく必要があります。ですから今は、特に所管する人事部にはエンゲージメントスコアと実態を両面から深く見るように伝えています。
離職で注目すべきは「中身」
リンクアンドモチベーション 川内:山陰合同銀行様は、人的資本指標の一つとして「30歳未満の行員の離職率」を5%以内に収めるという目標を設定しており、すでに達成が見えてきていると伺っています。
山陰合同銀行 吉川頭取:離職率の目標は達成見込みです。多様性という観点では、性別や国籍といった側面だけでなく、年代の多様性も欠かせません。そのために、「30歳未満の行員の離職率」を目標に掲げました。
私たちの人材ポートフォリオは50代が非常に厚くなっている一方で、若い年代は比較的薄くなっています。これは組織として大きな課題として捉えています。だからこそ、若い人に入っていただき、その発想や力を存分に発揮してほしいと思っています。若い世代がたくさんいることは組織として大きな武器になるので、せっかく門を叩いて入ってきてくれた人材には、できるだけ長く活躍してほしいという思いがあります。
ただ、30歳未満の行員の離職率が5%を下回ればそれでいいのかと言えば、そんなに単純な話ではありません。一時的には離職率の変動があると思いますし、離職の理由も様々です。たとえば、「新しいことに挑戦したい」「地元を活性化するために創業することにした」「資格を取ってより高いステージに挑みたい」など、前向きな理由による離職もあります。こうした離職には、むしろエールを送りたいと思っています。
逆に、会社への不満から辞めてしまったり、人間関係に疲弊して辞めてしまったりといったネガティブな離職は、私たち銀行にとっても本人にとっても不幸なことです。ですから、このような離職を減らすことにフォーカスしたいと考えています。もちろん、離職率は低いに越したことはありませんが、その中身に向き合うことが大切だと思います。
守島教授:10年ほど前までは、若い人たちはワークライフバランスやプライベートの充実を強く重視する傾向があったように思います。しかし今は少し変化しており、「どれだけ成長機会があるか」「どんな仕事ができるか」「社会にどう貢献できるか」といった点で会社を選ぶ人が増えています。こうした人材を引き止めるためには、成長機会を与えたり、資格取得を支援したりするのが有効です。
その意味で、吉川頭取がおっしゃっていた「銀行を辞めても、別の場で新しいチャンスをつかむのであれば喜んで送り出す」という姿勢は素晴らしいなと思いますし、実際にこうした姿勢の企業が今、人材確保の面で勝ち組になっています。山陰合同銀行さんはまさに好例の一つだと言えるのではないでしょうか。
山陰合同銀行 吉川頭取:今後は、当行離職後の「キャリアリターン」も積極的に受け入れていきたいと思っています。外の水を飲み、外の空気を吸うことで、自分がいた山陰合同銀行がどんな組織だったのかをあらためて感じると思います。その時に、「やりがいがあったな」「楽しかったな」と思ってもらえなければ、当然戻ってきてくれません。ですから、辞めた人が外から見た時に、あらためて魅力を感じられるような組織にしていかなければいけません。
山陰合同銀行が目指す「これから」
リンクアンドモチベーション 川内:最後に、今後の展望についてお伺いできればと思います。
山陰合同銀行 吉川頭取:人的資本経営というのは、ゴールのないテーマだと思っています。常に改善を意識し、1ミリでも前に進むことを考え、常に改善点はないかと見渡しながら経営していかなければいけません。
山陰合同銀行は業界の中でも「女性活躍が進んでいる銀行」だと言われていますが、さらに多様性を深めていくことが重要だと考えています。現在、職員の男女比はほぼ半々ですが、次に目指すべきは、管理者層やボードメンバーも男女半々に近づけていくことです。私がよく人事部に言っていることなのですが、「女性活躍」という言葉自体をなくしていきたいですね。
守島教授:今は、人的資本経営の時代だと言われています。その背景には、労働市場の逼迫、人材不足の深刻化という事実があります。その結果として起こっている変化が、働く人たちのバーゲニングパワー(交渉力)が非常に強くなっているということです。
私は、人的資本経営の時代というのは、言い換えれば「人材主権の時代」だと思っています。これからは、人材が力を持ち、労働市場の中を主体的に動き、自分の欲求を通していく時代です。そのなかで企業は、こうした人材をどのように戦力にするかを考えていかなければいけません。従来の戦力は、「割と簡単に言うことを聞いてくれる人材」でした。しかし、今後はそうではありません。極端な言い方をするなら、「言うことを聞かない人材」をいかに戦力にしていくか。これが、人的資本経営の時代の大きなポイントになると思っています。
山陰合同銀行 吉川頭取:私たちの取り組みは、まだまだ道半ばです。山陰合同銀行という名のとおり、山陰を本拠地とする銀行ではありますが、本拠地を守り抜くためにも、他の地域でも挑戦をして、他の地域のお客様のお役にも立っていきたいと考えています。少々宣伝めいてしまいますが、山陰以外のエリアの学生さんにも「ここで働きたい」と志してもらえるような銀行になっていきたいと思っています。様々な地域のみなさまに山陰合同銀行に興味を持っていただけたら嬉しいですね。
リンクアンドモチベーション 川内:お時間が迫ってまいりましたので、以上をもちまして、本日のトークセッションは終了とさせていただきます。ご登壇いただいたお二方、ありがとうございました。

▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら