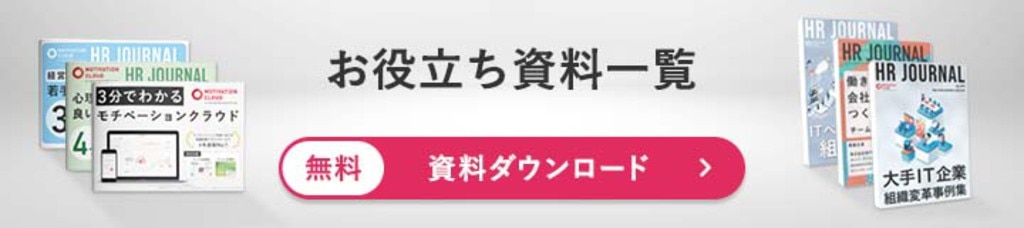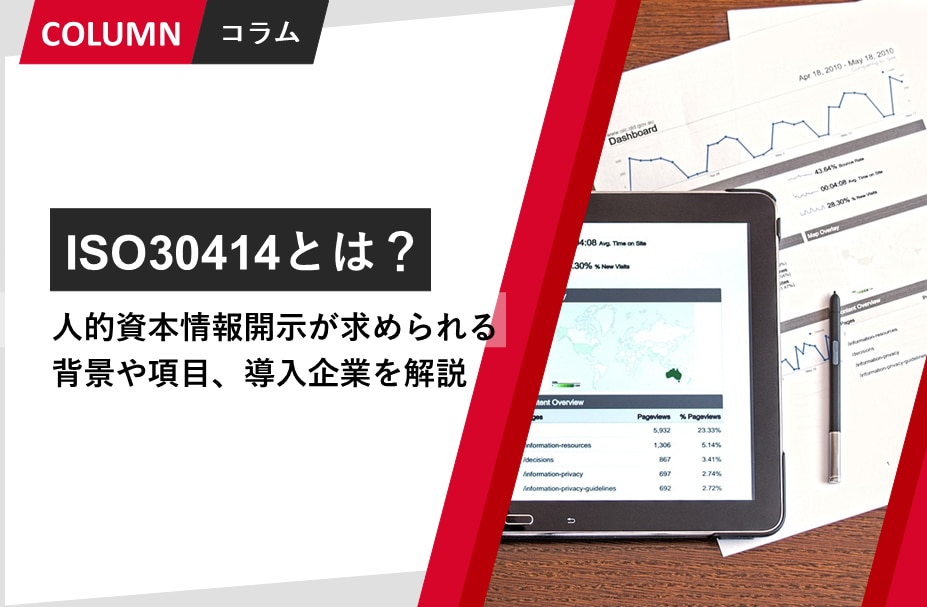
ISO 30414導入の実践ステップと企業課題
ISO30414は人的資本に関する情報開示の国際的なガイドラインです。2018年にISO30414が公開されたのを契機に、欧米企業では人的資本に関する情報を開示する動きが見られるようになり、日本でも人的資本経営への関心が高まるきっかけになりました。
今回は、ISO30414の内容や注目される背景、人的資本に関する具体的な開示項目などについて解説していきます。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
目次[非表示]
▼ISO30414日本第一号取得企業が語る「人的資本開示」の義務化に向けて行うべきこととは
▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら
人的資本開示に関する国際標準ガイドライン「ISO30414」
ISO30414は人的資本に関する情報開示の国際的なガイドラインで、2018年にISOが公開したものです。
▼ISO30414日本第一号取得企業が語る「人的資本開示」の義務化に向けて行うべきこととは
ISO30414とは?
上述のとおり、ISO30414は人的資本に関する情報開示のガイドラインで、ISOのマネジメントシステム規格の一つです。組織が自社の従業員に関する人的資本の情報を定量化し、開示するための国際的な指標として設けられました。
人的資本開示とは?
人的資本開示とは、従業員に関する情報(スキル、定着率、多様性、健康、安全など)を、投資家やステークホルダーに対して非財務情報として開示することを指します。これは従来の「人件費=コスト」という見方から一歩進み、人材を企業の持続的成長を支える“資本”として捉える発想に基づいています。
たとえば、ある企業が「研修投資額」「女性管理職比率」「従業員エンゲージメントスコア」などを開示することは、単なる人事情報の公開ではなく、「人材にどれだけ投資し、それが成果にどうつながっているか」を明らかにする行為です。これは、人的資本を“無形資産”として評価し、企業価値の一部として示すことに他なりません。
近年、ESG投資やサステナビリティ経営の観点から、人的資本開示は国際的にも注目されており、ISO 30414をはじめとする基準がその整備を後押ししています。
ISO30414と他の人的資本関連規格との違い
ISO30414は、人的資本に関する情報を定量的かつ体系的に開示するための国際規格であり、企業内外のステークホルダーに対して透明性と信頼性のあるデータ提供を可能にします。これは主に、内部報告と外部開示の両方に対応したガイドラインで、11の評価カテゴリ(例:採用、育成、多様性、労働生産性など)を網羅しています。
他の規格との違いは以下の通りです:
・GRI(Global Reporting Initiative):サステナビリティ報告の国際基準であり、人的資本もカバーしますが、環境・社会・ガバナンス全体を対象としており、人的資本単独での詳細な指標は限定的です。
・SASB(Sustainability Accounting Standards Board):業種ごとのESG関連の指標を提供。人的資本に関する情報も含みますが、産業別のマテリアリティに焦点を当てています。
・IIRC(International Integrated Reporting Council):財務・非財務を統合した「統合報告」を推進。人的資本は「人的資源」として位置付けられますが、開示項目の具体性はISOより限定的です。
企業が複数のフレームワークに対応する際のポイントは、重複する指標(例:従業員定着率、多様性)を共通KPIとして統合管理し、各規格の目的に応じて出力フォーマットを調整することです。ISO30414は、これらの規格と相補的に活用することで、より信頼性の高い人的資本戦略の開示が可能となります。
ISO30414に記載されている項目
項目 |
内容の概要 |
主な指標例 |
|
企業の倫理遵守への取り組み |
苦情件数、懲戒処分件数、研修受講率 |
|
労働力関連の費用把握 |
総労働力コスト、採用コスト、離職コスト |
|
多様性の実践度 |
性別・年齢別構成、経営陣の多様性 |
|
リーダーシップ能力の評価 |
管理職一人あたり部下数、研修受講率 |
|
従業員満足度やエンゲージメント |
従業員満足度、定着率 |
|
健康・安全環境の実態 |
労災件数、健康・安全研修受講率 |
|
企業の生産性 |
従業員あたり売上・利益、人的資本ROI |
|
採用や離職に関する指標 |
採用効率、離職率、異動率 |
|
能力開発への投資状況 |
研修コスト、研修参加率、受講時間 |
|
後継者育成の進捗度合い |
内部継承率、後継者準備率 |
|
労働力の構成と外部依存度 |
従業員数、臨時労働力、フルタイム当量 (FTE) |
ISO30414の歴史と発展
ISO30414は、2018年に発行された初の人的資本情報に関する国際規格であり、企業が人的資本を数値で「見える化」し、社内外に開示できるよう支援することを目的としています。発行当初は任意適用のガイドラインとしてスタートしましたが、ESG投資やサステナビリティ経営の潮流とともに注目が高まり、特に欧州や日本の先進企業を中心に導入が進んでいます。
さらに、2025年春には大幅な改訂が予定されており、「人的資本の質的評価項目の拡充」「AI・DXスキルやウェルビーイング指標の追加」「サプライチェーンを含めた人的資本管理」などが新たに盛り込まれる見込みです。これにより、ISO30414は企業の人材戦略をより包括的に示す基準へと進化し、人的資本経営の国際的な共通言語としての役割が一層強化されることが期待されています。
ISO30414に注目が集まる背景
ESG投資への関心の高まり
ISO30414に注目が集まっている背景として挙げられるのが、ESG投資への関心の高まりです。ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を取った言葉です。
従来の投資判断は財務情報、つまり「儲かっているかどうか?」が基準とされてきました。しかし、VUCAと言われる、将来の予測が困難な時代において、財務情報だけで投資をするのはリスクが高いと考えられるようになりました。
企業が持続的に成長していくためには、短期的な利益だけを追求するのではなく、環境や社会、企業統治に関する課題と向き合い、その課題解決に貢献していかなければいけないとい考えられるようになり、投資家サイドも、ESGにどれだけ配慮し、どれだけ社会に貢献している企業なのかという点に注目して投資をするようになりました。これがESG投資です。
ESG評価が高い企業は、投資家から「持続的な成長が期待できる企業」という評価を受けやすくなっています。ESGのなかでも「Social(社会)」「Governance(企業統治)」は人的資本との関連性が高いため、人的資本に関する情報開示のガイドラインであるISO30414に注目する企業も増えているのです。
人材版伊藤レポートの発表
2020年9月、経済産業省は「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書(人材版伊藤レポート)」を発表しました。
人材版伊藤レポートとは、人的資本経営についての取り組みや、人材戦略に関わる経営陣、取締役、投資家の役割などの方策などを検討する研究会の報告書です。一橋大学の特任教授である伊藤邦雄氏を座長とする研究会であることから、通称「人材版伊藤レポート」と呼ばれています。
このレポートにおいては
「持続的な企業価値の向上を実現するためには、ビジネスモデル、経営戦略と人材戦略が連動していることが不可欠である」
としており、そのうえで、
「これまでも、人的資本に関しては定性的な評価や従業員数等の一部の数値が開示されてきたが、人的資本が競争力の源泉となる時代においては、経営戦略との連動という観点で人的資本、人材戦略を定量的に把握・評価し、ステークホルダーに開示・発信することが求められる」
としており、人的資本開示の重要性が記されています。
※参考:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~|令和2年9月 経済産業省
人材版伊藤レポートの発表は、日本企業が人的資本に関する情報開示に関心を持つきっかけになったと言われています。そして同時に、人的資本に関する情報開示の国際ガイドラインであるISO30414にもスポットが当たることになりました。
2021年のコーポレートガバナンス・コードの改訂
現時点において日本では、人的資本に関する情報開示について法令上の義務はなく、開示するかどうかは各企業の判断に委ねられています。しかしながら、2021年に東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを改定したことによって、上場企業には人的資本に関する情報開示が迫られることになりました。
2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改定では、以下のような補充原則が新設されています。
▼補充原則 2-4①
上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。
▼補充原則 3-1③
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。
▼補充原則 4-2②
取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。
※参考:コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)|株式会社東京証券取引所
ISO30414の目的
ISO30414が策定された目的としては、大きく以下の2点が挙げられます。
組織や投資家が人的資本について把握するため
ISO30414が策定された目的の一つとして、組織や投資家が人的資本について正しく把握することがあります。これまでも、統合報告書などに人的資本に関する情報を記載する日本企業はありましたが、人的資本に関する内容は定量的に記載するのが難しいため、定性的に記載されることがほとんどであり、企業によって項目も書き方もバラバラでした。
しかし、ISO30414によって人的資本に関する指標が明確にされたほか、多くの指標に計算式が設定されているため、定量的に記載しやすくなります。そのため、過去比較や他社比較もしやすくなります。これにより、企業側も投資家側も、より客観的かつ詳細に人的資本に関する情報を把握できるようになります。
企業の持続的な成長を支援するため
企業が人的資本に関する情報を開示するためには、まず人的資本を可視化しなければいけません。人的資本を可視化するためには、ISO30414に定められている項目に関するデータが必要になるため、データ収集のための仕組みや制度を整える必要があります。
こうしてデータを収集し、モニタリング・分析することで、自社の人的資本が組織の成長にどのくらい貢献しているのかということが分かるようになるため、より効果的な人材戦略を講じることができるようになります。効果的な施策・戦略によって人的資本を強化できれば、生産性や競争力が高まり、持続的に企業価値の向上を図っていくことができます。
ISO30414、人的資本開示に関する動き・取り組み
ISO30414、人的資本開示に関する動き・取り組みについてご説明します。
欧米諸国における動き・取り組み
近年、人的資本情報の開示義務化が世界的に進展しています。特に米国、EU、アジア各国では、企業に対して人的資本に関する情報の透明性を求める動きが強まっています。
米国(SEC)
米国証券取引委員会(SEC)は、2020年にRegulation S-Kを改訂し、上場企業に対して人的資本に関する情報の開示を義務付けました。具体的には、従業員数や人材の獲得・育成・維持に関する施策など、企業のビジネス理解に重要な人的資本の指標や目標を開示することが求められています。この開示は原則主義に基づいており、企業は自社にとって重要な情報を判断して開示する必要があります。
さらに、SECは人的資本管理(HCM)に関する開示要件の強化を検討しており、2024年10月に新たな提案を発表する予定です。
欧州連合(EU)
EUでは、2024年7月に「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」が発効しました。この指令は、企業に対して自社およびサプライチェーン全体における人権や環境への悪影響を特定し、対処する義務を課しています。対象となるのは、従業員1,000人以上かつ世界売上高が4億5,000万ユーロを超えるEU企業、およびEU域内で同等の売上高を持つ非EU企業です。
また、2024年からは「企業持続可能性報告指令(CSRD)」も適用され、対象企業は人的資本を含むESG情報を詳細に開示することが求められています。この報告は「ダブル・マテリアリティ」の原則に基づき、企業がESG課題から受ける影響と、企業が社会や環境に与える影響の両方を評価・報告する必要があります。
アジア諸国
アジアでもESG情報開示の動きが加速しています。中国では、2024年初頭に上海、深圳、北京の証券取引所がESG報告ガイドラインを発表し、主要インデックスに含まれる企業に対して2026年からのESG情報開示を義務付けました。これには人的資本に関する指標も含まれます。
日本では、2023年3月期から有価証券報告書において人的資本情報の開示が義務化され、企業は人材戦略や多様性指標などを報告する必要があります。
規制の違いと今後の展望
米国のSECは原則主義に基づき、企業が自社にとって重要と判断する人的資本情報を開示することを求めています。一方、EUのCSRDやCSDDDは詳細な報告基準を設け、企業に対して具体的な指標や目標の開示を義務付けています。アジアでは国ごとに異なるアプローチが取られており、各国の規制に対応する必要があります。
今後、企業は複数の規制に対応するため、ISO 30414などの国際的なガイドラインを活用し、人的資本情報の標準化と透明性の向上を図ることが求められます。これにより、ステークホルダーとの信頼関係を強化し、持続可能な成長を実現することが期待されます。
日本における動き・取り組み
企業に経営環境の変化に応じた人材戦略の構築を促し、中長期的な企業価値の向上につなげる観点から、人材戦略に関する経営陣、取締役、投資家それぞれの役割や、投資家との対話の在り方、関係者の行動変容を促す方策等を検討するため、2020年1月、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」が発足しました。この研究会の報告書は、通称「人材版伊藤レポート」として2020年9月に公表され、日本企業において人的資本経営、人的資本開示への関心が高まる契機になりました。また、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードには、人的資本に関する記載が盛り込まれました。 しかしながら、海外に比べると人的資本に関する日本企業の取り組みは後れをとっており、コーポレートガバナンス・コードへの対応を形式的なものにしないためにも、一歩踏み込んだ、具体的な行動が求められていました。そこで、経産省は2021年7月に「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置し、持続的な企業価値の向上に向けて、経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するかという議論を重ねてきました。そして、2022年5月にその報告書として、通称「人材版伊藤レポート2.0」を公表しています。 人的資本開示のグローバル基準であるISO30414への関心も高まっており、日本においては、株式会社リンクアンドモチベーションが国内で初めて認証を取得し、その後、豊田通商株式会社やModis株式会社も認証を取得しています。 ISO30414発効に対する企業への影響・課題などについては、以下の記事で詳しく解説しています。 >> ISO30414発効に対する企業への影響・課題とは?リリースの背景についても解説 https://www.motivation-cloud.com/hr2048/39774
ISO30414の導入によって期待できる効果・メリット
上述したISO30414の目的と表裏一体になりますが、ISO30414を導入することで以下のような効果が期待できます。
▼ISO30414日本第一号取得企業が語る「人的資本開示」の義務化に向けて行うべきこととは
ステークホルダーに透明性の高い人的資本情報を提供できる
ISO30414に則って情報開示をすることで、投資家をはじめとするステークホルダーは、企業の人的資本の状況を定性・定量の両面から把握することができます。そのため、従来以上に適正な評価を受けることができるはずです。
また、ISO30414に則って開示した情報は比較しやすいため、転職者が企業選びをする際も、人的資本に関する指標に優れた企業を選びやすくなります。労働市場においても差別化を図れるポイントになるでしょう。
人的資本の価値を効率的に高めていける
ISO30414に則って人的資本の状況を定量化し、それを分析することで、人的資本に関する課題も見えやすくなりますし、課題に対する改善施策も打ちやすくなります。経年でデータをとることで施策の効果測定もできるので、より効果的な取り組みや投資をすることができます。
ISO30414というものさしを基準にして、人的資本に関する課題改善、投資を繰り返すことで、人的資本の価値を効率的に高めていくことができるでしょう。
HRテクノロジーの推進
HRテクノロジーを推進することも、ISO30414の目的になり得ます。ISO30414の根幹にあるのは、人的資本を定量化してレポートすることです。たとえば、企業風土などの定性的な要素も、エンゲージメントスコアなどの定量的な指標を用いて説明することが求められます。
このように、従来であればデータ化するのが困難だったものも、昨今ではHRテクノロジーを活用することでデータ化でき、定量的に把握することができる時代になっています。定量的なデータに基づいて人事戦略を策定・実施し、成果を測定して改善するというPDCAサイクルを回すことは、ISO30414においても不可欠な取り組みになるはずです。そして、その基盤になるのがHRテクノロジーなのです。
ISO30414導入における課題と対応策
ISO30414は、コンプライアンスやダイバーシティ、生産性や後継者計画など、ステークホルダーの関心が高い11項目・58指標を網羅的にカバーしています。
すべての指標を開示することが推奨されているわけではなく、大企業と中小企業という分類に加え、社内に開示するのが良いか、社外に開示するのが良いという分類がされています。各項目・各指標を見ていきましょう。
▼ISO30414日本第一号取得企業が語る「人的資本開示」の義務化に向けて行うべきこととは
1. コンプライアンスと倫理
①苦情の件数と種類
不満や相談などを含む苦情の件数、および内訳。苦情に対する企業の取り組みを測る指標です。
②懲戒処分の件数と種類
懲戒処分の件数と内訳。違反・不正行為に対する企業の取り組みを測る指標です。
③コンプライアンス・倫理に関する研修を受けた従業員の割合
組織の行動規範、倫理、コンプライアンスなどに関する研修を受講した従業員の割合。倫理・コンプライアンスに対する企業の取り組みを測る指標です。
④外部に解決が委ねられた係争
外部の第三者に解決が委ねられた内部係争の数。内部係争に対する企業の取り組みを測る指標です。
⑤外部監査で指摘された事項の件数、種類、要因
外部監査で指摘された事項の数、種類および発生源とそれらへの対応。外部監査の指摘事項に対する企業の取り組みを測る指標です。
2. コスト
①総労働力コスト
組織が従業員に対して支出した金額。労働力の財務価値を測る指標です。
②外部の労働力コスト
コンサルタント、監査法人、派遣労働者、ギグワーカーなど、外部の労働力に関する費用の総額。企業が外部の労働力をどれだけ活用できているかを測る指標です。
③総給与に対する特定職の報酬割合
全従業員の総給与額に占める特定層の報酬割合。企業が、職種や階層にかかわらず公平な待遇を提供しているかを測る指標です。
④総雇用コスト
給与や諸手当など、従業員のために企業が負担した費用の総額。企業負担の保険料や人材育成、雇用、福利厚生などにかかる費用も含まれます。従業員の雇用にかかる費用を網羅的に測る指標です。
⑤一人あたり採用コスト
一人あたりの採用にかかるコスト。採用活動の効率を測る指標です。
⑥採用コスト
採用にかかる内部および外部の総コスト。採用活動の効率を測る指標です。
⑦離職にともなうコスト
自発的離職にともない発生するコストの総額。離職にともなう費用や機会損失額を測る指標です。
3. ダイバーシティ
①年齢
年齢層ごとの労働力の分布を測る指標です。
②性別
男女がどのくらいの割合で雇用されているかを測る指標です。
③障害者
障害者の労働力を活用できているかを測る指標です。
④その他
従業員の国籍や勤務年数など、ダイバーシティの実践度を測る指標です。
⑤経営陣のダイバーシティ
経営陣の性別や年齢、障害など、経営陣のダイバーシティの実践度を測る指標です。
4. リーダーシップ
①リーダーシップへの信頼
従業員サーベイなどのツールを用いてリーダー・管理職のパフォーマンスや従業員からの評価を測る指標です。
②管理職一人あたりの部下数
一人の管理職が直接管理している部下の数から、マネジメント効率を測る指標です。
③リーダーシップ開発
リーダーシップ研修などに参加したリーダーの割合。リーダー育成の実践度を測る指標です。
5. 組織風土
①エンゲージメント/従業員満足度/コミットメント
従業員サーベイなどのツールを用いて従業員のエンゲージメントや組織に対するコミットメントの度合いを測る指標です。
②従業員の定着率
企業が従業員をどれだけ定着させられているかを測る指標です。
6. 健康・安全・幸福
①労災により失われた時間
業務に起因して発生したケガや病気により失われた労働時間。労働環境の良し悪しを測る指標です。
②労災の件数
業務に起因して発生したケガや病気の件数。労働環境の良し悪しを測る指標です。
③労災による死亡者数
業務に起因して発生した死亡者数。労働環境の良し悪しを測る指標です。
④健康・安全に関する研修の受講割合
健康・安全に関する研修を受講した従業員の割合。健康・安全に関する知識の習得度合いを測る指標です。
7. 生産性
①従業員一人あたりEBIT/売上/利益
従業員一人あたりの業績。企業の生産性を測る指標です。
②人的資本ROI
人的資本に支払われた金額から得られたリターンの割合。人的資本に対する投資効率を測る指標です。
8. 採用・異動・離職
①募集ポストあたり書類選考通過者
募集したポストあたりの書類選考通過率、および全応募者のうちの書類選考通過者の数。企業の採用効率や採用力を測る指標です。
②採用従業員の質
採用した従業員のパフォーマンスを入社前の期待と入社後の評価で比較。質の高い人材を採用できているかどうかを測る指標です。
③採用にかかる平均日数
募集開始日から求職者の応募を受け入れる日までの平均日数。採用効率を測る指標です。
④重要ポストが埋まるまでの日数
重要ポストについて、募集開始日から求職者の応募を受け入れる日までの平均日数。重要ポストの採用効率を測る指標です。
⑤将来必要となる人材の能力
将来必要になる人材の能力に関する説明。中長期的な人材育成の方針を測る指標です。
⑥内部登用率
空席ポストに対して内部登用を通して埋まったポストの割合。企業内で有能な人材を育成・確保できているかどうかを測る指標です。
⑦重要ポストの内部登用率
重要ポストに対して内部登用を通して埋まったポストの割合。企業内で有能な人材を育成・確保できているかどうかを測る指標です。
⑧重要ポストの割合
企業全体に占める重要ポストの割合を測る指標です。
⑨全空席中の重要ポストの空席率
全空席ポストにおける重要ポストの空席数の割合。重要ポストへの人材の充当がうまくいっているかどうかを測る指標です。
⑩内部異動率
地域や機能を越えた組織内の異動の割合。企業内の人材の流動性を測る指標です。
⑪幹部候補の準備度
将来、重要ポストに就く可能性がある幹部候補の能力と準備度合い。重要ポストに対する後継者を育成できているかどうかを測る指標です。
⑫離職率
解雇、人員削減、転職、定年など、理由を問わず離職した従業員の割合。従業員の定着度合いや職場環境を測る指標です。
⑬希望退職率
自発的に離職する従業員の割合。従業員の定着度合いや職場環境を測る指標です。
⑭痛手となる希望退職率
離職による損失が大きい従業員が自発的に離職した割合。痛手となる離職の度合いを測る指標です。
⑮離職理由
離職理由ごとの割合を測る指標です。
9. スキルと能力
①人材開発・研修の総コスト
人材開発や研修、OJTにかけた総費用。従業員の教育にどのくらい投資をしているかを測る指標です。
②研修への参加率
研修に参加した従業員の割合。従業員にどのくらい能力開発の機会を提供しているかを測る指標です。
③従業員一人あたりの研修受講時間
従業員一人あたりの研修の平均受講時間。従業員にどのくらい能力開発の機会を提供しているかを測る指標です。
④カテゴリ別の研修受講率
研修のカテゴリごとの受講率。従業員が職種や役割に応じた研修を受講できているかを測る指標です。
⑤従業員のコンピテンシーレート
従業員のコンピテンシーについて、評価ツールやチェックリストを使ってアセスメントした結果の平均値。従業員のコンピテンシーを測る指標です。
10. 後継者計画
①内部継承率
重要ポスト数に対する、内部登用者の割合を測る指標です。
②後継者候補準備率
重要ポスト数に対する、後継者候補者数の割合を測る指標です。
③後継者の継承準備度
計画的に後継者を育成・確保できているかを測る指標です。
11. 労働力
①総従業員数
フルタイム、パートタイムにかかわらず、直接雇用されている従業員の数。直接雇用の労働力を測る指標です。
②総従業員数(フルタイム・パートタイム)
直接雇用の従業員数を、フルタイムとパートタイムに分けて算出した指標です。
③フルタイム当量(FTE)
フルタイムの人員に換算したときの総従業員数を測る指標です。
④臨時の労働力(独立事業主)
個人事業主の外部労働者数。外部の労働力をどのくらい活用できているかを測る指標です。
⑤臨時の労働力(派遣労働者)
外部の組織が雇用する外部労働力数。外部の労働力をどのくらい活用できているかを測る指標です。
⑥欠勤
病気、ケガ、個人的な事情など、突発的な欠勤の発生率を測る指標です。
ISO30414や人的資本開示の最新動向と今後の展望
ISO30414や人的資本開示に対する関心は、国内外で急速に高まっており、近年では法的・制度的な整備も進んでいます。
グローバルでは、米国・欧州を中心に義務化の流れが本格化しています。米国では、SEC(証券取引委員会)が2020年より上場企業に対し、人的資本に関する情報の開示を義務化。今後さらに詳細な指標の開示が求められる可能性もあります。EUではCSRD(企業持続可能性報告指令)やCSDDD(デューデリジェンス指令)により、2024年以降、多くの企業が人的資本を含むESG情報の詳細な報告を義務づけられます。
日本国内でも2023年3月期から、上場企業に対して人的資本の開示が義務化されており、「人的資本に関する基本方針」「指標(KPI)」「多様性」などが有価証券報告書に記載されるようになりました。経産省や東証も開示の質的向上を促すガイドラインを発行しており、企業の対応は今後さらに進む見込みです。
今後の展望としては、ISO30414の2025年改訂が予定されており、ウェルビーイング、AIスキル、多様性、社内風土などの項目が強化される見込みです。企業はISOやGRI、SASBなど複数の基準に対応しながら、人的資本を「見える化」し、経営・財務戦略に一体化する流れが加速しています。
投資家が求める人的資本開示の充実化
人的資本に対する投資家の関心は近年急激に高まっており、財務情報だけでは把握できない企業の「持続可能な成長力」を評価するために、人的資本の質的・量的な情報が重視されています。
投資家が企業に対して特に求める情報は、以下のような項目です:
・離職率や定着率:人的リスクの有無を測る指標
・研修・育成投資の金額と効果:人材のスキル向上と企業競争力の関係
・ダイバーシティ指標:女性・外国人・中途採用管理職比率などの多様性に関するデータ
・従業員エンゲージメントスコア:モチベーション・生産性との相関を見る指標
・労働生産性や人的資本ROI:人的資本に対する投資対効果
これらの情報は、企業の持続的競争力・組織の健全性・成長余地を判断する材料として評価され、投資判断に直接影響を与える要素となっています。
ISO30414の認証取得企業と導入事例
ISO30414の導入は、人的資本を「戦略的資産」として捉え、透明性と客観性をもってその価値を外部に示す取り組みです。認証取得は国内外で広がっており、導入企業は人的資本経営の高度化や、投資家・求職者への信頼性向上といった効果を得ています。
たとえば、ドイツのDWSやドイツ銀行は、早期からISO30414に基づく人的資本開示を行い、従業員のエンゲージメント改善や経営層の意思決定支援に活用。開示データをもとにした多様性向上施策やキャリア支援制度の設計により、人的資本ROIの改善を実現しました。
日本では、リンクアンドモチベーションが2020年にアジア初のISO30414認証を取得。人的資本の見える化により、従業員エンゲージメント指標の経年比較や部署別分析が可能となり、人事施策の精度が大きく向上しました。同社は開示情報をIRにも活用し、ESG投資家からの評価も高めています。
その他、国内では製薬・IT・製造業などを中心に導入が進んでおり、「離職率の定量把握と早期対策の実現」「研修投資の効果測定」などの成功事例が多数報告されています。
DWS、ドイツ銀行
2021年1月、ドイツ銀行グループのアセットマネジメント会社であるDWSが、世界で初めてISO30414の認証を取得しました。同年3月には、ドイツ銀行も人的資本に関する情報を開示した「Human Capital Report 2020」の評価を受け、ISO30414の認証を取得しています。
リンクアンドモチベーション
株式会社リンクアンドモチベーションは、2000年の創業以来、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を基盤に多くの企業変革を実現してきた企業です。2021年より、ISO30414の認証取得に向け、社内プロフェッショナルの育成をはじめとした準備を進め、2020年3月、世界で5番目、日本・アジアでは初となるISO30414の認証取得企業となりました。
まとめ
人材版伊藤レポートの発表やコーポレートガバナンス・コードの改定など、日本においても人的資本経営、および人的資本開示に対する関心が高まっています。
ISO30414の日本語訳版が発刊されるなど、人的資本開示の流れはますます加速していくと考えられているため、後れをとらぬよう、情報収集と準備を進めていきましょう。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
ISO30414に関するよくある質問
Q:ISO30414は義務ですか?
現時点(2025年時点)では、ISO30414の導入や認証取得は義務ではありません。ISO30414は、人的資本の情報開示に関する国際的なガイドラインであり、あくまで任意での活用が基本です。
ただし、今後の義務化の可能性は高まっています。たとえば、アメリカではSEC(証券取引委員会)が上場企業に対し、人的資本に関する情報の開示を求める動きを進めており、EUでもCSRD(企業サステナビリティ報告指令)により、非財務情報開示の義務が段階的に拡大しています。
一方、日本ではまだISO30414に関する法的義務はありませんが、政府は人的資本の「見える化ガイドライン」などを通じて開示を推進しており、将来的に準拠が実質的に求められる可能性もあります。
各国・地域で規制の濃淡はありますが、グローバル企業を中心に、国際基準に沿った開示体制の整備が求められる流れが強まっているといえます。
Q:ISO30414を取得するには?
ISO30414の認証を取得するためには、まずISO30414の58項目の指標に従って必要なデータを揃えることからスタートする必要があります。ある程度、データを収集できたところで、ISO30414の認証機関に申し込み、審査を受ける形になります。
Q:ISO30414を取得するメリットは?
ISO30414の認証を取得する最大のメリットは、社会的信頼を獲得できることです。外部の第三者である認証機関から証明(第三者認証)を受けることで、組織内外に対する説明責任を果たすことができ、それによって社会的信頼を得ることができます。統合報告書などで開示することで、投資家からもポジティブな評価を得ることができるでしょう。
また、人事部門の変革を促すことができるのもメリットだと言えるでしょう。企業がISO30414の認証を取得することで、人事部門の取り組みがどの程度、経営に貢献しているかが可視化されるようになります。人的資本に関するデータを効率的に収集するためにはHRテクノロジーが不可欠であり、体制構築を通して人事部門のDXを推進することができます。こうした取り組みによって、より経営に貢献できる人事部門へと変革を遂げることができるでしょう。