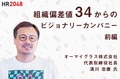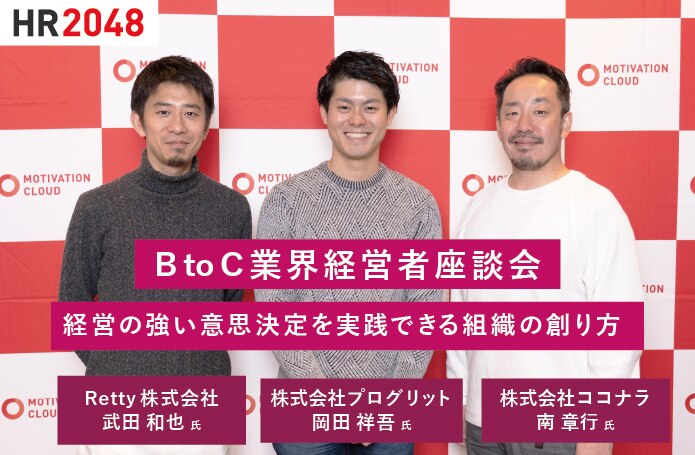
BtoC業界 経営者座談会 経営の強い意思決定を実践できる組織の創り方
【特別企画】
業界別経営者座談会 BtoC業界編。今回は下記の3社の経営者にお越しいただき、自社の経営において今悩んでいること、昔経験してきたこと、そしてこれからやりたいと考えていることなどを、ざっくばらんにお伺いしました。
■株式会社ココナラ:『一人ひとりが自分のストーリーを生きていく世の中をつくる』というビジョンを掲げ、インターネット上で個人の知識・スキル・経験を売り買いできるマーケットプレイスである「ココナラ」を運営。
2012年7月にローンチし、現在のユーザー数は150万人、累積取引件数は420万件を超える。知識・スキル・経験を売買できる国内最大級のマーケットプレイス。デロイトトーマツによる2017年度日本テクノロジーFast50(3年間の収益成長率)では、第1位(1,252%)を受賞。
■株式会社プログリット:“短期集中型”で実践的な英語力を身に付けられる英語コーチングサービス『プログリット』を展開。
従来の英会話教室のように講義形式ではなく、専属コンサルタントが一人ひとりの目標と課題に応じた英語学習の独自カリキュラムを作成し、生徒の学習をフォローすることに特化している。
■Retty株式会社:グルメサービス「Retty」を運営。2011年にサービスリリース、2018年には4,000万UUを突破。グルメサービス「Retty」は、エリアごとでおすすめしたい飲食店を紹介できる、実名制のグルメサービス。
直近ではヤフー株式会社と提携、戦略的なパートナーとして互いのリソースを活かしサービスを展開予定。
– 出た話題 –
・BtoC事業とBtoB事業で求められる組織の特徴
・組織の特徴に合わせたマネジメント必要
・エンゲージメントスコアが高いことが大事なのではなく、理解・コントロールできることが大事
【スピーカープロフィール】
株式会社ココナラ 代表取締役社長 南 章行氏
株式会社プログリット 代表取締役社長 岡田 祥吾氏
Retty株式会社 代表取締役 武田 和也氏
【モデレーター】
株式会社リンクアンドモチベーション 中堅・成長ベンチャー企業向けモチベーションクラウド事業 事業責任者 田中 允樹
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ エンゲージメントを可視化し、組織改善を行うサービス【モチベーションクラウド】はこちら
大きく異なるBtoCとBtoBの組織の特徴
リンクアンドモチベーション 田中 (以下、田中):本日は、モチベーションクラウドを活用頂いているBtoC業界の経営者お三方にお越しいただきました。BtoC業界ならではの組織創りの難しさや、その中で工夫されていることなどお聞きできれば幸いです。
プログリット 代表取締役社長 岡田 祥吾氏 (以下、岡田氏):よろしくお願いします。
Retty 代表取締役 武田 和也氏 (以下、武田氏):よろしくお願いします。
ココナラ 代表取締役社長 南 章行氏 (以下、南氏):よろしくお願いします。早速最初のテーマを私から。今回BtoC業界ということなのですが、改めて「to B(Business)」と「to C(Customer)」のサービスをやっている企業では、組織の違いが結構あるのではないかと思っています。
そもそも企業の成り立ちとして、to Bって「負の解消」を目的にサービスがつくられていることが多いと思います。そのためには、お客様の声をきちんと聞いて、論理的にサービスをつくり整えていくことが大切になってくる。
なので、しっかりお客様の声を活かすという意味でも、ボトムアップの経営が向いているんじゃないかと思います。to Cは「希望の実現」のような、「社会がもっとこうなればいいな」「人がもっとこうなればいいな」という願いからスタートしていることが多い。
お客様は多岐に渡るので、お客様の声全てを実現しようと思ったら、下手したら凡庸なものになってしまう。やることとやらないことを決めて、大切な1を取るけれど9は捨てるといった意思決定や一貫性が必要とされると感じます。
なので、組織としての意思決定も1人に寄せて、トップダウンで進めるということが多いのではないか、と感じます。
また、経営者がバリューで引っ張る会社なのか、ミッションで引っ張る会社なのか、という違いもあると思います。バリューであれば「いい会社をつくりたい」という人を惹き付け、ミッションであれば「いい事業をつくりたい」という人を惹き付ける。
例えば、うちは「to C」且つ「ミッションドリブン」の会社なので、モチベーションクラウドで測ると「経営理念」に関する項目への期待が異常に高いんです。

田中:すごく高いですよね。どうしてそんなに高まっていったのですか?
南氏:採用ですね。僕がほぼ全員の面談をしていて、めちゃくちゃミッションやビジョンを語っています。そして応募者の方にも、小学校時代まで遡って人生を聞き、この人の生き方とココナラが目指す世界観と合うのかどうかを考えています。
ココナラという会社のビジネスを頭で理解しているかどうか、というのはあまり重要視していません。それよりも、その人の生き方とココナラの世界観が合うかどうか。共感というよりも共鳴できるかどうかということを大切にしています。
そんなプロセスを経て入社した人たちなので、入社後に僕がミッションやビジョンをあまり語らないなんてことがあると、期待とのギャップが出てしまう。
組織のエンゲージメントは、ビジネスの成り立ちや組織の成り立ち、採用のところから繋がっているので、工夫が必要だなと感じます。
自社の組織の特徴に合わせたマネジメントを
田中:面白いですね。組織それぞれの成り立ちによってタイプがある、と。
南氏:難しさもあります。「to B」且つ「バリュードリブン」の会社とかを見ると、すごく楽しそうに働いているように見える。そういう会社は人や組織の在り方で惹きつけていたりするので、権限移譲されていて自由なように映る。
「あの会社はすごく楽しそうな施策をやっているから、うちでもやりましょう」みたいな声が挙がったりするのですが、そもそもの組織のタイプが違う中で、表面的な施策だけ真似ても意味がない。
組織のエンゲージメントを高めていく上で、期待に必ず応えることと、期待を下げることを明確にしていくことが大切だと思います。
武田氏:わかります。当社だと、「to C」と「to B」のサービスが6:4ぐらいの割合であるので、難しさは感じますね。社内で一番議論になるのが「User Happy」という考え方。ユーザーとは「店舗」なのか「エンドユーザー」なのかという議論です。
いつも喧々諤々の議論になりますが、「エンドユーザー」であると振り切っています。
田中:議論が難しそうですね。
武田氏:そうですね。いつも白熱した議論になります。最終的には全員で視点を上げて「どこを目指すのか」というところから皆で考えます。「店舗のハッピー」はもちろん大切。
けれど、僕らがもっと突き抜けたサービスを提供していくためには、やっぱり「エンドユーザーのハッピー」を大切にしよう、と伝えます。
これはいろんな企業が抱える永遠のテーマなんじゃないかなと思います。

岡田氏:当社は企業向けに英語研修を提供しているチームがあるのですが、ほとんどは「to C」ですね。
社員は「どうやってお客様の人生を変えるか」「それによって日本、世界を変えることができるのか」ということに100%の思いをぶつけている集団です。その点では「ミッションドリブン」と言えると思います。
ただ、当社はミッションとバリューのバランス型だとも思います。僕自身、会社を経営する意義についていつも考えるのですが、基本的には2つです。
1つは、会社のミッションである「世界で自由に活躍できる人材を増やす」を実現するということ。
もう1つは、社員の人間的成長です。社員が入社してからいつか辞めていくまで、人によって期間は様々だと思いますが、その期間の中でスキルだけじゃなくて「人間として成長した」と思って卒業していってほしいと強く願っています。
ですので、僕はバリューをすごく大事にしています。当社には、これだけは大切にしてほしいというバリューが5つあります。
「Customer Oriented – 顧客起点で考えよう」「Go Higher – 高い目標を掲げよう」「Own Issues – 課題は自ら解決に導こう」「Respect All – 互いにリスペクトし合おう」「Appreciate Feedback – フィードバックに感謝しよう」、この5つを実践できたら人として成長できるし、仮に卒業しても今後も絶対に活躍できると思っています。
ですので、ミッションで束ねるのに加えて、バリューもとても大切にしています。
南氏:ミッションとバリューがきちんと接続されていますよね。
指針を伝え続けることで判断基準が揃う
田中:to Cのビジネスということで、先ほどお客様からの要望が多岐に渡るというお話もありましたが、例えばお客様の声に対してNOということを社内に伝える上で、工夫されていることってありますか?
岡田氏:僕はよくNOと言います。よくあるのが、当社は英語コーチングサービスを提供しているのですが、3ヶ月で約50万円のサービスです。
この価格を高いと感じるお客様もいるし、社員が「お客様のために値引きしないんですか」と質問してくることもあります。
僕はそれに対して、「しない」と伝えます。「提供する価値」や「利益を出すこと」についての経営ポリシーに基づく考えなのですが、社員にきちんと伝えるために必ず週に1回社員に向けてブログを書くようにしています。
そこに社員がコメントすれば、必ず僕がコメントを返す。それを毎週、約2年間続けてきました。何がYESで何がNOなのか、その考え方の土台になっている思想は何か、ということをとにかくずっと伝え続けるというのを意識しています。

田中:2年間毎週、ポリシーや指針を伝え続けるのはすごいですね。
岡田氏:ポリシー、指針、思想みたいなところを発信し続けることによって、普段の仕事の中での意思決定の時に「確かあんなことを言っていたな」という判断の拠り所になっていけばいいなと思っています。
南氏:僕らも、「スキルマーケット」というサービスを提供する中で、最初「500円均一にします」とか「会うのは禁止」とか、普通に考えたら異常です。
でもそうしないと立ち上がらないという強い思いと戦略があってのことで、多数決で決めたら絶対実現できなかった。「値段を上げてください」とユーザーさんからも社員からもよく言われました。
でも「500円じゃないとダメなんだ。マーケットが立ち上がらないんだ」と言い続けてきました。この辺りを社員にどうやって納得してもらうかというのは、組織コンディションを整えたり、コミュニケーションスタイルを工夫したり、プロセスが大事なところだと思いますね。
武田氏:そうですね。当社でもto Cのサービスは、プロダクトオーナーを最初に決めて、プロダクトオーナーの意思決定でどんどん使いやすいものにしていきます。
広告やマーケティングという予算も含めた判断が必要なところに関しては、僕がしているという感じですね。
エンゲージメントスコアをコントロールできるかどうかが重要
田中:ありがとうございます。モチベーションクラウドをご活用頂いている会社さんもいらっしゃいますが、率直に効果や価値についてどう感じられますか?
岡田氏:僕はモチベーションクラウドは“競馬”のようなものだと感じています。
田中:競馬というのは新しい例えですね。どういう意味でしょうか?
岡田氏:賭ける方ではなくて、ジョッキーの感覚です。経営者がどれだけ上手く扱えるかが大事だと感じます。競馬って、走るべき時に走り、ゆっくりすべきときにゆっくりさせないと、結局勝てないんです。
モチベーションクラウドを使って一番良かったなと思うのは、僕がエンゲージメントスコアを扱うのが上手くなった。昔は、スコアが上がるのも下がるのもコントロールできなかったですね。「なんでこんなに上がるんだろう」「なんで下がるんだろう」というように、理解不能でした (笑)。
今は、「これぐらい満足度上がるだろうな」「これぐらい期待度が下がるだろうな」ということが分かってきて、精度が高まっています。
1年程前は、全然状況をつかめていなくて、スコアがえげつなかったんです。社員が約70名で、スコアが86とかでした。

南氏:すごいスコアですね。
岡田氏:これはおかしいんですよ。僕が理解できていない。コントロールできていないんです。競馬で言うと、暴走している状態。当時何をやっていたかと言うと、「楽しい会社をつくろう」ということだけ、僕が言っていたんです。
僕の意図としては「仕事を一生懸命頑張って、お客様が喜んで、結果として勝利を得て楽しむ」ということを実現したかった。
でも、みんなには全然違う伝わり方をしていて「リラックスオンザビーチ」みたいな。「楽しくワイワイ、なんか最高」、それは会社じゃないでしょうという状態。
田中:86だと出現率0.1%とかですね。
岡田氏:もはやサークルですね。会社じゃない。なので、「スコアが下がってもいいから厳しく仕事しよう」と振り切って。
スコアは1年間、ずっと下がりました。でもこれで良かった。スコアが高いことが大切じゃない。組織状態をコントロールできることが大事だな、と思いました。
南氏:僕らも「AAAまでは目指さない」と決めました。「AAで留めておこう」と。今よりも上のスコアを目指していくとなると、どこかで緩くなってしまうリスクもある。「勝って美酒に酔おう」という要素がないと、戦えない。
田中:そうですね。モチベーションクラウドは従業員の満足度を高めるためのもの、と捉えられがちですが、経営者が理想の組織状態を目指すためのものさしでもあると思います。
結果を見て、アクセルを踏むこともあれば、ブレーキを踏むこともある。
南氏:そうですね。ただ、確実に言えるのは、スコアが50を下回っているときはしんどい。上げないといけない。本当に、伝えたいことが伝わらなくて、事業が進まないし、経営者のマインドシェアも組織運営にとられてしまう。
組織がマイナスの状態の時に、課題を明確にしてきちんと対策をとって改善できるのがモチベーションクラウドのいいところですね。
岡田氏:質問項目に、更に踏み込んで考えてもらう項目があってもいいかもしれないですね。「上司はちゃんと厳しいですか?」とか。
南氏:わかります。「あなたは全力でやりきれていますか?」とか。問いかけるような質問があってもいいかもしれない。
田中:設問の追加や変更など、モチベーションクラウドというプロダクトへの期待もいただきました。本日はありがとうございました!

※本記事中に記載の肩書きや数値、固有名詞や場所等は取材当時のものです。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら