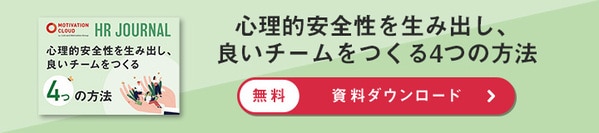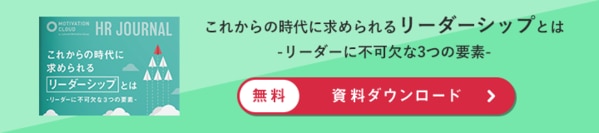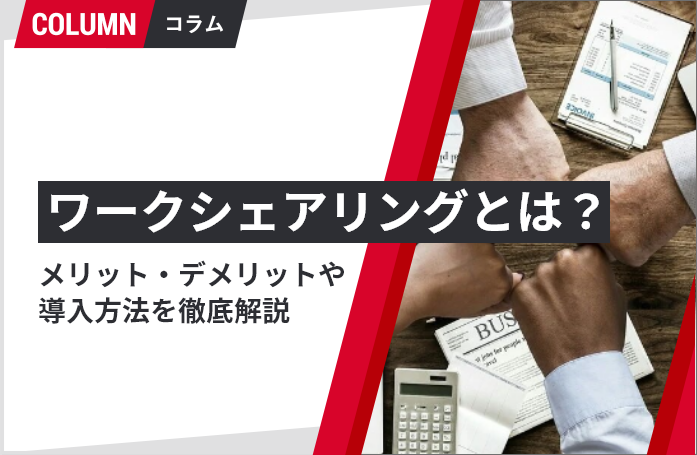
ワークシェアリングとは?メリット・デメリットや導入方法を徹底解説!
目次[非表示]
本記事では、ワークシェアリングの概要や導入のメリット・デメリット、更に導入の方法について説明していきます。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 今、知っておくべき【働き方改革の概要】がわかる!資料はこちら
ワークシェアリングとは?
ワークシェアリングとは、一人が担当していたタスクを複数人で分担することで一人あたりの労働時間を削減する取り組みのことを言います。「業務をシェアする仕組み」「労働時間を分け合う仕組み」と言われることもあります。厚生労働省のWebサイトには、「ワークシェアリングは、雇用の維持・創出を図ることを目的として労働時間の短縮を行うものであり、雇用・賃金・労働時間の適切な配分を目指すものである。」という記載があります。
※参考:ワークシェアリング導入促進に関する秘訣集及びリーフレットについて|厚生労働省
ワークシェアリングは、主に以下のような目的で導入されます。
・雇用の維持
ワークシェアリングは、経済的に困難な状況に対処するために雇用を維持し、従業員の解雇を回避します。
・失業率の増加抑止
ワークシェアリングは、失業率が急上昇するリスクを低減し、経済的な不況に対抗します。
・従業員の健康維持
ワークシェアリングは、一部の従業員に負担が集中して過重労働にならないよう、業務量のバランスをとり、従業員の心身の健康維持を図ります。
日本では、労働時間の削減や労働生産性の向上が課題とされており、働き方改革が推進されています。ワークシェアリングは、日本においては働き方改革の一環として位置づけられることもあります。
ワークシェアリングに注目が集まった背景
ワークシェアリングが今注目されている背景はどういったものがあるのでしょうか。
ワークシェアリングが提唱され始めたのは日本では約10年前からですが、海外では更に前から導入がされており、成功例も生まれ、進化をしています。
特に欧州では、失業率が急増した時代に、ワークシェアリングが失業対策の一つである雇用を創出する手段として広まっていった背景があります。
ワークシェアリングが注目されるようになった背景には2つのポイントがありました。
1つ目は、先程も説明をした失業率の高まりでした。失業率の改善が求められる時代や国において、ワークシェアリングは多くの人数で仕事を分担するために雇用口を増やすための解決策として用いられるようになったのです。
2つ目は、労働者への負担軽減です。長時間労働を強いらざるを得ない業務量では、ハードワークによって従業員が心身ともに疲弊してしまいます。これは離職や休職にもつながるため、安定的な労働力の確保をしたい企業にとっては問題です。
一人で行う業務を複数人で行うことにより、前述したように個人負担が軽減され、時間や心に余裕が生まれることで、効率的に生産性を上げることができるのがワークシェアリングなのです。
こういった背景から、ワークシェアリングが世界的に注目されるようになり、日本にもその流れがやってきています。
ワークシェアリングの種類
一口にワークシェアリングといっても、そのスタイルにはバリエーションがあります。ここでは基本的なワークシェアリングの形態をご紹介します。
■雇用維持型(緊急避難型)
雇用維持型(緊急避難型)とは、企業の業績が悪化した際に行うワークシェアリングを指します。
業績が悪化していても、すでに雇用している従業員を解雇することなく、その雇用を維持するために行うワークシェアリングのことです。
業績が悪化した企業では、人材の流出が大きな問題となります。そういった場合の対応策として、ワークシェアリングを取り入れ、現状の雇用を維持し、人材の流出を防ぐことが業績悪化を一日でも早く乗り越えるための土台となります。
■雇用維持型(中高年対策型)
2つ目の種類である雇用維持型(中高年対策型)は、中高年層の離職を減らすためのワークシェアリングです。
中高年層とは、定年以上の従業員をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。ワークシェアリングによって、短時間勤務や少ない勤務日数で中高年層を雇用し続けることで、より広く雇用を提供することができます。
さらにワークシェアリングを取り入れ、一人ひとりの負担を減らすことで中高年層が企業に残ってくれることは、ナレッジや技術の継承といった観点でも企業にとってメリットがあります。
■雇用創出型
雇用創出型とは、新たな雇用を生み出し、失業率を改善することに特化したワークシェアリングの形です。
ワークシェアリングによって、すでに雇用されている従業員一人あたりの労働時間を短くし、その分新たな従業員を雇うことで雇用の機会を増やすというものです。
景気低迷などで、求人倍率が低い場合、失業率を改善したい場合に用いられることがあります。
■多様就業促進型
多様就業促進型とは、多様なライフスタイルに合わせて、柔軟な働き方を実現するために用いられるワークシェアリングの形です。昨今進められている働き方改革の手段の一つでもあります。
育児や家事、介護などと仕事を両立するため、フルタイムだけではなく、短時間労働を導入する際に、一人あたりの業務量を減らすことができるワークシェアリングを導入するケースがあります。
多様就業促進型は、「ワークシェアリングで労働時間を調整する」「多様な働き方を企業や社会で受け止める」ことを目的とした業務の分かち合いなのです。
ワークシェアリング導入のメリット
ワークシェアリングを導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、企業側と従業員側に分けて、それぞれにとってのメリットを紹介していきます。
■企業側のメリット
企業にとってのメリットは、主に以下の5つがあります。
・労働環境の改善
従業員数を増やして、一人ひとりの業務量を減らすことにより、長時間労働などのハードワークが改善されます。
一人に対しての業務量が減るため、各人が本当に重要な業務に集中でき、生産性の向上が期待できるでしょう。また、業務の整理を行って無駄な会議などを減らし、効率を考えた「職場環境の改善」を行うことが可能です。
・従業員満足度の向上
ワークシェアリングを行うことは、「景気が悪化した場合に自分たちの雇用が守られるのか」という不安に対しての対応策ともなります。景気が悪くなっても会社は自分たちの雇用を守るための仕組みを持っているということは、社員からの企業への信頼が向上する要因の1つになりえます。
また、ワークシェアリングによって一人ひとりの業務量が減ることは、心身への負担も減るため、従業員の健康も守られますし、働き方改革の文脈でも多様なライフスタイル合わせた働き方の実現にもつながるため、そういった点を求めている従業員にとっては満足度が高まることが期待できるでしょう。
・企業イメージの向上
ワークシェアリングを取り入れていることを社外にアピールすることで、「雇用の機会を広く提供している企業」「一人ひとりがのびのびと働ける企業」といったイメージを作ることができるでしょう。
企業イメージの向上は当然企業価値そのものの向上につながるため、ワークシェアリングを戦略的に活用することも考えると良いでしょう。
・生産性の向上
ワークシェアリングを導入することで、タスクの負荷を均等に分散させることができます。これにより、個々の従業員の負荷が軽減され、作業効率が向上します。一人で多種多様なタスクを抱えていた従業員も、本来やるべき仕事に集中できるようになるので、全体として生産性の向上が期待できるでしょう。
・多様な人材の確保
ワークシェアリングを導入することで、柔軟な働き方を推進したり、ワークライフバランスを確保したりしやすくなります。そのため、育児中の人や介護中の人、シニア層や地方に住んでいる人など、多様な経験、生活スタイルを持つ優秀な人材を獲得しやすくなります。
■従業員側のメリット
一方で従業員にとってもメリットは以下の2つが挙げられます。
・雇用が守られる
生活のために必要な「働くこと」を既存社員へも、求職者へも提供できるのがワークシェアリングです。
求職者にとっては、ワークシェアリングによって新しい仕事に就く機会が増えますし、今現在雇用されている人にとっては、労働時間を短縮されるものの、雇用は維持されるため働き続けることがでます。
働く場所を確保できるということは、従業員にとっての何よりのメリットと言えます。
・ワークライフバランスの実現
ワークシェアリングによって、一人ひとりの業務負担が軽減されることで生まれた時間を、一人ひとりが有効に使うことができます。
育児、家事、介護、自己研鑽、地域貢献など、一人ひとりが自分らしく生活をするための時間を得られるのです。
こうした幅広い働き方を受け入れられる組織を作り、優秀な人材が集まる環境を作ることは、企業にとってもメリットだと言えます。
(参考)テレワークの活用で働き方改革を!導入事例やポイントを解説
ワークシェアリングを導入することで、それぞれの従業員の役割や責任が明確になるため、自身の仕事に集中しやすくなります。また、仕事量が分散され、業務負荷が軽減されるのもメリットです。その結果、ストレスが軽減されたり気持ちに余裕ができたりして、モチベーションが高まりやすくなります。
ワークシェアリングのデメリット
反対に、ワークシェアリングを取り入れることによるデメリットもきちんと理解しておきましょう。ここでも、企業側と従業員側に分けて解説をしていきます。
■企業側のデメリット
企業側にとってもデメリットは、以下の3つです。
・制度の再整備
ワークシェアリングを実装する場合には、すでにある制度を見直す必要があります。単に新規雇用を増やし、労働時間を減らせばよいというものではないのです。
制度の見直しが必要になる例としては、短時間勤務制度や格差是正のための制度などがあります。すでにある様々な制度をどの従業員にとっても公平なものにするためには、企業にとって負担になります。
・給与計算の増大・複雑化
ワークシェアリング導入により、短時間労働などの新たな働き方が増えるため、給与計算のコストが増大します。
単に、新たに給与計算の方法が変わるということだけではなく、当然従業員数が増えるため給与計算をする対象も増えます。
給与計算は従業員の生活に直結する重要な作業です。ワークシェアリングなど新たな働き方を導入する際は、丁寧に見直すことが必要でしょう。
・その他コストの増加
ワークシェアリングによって、従業員数が増加することで、企業が負担する金額が単純に増えます。
例えば、社会保険料は従業員の数の増加によって増えますし、従業員規模が大きくなることで福利厚生や衛生管理、社員教育を手厚く行う必要性も出てくるためコストが増える可能性があります。
従業員の多様化を促進することなりますので、雇用リスクへの対策も一層の充実が求められることも考えられるでしょう。
雇用者の増加と比例して、企業が負担する一部のコストが増加することは、経営面から考えた場合、企業側にとって大きなデメリットとなります。
■従業員側のデメリット
一方で従業員側のデメリットは、主に以下の2つが挙げられます。
・給与ダウン
ワークシェアリングを取り入れることで、一人ひとりの労働者の労働時間が短くなり、労働時間に応じて支払われる基本給も下がります。給与は生活の基盤ですから、当然従業員にとってはデメリットになるといえます。ただし、1時間当たりの給与が増加する場合、逆に給与が増加する場合もあるようです。
・格差が生まれる
ワークシェアリングをすべての従業員に対して平等に導入することができないこともあります。対象になる労働形態・対象にならない労働形態がある場合は、ワークシェアリングの対象労働者だけが労働時間が短縮されるため、両者に賃金格差、待遇の格差が生じてしまいます。
同一労働同一賃金が叫ばれていても、労働時間で賃金が決定してしまう現状は、従業員にとってデメリットとなります。
ワークシェアリングの導入は個人にとってはもちろん良いことばかりではないため、導入前にきちんと企業と従業員の間で、変わること、変わらないこと、のすり合わせをすることが重要です。
尚、企業側と従業員側、いずれにせよ小さなデメリットが引き金となり、企業側と従業員側の結びつき=エンゲージメントを揺るがす可能性も否めません。ワークシェアリングは時間と労力がかかる施策になりますので、取り組む際には企業側と従業員側双方にとって意味のある一歩であること、またこの施策の成功はただ施行すれば成立するものではなく、企業側と従業員側双方の歩み寄りによって初めて実りある結果をもたらすことができる旨を、経営から適切なタイミングやチャネルで発信することが必要になります。
【参考資料のご紹介】
「心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイント」はこちらからダウンロードいただけます。
ワークシェアリングの導入方法・手順
ワークシェアリングを取り入れるために必要な、代表的な導入ステップを解説していきます。
①現状の業務状況を把握する
業務を複数人で分け合うワークシェアリングを導入するためには、自社にどんな業務があるのかを把握することが必要です。そして、自社の業務状況について確認をしましょう。どんな業務があり、何人の従業員が関わっていて、どれほどの時間とコストがかかっているのかを整理します。
②業務の無駄を見直す
①で業務状況を整理したら、効率化できる業務がないか精査します。そもそも不要な業務や、現状のコストを削減できそうな業務を探していきます。また、現状とは違う方法で行えばもっと効率的になるものはないかという観点でも精査をすると良いでしょう。
③ワークシェアリングが適応可能な業務・職種を明確にする
②で業務の無駄を整理すると、ワークシェアリングを取り入れられそうな業務や職種が見えてきます。複数人で分担することができそうな業務、誰がやっても同じクオリティを出せそうな均一化された業務などが適切でしょう。
④ワークシェアリング運用のためのマニュアルを作成する
ワークシェアリング導入に向けて、責任者、運用方法、これまでと変更になる点(制度や福利厚生、教育制度など)を整理し、従業員に共有するためのマニュアルを作成しましょう。マニュアルと共に、ワークシェアリング導入の目的や背景、導入によって得られるメリットなどもきちんと説明することで、社員の理解を得るように心がけましょう。
⑤導入後、業務状況の評価を行い、進捗を確認する
ワークシェアリングの運用が始まったら、効果測定をしましょう。導入前に決めた、導入目的が果たされているかどうか、企業の業績に貢献できているかどうかを評価します。振り返りを行うことで、更にスムーズに効果的に運用をしていくための改善点を見つけ、ブラッシュアップをすることも重要なポイントです。
ワークシェアリングの活用事例
企業のワークシェアリング活用事例をご紹介します。
■トヨタ(緊急避難型)
トヨタは2009年、販売が急減している米国の6工場で働く約12,000人を対象にワークシェアリングを導入しました。背景には、世界景気の急減速による自動車不況があります。米市場で販売シェアを拡大し続けていたトヨタには日米自動車摩擦の再燃を回避する狙いもあり、「雇用を最大限守る」という方針のもと、ワークシェアリングの導入を決断しました。対象となったのはケンタッキー州など3つの自動車組立工場を含む計6工場で、それまでの2週間80時間労働を、2週間72時間労働に短縮し、賃金も同時間分に削減。人員削減を避けるとともに労務費の抑制を図りました。
■日本IBM(多様就業促進型)
日本IBMは、従業員のライフステージの変化に対応するため「短時間勤務制度」を導入しています。結婚や出産、介護などによってフルに働きたくても働けなくなったとき、従業員のキャリアや社内外の人脈が途切れないよう、通常の80%・60%の勤務を認めています。フルに働ける状況になったときには、再びキャリアを高めることが可能です。育児目的であれば、たとえば朝30分・夕方1時間の時間短縮をすることで子どもの保育園の送迎が楽になります。介護目的であれば、たとえば週3日勤務にして、週2日を親の介護Dayにすればリハビリをサポートすることができるでしょう。
※参考:IBM ダイバーシティー&インクルージョン: ワーク ライフ バランス - Japan
https://www.ibm.com/ibm/responsibility/jp-ja/inclusion/work-life-integration.html
■ベネッセコーポレーション(多様就業促進型)
ベネッセコーポレーションは、1992年から育児時短勤務制度を導入しています。育児休業から復帰したばかりの育児と仕事の両立が大変な時期に「通常勤務にスムーズに戻るための準備期間」として時短勤務制度を設けることで、従業員の長期的なキャリア形成を支援しています。同社における通常勤務者の所定労働時間は7時間ですが、時短勤務制度を利用することで1時間(子が小学3年生まで)、または2時間(休業復帰後1年以内)の短縮が可能です。育児と介護との「両立支援」を越え、両立しながらの「キャリア支援」を主軸にするとともに、対象を女性に限定せず、男性も含めた全従業員向けの人事施策として徹底していくことを目指しています。
※参考:株式会社ベネッセコーポレーション | 多様な正社員制度の導入事例
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/cases/case_0040/
記事まとめ
いかがでしたでしょうか。働き方改革が推し進められている中で、ひとりひとりの従業員の負担を軽減し、雇用を生み出すことができるワークシェアリングは、新しい働き方の形になるでしょう。
ワークシェアリングによって得られるメリットやデメリットを見極めつつ、自社にとって効果的な働き方の形を実現していきましょう。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
ワークシェアリングに関するよくある質問
Q:ワークシェアリングの導入において企業が認識すべきリスクは?
企業が認識しておくべきなのは、ワークシェアリングの導入によって生産性が低下してしまうリスクがあるということです。ワークシェアリングによって個々の従業員の負担が減っても、多くの従業員が業務に関わることで業務の引き継ぎやそれにともなう時間的なロスが発生するなどして、生産性の低下につながってしまうおそれがあります。
Q:ワークシェアリングとジョブシェアリングの違いは?
ジョブシェアリングとは、フルタイム労働者1人分の職務を特定の2人で労働時間を分担しておこなう仕組みのことを言います。分担した時間について各自が責任を負うのではなく、職務の成果について共同で責任を負い、評価・処遇も2人セットで受けるのがジョブシェアリングの特徴です。その意味で、ジョブシェアリングはワークシェアリングの一形態だと言えるでしょう。ジョブシェアリングは日本ではあまり馴染みがありませんが、海外では多様な働き方の一つとして広く認知されています。