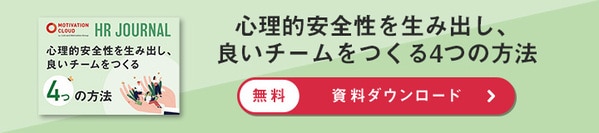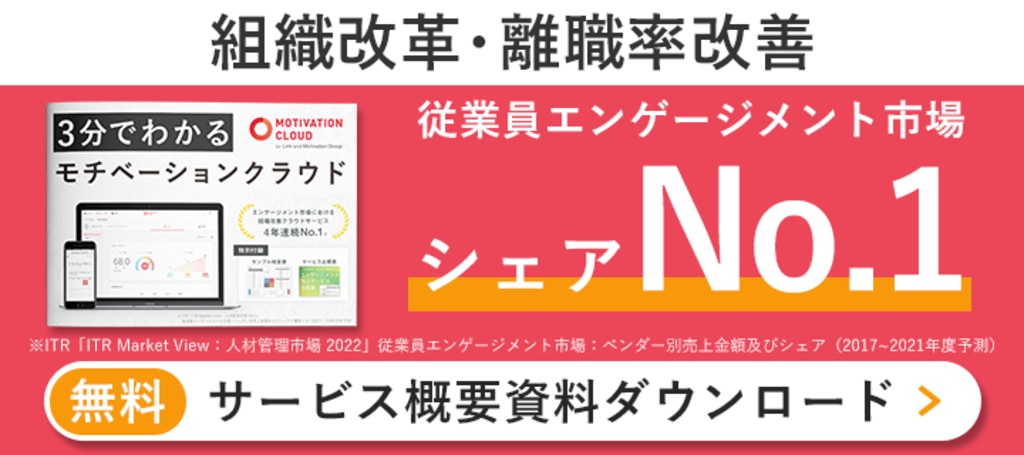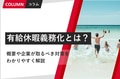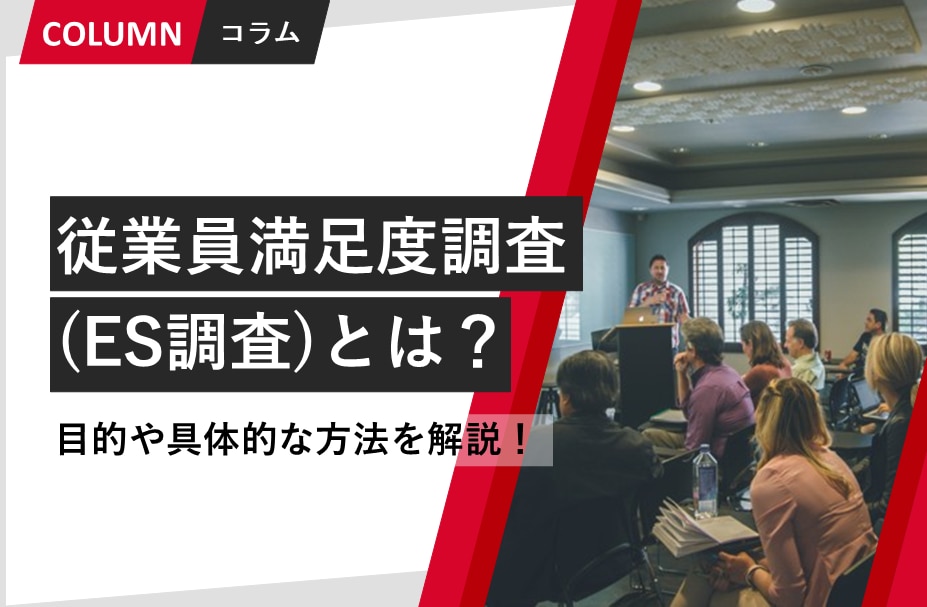
従業員満足度調査(ES調査)とは?目的や具体的な方法を解説!
「ダイバーシティ経営の実現」「従業員ストレスチェックの義務化」など企業活動において、顧客満足度の追求のみならず、従業員に対する施策の実施も求められる時代となってきています。
なぜ企業活動において従業員に対する施策が注目され、「従業員満足度」の追求が必要とされる時代となったのか。その背景や、向上するメリット、ポイントなどをまとめていきたいと思います。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら
目次[非表示]
従業員満足度調査(ES調査)とは?
従業員満足度(ES)とは?
従業員満足度とは、職場環境や社内の人間関係、働きがい、福利厚生、給与などの要素で計測される従業員の満足度のことを指します。
従業員満足度は英語で「Employee Satisfaction」と呼ばれ、頭文字を取った略称のESと表現される場合もあります。
従業員満足に関する基礎的な理論としては、ハーズバーグの「二要因理論」が用いられます。二要因理論とは、人間の仕事における満足度は、「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)によって構成されているという考え方です。
従業員満足度が重要視される背景
近年、従業員満足度を高めるために、あの手この手を尽くす企業が増えています。その背景として大きいのは、労働人口の減少です。日本は少子高齢化の進行にともない、労働人口が減少しています。
リクルートワークス研究所の調査によると、2030年には約341万人の労働人口が不足し、2040年には約1,100万人の労働人口が不足すると予測されています。この先、限られた労働力を求めて企業間の競争が激化することは予想に難くありません。
そのような状況のなか、人材を確保するための手段として今まで以上に従業員満足度が重視されるようになっています。
もう一つ、背景を挙げるとしたら人材の流動化です。価値観の変化によって、特に若い世代にとっては転職が当たり前の時代になっており、より良い職場を求めて転職する若手が増えています。
しかし、従業員満足度が高い職場なら、簡単に人材が流出することはありません。「この会社でずっと働きたい」と思えるような従業員満足度の高い職場をつくることができれば、離職率は低下し、貴重な人材を失うリスクを低減できるでしょう。
※参考:未来予測 - 労働力 不足 社会|リクルートワークス研究所
従業員満足度調査の目的
従業員満足度調査の目的は、大きく2点に整理できます。
まず第一に、組織の現状把握です。従業員が日々の業務や職場環境についてどのように感じているかを定量的・定性的に可視化し、満足度の高いポイントや不満の原因を明確にします。これにより、経営層と現場の意識ギャップを浮き彫りにし、課題の早期発見につなげることができます。
第二に、エンゲージメント向上施策への活用です。調査結果をもとに、従業員がより働きがいを感じられる施策を設計・実行し、定着率向上やパフォーマンス最大化を図ります。
このように、従業員満足度調査は単なる現状把握にとどまらず、組織の成長と生産性向上を支える重要な経営施策となっています。
従業員満足度調査の効果・メリット
従業員満足度調査には、組織にとって多くのメリットがあります。まず、従業員の声を定量的に把握できるため、感覚に頼らない組織運営が可能になります。次に、現場に潜在する課題を可視化でき、改善すべきポイントを的確に特定できます。
また、従業員の意見を組織改善に反映することで、エンゲージメント向上や離職防止にもつながります。さらに、調査データをもとに施策の効果検証ができるため、PDCAサイクルを回しながら持続的な組織改善を図ることができます。
■定量的に従業員満足度を把握できる
従業員満足度調査を実施することで、組織の状態を数値データとして客観的に把握できるようになります。たとえば、職場環境、上司との関係、業務負荷、成長機会などの項目ごとに5段階評価を行うことで、具体的な満足度スコアを出すことが可能です。
これにより、部署別・年代別の満足度傾向を比較・分析でき、どの部門や層に課題が集中しているのかを明確に把握できます。主観に頼らず客観的なデータで組織の状態を評価できるため、施策立案時の説得力も高まります。
さらに、過去データとの比較により改善効果の測定も可能となり、組織運営の精度が大きく向上します。
■会社の課題を発見できる
従業員満足度調査は、組織内に潜在する課題を発見する有効な手段です。たとえば、「上司とのコミュニケーション満足度」が低い部門では、マネジメントスタイルに課題がある可能性が示唆されます。
また、「業務負荷」や「成長機会」に関する不満が高い場合、適切な人員配置や教育施策が不足していることが推察できます。こうした課題を早期に特定できることで、表面化する前に対策を打つことが可能になります。
調査データは単なる満足度指標にとどまらず、組織課題の優先順位づけやリスク管理にも活用できる重要な情報源です。
■従業員の意見を取り入れることができる
従業員満足度調査は、単にデータを収集するだけでなく、従業員一人ひとりの声を組織運営に反映させるための重要な機会でもあります。調査の自由記述欄や追加アンケートを通じて、具体的な改善提案や現場で感じている課題が拾い上げられることもあります。
こうして集めた意見をもとに施策を設計・実行すれば、従業員は「自分たちの意見が反映されている」と実感しやすくなり、エンゲージメントやロイヤルティ向上にもつながります。双方向のコミュニケーションを促進し、組織文化をより開かれたものへと進化させる効果が期待できます。
■調査結果から施策を考察することができる
従業員満足度調査の結果は、単なる現状把握にとどまらず、具体的な施策立案の出発点となります。たとえば、「働き方に対する満足度」が低い結果が出た場合、フレックス制度やリモートワーク制度の導入を検討するきっかけになります。
また、「成長機会の不足」が指摘された場合には、研修体系の見直しやキャリア支援制度の強化が必要です。調査結果をもとに具体的な改善策を検討し、実行し、再度調査して効果を測定するというPDCAサイクルを回すことで、組織の持続的成長と人材定着力向上を実現できます。
従業員満足度を構成する要素
従業員満足度を向上させるうえではいくつかの要素があります。
■企業ビジョンへの共感性
企業ビジョンとは、企業が顧客に対してどのような価値を提供するのか、どのようにして社会に貢献するのか、という全体的な方向性のことです。
企業ビジョンに共感している従業員は、会社に対する期待感や誇りを持っています。そのため会社への信頼度は高く、能動的に自社の貢献に向けた行動を取ろうとします。
■上司(マネジメント)への納得感
部下の考えを理解したり、部下の仕事ぶりを把握してきちんと称賛したりしている上司がいる部署は、従業員満足度が高くなります。逆に、納得度の低い評価をしたり、部下を放置したりする上司がいる部署は、当然ながら従業員満足度も低くなります。
■自身の仕事の業績や社会に与える影響度
自分の仕事と、会社の業績や社会への貢献度と照らし合わせた際に、それを感じられない場合の従業員満足度は低くなります。
■職場内の人間関係
共に働くメンバーとの人間関係が良好であれば、従業員満足度は上がりますが、ひとたび人間関係がこじれれば、その不安や不満は従業員の大きなストレスとなります。
■快適な職場環境
職場環境を整えることも、従業員満足度の向上に繋がる取り組みの1つです。たとえば、従業員の業務効率が上がるシステムや制度を積極的に取り入れれば、働きやすさも高まります。
■福利厚生の充実度
福利厚生を充実させることも、従業員満足度の向上に欠かせません。有給が取りやすい環境を整えたり、法定外の休暇を用意したりすることは、高い従業員満足度に繋がります。 ▼福利厚生に関する記事はコチラ 福利厚生とは? 種類や制度の仕組み、導入のメリット・ポイントを紹介 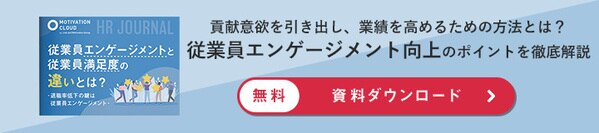
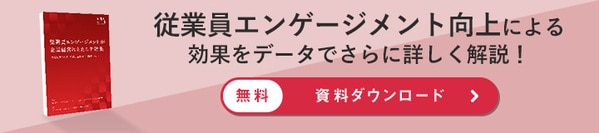
■従業員満足度を調査した先に分かること
従業員満足度を調査することで、結果としてどのようなものが得られるのか考えてみましょう。 一例として下記のような内容が挙げられます。
<企業や経営層の評価>
会社の理念が浸透しているか、トップは情報を適切に開示しているか、会社の組織や風土はどうか
<制度の評価>
評価は適当か、給料や人事制度に満足しているか、成長の機会を与えられているか
<仕事の評価>
仕事に意義ややりがい、誇りを感じているか、仕事の負荷は適切か、成長している実感があるか
<上司の評価>
上司のマネジメントについてどう感じているか、情報開示は適切か、相談しやすい雰囲気があるか
<職場の評価>
目標は共有されているか、自分の部署のチームワークは良好か、他部署との連携がされているか、コミュニケーションは機能しているか このように、従業員満足度を調査することで、単に従業員の満足度をはかるだけに留まらず、経営面や管理部の問題点など、企業全体で取り組むべき課題についても把握することができます。
そのため、人事や総務だけでなく、経営陣も一丸となって取り組むべき施策といえるでしょう。
従業員満足度調査の質問例
従業員満足度調査では、組織のさまざまな側面を総合的に評価するために、多様な質問項目が設定されます。基本的な質問に加え、仕事そのもの、会社の風土、処遇、経営への信頼感、そして総合的な満足度といった領域ごとに設問が設計されるのが一般的です。
各領域について、従業員のリアルな声を拾い上げることで、組織の強みと課題を客観的に把握し、改善施策に生かすことができます。
■基本項目
基本項目では、従業員の働く環境全体についての意識を把握する質問が中心となります。主なテーマは「労働時間」「休暇取得状況」「職場の人間関係」などです。
設問例としては、
「所定労働時間内で業務を終えられると感じますか?」
「休暇を取りやすい雰囲気が職場にありますか?」
「職場の同僚との人間関係に満足していますか?」
などが挙げられます。
これらの基本的な質問を通じて、働くうえでの最低限の環境条件が整っているかどうかを可視化し、改善の優先順位を明確にします。
■仕事
仕事に関する従業員満足度調査の項目では、日々の業務内容そのものへの満足度と、組織内における自身の役割認識の明確さに対する満足度を深く掘り下げます。
従業員一人ひとりが、担当している業務にどれほどの意義や達成感を見出しているか、また、自身の職務が組織全体の目標達成にどのように貢献しているかを理解しているかを把握することは、従業員のエンゲージメントを高める上で極めて重要です。
具体的には、以下の設問例を通じて、より詳細な情報を収集します。
「現在担当している仕事の内容は、自身の興味やスキルと合致していますか?」
「日々の業務において、創造性や自主性を発揮する機会が十分に与えられていますか?」
「自身の仕事の成果や貢献が、正当に評価されていると感じますか?」
これらの質問に加えて、自由記述式の設問を設けることで、定量的なデータだけでは捉えきれない、従業員のより具体的な意見や感情を把握することができます。
■会社風土
会社風土に関する項目は、組織文化、共有された価値観、従業員間の相互理解、協力体制、心理的な安全性など、組織全体を特徴づける要素の共有状況を詳細に測定することを目的としています。
これは、従業員が組織の一員であるという強い意識を持ち、自身の役割に誇りを持ちながら、安心して能力を最大限に発揮できる職場環境が整備されているかどうかを深く理解するために不可欠です。
具体的な設問例としては、以下のようなものが挙げられます。
「あなたは会社の理念やビジョンを深く理解し、それらに共感していますか?」
「職場で自分の意見やアイデアを率直に、かつ建設的に発言できる雰囲気がありますか?」
「困った時や新たな挑戦をする際に、上司や同僚からのサポートや励ましを十分に感じられますか?」
「組織内でのコミュニケーションは円滑に行われ、必要な情報が適切に共有されていますか?」
■処遇
処遇に関する項目は、従業員の組織への貢献度に対する評価と報酬の妥当性に対する認識を測る上で不可欠です。
具体的には、
「基本給の額に満足していますか?」
「各種手当の内容は理解できていますか?」
「賞与の額や支給基準に納得していますか?」
などが評価の対象となります。
また、金銭的な報酬だけでなく、従業員の長期的なキャリア形成を支援する
「昇進・昇格制度は明確に示されていますか?」
「研修制度は充実していると感じますか?」
「社内表彰制度は適切に運用されていますか?」
なども、広い意味での処遇として従業員の満足度に影響を与えます。これらの非金銭的報酬に対する従業員の認識も、エンゲージメントを高め、離職を防ぐために重要な要素となります。
■経営
経営に関する項目では、企業のビジョン、経営戦略、リーダーシップに対する従業員の信頼感や期待感を測定します。特に、企業が掲げる方向性や成長戦略について、現場レベルでどの程度理解と納得が得られているかを把握することが目的です。
設問例としては、以下のようなものがあります。
「会社の今後の成長戦略に期待していますか?」
「経営陣の意思決定プロセスに納得感を持っていますか?」
「会社の情報開示は十分だと感じますか?」
「経営陣の方針に共感できていますか?」
これらの質問を通じて、トップダウンの方針と現場の感覚との間にズレがないかを測定します。経営への信頼感が高い組織では、従業員が組織目標に対して自律的に貢献しようとする姿勢が育まれ、エンゲージメント向上や離職率低下にもつながります。
逆に、ビジョンが浸透していなかったり、経営層との距離感が強い組織では、社員のモチベーション低下や組織活力の低下を招きやすいため、定期的なモニタリングと改善アクションが不可欠です。
■総合満足度
総合満足度は、従業員が企業全体に対して抱く全体的な評価を測定する重要な指標です。組織の健全性や従業員のエンゲージメント状況を総括的に表すため、経営層が最も注視すべきデータの一つといえます。
設問例には、次のようなものがあります。
「現在の会社に満足していますか?」
「今後もこの会社で働き続けたいと感じますか?」
「友人や知人にこの会社を勧めたいと思いますか?」
「会社の将来に対して希望を持っていますか?」
総合満足度が高い場合は、組織文化や施策が効果的に機能していることを示しており、社員の定着率やパフォーマンス向上にも直結します。一方で、総合満足度が低下している場合は、どの領域に課題が集中しているかを詳細分析し、迅速な対応策を講じる必要があります。
具体的には、仕事満足度、処遇満足度、経営信頼度などの個別項目とのクロス分析を行い、不満の温床となっているポイントを特定します。そして、それらの課題に対してピンポイントで改善施策を打つことで、組織全体の活性化につなげることができます。
単純な数値比較だけでなく、時系列変化や属性別傾向を分析することも重要です。
従業員満足度調査の方法
従業員満足度調査は、組織改善に欠かせない重要な取り組みですが、効果を上げるためには体系的なプロセスに沿った実施が必要です。一般的な流れは、①調査目的の定義、②調査内容の設計、③調査の実施、④集計・分析、⑤施策の検討という5つのステップに整理できます。
それぞれの段階で明確なゴールと具体的なアクションを設定することで、調査の精度と成果を最大化することが可能です。以下、各プロセスについて詳しく解説します。
①調査目的を定義
従業員満足度調査を始める際は、まず調査目的を明確に定義することが不可欠です。
単に「現状を把握したい」というだけではなく、たとえば「離職率を改善したい」「エンゲージメントを高めたい」「マネジメント課題を抽出したい」といった、より具体的なゴールを設定することが重要です。
たとえば、「若手社員の定着率向上」を目的にする場合は、キャリア開発支援や評価制度に関する設問を重視する設計が求められます。目的が明確であればあるほど、調査設計・分析・施策立案がスムーズになります。
また、経営層や部門責任者と調整し、調査目的を全社的に共有しておくことも成功のポイントです。曖昧な目的のまま進めると、調査結果が活用できず、単なる「実施して終わり」になりかねません。
②調査内容(質問内容・方法・対象)を決定
調査目的が定まったら、次に質問内容・調査方法・対象者を具体的に設計します。質問内容は、仕事満足度、処遇満足度、組織文化、マネジメント評価など、多角的に設定するのが基本です。また、自由記述欄を設けてリアルな意見を拾う工夫も有効です。
調査方法については、匿名Webアンケートが主流ですが、場合によっては紙面調査やインタビューも併用します。匿名性を担保することで、本音ベースの回答を引き出しやすくなります。
対象者の選定も重要です。全社員対象とするのが理想ですが、特定部門や特定年齢層に絞ったスモールスタートも一つの方法です。たとえば「入社3年以内の若手社員に限定して実施する」など、目的に応じて柔軟に設計しましょう。
③調査の実施
調査設計が整ったら、いよいよ実施フェーズに移ります。ここで重要なのは、事前告知と実施環境の整備です。調査開始前には、必ず経営層や部門長から「なぜ調査を行うのか」「回答は評価に影響しない」ことを明確に説明し、回答の安心感を醸成することが成功のカギとなります。
実施期間は、1〜2週間程度を目安とし、リマインドメールを活用して回答率を高めます。Webアンケートの場合は、スマホでも回答できるフォームを準備し、利便性を高めると効果的です。
また、忙しい時期(期末、繁忙期)を避け、できるだけ多くの社員が集中して回答できる時期を選定することもポイントです。正確なデータを得るためには、実施段階でのきめ細やかな配慮が不可欠です。
④集計・分析
調査終了後は、速やかに集計・分析作業に移ります。まずは基本的な平均値、中央値、分布などの集計を行い、部門別や属性別(年齢層・役職別など)の比較を行います。これにより、どの層に課題が集中しているかを可視化できます。
さらに、各設問間の相関分析を実施すると、「満足度に最も影響を与えている要素」が浮き彫りになります。たとえば、「上司との関係満足度」と「総合満足度」の相関が強ければ、マネジメント改善が優先課題であると判断できます。
自由記述欄については、テキストマイニングツールを活用して、キーワード頻度や感情分析を行うと効果的です。定量データと定性コメントをバランスよく読み解くことで、より立体的な組織課題の把握が可能になります。
⑤施策の検討
調査分析結果を踏まえて、具体的な施策の立案を行います。ここで重要なのは、分析結果を単なる「報告資料」に留めず、実際のアクションプランに落とし込むことです。
たとえば、「成長機会への不満」が高かった場合には、新たな研修制度の導入やキャリアパス明示などが施策候補となります。また、「コミュニケーション不足」が課題であれば、1on1ミーティングの導入やオープンミーティングの推進が有効です。
施策立案の際には、「実行可能性」「効果インパクト」「リソース負荷」の観点で優先順位をつけることがポイントです。さらに、施策実施後もフォローアップ調査を行い、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善につなげていくことが、従業員満足度向上には不可欠です。
従業員満足度を高めた事例
【株式会社セールスフォース・ドットコム インサイドセールス本部様】
ここでは従業員満足度を向上させた企業の例として、CRM(Customer Relationship Management)のシステムを全世界で提供しているリーディングカンパニー「セールスフォース・ドットコム社」の取り組みを紹介します。
セールスフォース・ドットコム社では、リンクアンドモチベーション社の従業員満足度調査を行ったところ、モチベーション低下の要因は、「仕事のやりがいが見つけにくい状態に陥る」ということでした。
当時、会社全体の事業成長に伴い、若手がインサイドセールス本部に在籍する期間も次第に短くなっていき、できるだけ早く成長し、別の現場で活躍することが求められていました。
また、経験の少ないメンバーが増えていく中で、インサイドセールス本部の目標も年々高まっていくため、成果を維持・向上させていくことが、部門として重要なミッションでした。
当初マネジメント側は、他部署へ異動する前のタイミングで、異動後のハードルの高さに思い悩むのではないかと想定していましたが、実はそのもっと前にモチベーション低下のタイミングがあることが明確になったのです。
そこで、「数字管理」が多い状態をやめ、若手が仕事を楽しくするために、2つのことを変えました。
1つ目は数字進捗の管理だけではなく、1on1面談実施に注力し、個々人のキャリア相談や達成するための戦略を話すことに注力されたこと。メンバーが考えていること、個人として大切にしていることを可視化する取り組みを行ったことです。
2つ目は組織のビジョンの変更。元々はとても長くわかりづらかったものを、「Frontier spirits」「Grit」「FEPP」という短くシンプルなものに変えられました。それぞれを分かりやすく、合言葉のように社員全員が覚えられるように工夫をされました。
このような2つの取り組みを行った結果、ワースト1位だったチームが商談件数トップになるなどの成果を創出されました。
また全員記名式のアンケートでマネジャーに改善してほしいところを出すなど、とことん腹を割って話し合われた結果、商談数も急上昇。翌月には7名ものメンバーが初めて目標達成を果たしました。
それに刺激された別チームでも同様の施策を実施し、結果として商談金額が一気に上昇したといいます。
※参考:米フォーブス誌『世界で最も革新的な企業』 No.1受賞 セールスフォース・ドットコム モチベーションクラウドの結果分析から見えた、 インサイドセールス組織の“穴”と対策
まとめ
いかがでしたでしょうか。従業員満足度が高い職場では、生産性の向上や優秀な人材の定着といった沢山のメリットが生まれます。また従業員満足度を向上させるうえで、企業ビジョンへの共感やマネジメントへの納得感もカギとなます。
リンクアンドモチベーションでは、従業員満足度を可視化・分析し、改善につなげるための「モチベーションクラウド」を提供しています。8,740社、237万人のデータをもとに、コンサルタントが併走しながら組織改善を徹底サポートします。
今一度、自社の組織風土や組織文化を見直し、必要に応じた組織、人事施策を講じてみてはいかがでしょうか。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
ES(従業員満足度)に関するよくある質問
Q:ES(従業員満足度)とは?
ESとは「Employee Satisfaction」の略で、日本語では「従業員満足度」のことを言います。従業員が自分の仕事や職場環境にどのくらい満足しているか、もしくは満足していないかを評価する指標です。
ESは、組織の生産性や風土、離職率などに影響を及ぼす重要な指標とされています。ESの向上を図るためには、従業員満足度調査によって現状を把握し、結果に基づいて適切な施策を講じることが重要です。
Q:従業員満足度を高めるには?
従業員満足度を高めるための特効薬はありません。従業員満足度調査によって現状を把握して、従業員のニーズや自社の組織課題に即した施策をおこなうことが重要です。一般的なものとしては、以下のような施策が考えられるでしょう。
・コミュニケーションの促進
・役割や仕事量の調整
・ワーク・ライフ・バランスの尊重
・スキルアップやキャリア形成の機会提供
・報酬や評価の公平性担保
・組織風土の改善 など
▼無料デモはこちら