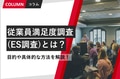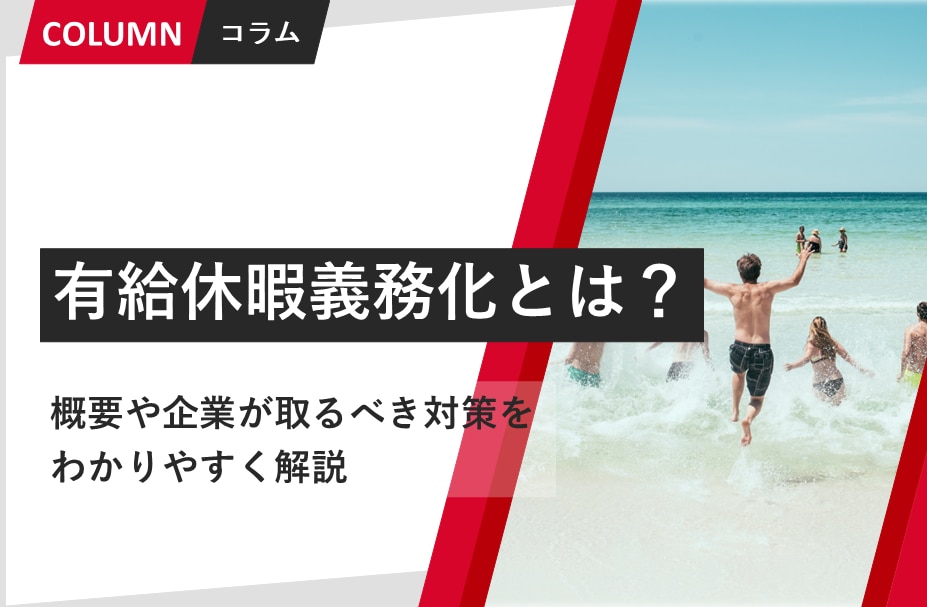
有給休暇義務化とは?概要や企業が取るべき対策をわかりやすく解説
働き方改革の流れに沿って、2019年4月から有給休暇の取得が義務化されました。具体的には「年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者は、必ず有給を5日取得する」という内容です。
しかしながら、この制度にはまだまだ知っておくべき内容があります。そこでこの記事で有給義務化の背景や、その内容、義務化に伴う労務管理における注意点などを解説していきます。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 今、知っておくべき【働き方改革の概要】がわかる!資料はこちら
有給休暇とは?
まずは有給休暇の定義の確認します。有給休暇を一言で言うと、「会社からの給料が発生する、労働が免除された日」と表現することができます。「会社からの給料が発生する」という部分が「有給」、「労働者が労働をすることを免除された日」という部分が「休暇」を指しています。
元々労働をする予定ではない「休日」とは異なり、労働する予定だった日から労働予定を免除する、という意味で「休暇」という表現を活用しています。
この有給休暇は労働基準法第39条に定められており、使用者は労働者に対して有給休暇を与える義務があることが明記されています。
有給休暇が付与される条件は、「雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合、1年ごとに最低10日を付与しなければならない」とされています。
また、この条件は正社員や契約社員などのフルタイム労働者に限らず、パートタイム労働者にも有給休暇は付与されます。
有給休暇義務化とは
2019年4月1日の労働基準法改正により、全ての企業に年5日の有給休暇取得が義務付けられました。これは長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの実現、そして労働者の心身の健康維持・増進を目的とした「働き方改革」の一環です。
従来、有給休暇の付与は義務でしたが、取得は従業員の裁量に委ねられており、取得率は低迷していました。この状況を改善するため、企業は従業員に年5日を確実に取得させる具体的な措置を講じる必要が生じました。
企業が取るべき措置として、使用者による時季指定、従業員による計画的取得、労使協定による計画的付与があります。企業は自社の状況に合わせて適切な方法を選択し、就業規則に明記します。取得状況の管理や、取得困難な従業員への個別対応も求められます。
義務化の背景
日本では、従業員が有給休暇を取得しにくい職場環境や文化が根強く、取得率が低迷していました。厚生労働省の調査によると、2017年の有給休暇取得率は約51.1%にとどまり、先進国の中でも低い水準でした。
このような状況を改善し、従業員の心身の健康を守るため、政府は有給休暇の取得を促進する必要があると判断しました。また、少子高齢化による労働力不足や多様な働き方への対応も、制度導入の背景にあります。
有給休暇取得義務化の主なポイントは以下のとおりです。
・対象者: 年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者(正社員、契約社員、パートタイム労働者を含む)
・取得義務: 使用者は、対象となる労働者に対して、毎年5日間の有給休暇を取得させる義務があります。労働者が自発的に5日以上取得しない場合、使用者が時季を指定して取得させなければなりません。
・管理簿の作成: 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇の取得状況を記録した「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する必要があります。
・罰則: 義務に違反した場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の対象になる労働者
2019年4月に施行された年次有給休暇の取得義務化では、一定の条件を満たす労働者に対して、企業が年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務づけられています。これは正社員だけに限らず、契約社員やパートタイム労働者も含めた幅広い雇用形態が対象です。
以下に、具体的に義務化の対象となる労働者の条件を4つに分けて解説します。
・正社員(フルタイム労働者)
・契約社員・有期雇用労働者
・パートタイム労働者
・派遣社員
正社員(フルタイム労働者)
所定労働日数が週5日以上または年間217日以上ある正社員は、年10日以上の有給休暇が付与されるため、義務化の対象となります。一般的に最も多い雇用形態であり、企業は管理簿の整備と取得日の指定が必要です。
契約社員・有期雇用労働者
契約期間の定めがある有期雇用労働者でも、継続勤務が6か月を超え、かつ所定労働日数が週5日以上ある場合、年10日以上の有給休暇が付与されます。したがって、義務化の対象になります。雇用期間の長さにかかわらず、条件を満たせば義務が生じます。
パートタイム労働者
所定労働日数が週4日以下であっても、勤務日数や時間数に応じて比例付与された結果、年10日以上の有給休暇が付与されるパートタイム労働者も対象になります。たとえば、週4日勤務を長期間継続している場合が該当します。
派遣社員
派遣労働者であっても、派遣元企業において雇用契約が継続し、かつ週5日以上働いていれば年10日以上の有給が付与され、義務化の対象となります。管理責任は派遣先ではなく、雇用主である派遣元企業にあります。
有給休暇義務化に違反した場合の罰則は?
2019年4月から施行された「年次有給休暇の取得義務化」は、すべての企業に対して、対象労働者に年5日以上の有給休暇を取得させることを義務づけています。この法令に違反した場合、企業には罰則が科される可能性があります。
罰則内容と法的根拠
企業が労働者に対して年5日以上の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第39条第7項違反となり、労働基準法第120条に基づき、1人につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
これは、企業が「取得させる義務」を怠った場合に適用されるため、労働者本人の希望や取得状況にかかわらず、企業側に休暇取得を管理・促進する責任があるという点に注意が必要です。
実際の運用と行政指導
労働基準監督署による調査や立ち入り監督で、有給休暇の取得義務が果たされていないと判断された場合、まずは是正勧告が出されます。その後も改善が見られなければ、送検・罰金といった法的措置が取られる可能性があります。
特に複数名の違反がある場合は罰則が人数分発生するため、中小企業であっても数百万円規模のリスクを抱えることになりかねません。
管理簿の未整備もリスク
企業は「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保存義務も課されています。これが整備されていない場合も、別途罰則対象になる可能性があるため、制度運用だけでなく書類管理にも十分な注意が必要です。
企業が取るべき対策
有給休暇取得義務化への対応は、企業の労務管理体制を見直す好機でもあります。ここでは企業が取るべき4つの対策を具体的に紹介します。
年次有給休暇の管理簿を整備する
労働基準法に基づき、企業にはすべての労働者の有給休暇の「付与日」「取得日」「残日数」を記録した年次有給休暇管理簿の作成・保存義務があります。紙やエクセルでの管理でも構いませんが、システム化することで精度と効率が向上します。
具体的な管理方法としては:
・勤怠管理システムとの連携による自動記録
・部署ごと・従業員ごとの取得状況を可視化するダッシュボードの導入
・管理職に対する定期的な確認依頼とフィードバック制度の実施
これにより、罰則リスクの軽減に加え、従業員の休暇取得推進にもつながります。
計画的付与制度を活用する
企業は就業規則で定めることで、有給休暇の一部を計画的に割り当てること(計画的付与)が可能です。たとえば、繁忙期を避けた閑散期に「一斉取得日」や「交代制取得日」を設けることで、業務負荷を分散しながら制度の実効性を高められます。
導入時のポイント:
・労使協定の締結(対象日数・時期・対象者)
・部署間での業務調整・バックアップ体制の構築
・取得希望との調整による従業員満足度の維持
計画的付与は、労使双方にとってメリットが大きく、制度遵守の強力な支援策となります。
管理職への教育と意識改革
有給休暇の取得促進において、現場の管理職の理解と行動がカギを握ります。単なる法令周知ではなく、休暇取得が業務効率やチームパフォーマンスにどう影響するかを、研修やミーティングを通じて伝えることが重要です。
実施すべき取り組み:
・管理職向けの法令研修とケーススタディ共有
・チームでの取得率目標の設定と評価制度への連携
・有給取得を推奨する上司自身の行動(ロールモデル化)
これにより、取得しやすい職場文化の醸成につながります。
従業員への周知と取得推進
従業員にとっても、「取得していい」と明確に伝えられることで心理的ハードルが下がります。社内ポータルや面談などで、制度の内容や取得方法を丁寧に周知し、有給休暇の価値を可視化することが大切です。
実施例:
・年初に付与された有給日数と期限の通知
・取得推奨日・推奨月の明示
・定期的な取得状況のフィードバックとリマインド通知
また、従業員が理由なく有給休暇を取得できるような社風作りも、制度を機能させるうえで欠かせません。
有給休暇取得率向上により、業績が上がった企業事例
有給休暇の有効活用によって、事業に良い影響を与えている企業の事例をいくつかご紹介します。どの制度も「義務だから」ではなく「有効活用しよう」と有給休暇のユニークな活用をしているのが特徴です。
・ヤフー株式会社:課題解決休暇
ヤフーでは、年に3回まで、誰かのための課題を解決するために使える有給の制度を設けていました。地域のボランティアに参加したり社会の課題解決に取り組んだりする方が学習効果も高く、経験値が上がり、ネットワークも広がっていくという考えを基に作られました。
最近では副業人材の募集も行うなど、「外部からの視点」を有効活用し、
自社に新たな刺激を入れて成長を促進させていこうという動きが活発なヤフー株式会社。休暇においてもひと工夫を凝らしているのが分かります。
・株式会社ノバレーゼ:アイデア休暇
ブライダル業界のノバレーゼは、業界的に1年~3年未満で辞める人が多い業界の姿を変えようという目的から休暇制度改革に取り組む必要を感じていました。
そこで2010年3月に「アイデア休暇」という有給休暇制度を導入。嘘か本当かを問わず、「サッカー日本代表に選ばれた」「石油王と結婚」などを理由に休んでも良いというユニークな制度です。
エンターテインメント性が求められる業界だからこそ、楽しいことを自ら考えて実行するという姿勢を磨くことも企図して設置されました。
・株式会社リンクアンドモチベーション:ピットイン休暇
リンクアンドモチベーションでは「世の中の4倍の速度で成長する」というコンセプトのもと、目標設定や評価、部署の計数管理などをすべて四半期サイクルに合わせています。
また、そのサイクルを組織面にも応用し、四半期ごとに全社員が集まる総会を実施しているのと、その直後に3日間の「ピットイン休暇」をセットで取っています。
(四半期を「1年」とみなして4倍速の成長を実現しようとしているため、全社総会は「忘年会」、その直後の「年末年始休暇」という位置づけで休暇をまとめて取得)
「ピットイン」の意味はF1レースから来ており、立ち止まって心身のリフレッシュや長期のキャリアを考える時間を取ることによって、休み明けのパフォーマンスを高めることを狙いとしています。この休暇と有給を併せることで大型の休暇にも膨らませることが可能です。
以上、3社の有給休暇活用事例をお伝えしました。
共通しているのは「ただ5日間の有給取得を促す」という手段ベースではなく、「どうしたらこの制度を業績やモチベーション向上に繋げられるだろうか?」という観点で制度活用を考えて頂くと効果的かと思います。
あくまで事例は一例ですが、無味乾燥な内容では無く、自社らしい遊び心を加えることで能動的な活用が促進されることもあるかと思いますので、参考にしてください。
よくある質問
有給休暇義務化に関して、企業や従業員の間でよく寄せられる疑問をわかりやすく解説します。制度の理解を深め、トラブルの未然防止に役立ててください。
有給休暇は義務ですか?
はい、一部の労働者に対しては有給休暇の取得が企業の「義務」です。労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日以上を確実に取得させる義務があります。
有給を5日取らないとどうなる?
企業が年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法違反となり、1人あたり最大30万円の罰金が科される可能性があります。個人に罰則はありませんが、企業の管理責任が問われます。
まとめ
2019年から施行された有給休暇義務化は、企業にとって重要な労務管理上のポイントです。対象者に年5日以上の取得をさせる義務があり、違反すれば罰則のリスクもあります。
制度の正しい理解と、管理体制の整備、計画的な取得推進が不可欠です。有給休暇の適切な運用は、従業員満足度や企業イメージ向上にもつながる重要な取り組みです。