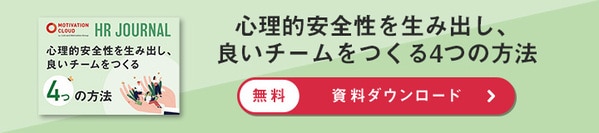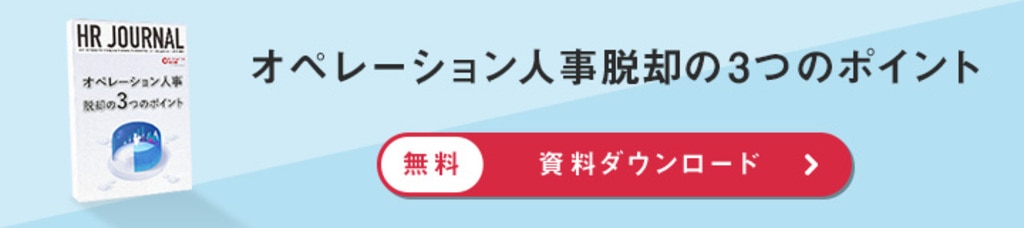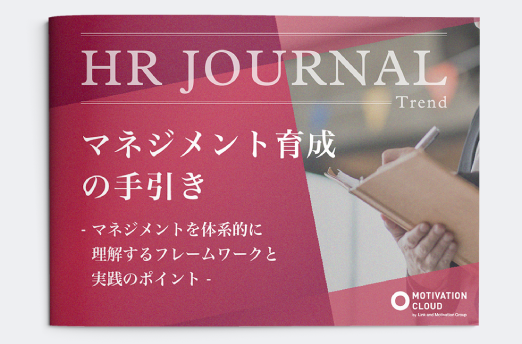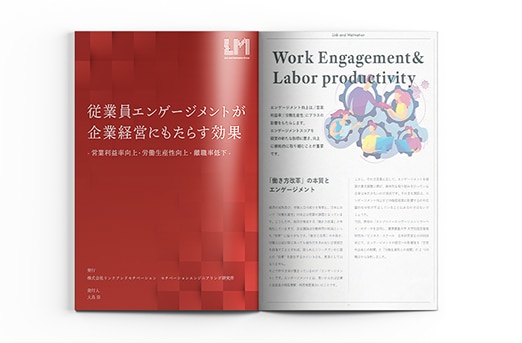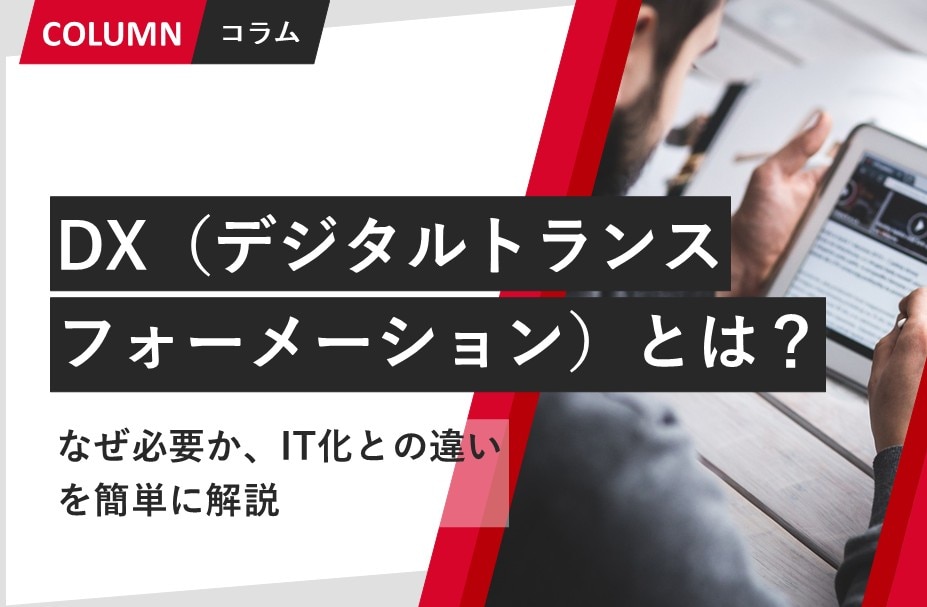
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?なぜ必要か、IT化との違いを簡単に解説
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にしない日はないほど、DXの推進が叫ばれていますが、「そもそも、なぜDXに取り組む必要があるのか?」という疑問を感じている方も少なくないはずです。
今回は、DXが注目されている理由やDX化のメリット、またDX化を推進する際のポイントなどについて解説していきます。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?簡単に解説
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略です。経済産業省によって「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義されています。
■DXの一般的な定義
あらゆる産業において、新しいデジタルテクノロジーを活用してこれまでにないビジネスモデルを構築する新規参入者が登場しています。
このような時代を生き抜いていくためには、やはり同じようにデジタルテクノロジーを駆使して、ビジネスモデルや経営の仕組みを変革する「DX」を進めていかなければいけません。日本政府も、日本企業が世界において競争力を維持・強化していけるよう、DXを推進しています。
2018年に経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」では、DXを以下のように定義しています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
※参考:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0|経済産業省
また、日本のIT国家戦略を技術面・人材面から支えるために設立された独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)は、DXを以下のように定義しています。
AIやIoTなどの先端的なデジタル技術の活用を通じて、デジタル化が進む高度な将来市場においても新たな付加価値を生み出せるよう従来のビジネスや組織を変革すること
※参考:デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査|IPA
■デジタイゼーションはアナログデータのデジタル化
デジタイゼーションとは、アナログ・物理データをデジタルデータ化することを言います。たとえば、紙の印刷物をデータに変換してデータで管理することや、各種文書や申請手続きを電子化することはデジタイゼーションに当たります。
■デジタライゼーションは業務・製造プロセスのデジタル化
デジタライゼーションとは、個別の業務・製造プロセスをデジタル化することを言います。たとえば、RPA(ロボティクスプロセスオートメーション)の導入による業務改善はデジタライゼーションに当たります。
DX化とIT化の違い
DX化とIT化が混同されることがありますが、両者は別の概念です。
IT化とは、ITテクノロジーの活用によってアナログな作業をデジタルに変換し、業務効率化やコスト削減を目指す取り組みのことを言います。たとえば、紙の書類で管理していた情報をデジタルデータでの管理にしたり、CRMシステムを導入して顧客情報を管理したりするのはIT化の一例です。
一方で、DX化はデジタルテクノロジーを活用することで、ビジネスモデルや事業そのものを変革することを目指す取り組みです。IT化は既存業務の効率化に留まるものですが、DX化は既存のビジネスの範囲にとらわれず新しい価値を創出することを目指します。
このように、両者の目的は異なっていますが、DX化を推進するためにはIT化が欠かせません。IT化はDX化の「手段」の一つだと捉えるようにしましょう。
■ IoT・ICTはDX化のための手段
IoT(Internet of Things)とは、「モノのインターネット」のことです。エアコンや冷蔵庫などの家電、体重計や血圧計などのヘルスケア機器、自動車やバス、タクシーなど、様々なモノがインターネットに接続されるようになりました。
今後、IoTはさらに拡大し、あらゆるモノがインターネットにつながる社会が到来すると言われています。
また、ICT(Information and Communication Technology)とは、「情報伝達技術」のことです。コミュニケーションを主体としたデジタル技術である点が特徴で、SNSやチャット、スマートスピーカーなど、情報を伝達するためのシステムやデバイスがICTに当たります。
DXはIoT、ICTを内包する概念であり、IoTもICTもDXを推進するための一つの手段になり得る技術群だと言えます。
▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら
■ ICTもIoTと同様にDX化の1つの手段
ICT(Information and Communication Technology)とは、「情報伝達技術」のことです。コミュニケーションを主体としたデジタル技術である点が特徴で、SNSやチャット、スマートスピーカーなど、情報を伝達するためのシステムやデバイスがICTに当たります。
DXはICTを内包する概念であり、IoTと同様、ICTもDXを推進するための一つの手段になり得る技術群だと言えます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)がなぜ注目されているのか
日本においてDXという概念が広く知られるきっかけになったのが、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」です。このレポートで経済産業省が警鐘を鳴らしている「2025年の崖」が当時話題になりました。
■2025年の崖とは?
DXレポートでは、日本企業が市場で勝ち抜くためにはDXの推進が不可欠であり、DX化を推進していかなければ競争力の低下は避けられないとしています。
競争力が低下した場合の想定として、2025年から年間で約12兆円もの経済損失が発生すると予測しており、これを「2025年の崖」と呼んでいます。
同レポートでは、日本企業のDX化を阻害している要因として、既存システムにまつわる以下の課題を挙げています。
- 既存システムが事業部門ごとに構築されており、全社横断的なデータ活用ができていない
- 既存システムが過剰にカスタマイズされており、複雑化・ブラックボックス化している
そして、このような課題を解決できないままでいると、以下のようなリスクが待ち受けていると指摘しています。
- 爆発的に増加するデータを活用しきれず、DXを実現できないため、市場の変化に対応してビジネスモデルを柔軟・迅速に変更することができず、デジタル競争の敗者になる
- 既存システムの維持管理費が高額化し、業務基盤そのものの維持・継承が困難になる
- 保守運用の担い手がいなくなり、サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失・流出などのリスクが高まる
このように、2025年を節目に多くの問題が企業に立ちはだかることを予測しており、2025年までに集中的にシステムの刷新をおこない、DXを推進する必要があると訴えています。
※参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~|経済産業省
DX化(デジタルトランスフォーメーション化)の3つのメリット
企業がDX化を推進することで、以下のようなメリットが期待できます。
■新たな事業・ビジネスモデルの開発による競争力の向上
DX化を推進することは、新たな事業・ビジネスモデルの開発につながります。タクシーもドライバーも持たずにタクシー事業を運営する「Uber」や、家庭の空き部屋を活用して宿泊サービスを提供する「Airbnb」は、DX化によって新たな事業を創出した最たる例だと言えるでしょう。
今後、AI、IoT、ビッグデータ、5G、ブロックチェーンなどの技術活用が飛躍的に進み、ユーザーのニーズや消費行動は大きく変化していくと考えられています。
DX化の推進によって、このような変化に対応し、顧客のニーズを満たす事業・ビジネスモデルを生み出すことができれば、企業は大きな競争力を獲得することができるはずです。
▼人事領域のデータ活用についてはこちら:人事データを活用するには?DXを推進し成果を出すためのデータ活用のポイントとは?
■生産性の向上
DX化を推進することで、業務の生産性向上が期待できます。例えば、営業やマーケティング業務の自動化など、システムを活用することでマンパワーに頼っていた業務を効率化することができます。
生産性が向上すれば、作業時間の短縮によって人件費の削減にもつながりますし、人が関わる作業を減らすことでヒューマンエラーの削減にもつながります。
■BCPの充実
BCP(事業継続計画)とは、災害やシステム障害に見舞われた場合にも損害を最小限に抑え、スムーズに業務を継続するための計画のことです。自然災害の多い日本では、BCP対策の重要性が高まっています。BCP対策の軸になるのが機能や業務の分散化ですが、そのためにはDXが必要です。
DX化によって業務の自動化・省人化、情報のクラウド管理などが進んでいれば、有事の際も損害を最小限に抑えられ、事業の継続・早期回復が可能になります。
DX化(デジタルトランスフォーメーション化)の成果状況
IPAが2023年2月に公表した『DX白書2023』に基づき、「各企業のDX取組状況」、「ITシステム対応」、「IT人材の不足への対応」という3つの視点から内容を振り返ります。
各企業のDXの取り組み状況
『DX白書2023』によれば、2022年には日本企業全体でデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に注力する企業の割合が顕著に増加しました。この背景には、社会全体のデジタル化の加速や、コロナ禍を経て浮き彫りになった企業のデジタル対応の遅れに対する危機感などが考えられます。
しかしながら、企業規模別に詳細に見ると、DX推進の状況には大きな差異が存在することが明らかになっています。
具体的には、リソースや技術力、組織体制などが比較的充実している大企業においては、その約4割が積極的にDX推進に取り組んでいる一方、人的リソースや資金的な制約を受けやすい中小企業においては、DX推進に取り組む割合はわずか1割程度に留まっているという現状が報告されています。
ITシステムへの対応
日本の企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、多くの課題に直面しており、特に長年にわたり使用されてきたレガシーシステムの存在が大きな障壁となっています。
これらの旧来の情報システムは、現代のビジネスニーズや技術動向との整合性が低く、業務効率の低下、データ連携の困難さ、セキュリティリスクの増大など、様々な問題を引き起こしています。
経済産業省の調査によれば、依然として4割以上の日本企業が、基幹系システムを含む多くのレガシーシステムを抱えており、その刷新の遅れは、グローバル市場における競争力の低下を招く要因の一つとされています。
IT人材の不足
日本の企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で、DX人材の確保は差し迫った最重要課題であり、その不足は単に数的な問題に留まらず、求められる高度なスキルや専門性を持つ質の高い人材が大幅に不足しているという深刻な状況にあります。
この人材不足の背景には、従業員のスキル再開発(リスキリング)支援の遅れに加え、企業側が具体的にどのような知識・スキルを持ったDX人材を必要としているのかという人材像の不明確さが存在します。
このような課題を克服し、日本企業がグローバル競争を勝ち抜き、持続的な成長を実現するためには、目先の採用活動だけでなく、長期的な視点に立った戦略的なDX人材の確保と育成が不可欠です。
関連リンク:
DX動向2024 DXの取組状況(経年変化および米国との比較)
IPA:DX白書2023
DX化の成功事例3選
数々の企業がDX化に取り組んでいますが、ここではその成功事例として代表的なものをご紹介します。
ホンダ
ホンダは、自動車産業におけるDX化の一環として、IoT技術を活用した新しいサービスを開発しました。この新しいサービスは、自動車の運転者にとって非常に便利であり、ホンダの車に搭載されたIoTモジュールにより、車両の情報をリアルタイムに収集することができます。
この情報を利用することで、車両の状態や走行距離、燃料消費量などを管理することができます。 さらに、この新しいサービスは、ホンダにとっても非常に有益であり、車両のメンテナンスや修理をより効率的に行うことができるようになりました。
三井住友銀行
三井住友銀行は、DX化の一環として、AI技術を活用した新しいサービスを開発しました。このサービスは、AIによる顧客のニーズ分析を行い、顧客に最適な商品やサービスを提供することができます。
顧客がより多くのオプションを持つことで、銀行の商品やサービスの選択がより多様化されました。また、AIによる自動判定により、ローンやクレジットカードなどの申請プロセスをスピードアップすることができます。
ユニクロ
ユニクロは、DX化の一環として、デジタルマーケティング戦略を展開しました。この戦略の一環として、SNSやメールマガジンを活用して、顧客とのコミュニケーションを強化しました。 さらに、オンラインストアにおいては、購入履歴やクリック履歴を分析し、顧客に合わせた商品の提案やコンテンツの配信を行うことで、顧客満足度を高めることにも成功しました。
オンラインストア内でのコンテンツ配信においては、トレンド情報やスタイリングのアイデアを提供することで、顧客に興味深い情報を届けることにも成功しました。
DX化(デジタルトランスフォーメーション化)における課題とは?
DX化を進めることで、多くのメリットを得ることができますが、そのためには乗り越えるべきいくつかの課題があります。
システムの統合
企業が保有するシステムは多岐にわたります。人事管理システム、財務システム、生産管理システムなどがあり、それぞれ独自の仕様やデータ形式を持っています。こうした複数のシステムが存在する場合、システム同士の連携に課題が生じます。 しかし、システムの統合を行うことで、データの一元管理が可能となり、業務効率の向上につながります。
システム統合には、様々な手法があります。 たとえば、データ変換やAPIの活用による連携などがあります。このような手法を適切に活用することで、システムの統合をよりスムーズに進めることができます。さらに、システム統合には、リスクが伴うこともあります。 たとえば、データの不正確性やデータの漏洩などが考えられます。
このため、システム統合を行う前にリスク分析を行い、適切な対策を講じることが必要です。
安全性の確保
DX化により、企業の情報システムへのアクセス箇所が増加することが予想されます。このような状況下で、情報セキュリティの確保がますます求められることになります。例えば、情報の機密性、可用性、完全性を確保することが必要です。
これらの要件を満たすために、適切なネットワークインフラストラクチャの導入、セキュリティポリシーの策定、従業員教育などが必要です。また、外部からの攻撃リスクが高まるため、セキュリティ対策に関する新しい技術やツールを取り入れることが重要です。
このような取り組みにより、企業は情報セキュリティの確保をより効果的に行うことができるでしょう。例えば、適切なネットワークインフラストラクチャの導入には、従来のネットワークに比べてより高度な技術力が必要とされます。
人材の確保・育成
DX化に必要な人材は、IT技術やデータ分析などのスキルを持った人材が求められます。ただし、それだけで十分なわけではありません。DX化には、ビジネス理解やコミュニケーション能力など、多岐にわたる要素が必要です。
例えば、DX化においては、エンジニアとビジネス側が密にコミュニケーションを取り合うことが必要です。エンジニアは技術的な観点からシステムを考える必要があり、ビジネス側はビジネス観点からシステムを考える必要があります。
また、DX化に成功するためには、経営層がその必要性や意義を理解して、社員に伝えることが必要不可欠です。社員にDX化の重要性を伝え、その先頭に立つ経営陣が変革をリードすることが求められます。
▼人材育成について詳しくはこちら 人材育成マネジメントとは?必要なスキルや手順、成功のコツを徹底解説
顧客体験の向上
DX化を進める際には、企業が提供するサービスの利便性や品質を向上させることも考えなくてはいけません。例えば、ユーザーが自分のアカウントから直接購入履歴を確認できるようにしたり、迅速かつ正確なカスタマーサポートにアクセスできるようにすることなどを考えて、顧客体験を向上させることが求められます。
顧客との継続的かつ積極的なコミュニケーションを通じて、顧客の意見や要望を正確に把握することや、マーケット調査を実施するといった取り組みを行うことで、顧客ニーズを把握し、サービスの改善点を洗い出すことが必要です。 自社の商品・サービスの強みを活かしつつ、弱みを克服することは、システム導入を先行する前に考えるべきことであると言えるでしょう。
DX化(デジタルトランスフォーメーション化)を推進する際のポイント
DX化を推進する際のポイントとしては、DX化への取り組みに対する従業員の意識やモチベーションを向上させることが重要です。従業員の意識やモチベーションを向上させるには、会社やDX推進担当者が「モチベーションの公式」を活用し、従業員に働きかけることが必要です。
会社全体のモチベーション維持が重要
DX推進は、組織全体に大きな変化をもたらすため、従業員のモチベーション維持が不可欠です。新しい技術やプロセスへの適応は、時に抵抗や不安を生み出す可能性があります。そのため、経営層はDXの目的や意義を明確に伝え、全従業員が共通の目標に向かって進むよう促す必要があります。
進捗状況や成功事例を定期的に共有し、小さな成功も積極的に評価することで、チーム全体の士気を高めることができます。また、研修やワークショップを通じて、必要なスキルや知識を身につける機会を提供することも重要です。従業員が変化を恐れず、主体的にDXに関われるような環境づくりが、成功への鍵となります。
レガシーシステムによてDXが阻害される
長年使用されてきたレガシーシステムは、DX推進の大きな障害となることがあります。これらのシステムは、最新の技術との互換性が低く、データの連携や共有が困難な場合があります。また、システムの維持管理には多大なコストがかかる上、セキュリティ上のリスクも高まります。
DXを効果的に進めるためには、レガシーシステムの見直しや刷新が不可欠です。既存のシステムを詳細に分析し、必要な機能やデータを洗い出すことで、最適な移行計画を立てることができます。段階的な移行や、クラウドサービスの活用など、柔軟なアプローチを取ることで、業務への影響を最小限に抑えつつ、スムーズなシステム刷新を進めることが可能です。
中長期的な目線を持つ
DXは、短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点を持って取り組むべき課題です。技術の導入やプロセスの変革には時間がかかるだけでなく、その効果が現れるまでにも一定の期間が必要です。初期段階での成果が見えにくい場合でも、焦らずに計画に沿って進めていくことが重要です。
また、市場や技術の変化に合わせて、戦略を柔軟に修正することも必要となります。定期的な進捗確認や効果測定を行い、得られたデータをもとに改善策を講じることで、持続的な成長に繋がるDXを実現できます。経営層だけでなく、全ての従業員が長期的な視点を共有し、粘り強く取り組む姿勢が、DX成功の鍵となります。
DXの進め方
企業の成長戦略においてDX(デジタルトランスフォーメーション)は不可欠な要素となっており、その推進には明確な計画と段階的なアプローチが求められます。単なるデジタルツールの導入に留まらず、事業全体の変革を目指すDXは、組織全体の共通理解と協力が不可欠です。ここでは、DX推進の各ステップを詳細に解説し、成功への道筋を示します。
①DX化の目的の明確化
DX推進の第一歩として、具体的な目的を明確化することは、単なる技術導入に留まらない、組織変革の羅針盤となる極めて重要なプロセスです。「デジタル化を進める」という抽象的な目標設定では、組織全体のベクトルが定まらず、結果として期待される効果を得られない可能性が高くなります。
そうではなく、「顧客体験の向上」であれば、具体的にどのようなタッチポイントで、どのような課題を解決し、顧客満足度を何パーセント向上させるのか、「業務効率の大幅改善」であれば、どの業務プロセスをデジタル化し、どれだけの時間とコストを削減するのか、「新規ビジネスモデルの創出」であれば、どのような新しい価値を顧客に提供し、どのような収益モデルを構築するのかといった、具体的かつ測定可能な目標を設定する必要があります。
②DX戦略の策定
明確になった目的に基づき、具体的なDX戦略を策定する段階では、まず現状の課題を徹底的に分析します。各部門の業務プロセスにおける非効率な点、ボトルネックとなっている箇所、データ連携の不備、顧客体験における課題などを洗い出します。
その上で、これらの課題を解決し、設定した目標を達成するために、どのようなデジタル技術やツールを導入すべきかを具体的に検討します。AI、IoT、クラウドコンピューティング、ビッグデータ解析、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)など、多岐にわたる選択肢の中から、自社のビジネスモデルや課題、予算に最適な技術を選定します。
③必要な人材・スキルの定義
DX戦略を実行し、その目標を達成するためには、適切な人材の確保と育成が不可欠です。まず、DX戦略の全体像と各フェーズにおける具体的なタスクを分解し、それらに対応するために必要となる役割を明確に定義します。
例えば、データ分析に基づいた意思決定を推進するデータサイエンティスト、新たなデジタル技術を活用したシステムやサービスを開発するエンジニア、顧客体験を向上させるためのデジタル戦略を立案・実行するマーケター、そしてこれらの活動全体を統括し、組織を横断して変革を推進するDXリーダーなどが考えられます。
それぞれの役割に対しては、求められるスキルを具体的に洗い出します。技術的なスキルはもちろんのこと、問題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力なども重要になります。
④DX推進の過程の明確化
DX戦略を実行に移すための具体的なプロセスを明確化することは、単なる計画策定に留まらず、実行可能性を高める上で不可欠です。
各ステップにおいては、責任の所在を明確にする担当者を割り当て、現実的なスケジュールを設定し、必要な予算や人員、技術などのリソースを具体的に洗い出す必要があります。例えば、データ分析基盤の構築であれば、IT部門の担当者、完了までの期間、必要なサーバーやソフトウェア、関連する予算などを詳細に定義します。
さらに、初期段階でのリスクを低減し、実行の確実性を高めるために、パイロットプロジェクトの実施は非常に有効です。一部の業務や部門で試験的にDX戦略を導入し、その過程で明らかになる課題や改善点を早期に発見し、本格的な展開前に対応することで、よりスムーズな移行が可能になります。
⑤DX化の進捗を把握する
DX推進においては、進捗状況の定期的な把握が不可欠であり、目標達成への道筋を確実なものとするために重要なプロセスです。KPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、収集される数値データを基に、客観的かつ定量的に進捗度合いを評価します。単に進捗状況を記録するだけでなく、KPIの達成度合いを詳細に分析し、目標との差異や傾向を把握することが重要です。
もし進捗に遅れが見られる場合は、その根本原因を徹底的に分析する必要があります。ボトルネックとなっているプロセス、リソースの不足、担当者のスキル不足、想定外の課題の発生など、多角的な視点から原因を特定します。原因が特定されれば、具体的な改善策を策定し、実行に移します。
まとめ
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革し、競争優位性を確立することです。単なるIT化とは異なり、組織全体の変革を目指します。
成功事例として、ホンダ、三井住友銀行、ユニクロなどが挙げられます。課題としては、レガシーシステムの存在や人材不足があります。推進のポイントは、全社的なモチベーション維持、レガシーシステムの見直し、中長期的な視点を持つことです。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら