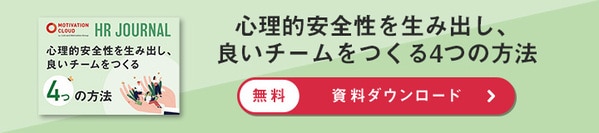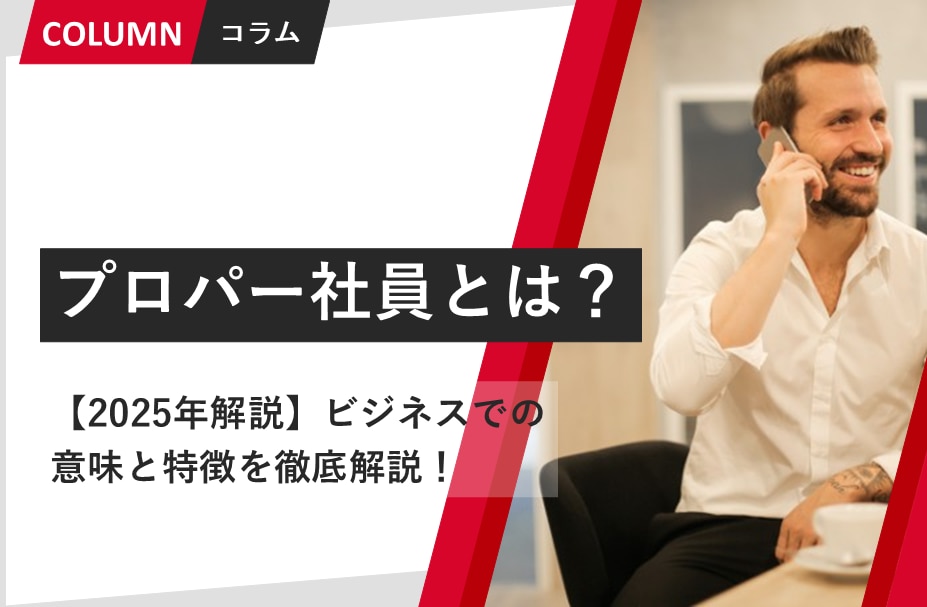
プロパー社員とは?【2025年解説】ビジネスでの意味と特徴を徹底解説!
日本のビジネスシーンでよく使われる言葉の一つに「プロパー社員」というものがあります。これは、英語の「プロパー(proper)」に「社員」を付けた和製英語ですが、いくつかの異なる意味を持っているため、意味があいまいなまま使っている人もいるかもしれません。
今回は、プロパーの意味や特徴について考察していきます。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら
プロパーとは?ビジネスにおける意味
プロパーとは、「適切な」「本来の」「ふさわしい」といった意味を持つ英語の「proper」を元にした言葉です。日本のビジネスシーンでプロパーという言葉が登場する場合のほとんどは、「プロパー社員」という使われ方をします。
ビジネスシーンでのプロパーの使い分け
「プロパー」という言葉は、ビジネスシーンにおいて業界ごとに微妙に異なる意味で使われています。まず金融業界では、プロパーとは「保証や担保を必要とせず、銀行自身が信用力を判断して融資を行う貸出」を指します。
たとえば、メガバンクが企業に対して保証協会を介さずに直接融資を実施するケースがこれに当たります。
一方、アパレル業界では、プロパーは「通常価格販売商品」を意味します。つまり、セールや割引を適用していない、定価で販売されている商品をプロパー商品と呼びます。販売戦略や売上分析の際にも頻繁に登場する用語です。
また、IT業界では、プロパー社員という形で使われることが多く、「元請け企業に直接雇用されている社員」を指します。システム開発などで、下請けや派遣ではない正規雇用社員を区別する意味合いで使用されます。
このように、「プロパー」という言葉は業界や文脈によって異なるニュアンスを持つため、適切な理解と使い分けが求められます。
業界別プロパーの意味の違い
各業界における「プロパー」の意味を表形式で比較すると以下の通りです。
業界 | プロパーの意味 | 使用例 |
金融業界 | 保証協会を介さない、銀行独自の信用判断による融資 | 「プロパー融資を実行する」 |
小売・アパレル業界 | セール対象外の通常価格販売商品 | 「プロパー比率が高い店舗」 |
製造業界 | 自社で採用・育成した正社員(中途・派遣ではない) | 「プロパー社員による開発チーム」 |
このように、同じ「プロパー」という言葉でも、業界ごとに対象やニュアンスが異なります。ビジネスシーンでは、相手の業界や文脈を正確に読み取って、適切な意味で使用することが求められます。
プロパー社員とは?他の社員との違いとは?
プロパー社員という言葉には、大きく3つの意味があります。
1つ目が、中途社員に対する「新卒社員」の意味、2つ目が、派遣社員や契約社員などの非正規社員に対する「正社員」の意味、
そして3つ目が出向社員や協力会社の社員に対する「自社社員」の意味です。プロパー社員という言葉が、この3つのうちどの意味で使われているのかは企業によって変わってきますし、文脈によっても変わってきます。
■プロパー社員と中途社員の違い
中途社員と区別する意図で、新卒入社の生え抜き社員をプロパー社員と呼ぶことがあります。新卒採用は日本独自の文化なので、「プロパー社員 = 新卒社員」という意味が通じるのも日本だけです。
たとえば、外資系企業の面接などで「御社ではプロパー社員の割合はどのくらいですか?」と質問しても、意味は通じないと考えておいたほうが良いでしょう。
■プロパー社員と非正規社員の違い
非正規雇用の社員と区別する意図で、正規雇用の社員(正社員)をプロパー社員と呼ぶこともあります。派遣社員や契約社員、アルバイトやパートなどと区別するような文脈でプロパー社員という言葉が使われたら、正規雇用の社員のことを指していると考えましょう。
この場合は雇用形態に注目しているため、新卒入社でも中途入社でも正社員であればプロパー社員ということになります。
■プロパー社員と協力会社社員の違い
他社の社員と区別する意図で、自社で雇用されている社員のことをプロパー社員と呼ぶこともあります。協力会社など外部の社員や、関連会社からの出向社員と区別するような文脈でプロパー社員という言葉が使われたら、自社社員のことを指していると考えましょう。
この場合は雇用元に注目しているため、新卒・中途にかかわらず、また正規雇用・非正規雇用にかかわらず、自社と雇用契約のあるスタッフならプロパー社員ということになります。
なお、この場合、プロパー社員側が自らのことをプロパー社員と称するケースは稀で、たとえば、業務委託の社員が客先常駐をしているシーンなどで、客先の社員のことをプロパー社員と呼んだりするのが一般的です。
プロパー社員の特徴
上述のとおり、プロパー社員には3つの意味がありますが、ここでは一般的に共通していると考えられるプロパー社員の特徴についてご説明します。
■プロパー社員は愛社精神が強い
前述の3つのいずれにせよ、自分が所属する会社であるため、愛社精神は当然相対的に高くなります。さらに新卒社員にとって自社は、社会人として一から育ててもらった場所であり、理念やビジョンに親しみながら仕事をしてきた場所です。
また、勤続年数が長くなるほど会社への帰属意識が高まっていき、「自分が作ってきた会社」として愛社精神が強くなる傾向にあります。それゆえ、自社の歴史や実績、商品やサービスにも強い誇りを持っています。
また、会社からの評価を重視し、会社の方針に従順な社員が多いのもやはりプロパー社員の特徴となるでしょう。
■プロパー社員は給料などの待遇面で優遇されやすい
プロパー社員は、給料などの待遇面で優遇されやすい傾向にあります。長く会社にいる社員の中には生え抜きの新卒社員を可愛がる人もいるでしょうし、年功序列の会社であれば、新卒で入社したプロパー社員は勤続年数とともに順調に昇給・昇格をしていくのが一般的です。
■プロパー社員は自社のことを熟知している
プロパー社員は、会社に入社してすぐに新入社員研修を受けます。新入社員研修では、会社の理念やビジョン、歴史はもちろん、事業内容や商品の特徴などを徹底的に教え込まれることが多いでしょう。
それ以降も、実務経験を積んだり定期的に研修を受けたりして理解を深めていくため、プロパー社員は自社のことを知り尽くしています。他社員に比べて商品知識が豊富なのはもちろん、社内の人間関係やパワーバランス、不文律などを熟知しているのもプロパー社員の特徴です。
■プロパー社員は視野が狭く柔軟性に欠ける傾向がある
特に新卒入社者=プロパー社員のケースにおいては、一つの会社で育っているため、自社の方針や考え方に染まりきっている人も少なくありません。そのため、自社のやり方に疑問を持たず、常に自社基準で物事を判断する傾向にあります。
その他の社員から見ると「視野が狭い」「柔軟性がない」と感じることもあるようです。
■プロパー社員は保守的で変化を嫌う傾向がある
新卒で入社したプロパー社員は他社のことを知らないがため、比較の対象が自社の過去しかなく、会社の方針や伝統を変えるのを嫌う傾向にあります。
他の社員が新しい方法を提案したとしても、「前例がないから・・・」「うちの会社的にはちょっと・・・」といった理由で受け入れないケースが多いようです。
■新卒プロパー社員は中途社員との間に摩擦が生まれやすい
新卒の同期入社者の間には、強固な連帯感があります。年齢が同じで、初めて社会人になったときから「同じ釜の飯」を食べている間柄なので、プロパー社員同士の絆は自然と強くなるものです。
それ自体は悪いことではありませんが、プロパー社員同士の関係性が強すぎて中途社員が馴染みにくいという会社も少なくありません。また、中途社員との間に摩擦が生まれやすく、それが円滑な業務に支障をきたしてしまうこともあります。
プロパー社員のキャリアパス
プロパー社員とは、新卒採用などで企業に直接雇用され、長期的に育成・登用される社員を指します。一般的に、プロパー社員は計画的な人材育成プランに基づき、明確なキャリアパスを歩むケースが多いです。以下に、典型的なプロパー社員のキャリアルートを図示します。
【プロパー社員のキャリアパス例】
入社(新卒採用)
↓
基礎研修・OJT(1〜3年)
↓
現場リーダー・チームリーダー(3〜5年目)
↓
係長・主任クラス(5〜8年目)
↓
課長クラス(8〜12年目)
↓
部長クラス(12〜18年目)
↓
事業部長・本部長(18年以上)
↓
経営幹部(取締役・執行役員など)
このように、プロパー社員は、組織内での経験蓄積を重ねながら段階的に昇進していくのが一般的です。長期的視点での能力開発やマネジメントスキルの習得を重視し、将来の幹部候補としての成長を期待されています。
■プロパー社員の平均的な待遇
プロパー社員の待遇は、安定的で福利厚生が充実していることが多いのが特徴です。たとえば、給与面では、30歳時点での年収平均は約450万円〜550万円程度(業界平均比+5〜10%)とされています(※厚生労働省賃金構造基本統計より)。
賞与についても、年間4〜6ヶ月分(基本給ベース)を支給する企業が多く、これは中途入社者と比較してやや高水準です。
福利厚生面では、住宅手当、家族手当、企業年金、持株会制度などが整備されている場合が多く、長期雇用を前提とした手厚い制度設計がなされています。
このように、プロパー社員は「安定志向」の待遇パッケージが整っており、長期にわたり安心してキャリア形成を図ることができる環境が用意されています。
プロパー社員と中途社員の協業のポイント
プロパー社員と中途社員がうまく協業するためには、互いの強みを尊重し合う文化づくりが重要です。以下、成功事例を3つ紹介します。
1.製造業A社(自動車部品メーカー)
中途社員が専門スキルを生かして製造現場改善プロジェクトを主導。プロパー社員が組織内調整と社内文化の理解をサポートし、現場の抵抗感を和らげた結果、半年で生産性15%向上を実現。
2.IT企業B社
中途入社のエンジニアが最新技術導入を提案。プロパー社員が経営層への橋渡しを行い、導入決定をサポート。両者の連携により、プロジェクト成功率が従来の1.5倍に向上。
3.金融機関C社
営業部門で、中途社員が新しい市場開拓を推進。プロパー社員が既存顧客基盤を活用してクロスセル提案を実施。相互補完により、前年比120%の売上拡大に成功。
このように、プロパー社員の「社内ネットワーク力」と中途社員の「外部視点・専門スキル」を掛け合わせることで、組織全体の成果を最大化することが可能です。
プロパー社員と他の社員の連携力を高める方法
プロパー社員とその他の社員の連携を強化するためには、大前提として、同じ船に乗っている者同士、同じ目的地を目指していなければいけません。そのため、企業の理念・ビジョンの浸透を徹底することがもっとも重要です。
その他、社内レクリエーションを企画したり、研修を一緒に受けさせたり、同じプロジェクトにバランス良くアサインするなどして、プロパー社員とその他の社員のコミュニケーションを促すことも大切です。
また、人事評価がプロパー社員に有利になっていたり、逆に中途社員が優遇されていたりするようであれば、評価基準などを見直す必要があるでしょう。
プロパー社員における注意点
「プロパー社員」という言葉は、業界によって、また文脈によってニュアンスが変わってくる言葉です。マイナスのニュアンスで使われることもあり、文脈によっては差別だと感じる人もいるようです。
悪意なく口にした場合でも、相手を不快にさせたり誤解を生んだりすることがあるため、使用する際には注意が必要です。「新卒社員」「正社員」「自社社員」と言えば、わざわざ「プロパー社員」と言う必要もないので、使わないようにするのも一つの手です。
プロパーに関連するその他の用語
プロパーに関連する用語について解説します。
プロパー融資(プロパーローン)
プロパー融資(プロパーローン)とは、主に金融業界や不動産業界で使われる言葉で、金融機関が信用保証協会の保証無く、直接自身の責任で実行する融資・ローンのことを言います。これに対し、信用保証協会の保証が付く融資は「保証付き融資」と呼ばれます。
プロパーカード
プロパーカードは、クレジットカード業界で使われる言葉で、クレジットカード会社が自ら発行するカードのことを言います。これに対し、クレジットカード会社が他社と提携して発行するカードは「提携カード」と呼ばれます。
プロパー価格
プロパー価格は、主にアパレル業界で使われる言葉で、値下げをしていない正規の価格のことを言います。なお、プロパー価格で販売される商品は「プロパー商品」と言われます。
○○学プロパー
○○学プロパーは、学問の分野で使われる言葉で「○○学を専攻している人」や「○○学本来の」という意味があります。たとえば、「経済学プロパーの学生」と言ったら「経済学を専攻している学生」という意味になり、「経済学プロパーの問題」と言ったら「経済学固有の問題」という意味になります。
組織変革のことならモチベーションクラウド
リンクアンドモチベーションは、導入実績8,740社、237万人以上という国内最大級のデータベースによる精度の高い組織診断と、コンサルタントの併走による実行力のある改善を行ってきました。
・業績が上がらず、組織にまとまりもない
・いい人材の採用や育成が進まない
・給与や待遇への不満が挙がっている
といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供します。
▼モチベーションクラウドの具体的な機能や得られる効果が分かる資料 「3分でわかるモチベーションクラウド」はこちら
まとめ
プロパー社員にはプロパー社員ならではの良い面もありますが、その他の社員との間に摩擦が生じてしまったりするケースも少なくありません。とはいえ、人材不足の昨今で多様化が進む中、プロパー社員は会社の根幹を支える貴重な存在です。
会社としては、非プロパー社員との相対でプロパー社員の特性や問題点を理解したうえで、プロパー以外の社員も含め、働きやすい環境づくりをしていく必要があります。プロパー社員とその他の中途社員双方のシナジーを生み出すことができれば、会社にとって大きな競争力になるはずです。
そして、シナジーを生み出す際には必ずなくてはならない考え方があります。それは組織を「要素還元できない協働システムである」と捉え、「組織の問題は『人』ではなく『間』に生じる」という関係論的、システム論的な見方をすることです。言い換えれば「組織は生き物」なのです。
何か問題が起きた時に「プロパーだから」「中途社員だから」「業務委託だから」「非正規雇用だから」とそれぞれの属性に問題の原因を安易に帰着させたり、犯人探しをしたりするような方法では本質的な課題を捉えられず、言わずもがな改善やシナジーを生み出すことは難しいです。
何か問題が起きたときこそ、互いの立場やバックグラウンドを理解し歩み寄ること、批判ではなく提案を心がけることが、シナジーを生み出す一歩になります。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
プロパーに関するよくある質問
プロパーに関連する用語について解説します。
Q:中途採用比率の公表義務化とは?
中途採用比率の公表義務化とは、正規雇用労働者数のうち中途採用者数が占める割合を公表する制度のことです。
令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できる形で「直近3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが義務化されました。
対象となる企業は、少なくとも年に1回はインターネットなどで公表する必要があります。詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。
>> 正規雇用労働者の中途採用比率の公表|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
Q:非プロパー社員の教育はどうすればいい?
中途社員への研修・教育は、プロパー社員への研修・教育と比較して簡易的なものになっている企業が少なくありません。しかし、あまりに簡易的なものだとプロパー社員との間に価値観や熱量の差が生まれてしまう可能性があります。
業務に関する教育はプロパー社員ほど時間をかける必要はありませんが、理念やビジョン、行動指針などに関する教育・研修は、プロパー社員と同等の機会を設けるべきです。時期が合えば新卒研修に参加させて、自社の理念やビジョン、沿革について一から学んでもらうのも良いでしょう。