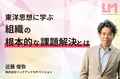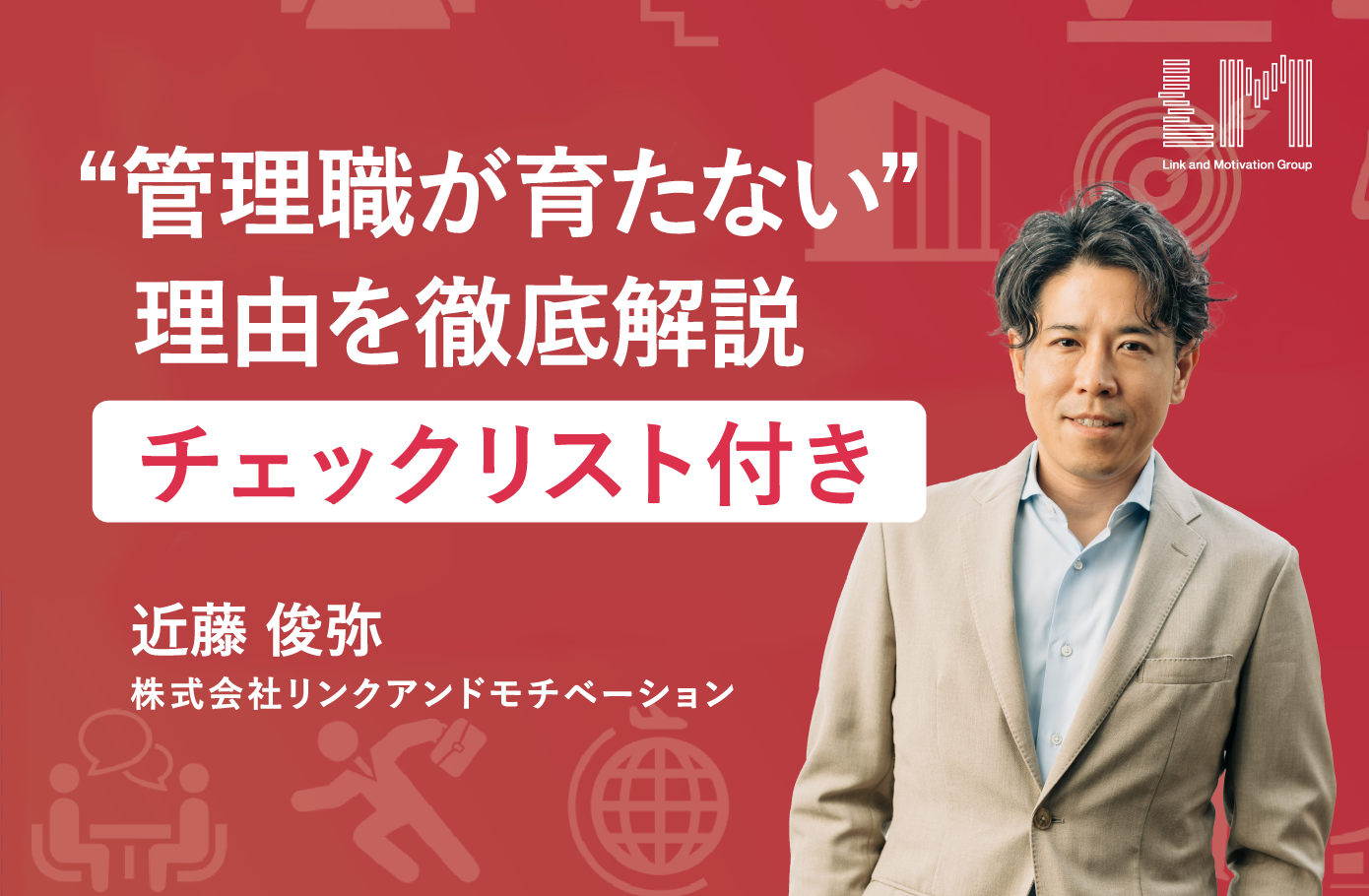
”管理職が育たない”理由を徹底解説 ~チェックリスト付き~
現在、持続的な企業成長を実現するために、日本のみならず世界中で「従業員エンゲージメント*の向上」に力を入れる企業が増えている。アジアのビジネスハブであるシンガポールにおいても、多様な人材が集まる環境に適応するため、従業員エンゲージメントの重要性が高まっている。
*従業員エンゲージメント=企業と従業員の相互理解・相思相愛度合いを示す指標
リンクアンドモチベーションシンガポールおよびグローバルチームで代表を務める近藤俊弥が、従業員エンゲージメントについて解説する本連載。今回は、従業員エンゲージメント向上に不可欠な「管理職の育成」に焦点を当てる。
「優秀な個人プレイヤーは多いが、管理職としての育成がうまくいかない」
「組織の中でリーダーシップを発揮できる人材がなかなか育たない」
――これは、シンガポールをはじめ、世界中の日系企業からよく聞かれる声だ。
本稿では、こうした「管理職が育たない」という課題の背景にある要因を明らかにし、育成を進めるための具体的なポイントを解説していく。
シンガポールの労働市場と管理職育成の必要性
シンガポールの労働市場の特徴
シンガポールは、政府による積極的な人材誘致政策のもと、世界中から優秀な人材が集まる都市国家だ。
過去の記事でも解説した通り、同国の労働市場では、「柔軟化」と「多様化」という2つの大きな変化が起きている。具体的には、失業者一人当たりの求人数が大幅に増加し、働き先の選択肢が広がることで「柔軟化」が進み、同時に、働く個人の価値観も多様化している。
こうした環境下において、企業が人材から選ばれ続けるために、従業員エンゲージメントの向上は重要性を増している。このエンゲージメント向上の鍵を握るのが、管理職育成だ。
過去解説記事を読む:
管理職育成が必要な理由
そもそも、なぜ管理職は重要なのだろうか。
当社では、管理職の役割を「結節点」と定義している。管理職は、経営層と現場、部署間など、組織内のあらゆる関係性の間に立ち、それらをつなぐ役割を担っている。
組織には多様な人材が存在し、放っておけば関係性は容易に複雑化する。そのため、結節点としての機能を果たす管理職は、組織内のコミュニケーションを整理し、複雑性を縮減するうえで欠かせない存在だ。
つまり管理職は、単なる中間管理者ではなく、組織の有機的なつながりを支える中核的な存在である。
このように、管理職の役割は組織運営そのものにとって不可欠であり、エンゲージメント向上においても重要な鍵を握っている。当社のサーベイ結果からも、管理職のマネジメントが職場のエンゲージメントに大きな影響を与えることが明らかになっている。
特に、エンゲージメント向上の重要性が一層高まっているシンガポールにおいては、管理職の育成は単なる人材開発にとどまらず、組織の競争力の根幹に関わるテーマとして、戦略的に捉える必要がある。
もちろん、すでに管理職の育成に取り組んでいる企業や、その重要性を認識し、管理職の役割発揮に向けた支援を進めている企業も少なくない。
しかしその一方で、「育成に取り組んでいるはずなのに、管理職がなかなか育たない」といった声も多く聞かれる。
ではなぜ、育成の取り組みが期待どおりの成果につながらないのか。その背景には、共通する組織的な課題が存在している。
次に、管理職が育たない組織に見られる、代表的な2つの原因について解説したい。
管理職が育たない原因
原因① 管理職の役割が定まっていない
管理職が育たない原因の一つに、「役割の不明確さ」が挙げられる。
多くの企業では「管理職=マネジメント」という前提はあるものの、その具体的な役割や責務を定義し、管理職本人に適切に伝えているケースは意外と少ない。
たとえば、「部下を持たせれば管理職になる」「業務遂行能力が高い人材を管理職に登用する」といった運用も見られるが、そもそも“管理職”としての役割が明確でなければ、適切なマネジメントは実行できない。
これは、スポーツチームにおいて「君はフォワードだ」と言われただけで、具体的なプレー内容や役割の説明がない状況と似ている。得点を狙うべきか、ディフェンスを重視すべきか、どこにポジショニングすべきかが分からなければ、選手は迷い、チーム全体の連携も崩れてしまう。
企業組織においても同様だ。管理職の役割が曖昧なままでは、本人がどのようにリーダーシップを発揮すべきか判断できず、結果として組織全体の生産性やエンゲージメントの低下につながりかねない。
さらに重要なのは、役割を一方的に「伝える」だけでなく、管理職本人がその内容に納得し、合意しているかどうかだ。経営層と管理職との間で期待値の認識をすり合わせることによって、初めてその役割は“自分の仕事”として内在化され、実行力につながっていく。
ポイント:
- 管理職の役割を明文化し、期待値を明確にする
- 経営層と管理職の間で役割に対する合意形成を行う
原因② 管理職に対するフィードバック体制が機能していない
もう一つの大きな原因は、「フィードバック体制の不備」である。
管理職にマネジメントを任せっぱなしにしていないだろうか。たとえ管理職の役割を明確に定義していたとしても、それを任せきりにしてしまっては、育成効果は限定的になる。実際、管理職がフィードバックを受ける機会がほとんどなく、本人が「何も言われないということは、問題がないのだろう」と解釈してしまい、結果として成長につながらないケースも少なくない。
そもそも、人は知識をインプットするだけでは成長しづらい。行動に対する適切なフィードバックがなければ、自分の現在地を正しく把握できず、改善に向けた試行錯誤のサイクルも回らなくなってしまう。その結果、マネジメントスキルは停滞しやすくなる。
これはスポーツにおいても同様だ。たとえば、まったく新しい競技――フェンシングを始めたとしよう。最初にルールや基本動作を学んだとしても、ただ本や動画を見るだけでは、実践においてうまく動けるようにはならない。実際にプレイしてみても、自分の動きが正しいのかどうか判断できず、うまくいかない理由も見えてこない。
そこでコーチが、「今の動きは良かった。ただ、もっと重心を落とせば守りが安定する」といった具体的なフィードバックを与えることで、選手は自分の課題を理解し、次の試合に向けて対策を立てることができるようになる。
企業における管理職育成もまったく同じである。「何も言わない=問題がないと捉えられる」状態を脱し、「適切なフィードバックを日常的に伝えている」状態をつくることが、管理職の成長においては不可欠だ。
また、成長を促すには、フィードバックの機会を一方向に限らず、複数の視点から提供することが効果的である。
具体例:
- 定期的な1on1ミーティングの導入
- 360度フィードバックを活用し、管理職自身の成長を促す
管理職が育つための環境を作るには?
これまで、管理職育成の重要性や、育成がうまく進まない原因について見てきた。では、実際に育成の取り組みを成果につなげていくには、どのような環境が必要なのだろうか。
個別の対策を講じること自体は重要だが、それだけでは十分ではない。効果の検証や改善が継続的に行われなければ、取り組みは再現性を欠いた対処療法にとどまり、同じ課題が繰り返されるリスクを抱えることになる。
そこで求められるのは、管理職が定期的に自身のマネジメントを振り返り、次の成長につなげられるような仕組みを、組織として備えることだ。
その一例として有効なのが、「マネジメントの好事例を可視化し、社内で共有すること」である。たとえば、マネジメントの役割を体現した管理職を社内で表彰したり、全体会議の場でその実践を紹介したりすることで、具体的な成功モデルを組織全体に示すことができる。
こうした成功事例の共有は、単なる評価や称賛にとどまらない。「どのようなマネジメントが求められているのか」という共通認識や行動基準を、組織内に育てていく起点となる。
このようにして、管理職が自ら成長サイクルを回せるような環境を整えることが、継続的な育成の鍵となる。
管理職育成のためのチェックリスト
管理職育成に取り組むうえで、まず重要なのは、自社の現状を客観的に把握することである。現状が不明瞭なままでは、育成の方向性が定まらず、適切なアプローチを選択することは難しい。
以下のチェックリストは、自社における管理職育成の取り組みを見直す際のヒントやきっかけとして活用いただきたい。いまの状況を振り返りながら、改善の糸口を探る手助けになれば幸いである。
✅ 管理職の役割について、明確な定義や文書化された情報や伝達の機会があるか?
✅ 管理職がその役割について合意しているか?
✅ 管理職に対するフィードバックを適切に伝えているか?
✅ 定期的に管理職のスキル向上を図る施策を実施しているか?
✅ マネジメントの成果を評価し、フィードバックの場を設けているか?
まとめ
管理職の育成は、企業の持続的な成長を支えるうえで、欠かすことのできない要素である。現場におけるマネジメント機能が弱まれば、従業員エンゲージメントの低下や生産性の停滞を招き、ひいては企業全体の競争力に影響を及ぼす可能性がある。
本記事では、管理職が育たない原因として、「役割の不明確さ」と「フィードバック体制の不備」の2点を取り上げた。これらはいずれも、現場でよく見られる共通課題であり、組織としての仕組みづくりが不十分なままでは、いくら育成に取り組んでも成果につながりにくい。
マネジメントの強化は、一朝一夕に実現できるものではない。だからこそ、企業としては次のような取り組みを、継続的かつ戦略的に進めていくことが求められる。
- 管理職の役割を明確にし、期待値をすり合わせること
- フィードバックを通じて、成長の方向性を示し続けること
- 管理職が自ら成長サイクルを回せる環境を整えること
そして何より、こうした取り組みを通じて、組織全体でマネジメントを支援する文化を醸成していくことが、長期的な人材育成と競争力強化の土台となる。
本稿で紹介したチェックリストも、そうした取り組みを検討する際のヒントとして活用していただきたい。
※定員に達し次第、受付締締切予定ですので、ご参加希望の方はお早めにお申し込みください。