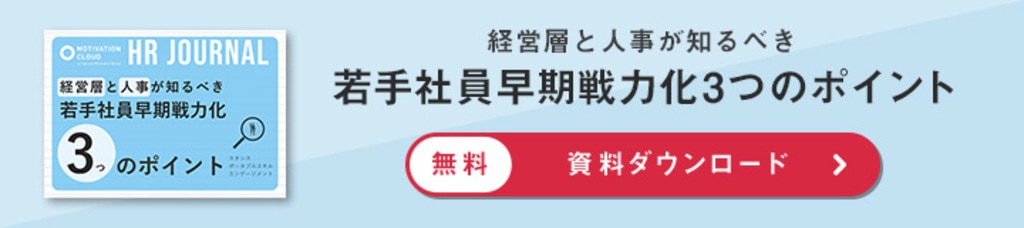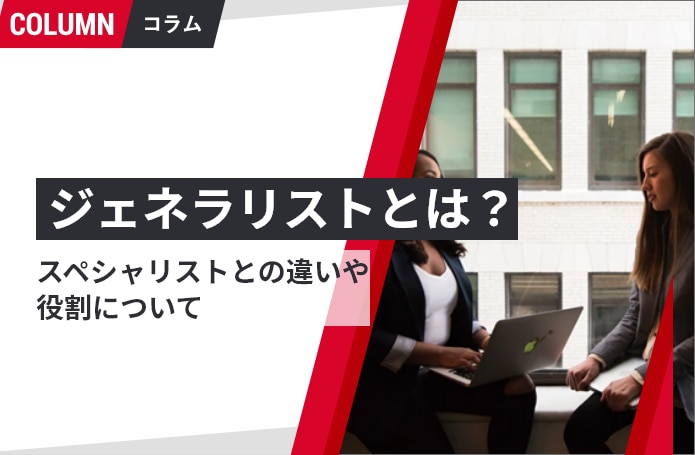
ジェネラリスト(ゼネラリスト)とは|スペシャリストとの違いや役割について
▼3分で分かる!!従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
目次[非表示]
皆さんは「ジェネラリスト」と聞いてどんな人を思い浮かべるでしょうか?またジェネラリストとスペシャリストはセットで使われることが多い言葉ですが、どんな違いがあるのでしょうか?
本記事では、ジェネラリストとスペシャリストの定義や具体的なキャリア形成についてご紹介します。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ 【組織診断】活用に向けた具体的なポイントを解説!資料はこちら
ジェネラリスト(ゼネラリスト)とは
「ジェネラリスト」とは、多岐にわたる分野に精通し、幅広く知識を持っている人のことです。
ジェネラリストは、専門家が気づかなかった問題点を発見し、相互に連携ができるチームづくりで課題を解決することができます。
■ジェネラリストの語源
日本語でも「ジェネラリスト」という言葉は定着してきましたが、この「ジェネラリスト」は英語のgeneralistが語源です。英語では、「多方面の知識を持つ博学な人」という意味の言葉です。
様々なことを知っている・精通している、という意味では「万能家」と和訳されることもあります。
スペシャリストとの主な違い
■スペシャリストとは
一方で、スペシャリストは、特定の分野において専門的な知識・スキルを有する人を指します。いわゆる「専門職」です。
たとえば、営業や企画、人事などを経験しながら総合的な知識を身につけていくのがジェネラリストだとすれば、スペシャリストは、エンジニアや医者などのように特定の分野で専門的な知識・スキルを深めて仕事に取り組む人たちです。
■スペシャリストとジェネラリストとの違い
スペシャリストは、その分野で高度なスキルを持ち、その分野に特化した業務において優れた成果を出すことができます。これに対して、ジェネラリストは、幅広い分野について知識を持っているため、他の分野の専門家たちと協力して業務に従事することができます。
ジェネラリストは一般的に、幅広い知識と経験を持っており、複雑な問題に対してクロスファンクショナルなチームで取り組むことができます。また、ジェネラリストは、新しい分野に挑戦することができ、その分野でのスキルを習得することができます。一方で、スペシャリストは、その分野の専門知識を深め、特定の業務に集中することができます。
両方の役割は、チーム内での効果的な協力に不可欠であり、組織内での重要な役割を果たしています。
ジェネラリスト(ゼネラリスト)を採用するメリット
働き方の革新や採用にかかる費用の観点から、余裕をもって人材を確保できる企業は稀です。これは、多くの企業が限られた人材を用いて、適切な役割分担と配置を通じて職場のパフォーマンスを最大化する必要があることを意味します。
このような状況下でジェネラリストの採用にはどのようなメリットが存在するのでしょうか。
■幅広い知識を持っているため、様々なプロジェクトに参加することができる
ジェネラリストは、専門家ではないため、ある程度の幅広い知識を持っています。そのため、様々な分野において業務に従事することができます。例えば、営業、マーケティング、人事、財務、顧客サービスなどです。ジェネラリストの柔軟性は、企業にとって非常に重要であります。
特に、急速に変化する現代において、多様な業務に対応できる人材は貴重です。また、ジェネラリストは、多様な業務を経験することによって、多角的な視点を持つことができます。そのため、企業の戦略的な意思決定に貢献することができます。
■ビジネスにとって重要な視点を提供することができる
ジェネラリストは、特定の分野に偏っていないため、幅広い視野を持っています。彼らは、ビジネスにおいて、問題解決のために必要な多角的なアプローチを提供することができ、ビジネスにとって重要な観点を提供することができます。
また、ジェネラリストは、様々な分野で経験を持っており、ビジネスにとって有益な知識を提供することができます。彼らは、経営戦略の策定、プロセスの改善、顧客ニーズの把握など、ビジネスにとって重要な課題を解決するために、幅広い分野の知識を活用できます。
■相互に協力・連携できるチームで業務に従事することができる
ジェネラリストは、様々な分野に関する幅広い知識を持っているため、様々な専門家たちと協力して業務に従事することができます。たとえば、医療の専門家、金融の専門家、法律の専門家、ITの専門家など、様々な分野の専門家たちと一緒に仕事をすることができます。
ジェネラリストは、様々な分野に関する知識を持っているため、様々な専門家たちと円滑なコミュニケーションを取りながら、業務に従事することができます。
ジェネラリスト(ゼネラリスト)を採用するデメリット
ジェネラリストを採用することには、メリットのみがあるわけではありません。では、ジェネラリストを採用することで、どのようなデメリットがあるのでしょうか。メリット・デメリットの双方に対する理解を深めることで、自社の採用・配置などを最適化することができます。ここでは、ジェネラリストを採用するデメリットについて代表的なものをご紹介します。
■スキルの深堀りが難しい
ジェネラリストは、多岐にわたるスキルを持っていることが特徴です。しかしながら、彼らは特定の分野での深い専門知識や技術を持つことが難しいため、専門的な課題やプロジェクトに対する対応力が制限される可能性があります。
ジェネラリストは、業界全体を俯瞰し、異なる分野のアイデアを組み合わせ・活かし合うことができるため、革新的なソリューションを生み出す可能性があります。ただし、深い洞察力と専門知識を必要とする課題に対しては、専門家と協力することが必要であり、それが前提となっています。
■役割の明確化が難しい
ジェネラリストは様々なタスクに対応可能な能力を持つことが求められますが、その一方で、ジェネラリストの役割が曖昧になりがちであることが指摘されています。このような状況では、組織内での役割の明確化や責任範囲の設定が難しくなり、結果として、パフォーマンスの評価やフィードバックの提供が困難になる可能性があると考えられます。
したがって、ジェネラリストの役割をより明確なものにするために、彼らが担当するタスクや目的を明確に定義することが重要です。また、ジェネラリストが専門的なスキルに欠けている場合は、それに対応するトレーニングや支援を提供することも必要です。
■育成コストがかかる
ジェネラリストは、幅広いスキルを持っているため、彼らの能力を最大限に引き出すためのトレーニングと開発プログラムを設計することは困難です。しかし、彼らが持っているスキルには、コミュニケーション能力、組織力、問題解決能力、多様性への理解、プロジェクト管理能力などがあります。
これらのスキルを一度に開発することは難しく、OJTやOff-JTなどの学習機会を通して体系的に育成をする必要があります。
ジェネラリストに必要なスキル
ジェネラリストは幅広い知識やスキルが求められる役割です。そのため、身につけるべきスキルも多岐に渡ります。例えば、以下のようなスキルがジェネラリストには求められます。
- コミュニケーション能力
- プロジェクトマネジメントスキル
- 問題解決能力
- データ分析能力
- 幅広い知識
- 自己学習能力
それぞれどのようなスキルであるのかを確認しておきましょう。
コミュニケーション能力
ジェネラリストは、プロジェクトの成功に向けて、様々な部署やステークホルダーとコミュニケーションを取りながら、協力して取り組む必要があります。また、プロジェクトの進行状況を正確に把握し、適切な対応を行うため、綿密なプランニングやデータ分析のスキルも重要です。
さらに、プロジェクトの成功に向けて新たなアイデアを導入することも必要であり、常に学習意欲や創造性を持ち合わせることが求められます。ジェネラリストには優れたコミュニケーションスキルが必要ですが、それだけではなく、多くのスキルや資質を持ち合わせることが求められます。
プロジェクトマネジメントスキル
ジェネラリストの役割は非常に重要であり、プロジェクトを成功に導くために様々なスキルが求められます。彼らは、プロジェクトを管理し、スケジュールを調整し、必要な資源を確保することで、プロジェクトの成功に貢献します。
また、彼らは、チームのメンバーやステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行い、問題が発生した場合には迅速に対処することも求められます。プロジェクトマネジメントのスキルを持つことは、ジェネラリストにとって非常に望ましいことです。
これには、プロジェクトの計画、実行、監視、制御、そして閉鎖に関するスキルが含まれます。また、リスクマネジメントや品質管理などのスキルも重要です。ジェネラリストがこれらのスキルを持っている場合、プロジェクトの成功に大きく貢献することができます。
問題解決能力
ジェネラリストの仕事は、問題が発生した場合に迅速かつ適切に対処することです。そのためには、優れた問題解決スキルが必要となります。例えば、問題が発生した際には、原因を特定するために情報収集が必要となります。また、解決策を見つけるためには、分析能力や判断力が必要となります。
さらに、問題解決にはコミュニケーション能力も重要です。他のチームメンバーや上司と協力して問題を解決することが必要となる場合もあります。つまり、ジェネラリストは、多くのスキルを必要とする職種であり、問題解決スキルのみならず、情報収集能力、分析能力、判断力、コミュニケーション能力など、さまざまな能力が求められます。
データ分析能力
ジェネラリストとは、データを収集し、分析し、結果を報告することが求められる職種です。データ分析スキルは、業務を円滑に進めるためにも重要ですが、それだけでは十分ではありません。
例えば、データの収集方法を選択する際には、どのようなデータが必要か、どのように収集するか、どのようにクリーンナップするかなど、複雑な判断が求められます。また、データ分析においては、分析手法の選択、データの可視化、結果の解釈など、多岐にわたるスキルが必要です。そのため、ジェネラリストは、幅広い知識とスキルを持つことが求められます。
幅広い知識
ジェネラリストは、多様な分野に関する知識を持っている必要があります。例えば、ビジネスの場合、マーケティング、会計、戦略、財務、人事など、幅広い分野について理解している必要があります。
また、技術分野では、プログラミング、データ分析、ソフトウェア開発、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティなど、最新の技術動向にも通じていることが欠かせません。
さらに、戦略分野では、競合分析、市場調査、SWOT分析、ビジネスプランの策定、プロジェクトマネジメントなど、企業経営に必要な戦略的思考力も必要です。ジェネラリストには、多岐にわたる分野に精通しているため、組織内の様々な部署と協力し、ビジネスやプロジェクトの成功に貢献することが期待されます。
自己学習能力
ジェネラリストは、常に新しいスキルや知識を習得し、業務に活かす必要があります。例えば、ビジネスの現場においては、営業、マーケティング、事業開発、および人事など、幅広い分野に渡るスキルが必要とされます。
そのため、ジェネラリストは、多様な経験を積んで、自己学習能力を高めることが重要です。ジェネラリストにとって、新しいスキルや知識を習得することは、自己成長を促し、キャリアアップにもつながります。また、自己学習能力があることで、常に最新の情報をキャッチアップし、業務に活かすことができます。
ジェネラリスト(ゼネラリスト)に適したポジション
では、ジェネラリストに適したポジション・業務はどんなものがあるでしょうか。
■ポジション例:管理職やマネジャー
こちらは先に紹介した通りです。
営業部門のマネジャーや企画室のマネジャーなど、部門全体をまとめる存在がそれに当たります。
現場の知識・ノウハウを持ちながら、組織を束ね、部門全体で成果を上げるために戦略・戦術を考え実行していく。このように全体を見わたして短期も中長期も見据えながら、仕事をするマネジャーは適したポジションとなるでしょう。
■ポジション例:総務や人事
総務や人事などのバックオフィス系の業務にも、ジェネラリストは向いていると言われます。
たとえば総務部は、経理、契約管理、庶務など多種多様な業務に対応する必要があるため、企業経営に必要な様々な知識が求められるでしょう。
人事部も同様です。採用関連でいえば、採用スケジュールの策定や、応募者や面接者との連携、個人情報管理、応募者のフォロー、経営陣や各現場部署とのやり取りなど、社内外を含めて臨機応変な対応が必要です。
社内のあらゆる部署、役職、職種の人とコミュニケーションを取り、それぞれの業務内容やニーズ、問題、課題を理解しなければいけないのも総務や人事の特徴です。こうした業務内容からも、このポジションはジェネラリストに適していると言えるでしょう。
■ポジション例:プロダクトマネジャー
IT・Web業界では馴染みのある職業ですが、この職種にもジェネラリストが適しています。尚、プロダクトマネジャーは、Webサービスの責任者のことを指します。
エンジニアをはじめ、デザイナー、コンテンツクリエイターなどさまざまな人をまとめながら1つのプロダクトを創り上げるポジションです。
この職種は、自ら手を動かして何かを作るわけではありません。プログラミングを設計、作成して動かしているのはエンジニアであり、デザインをしているのはデザイナーです。
しかし、そのエンジニアやデザイナーとコミュニケーションを取り、1つの理想のプロダクトを作るためには、プログラミングやデザインの知識が必要です。もちろん、「極める」必要はありませんが、その道のスペシャリストの方々と話ができる程度の知識は求められます。
このように幅広い知識を身につけ、それらを活かしながら、チームをまとめていくプロダクトマネージャーはまさにジェネラリストと言えるでしょう。
■ポジション例:コンサルタント
コンサルタントは、クライアント企業のビジネスモデルや業界トレンドなどを理解していなければ、成果を上げるのは難しくなります。それゆえ、幅広い経験を積んでいて、様々な業界・分野の知識を持っているジェネラリストのほうが担当できるクライアントの幅が広がり、最適な戦略を立てやすくなります。また、コンサルタントには常に情報のアップデートが求められることもあり、幅広くアンテナを張っているジェネラリストのほうが活躍しやすいと言われています。
ジェネラリストの役割は業種ごとに異なる
一口に「ジェネラリスト」と言っても、業界や業種でその扱いや定義は異なります。ジェネラリストは業種によって求められるスキルが異なるため、それぞれの業界におけるジェネラリストについても留意する必要があります。
医療業界でのジェネラリスト
医療業界においても、ジェネラリストの役割は非常に重要です。医療業界においては、専門分野に精通している医師や看護師などの専門家が必要不可欠ですが、それだけではなく、病院や診療所の管理、医療機器の導入、医療システムの構築、医療従事者の育成など、多岐にわたる業務が存在します。
ジェネラリストが医療業界において果たすべき役割は、以下のようなものが挙げられます。
- 病院や診療所の管理
- 医療機器の導入
- 医療システムの構築
- 医療従事者の育成
- 医療におけるコミュニケーション改善
- 医療経営の改善
医療業界においても、ジェネラリストは、複数の業務を遂行するため、多様なスキルを必要とします。たとえば、病院や診療所の管理に関しては、プロジェクトマネジメントスキルが必要となります。また、医療機器の導入に関しては、技術分野に精通していることが求められます。さらに、医療従事者の育成に関しては、コミュニケーション能力や指導スキルが必要となります。
IT業界でのジェネラリスト
IT業界においては、ジェネラリストは、多様な業務を遂行するため、多岐にわたるスキルを必要とします。たとえば、以下のような業務が挙げられます。
- プロジェクトマネジメント
- システム開発
- コンピューターセキュリティ
- ネットワーク管理
- データ分析
- ユーザーサポート
IT業界においては、ジェネラリストがプロジェクトマネジメントスキルを持っていることが望ましいとされています。また、システム開発においては、プログラミングスキルやデータベース管理スキルが必要となります。さらに、コンピューターセキュリティに関しては、セキュリティ対策の知識や技術力が求められます。IT業界においては、ジェネラリストが多様なスキルを持っていることが求められます。
ジェネラリストに適した企業
スタートアップ企業やベンチャー企業は、ジェネラリストが手腕を発揮しやすいと言われます。企業規模が大きくなると、「営業」「マーケティング」「人事」「経理」というように機能が分化していき、それぞれの分野のスペシャリストが業務を担うようになります。一方で、スタートアップ企業やベンチャー企業は十分な人員が揃っておらず、少数精鋭で運営している会社が多いので、「目の前にある仕事をできる人がやる」という形になりがちです。このような会社で重宝されるのが、幅広い知識・スキルを持ち、多様な業務に対応できるジェネラリストです。
スタートアップ企業やベンチャー企業については、以下の記事で詳しく解説しています。
>> スタートアップとは?ベンチャーとの違いやメリットを解説 https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c298
ジェネラリスト(ゼネラリスト)の育成方法とは?
優秀なジェネラリストを育成するための効果的な方法についてご説明します。
ジョブローテーションをおこなう
ジェネラリストに期待されるのは、組織を率いて成果をあげる管理職としての役割です。優秀なジェネラリストを育成するのに効果的だとされている人事施策がジョブローテーションです。ジョブローテーションによって、幅広い部署・職種の経験を積むことで、普遍的なヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルを磨くことができます。また、会社の全容を把握できるため、将来の幹部候補としての土台を築くことにもつながります。部署単位で見ると、ジョブローテーションは短期的な業績低下を招く可能性がありますが、管理職や幹部候補になり得るジェネラリストを育成するためには、中長期的な視点で様々な業務経験を積ませることが大切です。
研修の機会を提供する
ジェネラリストに必要な知識・スキルは、現場での実践から習得することも大切ですが、研修によって学ぶことも重要です。研修で体系的に学習することで、知識・スキルの習得スピードが早まるのはよくあることです。上述のとおり、会社がジェネラリストに求めるのは管理職としての活躍です。管理職として活躍できるジェネラリストを育成するための研修としては、マネジメント研修やリーダーシップ研修、チームビルディング研修やコミュニケーション研修などが挙げられるでしょう。
▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら
ジェネラリスト(ゼネラリスト)は時代遅れとされる理由
近年、多くの産業で高度な専門知識が求められるようになり、ジェネラリスト(広範囲にわたる知識を持つが、特定の分野に深い専門性を持たない人々)が時代遅れと見なされることがあります。この背景には、技術の進歩と市場の急速な変化があります。専門家は、特定の分野において最新の知識や技術を駆使して、より効果的な解決策を提供することができます。これに対し、ジェネラリストは広い視野を持ちつつも、特化したスキルが欠けているため、専門家に比べて競争で不利になる場合があります。
しかし、ジェネラリストの価値が全くないわけではありません。複雑で予測不可能なビジネス環境においては、異なる分野の知識を組み合わせ、新しい視点から問題を解決できるジェネラリストの能力が重要になることもあります。
ジェネラリストの今後
今後のジェネラリストに求められるのは、単に広範な知識を持つだけでなく、それをどのように統合し、新しい価値を創出するかという能力です。また、学び続ける姿勢と変化に柔軟に対応する能力も必要です。さらに、データ分析やプログラミングなど、新しい技術領域における基本的なスキルを身につけることで、その汎用性を高め、多様な業務に対応できるようになることが期待されます。
結局のところ、ジェネラリストとスペシャリストは相互補完的な関係にあり、どちらも現代のビジネス環境において重要な役割を果たすことができます。ジェネラリストは、これからも変化に適応し、その広範な知識を活かして新たな分野でのブリッジ役として、また多様なチーム内でのコーディネーターとしての価値を高めていく必要があります。
▼国内最大級のデータベースを持つエンゲージメントサーベイ活用法が3分でわかる!【資料DLはこちら】
人材育成に関することなら「株式会社リンクアンドモチベーション」
記事まとめ
様々な観点からジェネラリストとスペシャリストの違いなどを見てきました。それぞれ異なる役割があるため、企業にとってはどちらも必要です。どちらが優れているということはなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。
目指す方向も、自身の適性に合わせて選ぶ方法と、これからの人生設計に合わせて選ぶ方法など様々です。
終身雇用制度が崩壊しつつある今、どちらを目指すにしても、今後企業や組織に求められる人材になるための努力は怠ってはいけません。
是非、あらゆる側面から今後の方向性を考えてみてはいかがでしょうか。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
ジェネラリストに関するよくある質問
Q:T型人材とは?
スペシャリストは深い専門性を持つという意味で「I型人材」と呼ばれることがあり、ジェネラリストは幅広い知識を持つという意味で「一型人材」と呼ばれることがあります。
T型人材とは、「I型人材」と「一型人材」の特徴を兼ね備えた人材のことを言います。T型人材は幅広い知識・スキルを持つジェネラリストでありながら、特定分野の専門性を有するスペシャリストでもあるため、視野が広く、慣習や常識にとらわれない発想をすることができます。グローバル化や多様化が進む社会において、ニーズが高まっているのがT型人材です。
Q:ジェネラリストは転職に不利?
昨今のビジネス環境においては事業や業務の細分化が進んでおり、特定分野で突出した価値を発揮する企業が業績を伸ばす傾向にあります。それゆえ、人材ニーズとしても特性分野に特化したスペシャリストのニーズが高まっています。逆に、特定分野に関する知見・スキルを持たないジェネラリストは転職において不利になると指摘する声も聞かれます。
しかし、どれだけ優秀なスペシャリストが揃った組織でも、彼ら・彼女らを管理するのはジェネラリストです。業務が細分化し、スペシャリストが増えているからこそ、スペシャリストをまとめるジェネラリストの価値も見直されています。一人ひとりの人材が持てる力を最大限に発揮して、組織力を高めていくためにはジェネラリストの存在が不可欠です。
▼ 心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントはこちら