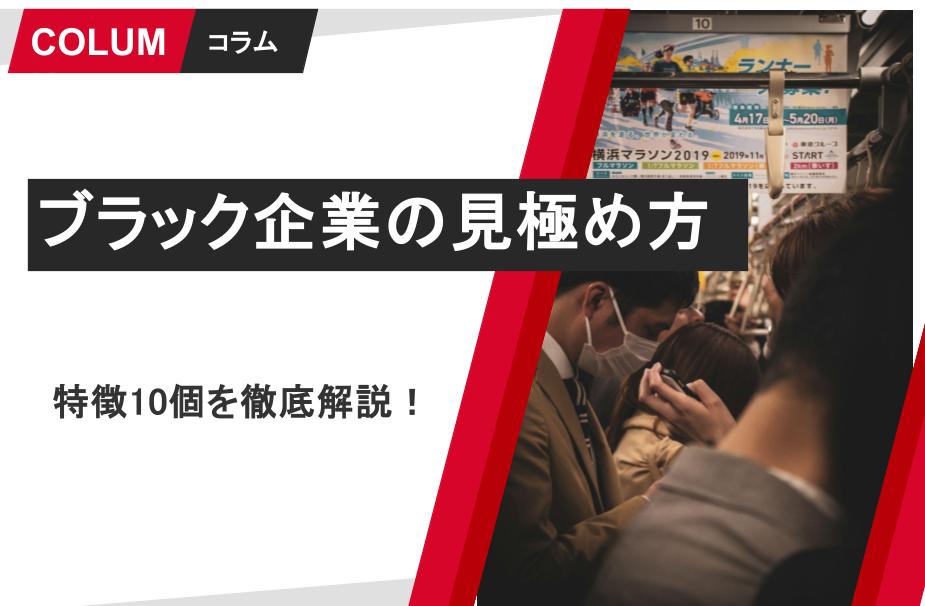
ブラック企業の見極め方 特徴10個を徹底解説!
ブラック企業は、労働者に劣悪な労働環境を強いる企業と定義されるのが一般的です。長時間労働やパワハラ、セクハラなどが社会問題化するとともに、ブラック企業という言葉も広く認知されるようになりました。
今回は、ブラック企業の実態や特徴、ブラック企業としてみなされるデメリットやブラック企業にならないための対策などについて解説していきます。また、求職者の方向けにブラック企業を避けるための対策についても触れています。
目次[非表示]
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
▼ エンゲージメントが高い組織の特徴を日本TOP3が語る!資料はこちら
ブラック企業の定義とは?
主に「労働者に劣悪な労働環境を強いる企業」という用い方をすることが多いワードです。近年では「ブラック企業大賞」という、ブラック企業のランキングなども公表されており、ブラック企業という名称がますます広がっていると言えます。
ブラック企業が社会問題化した背景
ブラック企業が社会問題として広く認識されるようになったのは、2000年代以降の労働環境の変化が大きな要因です。バブル崩壊後の長期不況を背景に、企業はコスト削減を最優先し、非正規雇用の拡大や人員削減を進めました。
その結果、少人数で過剰な業務量をこなす労働環境が常態化し、長時間労働やサービス残業、過重労働によるメンタルヘルス不調が深刻な問題となりました。
2000年代半ばには、過労死やうつ病による自殺といった痛ましい事例が相次ぎ報道され、劣悪な労働環境を放置する企業への批判が高まりました。
さらに、インターネットやSNSの普及により、労働者が企業の実態を告発しやすくなったことも、ブラック企業問題が社会的関心を集める要因となりました。
こうした背景から、政府も労働基準監督署の監視強化や働き方改革関連法の制定を進め、ブラック企業対策を本格化させるに至っています。
▼ホワイト企業に関する記事はこちら
ブラック企業の数と比率
厚生労働省が公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」から、リストをダウンロード可能です。このリストには規定以上の時間で従業員を働かせるなど、労働基準関係法令違反に引っかかった企業、つまり※ブラック企業が掲載されています。
過去に掲載されたことがある企業数は約2,500件、現在も掲載されている企業数は400件を超えています。
※厚生労働省はこういった企業を「ブラック企業」という曖昧な言葉ではなく、「労働基準違反企業」といった表現を使っています。
法律違反の観点から見るブラック企業
ブラック企業は、労働関係法令に違反しているケースが多く見られます。代表的な法律違反事例には、まず労働基準法違反があります。これは、長時間労働や残業代未払いが典型例で、法定労働時間を超える労働にもかかわらず適切な割増賃金を支払わないケースが問題視されています。
次に労働安全衛生法違反では、職場の安全配慮義務を怠り、過重労働やハラスメントによるメンタルヘルス不調を放置するケースが見られます。
また、労働契約法違反としては、雇用契約書の不備や、一方的な労働条件変更といった問題が挙げられます。
業界別のブラック企業の割合
厚生労働省の「労働基準監督年報」(令和4年版)によると、業界別の労働基準関係法令違反率は以下のようになっています。
・建設業:72.5%
・運輸業・郵便業:69.6%
・製造業:52.8%
・小売業:44.7%
・宿泊業・飲食サービス業:68.2%
特に建設、運輸、宿泊・飲食業界は高い違反率を示しており、長時間労働や安全配慮義務違反が問題となっています。違反率の高さは、その業界特有の構造的課題(人手不足、納期重視文化など)にも起因しており、業界ごとに適切な改善策が求められています。
サービス残業の常態化
ブラック企業において、サービス残業(未払い残業)は常態化している場合が多いです。
具体的な例としては、始業前の準備作業(開店準備や事前ミーティング)が労働時間にカウントされないケース、持ち帰り仕事(自宅での資料作成や業務メール対応)が残業扱いされないケース、休憩時間中の業務(電話番や接客対応)が労働時間として認められないケースなどがあります。
メンタルヘルス対策の不備
労働安全衛生法では、2015年からストレスチェック制度が義務化されています。この制度では、常時50人以上の労働者を抱える事業場に対し、年1回、職場におけるストレス状況を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが義務付けられています。
目的は、従業員自身がストレス状況に気づき、必要に応じて医師面談や職場改善につなげることです。しかし、ブラック企業では、この制度を形式的にしか運用せず、実施しても結果のフィードバックを行わなかったり、対策を講じないケースが目立ちます。
労働基準監督署への通報事例
労働基準監督署には、年間数多くの通報・相談が寄せられています。代表的な実例として、残業代未払いでは、社員に月80時間以上の時間外労働を課していたにもかかわらず、残業代が一切支払われていなかったケースがあります。
また、パワハラ通報では、上司からの暴言や無理なノルマ強制により、社員がうつ病を発症した事例がありました。労働安全衛生法違反として是正勧告が出され、企業側に改善命令が下されました。
さらに、違法な労働時間では、1日15時間労働を常態化させ、週1回の休みも取らせていなかった事例があり、使用者に対して罰則適用となりました。
ブラック企業を見分けるポイント
ブラック企業を見抜くには、求人票の細かなチェックが欠かせません。まず労働時間に注目しましょう。「みなし残業制度」「固定残業代込み」などの表記がある場合、実質的な長時間労働が前提になっている可能性があります。
次に給与体系です。基本給が極端に低く、手当やインセンティブで補填する形になっている求人は、安定収入が得られないリスクがあります。
また、離職率も重要な指標です。「社員数○○名(うち新卒入社者の定着率○○%)」など、定着率の記載がない場合は注意が必要です。ネット上の口コミや有価証券報告書の平均勤続年数も参考にできます。
このように、表面上の求人情報だけで判断せず、労働環境を慎重に見極めることが、ブラック企業に入社しないための第一歩となります。
ブラック企業が備えている特徴
それでは、ブラック企業にはどのような特徴があるのでしょうか?「ブラック企業=従業員のモチベーションを引き出せていない企業」だという定義を置くと、モチベーションを阻害するポイントを理解することがその特徴理解に繋がります。
以下に「従業員モチベーションを阻害する6つの要因」を整理しました。まずはこちらを見ていきましょう。
■未来への「不安感」
会社の将来への方向性が見えず、イメージ出来ない事からくる不安です。会社の将来像を明示出来ていない場合だけでなく、それが個々人の将来像と繋がっている感覚を持てない場合にもこの不安感が大きくなることがあります。
■仕事への「閉塞感」
仕事そのものがつまらない、やらされ感を感じる事からくる閉塞感です。仕事に対して行き詰まり、自身の成長が実感できない場合や、会社の行っている事業の将来に見通しがつかず事業規模が縮小する状態において蔓延します。
■風土への「既決感」
組織内で既に決まっていることが多く、「あきらめ」の心理が蔓延している事からくる既決感です。組織の風通しが悪く、「どうせ何を言っても無駄だろう」という諦めの感覚や、「既に決まっているから・・」と皆が消極的になると、負のスパイラルに入り組織の活力がどんどん減っていきます。
■待遇への「不満感」
評価・処遇・勤務実態などに納得できず、不満が溜まっている事から生じる不満感です。自分自身のパフォーマンスと、その報酬が釣り合っていないと感じる社員や、評価制度、休日休暇、終業時間、オフィス環境に対する不満足からも生じることがあります。
■上司への「失望感」
上司だからこそ、と期待していたにもかかわらず、その期待を裏切られた事からくる失望感です。期待していた上司が思いのほか頼れなかったという落胆や、上司を「非の打ちどころのない人間」と期待しがちな部下が期待を裏切られたと感じる際に生じるケースが多いです。
■職場への「無力感」
職場に対して働きかけをしても、どうせ無駄であると思っている事からくる無力感です。職場への一員として、自分自身の貢献実感を得られないことに起因したり、職場に対いて提案などの働きかけをしても、十分な反応が得られない時にも蔓延していきます。
(参考)モチベーションとは何か?維持する方法やメリット、ビジネスでのマネジメント成功事例について解説
ブラック企業で実際に生じている事象
前述したモチベーションの阻害要因は、具体的にどのような事象から生じているのでしょうか。ブラック企業でよく生じている具体事例を見ていきましょう。
■制度・待遇面の特徴
「長時間労働」
長時間の残業によって健康障害が起こりやすい残業が起きている場合があります。過労死ラインの月80時間を超える残業を強いられている場合もあります。
「休日の少なさ」
平均的な年間休日日数である120日前後を大きく下回る休日の場合があります。業務量の多さが休日日数の減少に繋がっていることがあります。
「ルールの未整備」
労働基準法や就業規則など、従業員の権利を守るルールが形骸化している場合があります。
■風土・人材面の特徴
「離職率の高さ」
従業員の扱いが悪いため離職率が高いです。入社後3年以内に離職した労働者の割合が30%を越える企業もあります。
「自殺者や過労死者の存在」
過度な労働時間など過酷な環境にさらされた従業員が自殺したり過労死したりする場合があります。
「人間関係の悪さ」
過度な業務負担により多大なストレスがかかり、従業員の心身に余裕が無いことから、人間関係が良好ではなく、風通しが悪い場合があります。
「採用基準が低い」
従業員が定着しないため、頭数を揃えるための人材採用が横行している場合があります。採用段階で十分なスクリーニングが出来ておらず、結果として定着しない事も多いです。
■上司に関する特徴
「過度な権力行使」
上司の権力を悪用して理不尽な要求をする、異性に性的な嫌がらせをする等の行為が状態化している場合があります。
「過度な目標設定」
1人当たりのキャパシティを大きく上回る目標や要求が横行しています。また、未達の場合の𠮟責なども理不尽な場合があります。
「上司に絶対服従」
上下関係に厳しく、小間使いのように従業員を扱う場合があります。理不尽な要求を断ると、業務に支障が出るような関わりが行われる場合があります。
ブラック企業としてみなされるデメリット
ブラック企業と見なされることで企業が受ける不利益には様々なものがあります。
以下それぞれ見ていきましょう。
■事業面
既存顧客との関係が悪化してしまう事があります。またブランドが棄損されていることから新規顧客との取引難易度も増大します。ブランドは最も蓄積難易度が高い資産であるため、一度失った取引は相当な期間を経ないと戻ることはありません。
■風土面
従業員のモチベーションが下がるので、業務の生産性は下がる傾向にあります。「悪貨は良貨を駆逐する」と言われますが、モチベーションが高い従業員も次第に元気を失ってしまう傾向があります。
■人材面
応募者が集まらない、もしくは人材のレベルが著しく低下します。過去に採用できていた人数や質が担保できなくなり、結果として組織力は大幅に低下してしまいます。家族や友人からの働きかけにより、離職が加速度的に増えることもあります。
会社側で必要なブラック企業対策
一度「ブラック企業」という評判が立つことで大きな不利益が生じるため、その状態になることを未然に防ぐことが大切です。以下に企業側がとる対策を紹介いたします。
■従業員との対話の機会を設置する
従業員が抱える悩みや意見を汲み取る仕組みがない事が、会社と従業員の溝を更に広げる事に繋がります。従業員満足度調査やストレスチェックなどの仕組みの設置や、1on1面談の定期的な設置など、従業員側が発信する機会を用意することが有効です。
■情報の見える化
「透明性」が高くないことが、従業員の不満を招き、心身の不調を助長させます。「企業方針」「業績状況」など会社全体に関わる情報に始まり、残業時間など職場状況に関する情報を見える化することで問題を未然に防ぐことや改善の促進に繋がります。
▼【組織の見える化】に関する記事はこちら
■第三者からの確認機会を用意する
往々として、自社内に情報が閉じていることが労務管理は法令順守を逸脱する行動に繋がることが多いです。その為、定期的に外部講師や社労士、組織人事の知見がある企業の支援を受けることであるべき状態から逸脱することが出来ます。
【参考資料のご紹介】
「従業員エンゲージメント向上のための効果的なアクションプラン」はこちらからダウンロードいただけます。
就職・転職時にできるブラック企業対策
就職・転職は人生のターニングポイントであり、どんな企業を選ぶかでその後の人生は大きく変わってきます。ブラック企業を避け、自分が納得・満足して働ける企業を選ぶにはどうしたら良いのでしょうか。
自分の理想の仕事の仕方を考える
仕事にどんなものを求めるのか
ブラック企業を避けるための前提として、自分自身の仕事観をあらためて明確にしておくことは重要です。「自分にとって仕事とは何なのか?」「仕事に何を求めるのか?」「仕事を通してどんな自分になりたいのか?」といったことを、あらためて考え直してみましょう。
仕事観を明確にしないまま、表面的な条件だけで企業を選んでしまうと、仮にその企業が一般的にブラック企業の定義に当てはまる企業ではなくても、働くのが苦しい「自分にとってのブラック企業」になってしまう可能性があります。
どんな働き方が良いか
ブラック企業を避けるためには、自分が理想とする働き方を明確にしておくことも大切です。「この会社に入りたい」という気持ちが強い人ほど、「残業や休日出勤も厭わず働きます!」「タフさには自信があります!」など、面接のときに無理をした回答をしがちです。
こうして入社した人は、労働環境がブラックだったとしても、それに耐えようとするあまり精神的に参ってしまうケースがあります。労働時間や労働日数、福利厚生やテレワークの可否など、働き方に関する希望を具体的にしたうえで、それを実現できる企業を選ぶようにしましょう。
求人情報をしっかり確認する
勤務時間
ブラック企業の分かりやすい特徴の一つが、勤務時間(労働時間)が長いことです。労働基準法では、労働時間の長さを1日8時間以内、週40時間以内に制限するとともに(法定労働時間)、毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけないと定めています(法定休日)。
36協定があれば、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりすることができますが、それでも時間外労働の上限は原則として「1ヶ月45時間」「1年360時間」の範囲内である必要があります。
36協定も含め、法定労働時間・法定休日を遵守しているかどうかが疑わしい企業は避けたほうが良いでしょう。
給与体系
給与体系も、その企業がブラック企業かどうかを「診断」するポイントになります。まず、業績給を含んだ給与体系にしている企業はブラック企業の可能性があります。ノルマの設定によっては、給与アップが期待できない可能性もあるからです。
また、「みなし残業代(固定残業代)」の割合が多い会社もブラック企業の可能性があります。
みなし残業代は、あらかじめ「毎月、何時間残業する」とみなしたぶんの残業代を含めて月々の給与を支払う方法で、それ自体は違法ではありませんが、長時間労働の「隠れ蓑」として使われるケースが多いからです。
福利厚生
福利厚生が充実している企業は「従業員を大切にしている企業」というイメージで魅力的に映るものですが、過重労働などブラックな実態を隠すために福利厚生を「隠れ蓑」にしている企業もあります。
一見すると福利厚生が手厚く見えても、よくよく見ると、従業員にそれほどメリットのない福利厚生が多かったり、「各種手当て充実」など、あいまいなアピールにとどまっている企業もあります。このような企業はブラック企業である可能性が否定できません。
面接で求人情報の内容や疑問点について質問する
求人情報の抽象的表現やデータについて注意する
求人情報では、「自分らしい働き方」「自己成長ができる」「やりがいがある職場」など抽象的な表現がよく使われます。このようなフレーズはポジティブな印象がありますが、まったく具体性がなく、企業側からしたら「何とでも言える」部分でもあります。
このようなフレーズを見たら、面接の際に「具体的に、どのように自分らしく働いている方がいるのですか?」「自己成長を促すために、具体的にどのような制度があるのですか?」などと質問してみましょう。そこで、あいまいな回答をする企業はブラック企業の可能性があります。
契約内容の確認
労働契約を結ぶ際に「必ず雇用契約書を交付しないといけない」という決まりはありませんが、通常であれば作成します。にもかかわらず作成しないのは、証拠を残したくないという意図がある。ブラックです。
また、事業者は労働条件を明示する義務があり、そのために「労働条件通知書」を発行するのが一般的です。そのため、通知書がない場合もブラックが疑われます。このような書類を確認しないまま入社すると、賃金や労働時間、解雇や未払い残業代などに関するトラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?仮に自社がブラック企業と見なされた場合、自社及び自社に勤めている従業員が受ける不利益を考えると、確固とした対策を取ることが不可欠だと言えます。
さらに昨今は、SNS等で簡単に評判が広まり、新たな優秀な人材の獲得という面でも悪影響を及ぼします。
事業会社として、商品市場だけを見て活動するのではなく、人材獲得という観点から労働市場へのブランディングも含めて、自社の状態を適切に振り返り、改善活動を行っていきましょう。
また、別記事で「ブラック企業」の対極である「ホワイト企業」についての記事をまとめておりますので、ぜひそちらの内容もご覧ください。(以下、記事のリンクになります)
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら








