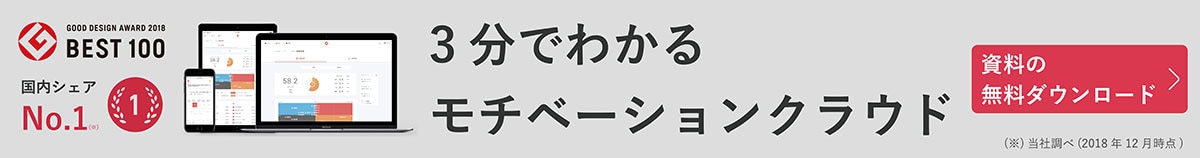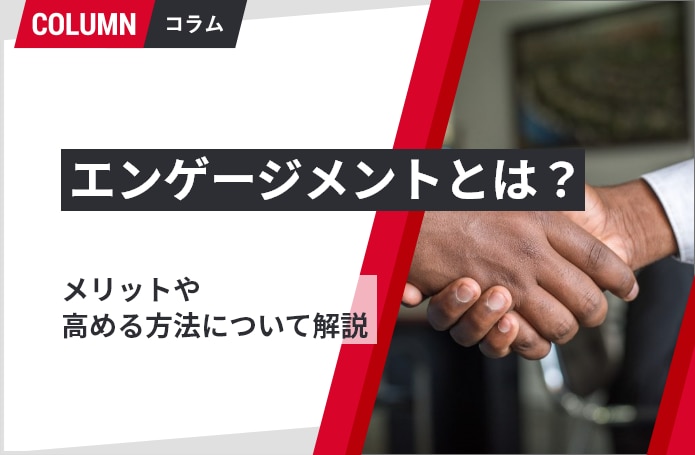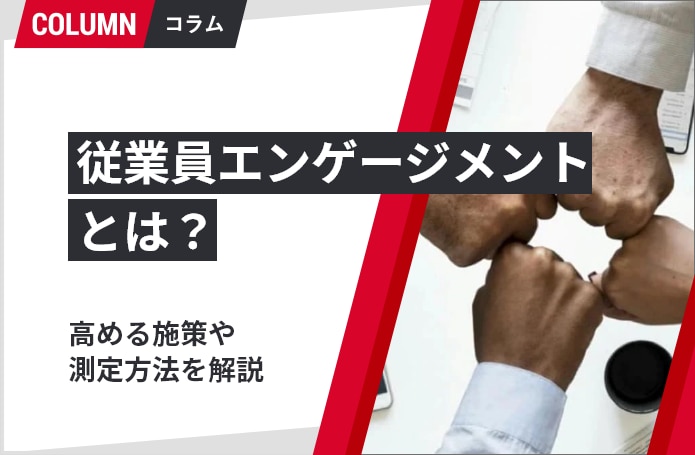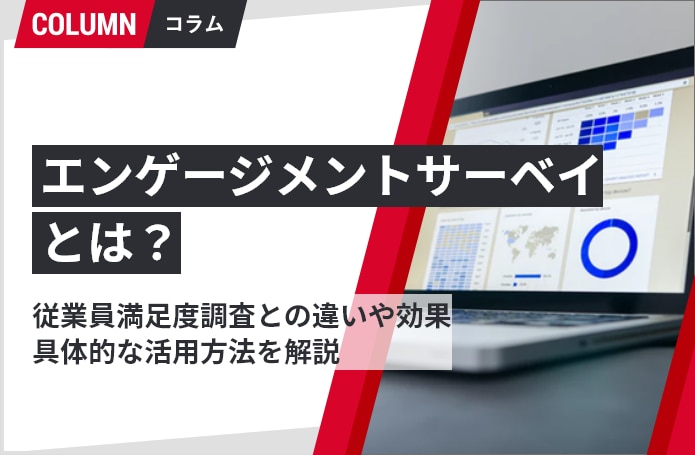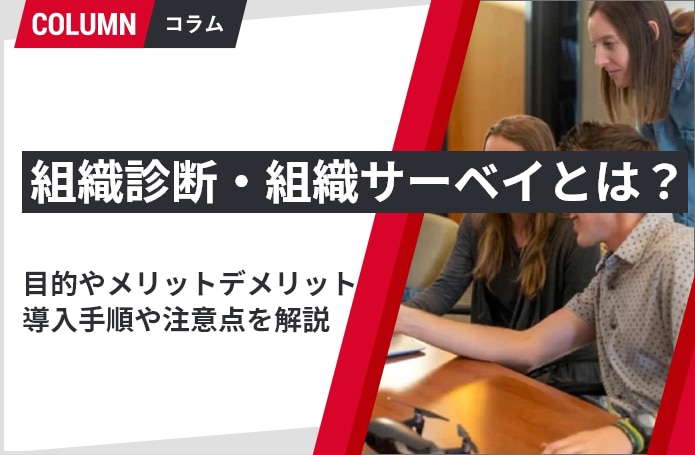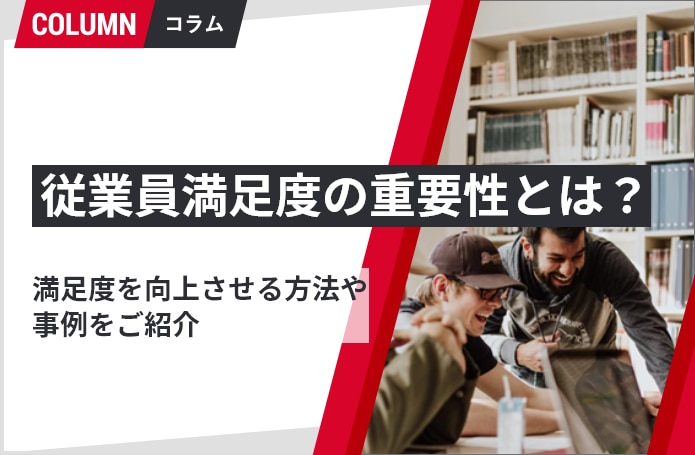人的資本経営は、一人一人が「この会社で働けて
良かった」と思える組織づくりから
大王製紙株式会社
部長 山本 高史 氏
人事課(制度企画グループ)課長 三宅 健彦 氏
人事課 中村 茜 氏

| 事業内容 |
・紙・板紙・パルプ及びその副産物の製造加工並びに販売 ・日用品雑貨の製造加工並びに販売 など |
|---|---|
| 業種 | 素材 |
|
企業規模 |
2001名~ |
| 導入規模 | 2001名〜 |
期待
-
人的資本経営の実践に向けて、内製の従業員満足度調査では把握できなかった「エンゲージメント」を測りたい
-
トップダウン体質を変革し、下からの提案がどんどん生まれる組織にしたい
効果
-
期待度と満足度の両方を見ることで、従業員が求めていることや優先度の高い課題を効率良く把握できた
-
サーベイの結果を見た管理職に気付きが生まれ、「変えていこう」という気運が高まった
紙・板紙の製造販売と、エリエール製品に代表される家庭紙の製造販売
「事業内容」
山本氏:大王製紙は、紙・板紙の製造販売と、エリエールに代表される家庭紙製品の製造販売、大きくはこの2本立てで事業を展開しています。紙・板紙事業のうち印刷用紙などの洋紙についてはペーパーレス化の影響などもあって需要は縮小傾向にありますが、板紙・段ボールは通販等の活発化により、需要が堅調に推移しています。また、家庭紙事業についてはティシューペーパー、トイレットティシューをはじめ、ベビー用、大人用の紙おむつなど様々な製品を生産・販売しており、海外展開の加速も含めた成長戦略を進めています。
人的資本経営の実践に向けて、モチベーションクラウドを導入
「モチベーションクラウド導入の背景」
山本氏:弊社では、5年前から従業員満足度調査をおこなっていました。この調査は、弊社が独自で設問を作って運用していましたが、組織の状態を把握するのに最適な設問になっているのだろうかと考えることもありました。
「エンゲージメント」という言葉の重要性が高まってきていますが、エンゲージメントとの関連性においても現状の調査には不十分な点があると感じていました。また、従業員満足度調査をもとにした組織改善の動きも生まれていませんでした。
近年、SDGsの観点からいかに人的資本を有効活用して企業価値を高めていくかということが経営の重要な課題になっていますし、従業員のエンゲージメント向上は1つの大きな柱として取り組むべきだと考え、従業員満足度調査からエンゲージメントサーベイに切り替えを行いました。

経営トップからも、オープンコミュニケーションにより社員が気兼ねなく率直な意見を述べ、提案がどんどん生まれる体質に変える方針が示されています。弊社は元々オーナー企業であり、トップダウンの性格が強い会社でした。「VUCA時代」とも言われる不透明な時代を生き抜いていくために、従来のスタイルの良いところは残しつつ、社員一人ひとりが考え提案していくような新たなスタイルが必要であると考えています。
新規事業や海外展開を加速していくためにも、弊社には今後、より多様な人材が活躍できる土壌が必要になってきます。そして、そこで働く社員の成長とイノベーションを達成しなければなりません。このような思いもあり、組織改善の足がかりとしてエンゲージメントサーベイの導入を決めました。
サーベイの導入に際しては、いくつかのサービスをピックアップしましたが、リンクアンドモチベーションのモチベーションクラウドは国内最大手ということでデータベースが大きく、エンゲージメントスコア (従業員エンゲージメントの指標) が算出されるため「他の会社と比べてどうなのか?」が分かります。以前の従業員満足度調査では、経年の比較はできても同業界での比較や他業界との比較はできません。エンゲージメントも競争原理を働かせながら高めていくべきだと考えていましたので、サンプル数が多く、他社との比較ができるのは大きな決め手になりましたね。「サーベイを取って終わり」では組織改善につながらない
「モチベーションクラウドの価値」
山本氏:期待と満足の2軸で見ていくという調査の手法に価値を感じています。期待度と満足度を測ることで、従業員が求めていることや優先度の高い課題を効率良く把握できますし、より的確な手を打つことができます。たとえば、満足度の低い項目があったとしても、期待度も低いのであれば、そこに労力をかけてもエンゲージメントは上がっていきませんよね。前提として、従業員が何を求めているのかを知ることはすごく大事だなと思います。
三宅氏:インターフェースが優れており、調査結果が分かりやすいのも良い点だと感じています。従来の従業員満足度調査はエクセルで管理しており、様々な分析もしていましたが、改善するための行動にまではつなげられていませんでした。ですが、モチベーションクラウドは、各所属長が調査結果を見たときに「どこが悪いのか?」がはっきり分かりますし、「こういう行動を起こさないといけないんだな」ということも見えてきます。数字として明確に示されて、強み・弱みがすぐ分かるというのは大きいですね。

中村氏:モチベーションクラウドは、事務局側として非常に使いやすいシステムだと思っています。操作面での不安がないと言いますか、どこを押したら良いのかが直感的に分かるのは、実際に運用していく際もすごく便利でした。
サポート体制が充実しているのも安心感がありますよね。今までは、サーベイを取っても「結果をフィードバックして終わり」でしたが、モチベーションクラウドは、コンサルタントの方が今後の改善にどうつなげていくのかというところまでサポートしてくれます。そこも非常に心強いなと感じています。
管理職が結果をきちんと受け止め、前向きなリアクションをしてくれた
「モチベーションクラウドを導入した感想」
山本氏:会社全体で見たときに、所属上司との関係性が良いスコアだったので、そこは良かったなと安心しました。部署レベルで見ていくと意外な点もありましたが、概ね「やはりそうか」と納得できるような結果でしたね。ただ、以前の従業員満足度調査のときは、何となく「満足度が低いんだな」くらいに捉えていましたが、モチベーションクラウドでは「こういう理由で低いんだ」という気付きが多々ありました。
サーベイでは、施設環境面に対する満足度が低いことが分かりました。実際に、テレワークなどでパソコンの動作が不安定だという声があがっていたのですが、サーベイの結果を受けてすぐに、IT部門がIT環境に関する社内アンケートをおこなっていました。サーベイではっきり数字が出ることで、改善の動きが促されるんだなというのを実感した例です。
制度・待遇に関しても弱みとして明らかになりました。多様化が進むなか、弊社の人事制度自体が時代にマッチしないものになってきていると感じさせられました。実際に、若手社員から「どのようにキャリアを歩んでいけば良いかが分かる指標が欲しい」といった声を聞くこともありますので、そういった声に応えられるよう、人事制度を見直していかなければいけないと考えています。
中村氏:今までの従業員満足度調査は、本部長までにしかフィードバックをしていませんでしたが、モチベーションクラウドを導入してから、サーベイの結果を本部長以下の部長や課長にもフィードバックするようにしました。そうすると、とてもたくさんのリアクションが来たんです。「気付かされることが多かったです」や「改善できるように頑張ります」などの、ほとんどがポジティブなリアクションでしたね。

山本氏:モチベーションクラウドのわかりやすい書式で自部署のサーベイ結果が明確に出てくると、管理職としては当然、思うところがあるのでしょう。驚きだったり落胆だったり、人によって様々な気持ちがあったと思いますが、「変えていかなきゃいけない」といった声が出てきたのは、結果をきちんと受け止め、管理職としての自分を見つめ直してくれた人が多かったからだと思います。
従業員発信のプロジェクトがどんどん生まれる組織へ
「改善のための取り組みと今後の展望」
山本氏:2021年4月より、社内呼称を「さん付け」に変えました。心理的安全性を確保し、率直な意見が言い合える風土にするための取り組みですが、まずはこういうところから変えていこうというはじめの一歩です。取り組みとしてはまだまだこれからで、仕組みも含めて変えていかなければいけないところはたくさんあります。
先ほどボトムアップと申し上げましたが、従業員から提案が生まれて、そこからイノベーションが起きるような状態にはまだまだなっていません。弊社は、発展途上国における「生理の貧困」問題の解決を支援する「ハートサポートプロジェクト」を進めていますが、これは従業員発信で立ち上げられたプロジェクトです。このような提案がどんどん下から生まれてくるような組織を目指していかなければいけません。
また、「隣の部署が何をしているのかよく知らない」というのは従来からの課題の一つですが、サーベイの結果も部署によってスコアに大きな差があり、あらためて「組織間の壁」を感じました。そこで今、検討しているのが社内SNSの導入です。社内SNSを使って横のコミュニケーションを活発にすることで様々なつながりを作り、組織間の壁を低くしていけたらなと思っています。
自分らしく働けて仕事が楽しい。理想は「月曜日が楽しみな会社」
「今後モチベーションクラウドで実現したいこと」
山本氏:従業員のエンゲージメントを高めていくことがモチベーションクラウドを導入した目的ですが、行き着く先は、従業員が生きがい・働きがいを持って働ける会社です。心理的安全性のある環境を作り、そのなかでお互いに協力し合って新しいものを創造していくようなチームがたくさん生まれてくれば良いなと思っています。個人個人も成長できて、みんなが「この会社で働けて良かった」と思えるような会社にしていきたいですね。
三宅氏:自分らしく働けたり、自分のアイデアが採用されたりすれば、仕事って楽しくなってくるじゃないですか。そうなれば、たとえばプライベートの時間でも、仕事につながりそうなアイデアがあればメモするような自発性が生まれてくると思うんです。こういった状態というのは一つの理想ではありますね。私がよく参加するセミナーに「月曜日が楽しみな会社」という言葉が出てくるのですが、そんな会社になれたら良いなと思います。
中村氏:私は以前、採用担当をしていました。そのときの経験もあり、若手社員にもっと好きになってもらえるような会社でありたいなと思っています。「好きで入った会社なのに、気付いたら嫌いになっていた」では残念です。エンゲージメントを高め、もっと従業員に愛される会社を作っていきたいと思います。
モチベーションクラウドなら組織を可視化・診断し、課題を解決することができます。