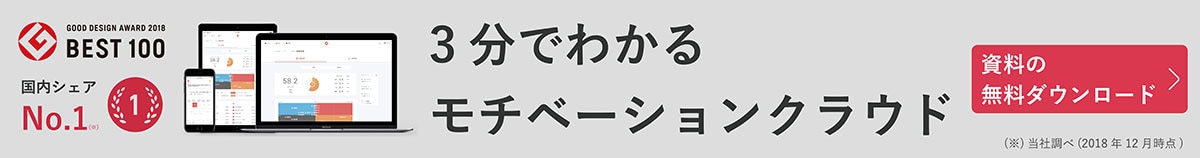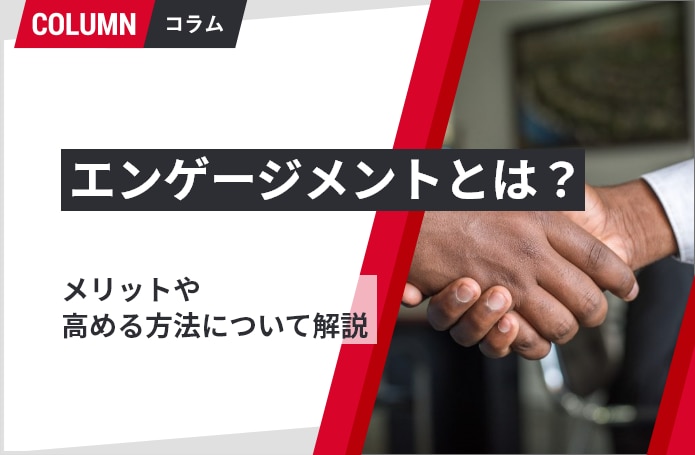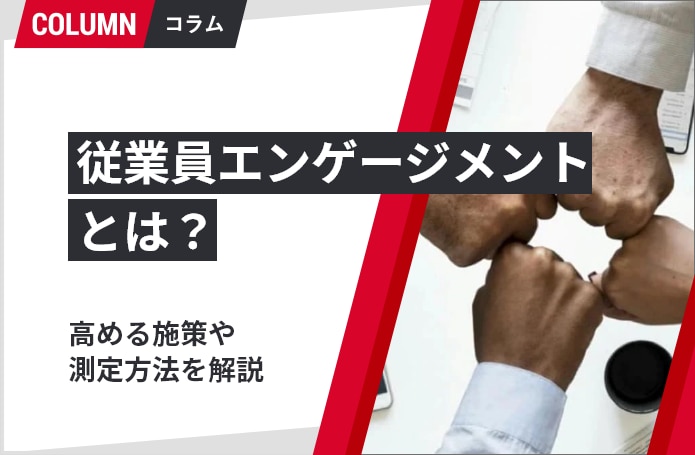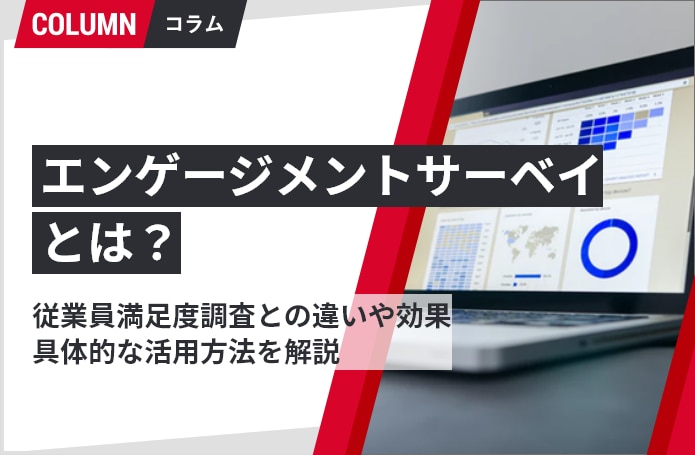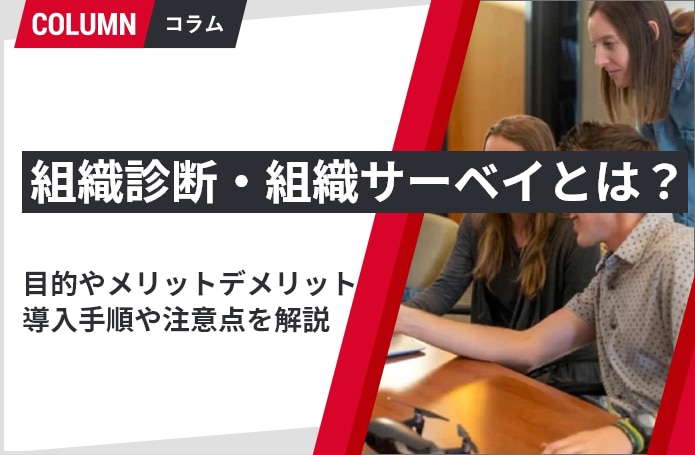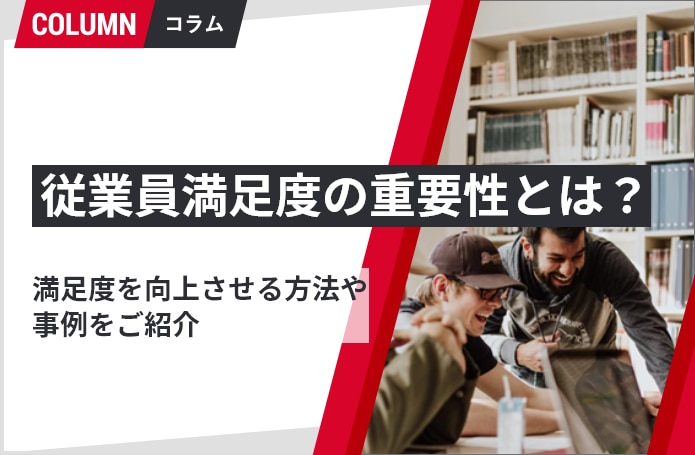声なき声を可視化し、
ベトナム市場で挑戦し続ける強い組織へ
LOTTE VIETNAM CO., LTD.

| 事業内容 |
菓子(ガム、ビスケット、アイスクリーム)の製造・販売 |
|---|---|
| 業種 | 食品 |
|
企業規模 |
1001名~2000名 |
| 導入規模 | 101名~300名 |
期待
-
現地スタッフが不満を表明しにくい文化の中では、組織の実態が見えないことがリスクになるため、エンゲージメントを可視化する仕組みが必要だった。
-
給与や待遇だけでなく、承認や感謝といった非金銭的価値からも意欲を引き出す風土を組織に根づかせたいと考えていた。
効果
-
約200名のマネジャーのマネジメントの実態をデータで俯瞰できるようになり、組織の強みや課題を客観的に把握できるようになった。
-
導入時の説明会を通じてエンゲージメントへの関心が高まり、働きがいの向上について、現場で前向きな意見交換が行われるようになった。
事例を生み出したプロダクト資料はこちら
挑戦に伴って起こる組織の問題を俯瞰して、組織をより良く変えていきたい
「会社および事業の概要」
小川氏:ロッテは、日本ではお菓子やアイスクリームなどで広く知られる大手菓子メーカーです。ロッテベトナムは、その株式会社ロッテの海外現地法人であり、ベトナム市場における事業展開の拠点となっています。
当社は、チューインガムの製造・販売から事業をスタートし、長年にわたりベトナム市場に根ざした取り組みを続けてきました。ベトナムでの展開は四半世紀を超え、日系企業として長年にわたり着実に存在感を築いてきた数少ない企業の一つです。
近年では事業領域をさらに広げ、2023年には新たに「ショコラ」というブランドを立ち上げて、ビスケットの製造工場を稼働させました。現在は、ガムとビスケットの二本柱で事業を推進しています。
ロッテベトナムの大きな特徴は、ベトナム全土に展開する5つの支店と2つの工場を持つことです。これらの拠点を通じて、製造から販売までを一貫して行える体制を整えています。現地市場に対して迅速かつ柔軟に対応できる点が強みです。
従業員数は約1,300名にのぼり、ベトナム国内でもガムシェアNo.1のキシリトールブランドを中心に、菓子メーカーではトップ10に入る規模の企業として、存在感を発揮しています。ベトナムは人口約1億人を抱え、日本よりも平均年齢も若く、非常に魅力的な市場です。
こうした環境の中で、ロッテベトナムは現地ニーズに寄り添いながら、さらなる事業拡大を目指しています。

組織の“声なき声”を可視化し、変革の起点にする
「エンゲージメント向上に取り組む背景」
小川氏:ロッテベトナムに赴任して最初の3か月間は、営業やマーケティングなどを中心に、ビスケット事業の強化に注力していました。営業に関してはBIツールなども導入されており、売り上げだけではなく、行動データの可視化や管理の基盤が整っていたため、数値に基づいた改善に取り組みやすい環境でした。
一方で、組織については現場の課題や従業員の不満が見えにくいという構造的な問題にも直面しました。もし問題が発生しても、現地スタッフが上司や会社に対して声を上げにくく、経営側からも実態が把握しづらいのです。そうした状況のまま、事業成長だけを追いかけることには危うさを感じました。
私は日本のロッテグループに在籍していた頃、モチベーションクラウドを活用していました。モチベーションクラウドでは、組織の状態を「エンゲージメントスコア」という指標で把握することができます。スコアは偏差値として算出されるため、他部署や他社との比較も可能です。それにより、組織の状況を相対的かつ客観的に捉えることができると実感しました。その実感から、ベトナムにおいても「まずは従業員の声を可視化すること」が必要だと考えました。営業やマーケティングにおける数値基盤が整っているからこそ、次は“人と組織”の見える化に取り組むべきだと確信しています。
モチベーションは、待遇だけで決まるものではない
「組織課題とサービス導入の背景」
小川氏:ベトナムでは、従業員のモチベーションが「給与」や「待遇」といった条件面に偏りがちです。実際、どの部署でも「自分たちのサラリーは低い」という不満の声が挙がっており、報酬への関心の高さを日々実感しています。特に、現場を回っている営業にとっては、業績連動型のインセンティブが生活に直結する重要な仕組みです。
しかし私は常に、自問し続けています。「本当に、お金だけで人は動くのだろうか」と。誰しも、自分の仕事が認められたときに得られる満足感があるはずです。私は、金銭的な報酬だけでなく、「承認」や「感謝」といった非金銭的な価値こそが、人の働く意欲を引き出すと信じています。
だからこそ私は人事部門に対して、金銭報酬以外の方法でも従業員満足度を高める施策を考えてくださいとリクエストしてきました。たとえば、「ありがとう」というたった一言でも、人は報われたと感じることがあります。また、全員の前で表彰されることによって、自信や誇りが生まれることもあります。こうした小さな積み重ねが、組織全体のエンゲージメントを高める原動力になると考えています。
実際、職場環境の改善を目的としたオフィスの改装を決断したのも、こうした非金銭的な価値への投資の一環です。従業員が何を求め、どのように感じているのかを丁寧に汲み取り、応えていくこと。それこそが、モチベーションクラウド導入の根底にある想いです。
経営視点を持ったマネジャーの育成が次の成長の鍵
「具体的な取り組み」
小川氏:ベトナム企業における組織運営の中で、今後の鍵を握るのは“マネジャー層”の育成です。現場の現地スタッフには、ベトナム市場ならではの柔軟さやスピード感といった、学ぶべき強みが数多くあります。一方で、組織全体を俯瞰し、経営的な視点から判断を下せるマネジャーを育てていくことが、これからの大きな課題だと感じています。
その背景には、ベトナムを含む多くの海外市場で主流となっている「専門職採用」の文化があります。たとえば、営業として入社したスタッフは長年にわたり営業職を担当し続け、経理やマーケティングも同様です。ジョブローテーションが一般的な日本とは異なり、他部門の視点を得る機会が限られているのです。
当社にも、営業や生産部門で数百人規模の部下を束ねる、“ひとつの会社の経営者”のようなマネジャーがいます。しかし、特定のスキルだけでは組織を成長させることはできません。生産・人事・財務といった複数の部門を横断的に見渡す視点を持ち、組織全体をリードできる存在が求められています。
なかでも大きな課題となっているのが、「育成」という視点です。マネジメント業務をこなすことはできても、人材を育てるという意識を持っているマネジャーは、まだ多くありません。だからこそ今、私たちは経営の視点と人材育成の視点の両方を兼ね備えた、“次世代型マネジャー”の育成に注力しようとしています。
もっとも、すべての社員を一度に育成対象とするのは現実的ではありません。そこで今回は、組織の中核を担う約200名のマネジャーと次期マネジャー層にフォーカスし、段階的に育成施策を展開する計画を立てています。
「マネジャーが変われば、組織が変わる。」そう信じて、戦略的な取り組みをスタートさせました。
ベトナムの現地事情を踏まえた、丁寧で実践的なサポート体制
「リンクアンドモチベーションに感じた価値」
小川氏:モチベーションクラウドの導入にあたっては、サービス自体の品質はもちろん、導入支援の丁寧さや現地事情への深い理解など、総合的に非常に満足度の高いサポートを受けることができました。特に、貴社のコンサルタントと当社人事部門との緊密な連携は、大きな価値をもたらしたと感じています。
正直なところ、導入当初から社内全体が前向きだったわけではありません。モチベーションクラウドは決して安価な投資ではなく、「なぜこのサービスが必要なのか」「ベトナムの現場で本当に活用できるのか」といった懐疑的な声も一部で上がっていました。というのも、「エンゲージメント」という概念自体が、ベトナムではまだ一般的な価値観とは言えない状況だからです。
そうした中で、当社の人事部門が率先してサービスの意義を理解し、「これからの会社づくりに必要な投資である」と社内に発信してくれたことは、大きな支えとなりました。そして何より、ベトナムの現地スタッフに対して、ベトナム語で背景や目的を丁寧に説明してくださった貴社のベトナム国籍のコンサルタントの存在が非常に心強かったと感じています。私自身も1〜2分間の導入メッセージを伝えましたが、詳細な説明については、貴社のコンサルタントの皆さんや当社の人事部門が担ってくれました。
導入時のキックオフでは、参加社員からは次々と質問があり、受け身ではなく、自分たちの言葉で「なぜこのサービスを導入するのか」「どんな価値があるのか」を考える姿勢が見られました。このような対話を通じて、サービスの目的や意義に対する理解が深まりました。30分以上にわたって集中して意見を交わしたキックオフセッションは、現場にとっても非常に有意義な機会となったと感じています。
このように、文化や言語、価値観の違いを丁寧に汲み取りながら、地道にコミュニケーションを重ねていただいたことで、導入に対する理解と共感が着実に醸成されました。初動の社内浸透を成功に導くうえで、貴社の伴走支援はまさに欠かせない存在だったと、心から感謝しています。
成長の裏には必ず新しい課題が生まれる
「サーベイを実施してみて」
小川氏:今回、モチベーションクラウドを活用し、組織の状態を可視化しました。当社には約200名のリーダーが在籍していますが、それぞれが現場でどのようにマネジメントをしているのか、うまく機能しているのかどうかを把握するのは難しいのが現実です。だからこそ、データを活用してマネジメントの実態を俯瞰し、組織のどこに強みや課題があるのかを見える化する仕組みの重要性を強く実感しました。
現在ロッテベトナムは、ガム事業に加え、ビスケット事業など複数の領域に挑戦しており、まさに新たな成長フェーズにあります。いまは現状維持や安定を目指す段階ではなく、新たな価値を創り出すために挑戦を続けるフェーズにあると言えるでしょう。
そのため、エンゲージメント向上の目的は、単に働きやすい環境を整えることではありません。困難な挑戦のなかにあっても、生き生きと前向きに取り組める組織状態を実現することです。
こうした変革期には、軋轢や摩擦、新たなコンフリクトが自然と生じます。それは組織が停滞しているからではなく、成長しようとしている証でもあります。ベトナム市場は2桁成長が当たり前というダイナミックな環境であり、それに伴って組織課題も複雑化していきます。
このような状況下で重要なのは、現場のマネジャー一人ひとりが組織や自分のマネジメントの状態をデータから正しく捉え、それを改善に活かしていく力です。データは単なる情報ではなく、変革を後押しするための起点であると考えています。
組織変革は、任せるだけでは前に進まない
「今後の展望」
小川氏:現地法人のトップとして日々痛感しているのは、「変革は人任せにはできない」ということです。もちろん、現地には優秀なスタッフが多く在籍しています。しかし、組織を根本から変えるような本質的な変化を起こすためには、自分自身が先頭に立たなければ前には進みません。どれだけ実現したい想いがあっても、それを他人に託すだけでは、思い描いた未来は実現しないのです。
経営とは、常に選択の連続です。たとえば、生産と営業の利害が対立するような局面では、どちらにも理があり、どちらにも課題があります。その中で、どちらの方向に舵を切るか。その一つひとつの判断が、やがて組織の姿勢をつくり、未来を形づくっていきます。もし挑戦を避ける選択を続ければ、組織はいつしか“挑戦しない会社”になってしまう。私は、自分が率いる組織を、決してそうした状態にはしたくない。そう覚悟を決めて、日々意思決定に向き合っています。
現地法人の経営者には、実質的に後ろ盾がありません。本社からの支援には限りがあり、最終的には自ら現場に立ち、判断し、動かすしかないのです。ときに厳しい決断を迫られたり、大きなプレッシャーに直面したりすることもありますが、それを乗り越えてこそ、本当にしなやかで強い組織が育っていくと信じています。
ASEANの組織変革における共創パートナーとして
「モチベーションクラウドを通じて実現したいこと」
小川氏:今回の導入は、単なるサービス契約にとどまらず、共に価値を生み出していく“共創パートナー”としての関係性を築けたことに、大きな意味があると感じています。私自身、この領域に強い関心を持っており、ロッテベトナムを“モチベーションエンジニアリング”を実践する先進事例に育てていきたいと考えています。
もちろん、すべてが順調に進むわけではありません。課題もあれば、試行錯誤もある。それでも、導入を通じて得られる知見や経験は、将来的に他のベトナム企業やASEAN地域の企業にとっても、必ず参考になるはずです。私たちの取り組みが、同じように変革を志す企業のヒントとなることを心から願っています。