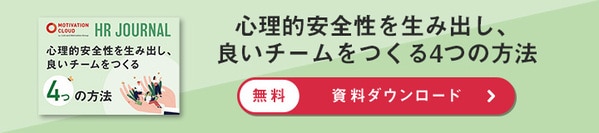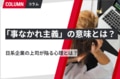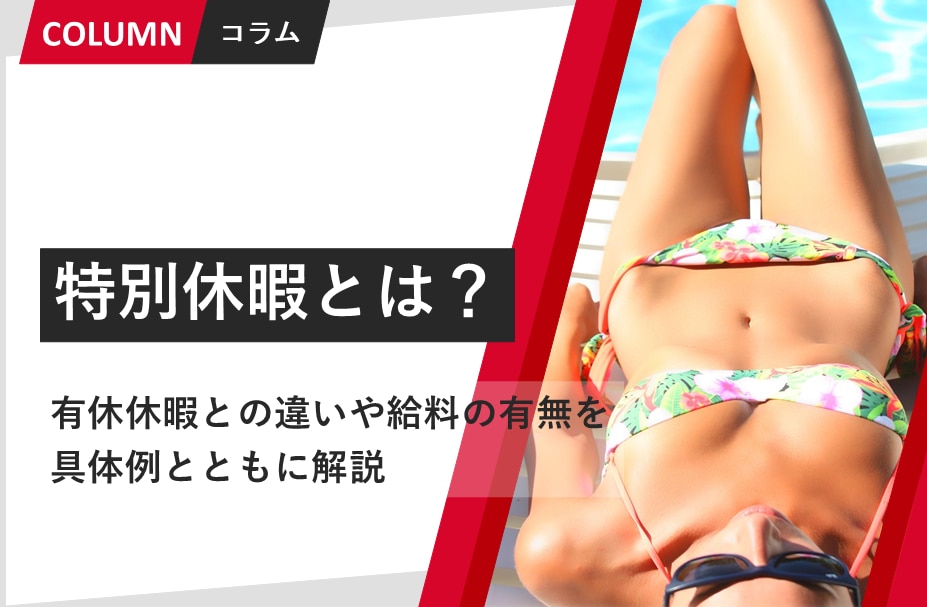
特別休暇とは?有休休暇との違いや給料の有無を具体例とともに解説
企業が自由に設定することができる特別休暇は、その企業の文化や考え方、従業員へのメッセージとも言えるものです。特別休暇は内容によっては企業の魅力の一つとなることもあります。
企業にとっても、働く従業員にとっても有効に特別休暇を活用するために、特別休暇の種類や導入方法を理解しましょう。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
目次[非表示]
▼ 人事が知っておくべき「働き方改革」の内容とは?その実現法についても独自の視点で解説!
特別休暇とは?
特別休暇とは、会社が任意で従業員に付与する休暇のことで、その会社独自の休暇制度と言い換えることもできます。法律で義務付けられている法定休暇と違い、福利厚生として扱われます。特別休暇の呼称は会社によって異なりますが、趣旨や目的に合った名前が付けられるのが一般的です。
よくある例としては、「病気休暇」「リフレッシュ休暇」「ボランティア休暇」などが挙げられますが、近年では「失恋休暇」や「ペット忌引き休暇」など、独自の特別休暇を設ける企業も増えています。
特別休暇は従業員のモチベーションアップだけでなく企業のイメージアップにもつながり、採用活動においてもプラスの効果が期待できます。
法定休暇と法定外休暇の違い
特別休暇は法律によって義務付けられた法定休暇と異なり、企業が自由に設定することができる休暇です。特別休暇について理解するために、まずは法定休暇と法定外休暇について詳しくみていきましょう。
■法定休暇
法定休暇とは、法律で定められている企業が従業員に与えなければならない休暇・休業のことです。法律で定められた従業員の権利であるため、企業は従業員から請求や申請があれば、取得を拒むことはできません。
法定休暇の種類は6種類で、労働基準法と育児介護休業法で定められています。
・法定休暇の種類
労働基準法:産前産後休業、年次有給休暇、生理休暇
育児介護休業法:介護休暇、育児休業、子の介護休暇
これらの法定休暇は、働く従業員が健康で充実した生活を送るために設定されているものです。
企業は主体的に取得の呼びかけ、休暇を取得しやすい風土づくりや、計画的な付与制度を活用するなど、環境づくりを行うことが大切です。
▼介護休暇に関する記事はこちら
介護休暇とは?介護休業との違いや条件は?給付金についても解説!
■法定外休暇
一方で、法定外休暇はこれまで説明したとおり、企業側が就業規則で独自に定める休暇のことです。そのため休暇の種類は企業によって多種多様です。
社員の福利厚生として設定するもので、一般的に有名なものとしては「慶弔休暇」があります。法的には付与する義務のない慶弔休暇ですが、その付与日数などは会社の就業規則で自由に設定することができます。
更に会社によってはユニークな特別休暇を設定している場合もあります。
このように特別休暇は、社員のモチベーションアップや、多様なライフスタイルに合わせた働き方を実現するために有効な施策です。それだけではなく、企業のイメージ向上にも効果があります。
▼福利厚生に関する記事はこちら
福利厚生とは? 種類や制度の仕組み、導入のメリット・ポイントを紹介
特別休暇の法的位置づけ
特別休暇とは、慶弔休暇や裁判員休暇など、法定外の休暇を指します。労働基準法には特別休暇の付与義務は明記されていませんが、第89条により、特別の休暇を設ける場合は就業規則にその旨を記載する義務があります。
つまり、会社が自主的に制度を設ける場合、その内容(対象者、日数、取得条件など)を明文化する必要があります。
なお、育児・介護休業や裁判員休暇など、一部の特別休暇については他の法律(育児・介護休業法、裁判員法等)で規定され、企業に対応が求められるケースもあります。したがって、特別休暇は法定義務ではないものの、就業規則上の整備と法令との整合性が重要です。
就業規則への記載方法
特別休暇を就業規則に記載する際は、対象となる休暇の種類(慶弔、裁判員、ボランティア等)や付与日数、取得条件、申請手続きなどを明確に記載することが重要です。
労働基準法第89条では、労働者に特別の休暇を与える場合は就業規則にその内容を明示する義務があるとされています。記載例としては、「従業員が結婚した場合は5日間の特別休暇を与える」など、具体的かつ客観的に定める必要があります。
また、会社が独自に設ける制度であっても、一度規定すれば法的効力が生じ、使用者はその内容に従って対応する義務があります。従業員への周知も重要であり、就業規則の変更や新設時には労働者代表の意見聴取と労働基準監督署への届出も必要です。
曖昧な表現はトラブルの元となるため、実態に即した明確な記載が求められます。
特別休暇と労働契約の関係
特別休暇は原則として法定外休暇であり、労使間の合意により労働契約に組み込まれることで、契約上の権利義務が発生します。労働契約書や就業規則に特別休暇の規定があれば、従業員はその取得を当然の権利として主張できます。
また、特別休暇制度の新設・変更・廃止を行う場合は、労働条件の不利益変更と見なされる可能性があるため、労働者の同意や十分な説明が不可欠です。
特に慶弔休暇などは、制度の有無や内容によって従業員満足度や採用力にも影響を与えるため、慎重な取り扱いが求められます。なお、特別休暇を付与した際の賃金支払の有無も労働条件に該当するため、契約内容として明示しておくことが望まれます。
特別休暇の目的
2019年4月の労働基準法改正により、有休休暇の取得が義務化されたこともあいまって有給休暇の取得率は高まっています。オープンワークの調査では、有給消化率は2021年では60%と10年前とくらべて20%近く改善、20代では63.3%まで向上しています。
厚生労働省は、特別休暇は労働者が心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備するために必要なものであるとしていますが、年次有給休暇に加えて特別休暇を設定する目的はなんでしょうか。
働く人々の個別の事情に柔軟に対応するためには、法律で定められた法定休暇に加えて、休暇の目的や取得形態を独自に設定できる特別休暇を活用することが有効としています。
法定休暇と年次有給休暇、そして特別休暇をあわせて設定、活用することで、ライフステージに合わせて、家庭生活、自発的なスキル開発、地域活動等に使う時間と労働時間を柔軟に組み合わせることを期待しています。
さらに「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」として、労働者の目的や状況に応じた制度としての認識が広まっています。「特に配慮を必要とする労働者」として、厚生労働省は以下のように例示しています。
・特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
・子の養育または家族の介護を行う労働者
・妊娠中および出産後の女性労働者
・公民権の行使または公の職務の執行をする労働者
・単身赴任者
・自発的な職業能力開発を図る労働者
・地域活動等を行う労働者
参考:オープンワーク株式会社 OpenWork 残業と有休 10年の変化
特別休暇と働き方改革の関係
働き方改革は、労働時間の短縮や柔軟な働き方の推進を通じて、労働者の健康確保と生産性向上を目指す取り組みです。この中で、特別休暇は「休み方改革」の一環として位置づけられています。
厚生労働省は、ボランティア活動や病気療養などを目的とした特別休暇制度の導入を企業に推奨しており、各種広報や導入事例の紹介を通じてその普及を図っています 。
企業側も、従業員の多様なニーズに応えるため、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇などの特別休暇制度を導入し、働きやすい職場環境の整備に努めています。
これにより、従業員のモチベーション向上や離職率の低下、企業のイメージ向上といった効果が期待されています。特別休暇の導入は、働き方改革の実現に向けた重要な施策の一つといえるでしょう。
ワークライフバランス向上への効果
特別休暇制度の導入は、従業員のワークライフバランスの向上に大きく寄与します。
例えば、株式会社ヤマハコーポレートサービスでは、育児や看護、旅行など多様な目的で利用できる「ライフサポート休暇」や「ライフサイクル休暇」を導入し、従業員から「安心して休める」との声が寄せられています 。
また、ある建設会社では、子どもの学校行事に参加できる特別休暇や育児短時間勤務制度を導入し、従業員の満足度向上と企業表彰の受賞につながっています 。
これらの事例からも、特別休暇制度が従業員の生活と仕事の調和を支援し、企業の魅力向上や人材確保に効果的であることがわかります。
特別休暇の種類
ここで代表的な特別休暇の例をご紹介します。厚生労働省が定めた「労働時間等見直しガイドライン」において、先程挙げた「特に配慮を必要とする労働者」に対して付与される特別休暇の例としてあげられているのは以下です。
■病気休暇
病気休暇は長期にわたる治療が必要な疾病を持つ従業員が、治療と仕事を両立するためのサポートのための特別休暇です。
治療や通院のために、時間単位や半日単位で取得ができる制度や、年次有給休暇とは別に取得ができる制度、さらに療養中・療養後に仕事の負担を軽減する短時間勤務制度もあります。
■ボランティア休暇
従業員が、自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う場合に、付与される特別休暇です。
「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもあります。
■リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇は、従業員の心身の疲労回復を目的として付与される特別休暇です。例えば、3年ごとに5日間の休暇を付与するといった制度があります。
■裁判員休暇
裁判員休暇とは、裁判員として活動することになった従業員が、その職務を果たすために必要な期間に対して付与される特別休暇です。
これは平成16年に「裁判員の参加する刑事判断に関する法律」が成立し、平成21年から国民が裁判員として裁判に参加する裁判員制度が開始されたことで必要性が呼びかけられている特別休暇です。
■犯罪被害者等の被害回復のための特別休暇
この特別休暇は犯罪等によって被害を受けた被害者及びその家族に対して付与される、被害回復のための特別休暇です。
例えば、犯罪被害による精神的ショックや体の不調からの回復を目的としての一週間の休暇や、治療のための通院、警察への手続き、裁判への出廷などのためにも利用できる休暇です。
■夏季休暇
夏季休暇は文字どおり、夏に付与される特別休暇のことで、お盆付近でまとまった休暇を付与するのが一般的です。なお、特別休暇として夏季休暇を付与する会社もありますが、夏季休暇を有給休暇扱いとしている会社もあります。
■バースデー休暇
バースデー休暇は一般的に、従業員の誕生月に付与される休暇のことを言います。基本的には誕生月に休みを付与しますが、繁忙期などであれば翌月に繰り越しができるなど、会社によってルールは異なります。
従業員本人の誕生日だけでなく、家族の誕生日を対象として「アニバーサリー休暇」として付与している会社もあります。
■慶弔休暇
慶弔休暇とは、お祝いごと(慶事)とお悔やみごと(弔事)があった従業員に付与される休暇のことです。慶事としては結婚や出産、弔事としては親族の通夜や葬儀が挙げられます。慶弔休暇を付与する条件や日数などは会社によって異なります。
なお、独立行政法人労働政策研究・研修機構がおこなった「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」によると、福利厚生として慶弔休暇制度を設ける企業は90.7%と、大多数の企業が慶弔休暇を導入していることが分かります。
■教育訓練休暇
教育訓練休暇とは、業務における知識・スキルの向上を図るため、業務から離れて教育訓練を受ける際に与えられる休暇のことです。ヨーロッパ諸国では教育訓練休暇が法制化されていますが、日本では法制化されておらず、必要に応じて付与することが求められている形です。
教育訓練休暇の導入によって受けられる助成金もありますが、日本では導入している会社は少数にとどまっています。
特別休暇を定めるメリット
会社によって独自に設定ができる特別休暇ですが、特別休暇を定めるメリットは主に下記のようなものがあります。
メリットを理解して、特別休暇を効果的に取り入れましょう。
■メリット①人材の安定的な確保
特別休暇の効果として、従業員の疲労回復やストレス解消によるワークライフバランスを叶えることが期待できます。
家庭と仕事の両立を目指すことで、従業員の多様なライフスタイルに合わせた働き方を提供することができます。
これにより、従業員の定着率の向上も期待ができます。離職率の低い企業は、転職市場でのイメージも良くなるため、優秀な人材を獲得しやすくなります。
また、新卒採用市場では、若い世代を含む新卒者は特別休暇をはじめとした福利厚生への感度が高いため、特別休暇の導入は採用にも有効であると考えられます。
■メリット②生産性の向上
特別休暇では、従業員が日々の労働におけるストレスや披露をリフレッシュすることができるため、会社への貢献意欲の向上、帰属意識の向上が見込め、モチベーションアップに繋がると考えられます。
また、自己啓発や資格取得などを目的とした特別休暇を設定することで、従業員のスキルアップを促すことができます。
会社の制度としてスキルアップのための特別休暇を設定することで、特別休暇を取得した本人の成長だけでなく、周囲への好影響も期待ができます。
特別休暇を取得した従業員が、習得した知識や能力を仕事に活かして活躍することで、周囲にも刺激を与えることができるでしょう。
このように、特別休暇の活用によって従業員の意欲向上と能力向上を実現することで、企業の生産性の向上を狙うことができます。
■メリット③労使の対話機会創出
休暇は積極的に取得できる環境を作りたいものの、雇用者側からすると休んでもらっては困る時期やタイミングがあるというのも正直否めないところです。
そこで、あらかじめ取得時期や取得対象が多少想定できるような目的を設定することができるのも特別休暇のメリットの1つと言えます。「親の長寿お祝い休暇」「子の入学式参加休暇」「勤続●年休暇」などが一例です。
また、あらかじめ目的を設定しておくことで休暇の取得時期を職場の管理者と従業員との間で相談しやすくなると考えられます。そのためにはだれもが目的を想像しやすいわかりやすい名称をつけることがポイントとなるでしょう。
■メリット④企業イメージの向上
特別休暇は、企業の個性や健全な労働環境を社外へアピールする手段の一つとしても捉えられます。
特別休暇を充実させることで、対内へは「帰属意識の向上」や「貢献意欲の向上」、対外へは「働きやすさ」や「長期雇用への期待」を見込むことができます。
前述したとおり、対外へのイメージ向上は、新卒採用や中途採用市場に対しても好影響があります。少子高齢化による人材不足が加速していく日本企業にとっては、企業イメージの向上は中長期的な発展のために欠かせないものと言えるでしょう。
【参考資料のご紹介】
心理的安全性を生み出し良いチームを作る4つのポイントをご紹介!
特別休暇を定めるデメリット
特別休暇制度は従業員の満足度向上に寄与する一方で、運用が形骸化するリスクもあります。例えば、制度があっても取得しづらい雰囲気や運用ルールが曖昧な場合、実質的に活用されず、従業員の不信感を招く可能性があります。
また、制度管理の煩雑さや業務調整の負担が増加する点も企業側の懸念材料です。こうした問題を回避するためには、制度導入時に運用ルールを明確化し、取得促進のための社内啓発も併せて実施することが重要です。
有給か無給かは企業側で決めることができる
特別休暇は法律で定められていない休暇のため、企業ごとに独自に決めることができると前述しました。特別休暇の無休、有給の判断もその一つです。
一般的には、冠婚葬祭のための特別休暇の場合、有給にする企業が多いと言われています。また、不法による帰省や、親族の挙式のための休暇に対しては、従業員へのお悔やみやお祝いの気持ちを込めて有給としているケースが多いようです。
社員のモチベーション向上が目的の特別休暇であれば、無休よりも有給休暇としたほうが、その効果を望むことができるでしょう。
また、有給休暇の取得率が低い企業は、もともとの風土として有給休暇取得がしにくい職場環境である可能性があります。
有給休暇を取りやすい勤務体制や組織風土があることが、特別休暇の効果を得るための前提になります。特に経営・マネージャー層が率先して取得をすることで、組織風土に変化をもたらすことができます。
人事は、従業員に休暇取得の現状や、社員が求めている休暇制度・福利厚生をヒアリングし、よく検討するとよいでしょう。
また、有給休暇を出勤日にするかしないかは、年次有給休暇の出勤率の算定に関わるため、社員への周知が必要でしょう。出勤日にするかどうかをはじめ、特別休暇の取得要件は就業規則にきちんと示しておきましょう。
▼有給休暇に関する記事はこちら
年次有給休暇とは?雇用側の義務や違反時の罰則、付与日数などの注意点を解説
特別休暇の付与条件
特別休暇を付与するにあたり、人事が決めておくべき付与条件がいくつかあります。ここでは一般的な種類と例を説明していきます。
■対象雇用者
特別休暇が取得できる対象者を決めましょう。
例えば、正社員は対象だけれども、アルバイトは対象外であるなどの場合があります。この対象者の条件は就業規則等で明記をしておきましょう。
■設定日数
特別休暇は、各企業が独自に設定することができる休暇であるため、同じ休暇内容であっても、付与される日数は企業ごとに異なります。
ここでは特別休暇として多くの企業で導入されているものの付与日数を例としてご紹介します。
・病気休暇
自身の病気で通院、療養するときのために使用できる休暇制度です。
会社によっては、どの従業員も一律の日数を取得できるのではなく、勤めた年数によって取得できる日数の上限が増えていくという仕組みをとっている企業もあるようです。
休暇期間にも数日程度から長期にわたる場合、有給として扱う場合、無休として扱う場合など様々なパターンが有ります。
こうした、病気と言っても様々なケースの病気からの復帰に備えて、以下のように様々なバリエーションの病気休暇を用意することの必要性が高まっています。
- 治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度
- 失効した年次有給休暇を組み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効年休積立制度
- 年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇
- 療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度
・ボランティア休暇
ボランティア休暇は、労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際に付与される特別休暇です。
企業は、地域活動やボランティア活動に参加する従業員に対して、その参加を可能にするよう、年次有給休暇の半日単位の付与などについて検討することが求められます。
・リフレッシュ休暇
リフレッシュ休暇は、勤労者の心身の疲労回復を目的として付与される休暇です。
一定年数勤務した従業員へねぎらいの気持ちも込めて付与されるものであるため、節目の5年、10年、15年などのタイミングで取得できるように設定されていることが多くあります。一度に取得できる日数は5日〜一ヶ月など、企業によって幅があるようです。
・裁判員休暇
裁判員制度とは国民が裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官とともに有罪・無罪や刑の内容を決める制度です。裁判員に選ばれた従業員が、裁判員としての活動と仕事を両立することができるよう、裁判員休暇の導入の必要性が高まっています。
裁判員休暇は約4割の企業で導入が進んでいますが、その付与日数はその場合によって必要日数を判断しているようです。
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
犯罪被害者等の被害回復のための休暇は、犯罪行為により被害を受けた被害者やその家族に対して、被害回復のために付与される休暇のことです、
付与日数の例としては、一週間程度の休暇を犯罪被害による精神的ショックや引退の不調からの回復のために付与したり、半日や一日単位の休暇を通院や警察への手続き、裁判所への出廷等のために付与するケースがあるようです。
・夏季休暇
夏季休暇の日数は会社によって異なりますが、お盆付近で土日につなげて付与する会社が多いようです。なお、平成31年に厚生労働省が実施した「就労条件総合調査報告」によると、1企業平均1回あたりの最高付与日数は4.4日となっています。
・バースデー休暇
バースデー休暇の日数は、多くの企業で年に1日とされています。ただし、アニバーサリー休暇の一環としてバースデー休暇を設けている会社の場合は、誕生日の前日・翌日を合わせて3日間などにしているケースもあります。
・慶弔休暇
慶弔休暇の日数も会社によって異なります。
お祝いごとで言えば、従業員本人が結婚する場合は5日、子どもが結婚する場合は2日など、お悔やみごとで言えば、配偶者や父母、子どもなどの1親等の人が亡くなった場合は5~7日、祖父母や配偶者の父母など2親等の人が亡くなった場合は2~3日というように、内容によって日数が変わるのが通常です。
・教育訓練休暇
教育訓練休暇は、従業員の業務上のスキルアップを目的にした休暇なので、どの程度のスキルアップを目指すかによって休暇の日数も変わってきます。実際に、数日~数ヶ月と会社によって大きな幅があります。
特別休暇導入の流れ
特別休暇を実際に導入するにあたり、必要な対応事項とその手順をご紹介します。
ただルールを決めるだけでは、特別休暇の本来得たかった成果を得ることができなくなってしまうので、注意しましょう。
■①特別休暇の目的設定
特別休暇の導入のためには、まずどのような目的で特別休暇を設定するのか、目的を明確にする必要があります。
有給・無休に関わらず従業員の労働義務が免除されるため、特別休暇の導入・取得が従業員のためになっていることが重要です。事前に従業員にヒアリングを行い、どのような内容の休暇が求められているのか把握しておくと良いでしょう。
また、企業の課題を解決する目的で特別休暇を導入することもできます。
例えば、従業員のスキル不足が課題であれば、業務に必要なスキル・資格の取得を目的とした「教育訓練休暇」の導入の検討などが有効です。
■②特別休暇の取得条件、申請フローの決定
特別休暇を制度化する際は、取得の条件や申請手続きについて明確に定める必要があります。例えば、「結婚による特別休暇は入籍日から3か月以内の申請に限る」といった具体的な要件や、上司への申請フロー、必要書類の有無などをルール化することで、運用の公正性と透明性を確保できます。
これらのルールは、就業規則に明記する義務があり、労働基準法第89条では「労働者に特別の休暇を与える場合」は就業規則に記載し、所轄労働基準監督署に届け出ることが求められています。
適切な制度設計とルールの明文化により、特別休暇の有効活用が進み、制度の形骸化を防ぐことが可能です。
■③社内周知
特別休暇を就業規則上で規定しても、従業員にその存在や目的が伝わっていなければ活用されなくなってしまいます。
特別休暇の利用を促すために、社内メールや社内報、社内サイト等を利用して、特別休暇の利用を促しましょう。
■④休暇を取得しやすい環境づくり
どんなに制度や仕組みを整えたとしても、それを実際に活用できていなければ意味がありません。従業員が制度を活用しやすい風土を作っておくことは重要です。
一方で、「残業をするほうが頑張っている」「労働時間が多いほうが評価が高い」「定時で帰るのは気が引ける」など、ステレオタイプな企業文化によって従業員が制度の活用をためらうケースは多くあります。
文化を変えていくためには、管理職がワークライフバランスや個人の生活と仕事の両立に理解を示し、制度を使いやすい職場を作るためのマネジメントをしていくことが必要でしょう。
▼パタハラに関する記事はこちら
パタハラとは?発生する原因は?対処法や予防策を徹底解説
中小企業における特別休暇の導入ポイント
中小企業が特別休暇を導入する際は、限られた人員や予算の中で、従業員の満足度向上と業務効率の維持を両立することが求められます。
まず、従業員のニーズを把握し、取得しやすい環境を整えることが重要です。例えば、慶弔休暇やリフレッシュ休暇など、業務への影響が少ない休暇から導入を始めると良いでしょう。
また、助成金や補助金の活用も検討することで、導入コストを抑えることが可能です。制度の導入にあたっては、就業規則への明確な記載と、従業員への周知を徹底し、制度の形骸化を防ぐことが大切です。
段階的な導入や柔軟な運用を心がけ、従業員が安心して休暇を取得できる職場環境を目指しましょう。
コスト効率の高い特別休暇設計
予算制約のある中小企業にとって、低コストで効果的な特別休暇の設計は重要です。
例えば、従業員の誕生日や結婚記念日などに取得できる「アニバーサリー休暇」や、ボランティア活動参加のための「ボランティア休暇」など、特別な日を祝う休暇制度は、金銭的負担が少なく、従業員のモチベーション向上につながります。
また、取得条件や申請手続きを簡素化し、運用の手間を減らすことも効果的です。制度の導入に際しては、従業員の意見を取り入れ、ニーズに合った休暇制度を設計することで、制度の活用率を高めることができます。
このように、創意工夫を凝らした特別休暇制度は、コストを抑えつつ、従業員満足度の向上に寄与します。
段階的な特別休暇導入アプローチ
特別休暇の導入は、一度にすべての制度を整備するのではなく、段階的に進めることが効果的です。まずは、業務への影響が少なく、従業員のニーズが高い休暇制度から導入を始めましょう。
例えば、慶弔休暇やリフレッシュ休暇など、取得しやすい休暇からスタートし、運用状況や従業員の反応を見ながら、徐々に制度を拡充していく方法が有効です。
また、制度の導入にあたっては、従業員への周知や取得促進のための啓発活動を行い、制度の定着を図ることが重要です。段階的な導入により、業務への影響を最小限に抑えつつ、従業員の満足度向上を実現することが可能です。
助成金・補助金の活用方法
特別休暇の導入に際しては、国や自治体が提供する助成金や補助金を活用することで、企業の負担を軽減できます。
例えば、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」では、特別休暇制度の新設や取得促進のための取り組みに対して、最大25万円の助成が受けられます。
また、「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」では、病気治療と仕事の両立を支援する制度の導入に対して、20万円の助成が提供されています。申請には、制度の導入計画や就業規則への記載、従業員への周知などが必要となります。
これらの助成金を活用することで、特別休暇制度の導入を効果的に進めることが可能です。
個性的な特別休暇
ここまでは特別休暇の意味や意義、一般的な例を紹介してきました。特別休暇は企業毎に自由に設定することができ、個性を出すことができることも大きな特徴です。
ここからは、個性的な特別休暇の事例をいくつかご紹介します。
■モンハン休暇
VRコンテンツなどの企画・開発を行う株式会社Mark-onでは、2021年3月26日に発売されたゲームソフト”MONSTER HUNTER RISE(©︎CAPCOM)”の発売日を、特別休暇に設定しました。
もともとこの休暇を設定する前から、有給取得を申請する従業員が多発していたことから、仕事へ集中できないことが想定されるため、休暇としたとのことです。
VRコンテンツ制作をしている同社だからこそ、従業員の「いち早く人気コンテンツをプレイしたい!」という思いを尊重した特別休暇と言えるでしょう。
こういった遊び心のある特別休暇も、社員のモチベーションを上げる一つのきっかけになりそうです。
参考:ハフポスト 3月26日は「モンハン休み」で休暇に。ある会社の発表にネット上で反響広がる。「羨ましい」の声が続々
■失恋休暇・離婚休暇制度
株式会社サニーサイドアップでは、失恋や離婚をすると取得ができる「失恋休暇・離婚休暇」を設定しています。
この制度は、「会社に出られなくなるほどの失恋や別れは、人生の中で良い経験になると思う」という社長の意向から設定されたそうです。
"人が気持ちよく働けてこそ"と、"たのしいさわぎ"という想いを掲げるPR会社である同社の、人の気持ちを大切にする価値観が投影された特別休暇です。
参考:株式会社サニーサイドアップ 弊社代表次原がハフィントンポストに寄稿『「失恋休暇」から「離婚休暇」まで、うちの会社が誇る32の福利厚生制度 』
■育自分休暇制度
株式会社サイボウズでは、「育自分休暇制度」という、自分自身を育てるための休暇制度を導入しています。
これは、一度退社をした社員が、6年以内であれば復職ができるという制度です。対象は35歳以下の社員で、期間中には青年海外協力隊への参加や転職も可能。
IT業界の特徴である高い離職率を解消するため、そして優秀な人材の育成や確保のために設定された休暇です。
■ピットイン休暇
株式会社リンクアンドモチベーションでは、「ピットイン休暇」を四半期(3ヶ月)ごとに年4回取得することが可能です。
これは、株式会社リンクアンドモチベーション独自の時間観としてある「世の中の3ヶ月はLMGの1年」「LMGは世の中の4倍のスピードで走る」という考え方、メッセージを発信するために設定された休暇です。
つまり、四半期(3ヶ月)のサイクルで敢えて時間を区切り、“年末年始”としての「ピットイン休暇」を敢えて設けることでメリハリがつき、常にスピード感をもって走り続けることができるような仕組みを整えています。
参考:株式会社リンクアンドモチベーション 当グループの制度へのこだわり
業種別の特別休暇導入事例
特別休暇制度は企業文化や業務特性に応じて多様に設計されています。特に近年では、業種ごとのニーズや働き方の違いを反映した制度設計が求められており、導入事例もさまざまです。それぞれが自社の事情に合った形で制度を活用しています。
以下に、具体的な事例を業種別に紹介します。
IT・テクノロジー企業の特別休暇
IT・テクノロジー業界では、社員の自己研鑽や創造性向上を支援するユニークな特別休暇制度が導入されています。たとえば、ある大手IT企業では「技術研修休暇」として、社外セミナーや開発合宿への参加を目的とした有給特別休暇を年に数日間付与しています。
別のスタートアップ企業では「ハッカソン休暇」を制度化しており、業務とは別に自主開発プロジェクトに集中するための休暇取得を奨励。
さらに、AI企業の中には「リセット休暇」と称し、メンタルヘルス維持や創造性回復のために半年に1回、3日連続の休暇を必須化している例もあります。これらの制度は、エンジニアの定着率向上や社内イノベーションの促進に貢献しています。
製造業の特別休暇
製造業では、肉体的・精神的な負荷への配慮や家族との時間確保を目的とした特別休暇の導入が進んでいます。
たとえば、ある自動車部品メーカーでは「交代勤務リフレッシュ休暇」として、夜勤明けの従業員に3日以上の連続休暇を推奨。これにより、労災リスクや離職率の低下が実現しました。
また、精密機器製造企業では「子ども参観日休暇」を設け、子どもの学校行事に参加できるよう配慮。さらに、高温環境での作業がある工場では「猛暑手当付き夏季休暇」を支給しており、従業員満足度と安全意識の向上につながっています。
このような取り組みは、現場の声を反映した制度として高く評価されています。
サービス業の特別休暇
接客やサービス業では、業務の特性上、休暇取得が難しいという課題がありますが、それを克服する工夫が多数見られます。
たとえば、飲食チェーンでは「シフト希望型バースデー休暇」を設け、誕生月に希望日での休暇取得を認める制度を導入。これにより、従業員のモチベーション向上が図られています。
また、ホテル業界では「繁忙期明け休暇」として、年末年始やGWなどの繁忙後に特別休暇を付与。さらに、小売業では「介護・看護サポート休暇」を法定外で独自に拡充し、家庭との両立支援を強化しています。
いずれの事例でも、シフト調整を柔軟に行うことで業務負担を分散させ、制度の実効性を高めています。
特別休暇の導入時のポイントと注意点
特別休暇を取得しやすい環境を整える
年次有給休暇に関してよく指摘されるのが、休みを取りにくく利用が進まないという問題です。「周りに迷惑がかかる」「後でしわ寄せが来る」「上司にいい顔をされない」といった理由から、有給取得にためらいを感じる人は少なくないようです。
特別休暇も同じ問題が起こる可能性があり、どれだけ素晴らしい特別休暇制度を設けても、従業員にとって使いづらいものであれば本末転倒です。
これを避けるためには、休暇中のフォロー体制を整えたり、管理者が積極的に利用を促したりして、気兼ねなく休める環境を整えることが大切です。
特別休暇の取得条件を明確にする
特別休暇を導入する際に注意しなければいけないのが、従業員と企業との間で認識に相違が生まれてしまうことです。
特別休暇の取得条件に不明瞭な点があると、解釈の違いなどからトラブルに発展するケースがあります。特別休暇を設けるときは、対象者や日数などの取得条件を就業規則で明確に定めておくことが重要です。
特別休暇が有給か無給か明確にする
特別休暇を取得しようとする従業員が「ちょっと待てよ・・・」と考えるのが、特別休暇が有給なのか無給なのかということです。無給の場合、特別休暇を取得することで給料が下がってしまいます。特別休暇を有給にするか無給にするかは、会社が決めることです。
たとえば、慶弔休暇の場合、配偶者や子ども、親が亡くなった場合は有給とし、それ以外の親族が亡くなった場合は無給とするケースもあります。いずれにしても、従業員との間でトラブルに発展しやすいポイントなので、就業規則で明確に規定しておきましょう。
記事まとめ
企業の理念や価値観を反映した特別休暇や、従業員のワークライフバランスの実現を促す特別休暇を設定することで、企業に対して多くのメリットが有ることを理解いただけたのではないでしょうか。
企業が独自に設定できる特別休暇の特徴を活用し、企業経営に活かしてください。
従業員エンゲージメントを可視化・改善するモチベーションクラウドはこちら
特別休暇に関するよくある質問
Q:法定休暇とは?
法定休暇とは、法律で定められている休暇のことで、従業員が自らの権利として使うことができる休暇です。法定休暇には、年次有給休暇、産前休暇、産後休暇、生理休暇、介護休暇、育児休暇、子の看護休暇などがあります。
年次有給休暇は1年ごとに規定の日数が付与されますが、その他の法定休暇に関しては、就業規則などで取得条件や社内の申請フローなどを定めておく必要があります。
Q:正社員とアルバイトで特別休暇のルールを変えてもいい?
2021年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用となっています。同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員との不合理な処遇格差をなくすことを目的としており、雇用形態の違いを理由に不合理な格差を設けることを禁止するものです。
特別休暇については、正社員とアルバイト・パートの間で条件や日数に差を設けている会社もありますが、そこに不合理な格差があってはいけません。不安がある場合は、一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。
Q:「ワクチン休暇」は特別休暇?
新型コロナウイルスのワクチンをスムーズに接種できるよう、また接種後に副反応が出た場合に安心して休みを取れるよう、有給休暇とは別に「ワクチン休暇」を導入する企業が増えています。ワクチン休暇は企業が任意で設ける休暇なので特別休暇に当たります。